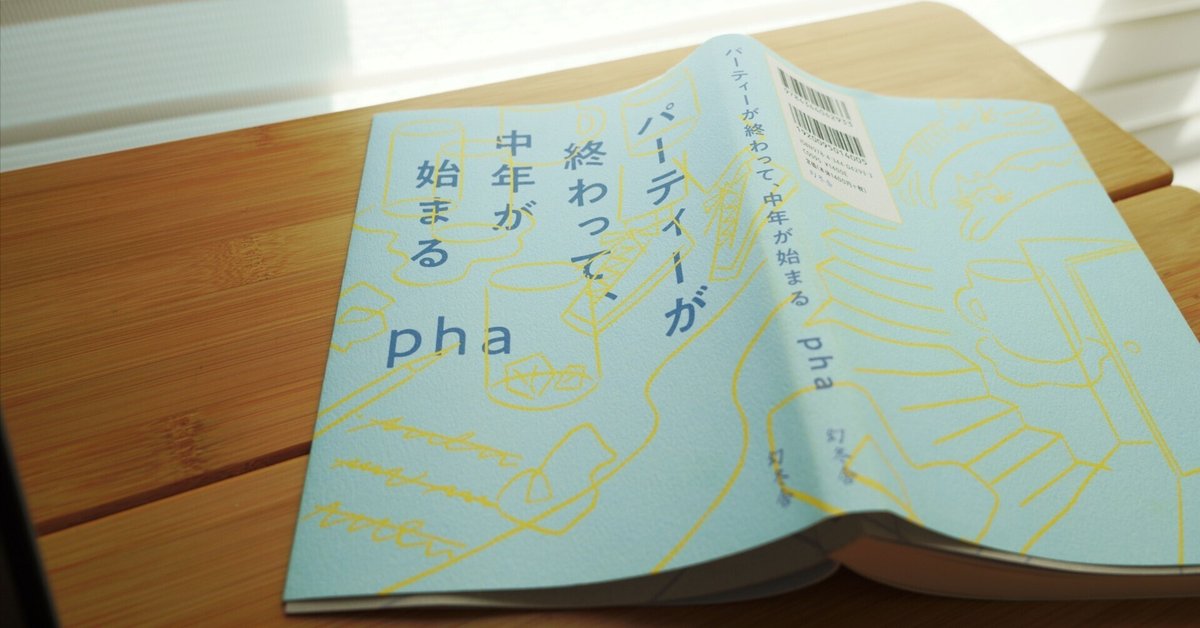
pha『パーティーが終わって、中年が始まる』 〜ピーク過ぎの最高傑作〜
身につまされる衰退のスケッチ
読むのをとても楽しみにしつつ、身につまされそうでページを開くのがむちゃくちゃに怖かった。
この本はphaさんが40代中盤になり”若さが完全に過ぎ去ってしまった”と感じている最中の”衰退のスケッチ”である。
「もうだめだ」が若い頃からずっと口癖だったけれど、今思うと、二十代の頃に感じていた「だめ」なんてものは大したことがない、ファッション的な「だめ」だった。四十代からは、「だめ」がだんだん洒落にならなくなってくる。これが本物の衰退と喪失なのだろう。
しかし、四十代半ばの今は、三十代の後半が人生のピークだったな、と思っている。肉体的にも精神的にも、すべてが衰えつつあるのを感じる。
この本で書かれているようなことは、phaさんと同世代のぼくには心当たりがあるどころではなく、そのほとんどすべてが自分にも起こっていると感じる。
日々、確かに感じている衰退だが、正面から向き合う勇気はなかなか出ない。そんなすべてが言語化されて、はっきり書きつけられてしまっている本ではないのか?
そして予想通り、そういう本だった。
ぼくは30代の最後をフィリピンで過ごした。パンデミックの後は、実家のある香川県でやり過ごしていたのだが、どうやらその間に完全な中年になってしまったようだ。
フィリピンでは英語を学んでいたので、その拙い武器を手に、世界のいろんな国に住もうと思っていた。フィリピンの後は、南アフリカなんていいのでは、と考えていた。アジア、ヨーロッパ、アフリカ、各大陸にひとつずつぐらい拠点があると人生楽しいのではないか? これからも楽しいことがどんどん起こるのではないかと期待していた。何かを信じていた。
パンデミックを頭を低くしてやり過ごしてみると、世界を駆け巡りたいという思いが、自分の中にかつてのような気力があまり残っていないことに気がついた。
刺激の時代の終わり
昔の自分は同じ店に通い続けるのが嫌いだった。それは堕落、つまり、環境をこまめに変えることで受け取れる刺を放棄する愚かな行為だと思っていた。毎日同じ街にいるのも嫌で、用もないのにいろんな違う街に出かけていたりもしていた。
いつからか、そういうのが面倒だ、と思うようになってしまった。
すべてのものが移り変わっていってほしいと思っていた二十代や三十代の頃、怖いものは何もなかった。
何も大切なものはなくて、とにかく変化だけが欲しかった。この現状をぐちゃぐちゃにかき回してくれる何かをいつも求めていた。喪失感さえ娯楽のひとつとしか思っていなかった。
以前は、ぼくも刺激ばかり求めていたと思う。モノがたくさんあって、何もかも面倒で同じアパートに長年住み続けていた。だからモノを極端に減らした後は羽が生えたように、恨みを晴らすかのようにいろんな場所にでかけていった。大切なモノも人もいないのだから、後ろ髪を引かれることもない。
気になった人や場所を訪れて、飽きたタイミングで去ることができる。そんなことをしている最中から、なぜ、どんなタイミングで、人は腰をおろし落ち着くのかが気になっていた。新鮮な出会いがあり、場面転換があり、環境がガラッと変わるほうが楽しいはずなのに?
最近は本を読んでも音楽を聴いても旅行に行ってもそんなに楽しくなくなってしまった。加齢に伴って脳内物質の出る量が減っているのだろうか。今まではずっと、とにかく楽しいことをガンガンやって面白おかしく生きていけばいい、と思ってやってきたけれど、そんな生き方に限界を感じつつある。
こんなことになってしまうのは、単に自分が年を取っていろいろな経験をして慣れてしまい、新鮮さを感じられなくなっているからだと思っていた。ひざを打ったのは「ひらめきアディクション」という一節だ。
孤独でもひらめきさえあれば良かった
今までは、ひとりで本を読んだり、散歩をしたり、旅行をしたりするのが好きだった。誰かといるよりもひとりでいるほうが、いろんなことを思いつくから楽しい、と思っていた。
それが、創作へのモチベーションが減ったとたん、楽しくなくなってしまった。
クリエイティビティと孤独というのは表裏一体なのかもしれない。頭の中に、作り出したいものがたくさんあるときは、ひとりでいても何も問題がなかった。
むしろ他の人間の存在はノイズだった。ひとりのほうがいいものを作れる。もっと、ひとりになりたい、と思って、近くにいるいろんな人を遠ざけてきたのが自分の人生だった。
創作を楽しめているときはそれでもよかった。しかしクリエイティビティが去ってしまうと、残ったのは単なる孤独だった。
確かに、ぼくが一人でい続けてきたのは、誰かといるより、自分から湧き出てくる感情やアイデアの方をより面白がっていたからなのかもしれない。けれども今のぼくは、場面を切り替えることよりも、自分の育った場所でいて、大事な人を大切にすることに自然と力点が移っていっている。
しかし、京都や大阪が居心地がいいのは、自分が京都と大阪で育ったせいなのかもしれない。生まれや育ちに影響されずにすべてを自分で選びたい、何にもとらわれず完全に自由に生きたい、と思ってここまでやってきたのだけど、幼少期に刷り込まれた経験はやはり断ち切れないものなのだろうか。
ぼくもphaさんと同様、普通の人が普通の生き方を選んで生きている理由がなんだかよくわかるようになってしまった。いわゆるミッドライフ・クライシス(中年の危機)の文脈で言うと、人生が中盤に差し掛かると、自分が選ばなかった人生について、ありえたかもしれない人生についてなんだか思い悩んでしまうようである。
若者に席をゆずる
この“衰退のスケッチ”では、歳を取ることを無理にポジティブに捉えることも排している。若者に対する目線もなんとなく温かい。
物事には何にでも順番がある。一般的な社会のルールとあまり関わらないように生きてきたつもりの僕でも、順番には逆らえないようだ。何も背負わずふらふらと危うげに生きていくのはもっと若い人たちに任せようと思う。がんばって僕の分までふらふらと生きてくれ。
性はやはり、若者のものなのだろう。若者が誰かとセックスをした話をネットで見かけると、いいぞ、もっとやりまくれ、とこっそり応援している。
「死は生命の最大の発明」と言ったのはジョブズだったが、中年になってすべてが衰えることは、若者に活躍の場所を与えることになのかもしれない。ぼくたちが20代や30代だった頃にも、誰かが衰退していったからこそ、活躍の隙間ができたのかもしれないのだから。
心理学では、自分の人生以外の物事に関心や活動を広げることを「ジェネラティビティ(次世代育成能力)」と呼ぶが、これが中年期を生きる力やわくわくする気持ちを引き出す。
ぼくももう自分が何か経験するより、より新鮮な気持ちで経験できる若者にその経験を回すほうがいいのでは? などと思うようになってきた。
むなしさと哀惜の追認
読後やる気に満ち溢れて何かを始めたくなるような本ではないと思う。作者に寄り添ってもらえて、自分だけがこんなじゃないんだな、と思えて安心しました! と言えたらいいのだが、実際、中年になることは結構厳しいものもある。
悲しいけれど、こうなんだよね、という追認でしかないようなものが、ただごろんとそこにある。
この本と同様に、「マヘル・シャラル・ハシュ・バズ」というバンドに触れた本を最近読んだ。三品輝起さんの『すべての雑貨』だ。三品さんは旅のゆく先々で出会う「むなしさ」を古い友人のような、安堵感があるものとして愛しているようだ。
濡れた世界一長いすべり台、尻の落葉、地元実業家による現代美術館、死んだ虻、一行も読めなかった小説などから放たれたむなしさは、あらゆる旅先で私を待っている。小淵沢の枯れ野で、飛騨高山のラーメン屋で、パリの移民街で、ムラーノ島の中庭で。いつだって先回りして私を待っていたのだ。
どんな感情でも、味わい尽くすことができれば、悪いものではない、そうぼくも願ってきた。
昔素晴らしかったものは、既にもう失われてしまった。大事な友達は、みんないなくなってしまった。すべては、どうしようもなく壊れてしまった。そんな物語を好んで読んできたし、そんな歌詞の歌を繰り返し聴いてきた。喪失感と甘い哀惜の気分を愛してきた。
子どもの頃から、大きな物語は終わった、偉大なものはすべて出揃った、だからただ終わりなき日常を生きるんだ、という雰囲気の中で育ってきた。そんな雰囲気のなかでも若い頃は、それなりに自分が世界の中心だ。文化祭やパーティーも終わり、自分が中心でもなくなった後にどうやって人は生きていくのか。
中年は自分をよく見せようとすることのないphaさんにはうってつけのテーマだと思う。この本はphaさんの最高傑作、という呼び声を耳にした。ぼくもそうではないかと思っている。
人生のピークと、最高傑作を書く時期は、ずれることもあるらしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
