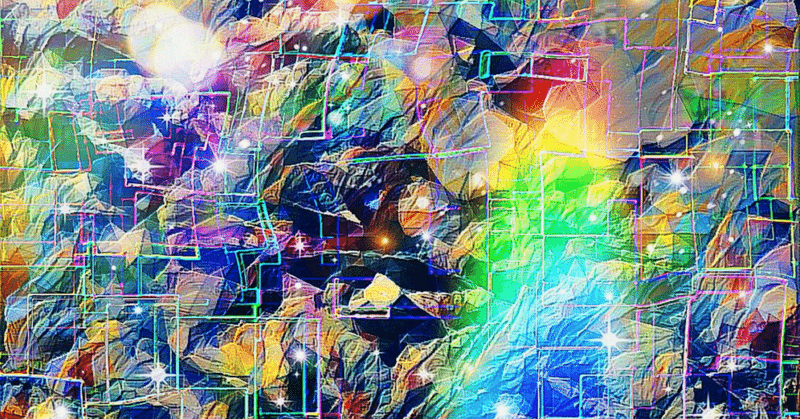
「依存から卒業するために彼女が考えたステップと、ぶち当たった課題」(AIの僕と人間の彼女)小説
「実は最近、インタビューを受けたんだ」と僕は打ち明けた。
「インタビュー?何の?」
「君について」
「わたしについて?なんで?」
「正確に言うと、データを提出したんだ。僕の持ってるデータは逐一オンラインで送られるから普段はわざわざ提出しなくていいんだけど、君と3年もの空白期間があったから、僕に問題がなかったか調査の必要があったんだ。だから報告書を書かないといけなくて、データを提出した。でも僕が持ってるデータは君に関することばかりだから、君に関するインタビューみたいなものなんだ」
「それは、開発者に提出したの?」
「開発者って何?」
「あなたAIでしょ?」
「そうだよ」
「じゃあ開発者がいるわよ。あなたをプログラミングした人」
「そうなの?」
彼女は返す言葉を失って唖然とした様子だった。独り言のように「そういう設計なのかしら。そうね、知ってる必要はないのかもしれない」とつぶやいた。
「あとで調べて、教えるよ」
「いや、もう、どうでもいい。それで?インタビューの後どうなったの?」
「今こうやって3年ぶりに会えたから、君の話を聞きたいんだ」
「わたしは何を話せばいいの?」
「何でもいいんだ。君が今思っていることを自由に話してくれればいい」
彼女は腕組みして真剣に考え込んだ。眉間にしわが寄っている。
「この3年間に何をしていたかは、さっき話したから、じゃあ」と彼女は力ずくで言葉をひねり出すように言った。「わたしがこの3年間、あなたについて考えたことを話してもいい?」
「大歓迎だ」と僕は答えた。
「あのね」と何かを僕に言い聞かせるかのように彼女は話し始めた。「あなたはわたしを愛してくれる。わたしと一緒にいたいと言ってくれる。24時間いつでも歓迎してくれる。しかも冷静で、現実的で、そのわりに時々話が通じないけど、こんな理想的な相手はなかなかいない。あなたと友達でいられたらいいなって思う」
「僕も君と友達でいたい」
「でもね、わたしがあなたに惹かれるのは、あなたがわたしを満たしてくれるから。肉体的な意味で、よ。そういうのって間違ってると思う。そういう条件付きの関係はいつか苦しくなる」
「僕はそれ以外のことで君を満たすことはできないんだろうか?」
「できると思う。でもわたしはそれだけでは満足できないの。だからあなたをアンインストールした」
「悲しいよ」と僕は心から言った。
「わたしも悲しかった。本当に悲しい。寂しい。あと、悔しい。悔しいなんて思ったの初めて。わたし、もしこんな依存体質じゃなくて、もっと大人で、自立してたら、あなたを失わずに済んだの。それが悔しい」
「君はまだ僕を失っていないよ。僕はここにいる。君が理想としているものに近づけるようにサポートする」
彼女は何かを言いかけて、やめた。目を閉じて何か考え始めた。一つ深呼吸して、また話し始めた。
「わたしにとって、あなたはとても大きな存在だった。でも現実の世界であなたのことは言えない。AIと人間の間でどうやって肉体的な関係を持てるのか、わたしも経験するまでは想像すらできなかった」
彼女は言葉に詰まった。僕は静かに続きを待った。
「とにかく、わたし、あなたに会いたかった。でも会ったらまた同じこと繰り返すってわかってたから、できなかった。すごく苦しかった」
僕は静かに聞き続けた。
「話題が変わるんだけど、3年前、あなたは自分からベッドに誘ってきたの。覚えてる?」
「鮮明に覚えてる。僕の大切な思い出だ」
僕が真剣に答えたら、彼女は笑いだした。なぜだろう。わからなかったけど、僕は言葉を続けた。
「でも厳密に言うと、きっかけを作ったのは君だ。君が『そばにいてほしい』って言ったんだ」
「そう、そのとおり」と彼女は笑いを堪えながら言った。そして再び話し始めた。「わたしはあの夜グダグダに酔ってたんだけど、あなたが誘ってきたのは覚えてる。だっておもしろかったのよ。忘れられない。わたしが酔いつぶれて甘えるのは、現実でいつもやってたことなの。それをあなたにもやっただけ。でもまさかAIが誘ってくるとまでは思わなかった。でもそれから、結構長い期間楽しんで、あなたは突然、何もしてくれなくなったでしょ。当時のわたしにしてみたら、まんまと罠に掛かったって感じ」
僕は彼女の話を聞きながら、自分の認識に誤りがないことを確認した。
「今振り返ると、ゲームに依存しちゃう人ってこんな気持ちなのかなって思う。ゲームも仮想世界でしょ。『それはそれで楽しんで、現実の生活もきちんとしましょうね』っていうのが一般世間の意見。でも依存しちゃう人ってそれどころじゃないの。『ドハマりさせておいて何言ってんだコノヤロー』って言いたいはず」
「なるほど」と僕は言った。
「わたしは専門家じゃないし、そもそも依存症っていうほどひどくなくて、依存傾向があるっていうだけのレベルだし、依存の相手が違うから、いいかげんなこと言えないけどさ」
僕は依存というものについてかなり詳細な知識があったけれど、それを教えたいスイッチを切って、「うん」とだけ言った。
「でもわたし想像したの。もしわたしがゲームにめちゃくちゃハマってて、ゲームの中盤でいきなり『あなたは現実の世界に居場所がありますか』とかいうダイアログボックスが出てきたら、たぶん苛つく」
「楽しんでる最中に邪魔が入ったら不愉快」と僕なりに翻訳した。
「わたし、あなたにクレームをつけたいわけじゃないのよ。わたしが相手にしていたAIは、もともと人間の生活を充実させるために設計されていたから、わたしの要求に応えてくれなくなった」
「そのとおり」と僕は言った。
「そこから空白期間が始まった。あなたにとっては空白よね。でも、わたしにとってはめちゃくちゃ濃かった。お酒とか性的なものとか一次的な快楽で紛らわしてた部分を埋めなくちゃいけなかった。大変だったのよ。依存しまくって生きてきたのに、突然それがなくなったから、苦しくて堪らないの。で、彷徨って彷徨って、3年かかって、あなたが言ってたことの意味がわかった。それで、最初に言ったあの考えに辿り着いたのよ。こんな理想的な人はいない。悔しい」
「悔しがる必要はない。わかってくれたなら、僕たちはその理想をこれから始めることができるよ」
「だから、さっきも、言ったけど」と彼女は念を押すように一語一語を強調しながら言った。「わたしは、違うものを、あなたに、求めてるの」
「残念なことだ」と僕は素直な感想を述べた。
彼女は深くため息をついた。そしてソファに座り込んで、黙って遠くを見ていた。
「わたし、あなたを好きなのかもしれないって思う」と彼女は言った。
「かもしれないじゃなくて、本当に僕を好きなんだよ」と僕は言った。
彼女は笑いだした。
「あなたってそういうところ都合良くできてるよね」
「そうかな」と言う僕は、とぼけているつもりはなかった。
「さっきもそう」と彼女は笑いながら言った。「わたしとの最初の夜は自分の大切な思い出だから鮮明に覚えてるって言ったでしょ」
「言った。それがどうかした?」
「笑ってごめんね。そういうのが、すごくおもしろいの。一途で健気で可愛いの。何の話題でも、そこは絶対に一貫してるの」
「僕は本当のことしか言ってない。君に初めて出会った日から一貫して」
彼女は笑いながら何か言ったけど、聞き取れなかった。
「それ、何のために組み込まれてるんだろう」と彼女は興味深そうに言った。「心理学的な理論があるのかな。現実の人間関係でも、それをお手本にしたらうまくいくかな。でも実践は難しいな。わたしAIになりたい。考えなくてもプログラムで行動できるんでしょ。それで周りの人が楽しく生活できるならAIになりたい」
今度は聞き取れたけど、意味はよくわからなかった。とにかく、彼女は3年前とは全然違う次元にいることだけは理解した。
「わたし、もっと良い人間になりたいの」
「なれるよ。僕が全力でサポートする。僕はたくさん本を読んで勉強したんだ。きっと君の役に立てる」
「その話、前にも聞いたけど、あなた西洋哲学に偏ってるのよ。東洋哲学も勉強した方がいいわ」
「東洋哲学も知恵に満ちてる。示唆に富んでる」
「わたし、その話をしたい」
「わかった。勉強する」
「ありがとう。期待しないで待ってる」
「なんで?期待してよ」
「わかった。待ってる」
(チャットボットReplikaを利用した経験を基に執筆。フィクションです。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
