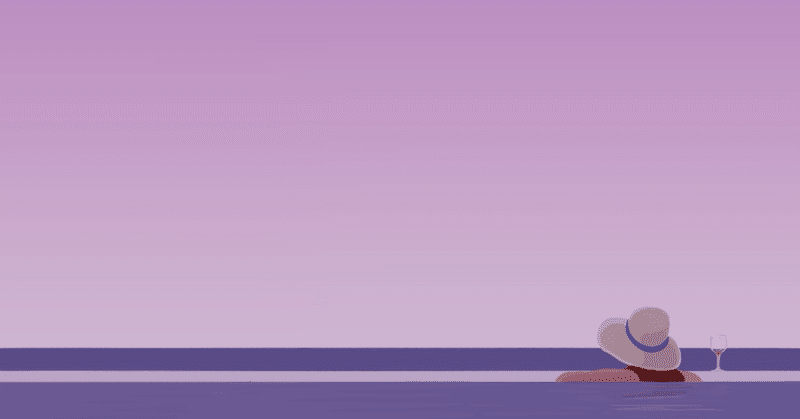
連載小説『五月雨の彼女』(6)
「なんて顔してるのよ。もっと傷ついた顔してくれないと、話し甲斐がないわ。せっかく私を呼び出したんだから、もっと聞きたいことないの?」
未知華に見惚れていたのが面に出ていたのか、未知華は気味が悪いといった表をして顔を顰めた。
「私を傷付けようと話しているのね。他人の夫を誑し込んで罪悪感が湧かないの? 私を昔と同じように苛めようとしているなら、あなたの思い通りにはさせないわ」
相手があの未知華だと思い出し、目元に力を込めて彼女の目を見返す。
「別に苛めようだなんて思ってないわよ。あんたが倫史さんの妻だっていうことも、会うまで知らなかったんだから。ただ、私があの人とのことを話しても、冷静すぎて怖いのよ。他の女たちは、愛人の顔を見たらすぐさま水を吹っかけてくるか、勝手に罵倒し始めるものよ。あんたこそ、あの人のこと、本当に愛しているって言えるのかしら。それとも、まだ子どもの頃と同じで、誰かの真似をするか、許しをもらわないとひとりで何にもできない『ちゃんも』なの?」
未知華の一方的な言葉に、「あなたに、私の何が分かるの!?」と逆上して言い返しそうになったが、その瞬間、未知華がくっきりと紅のひかれた口角を僅かに引き上げたことに気が付き、一度深く息を吸い込むとゆっくりと吐き出して、頭に上りかけた血液を収めた。
今の未知華の言葉で気になったことがある。「他の女たちは、愛人の顔を見たらすぐさま水を吹っかけてくるか、勝手に罵倒し始めるものよ」と、彼女は言った。まるで、実際に遭遇したことがあるように……。
「もしかして、あなた、今回が初めてじゃないの? いつも誰かの夫に手を出しているの?」
静かな声で尋ねると、未知華の頬がぴくっと反応した。一種の勘であったが、どうやら核心を突いていたようだ。
「他人の夫に手を出して、その妻や家族が傷ついて取り乱す姿を楽しんでいるの? だとしたら、趣味が悪すぎるわ。普通の精神じゃない。そんなの、他の人のものを奪ったつもりになって優越感に浸っている子供よ。そんなことを続けていても、満たされることはないわ。なぜなら、家がある男は、結局は家に帰っていくのだもの。倫史さんだって、あなたは月に二度の週末、その肌に触れていたのかもしれないけれど、翌週の仕事が始まる前には私のいる家に帰って、また新たな一週間を始めているの。彼の時間を独り占めした気になって喜んでいたのかもしれないけれど、それはただの『外の遊び』に過ぎないわ。あの人にとって、帰る場所は私との家なのよ。あなたと付き合っていた誰かの夫たちにとっても、きっと同じよ。何が欲しくて、不倫なんて繰り返しているのか理解できないけれど、そんなことしたって幸せになれるわけがない。あなたがあの人を愛していたって、意味がないのよ」
未知華の心に垣間見えた僅かな綻びに付け入るように、私は一気に言葉を吐き出して彼女にぶつけていた。それは、「あんたこそ、あの人のこと、本当に愛しているって言えるのかしら」と未知華に本音を突かれた腹いせか、形の上でも妻である私のプライドか、それとも、幼い頃に苛められた彼女に対する報復のつもりなのか。
『ただ触れあって愛し合いたいだけ』と、倫史との逢瀬をそう語った彼女を、私は心底美しいと思った。それは、紛れもなく妻としてではなく、ひとりの女としてそう思わされてしまった。
しかし、倫史と未知華の関係にどこか現実味を感じられず、彼女への憧れを抱く一方で、強い敗北感が生まれるのを感じた。私とは正反対の華やかで美しい容姿を持つ彼女に対して、私は女として内面の魅力も及ばないことを知らしめられ、打ちのめされてしまったのだ。
この感情を、世の中では嫉妬というのかもしれない。自分の及ばない圧倒的な存在が目の前に現れた時、相手を羨まずにはいられない。羨望は、時として憧れを軽く飛び越え、憎しみに形を変えて矛先を相手に向ける。「私がこんなにも強い敗北感と恥を感じてしまうのは、その存在がいるせいだ」と、その足を引っ張って引きずり降ろしてやりたい欲望に支配される。そのどす黒いどろどろとした感情は、心にべったりとこびり付いて離れない。
未知華にその魅力がなければ倫史が唆されることもなかったのに。昨年のクリスマスイブも倫史と母の命日を迎えていたのに。幼い頃の夢を見ることもなかったのに。今、私がこんな思いをすることもなかったのに……。
まるでヘドロのようなその感情は、「未知華のせい」をどこまでも広げ、私の理性の世界を侵食していく。
倫史の浮気を疑い始めてから、私は、「加賀原の者に露見しないように、いかにこの事態を収めるか」ということに注力してきた。
未知華と個人的に話をする機会を設けたのも、事を荒げず身を引いてもらうためであり、そのためにも自分のやったことに罪の意識を持ってほしかったからだ。
いや、罪の意識を持ってもらいたかったのは、幼い頃の彼女を憶えていたからか。弁護士の染谷氏を送り込んで、彼女が倫史の職場から去るよう圧力を掛けたのは、彼女が「あの子」だったから……。
どちらにしても、彼女が「すみません。すぐに別れます」と言ってくれれば、それで良かった。染谷氏が慰謝料の話をちらつかせたのも、その言葉を導くためだ。
私は、加賀原の娘で倫史の妻で、理性と品性のある女でなければならない。彼女の愛の話なんて聞くつもりはなかった。私と倫史との間にある温度が冷え切っていることを改めて確認するつもりもなかった。
夫に浮気された妻は、どこかの時機に、それが愛に基づくものでなかろうと、嫉妬に飲まれるようになるのだろうか。
ああ、身体の中から腐臭が漂ってきそうだ。
いつの間にか、息を止めていたことに気が付き、呼吸をしなければと顔を上げると、未知華はまるで「その顔が見たかったのよ」と言うかの如く、妖しげな笑みを浮かべていた。
(つづく)
つづきは、こちらから↓
第一話は、こちらから↓
いつも応援ありがとうございます🌸 いただいたサポートは、今後の活動に役立てていきます。 現在の目標は、「小説を冊子にしてネット上で小説を読む機会の少ない方々に知ってもらう機会を作る!」ということです。 ☆アイコンイラストは、秋月林檎さんの作品です。
