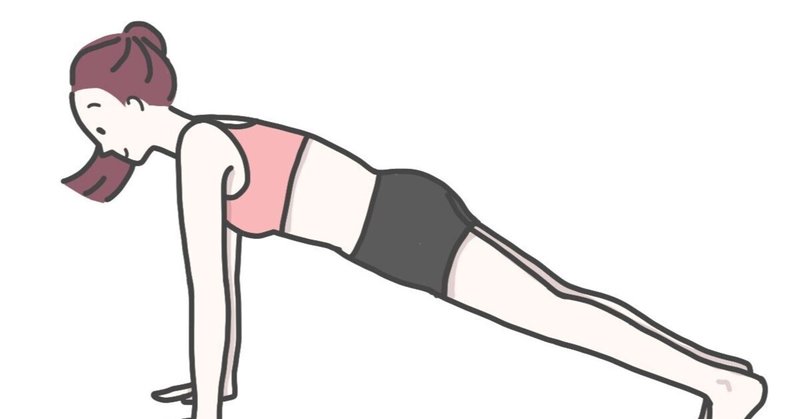
プランクポーズとは?|体幹を鍛える基本となるポーズを解説
「プランク」という用語は、体幹を鍛える上でよく耳にする言葉だと思います。
皆さんは、体幹に自信がありますか?体幹があまり鍛えられていない人は、プランクポーズをとると、お腹がダランと下がってしまったり、お尻が上がってしまったりしてしまいます。
本来のプランクポーズは、頭頂から踵まで一直線上にあるのが理想です。
また、皆さんは「体幹」とは何か分かりますか?
体幹とは、身体の頭と四肢(両腕・両脚)を取り除いたところ、いわば、胴体のところをいいます。プランクポーズは体幹の中のインナーマッスルを鍛えることに最適なポーズとなります。
今回は、体幹を鍛える基本となるプランクポーズの取り方のコツなどを解説していきます。

プランクポーズ
〇サンスクリット語:ファラカーサナ(Phalakasana)
クンバカーサナ(Kumbhakasana)
〇日本語:板のポーズ
〇英語:Plank Pose
※Phalaka…板
Kumbhaka…水瓶、つぼ⇒息を止めること
このポーズで息止めを行うところもあることから、名前の由来となりました
〇ジャンル:アームバランス
効果
①体幹を鍛える
②腕、手首、背中を鍛える
③持久力を向上させる
④集中力を高める
強化/ストレッチされる筋肉
〇強化される筋肉
…・体幹のインナーマッスル
→脊柱起立筋、多裂筋、腹横筋、腸腰筋、骨盤底筋 など
・お尻の筋肉
・上腕三頭筋
関節/身体の動かし方
〇肩関節:屈曲/外旋
〇肘関節:伸展 ←伸ばしすぎないように注意しましょう!
〇膝関節:伸展
やり方
①(イン)四つ這いの姿勢を整え、両足のつま先を立てる
②肩の真下に手首という位置を変えないように、脚の付け根が伸びるところまで両足を片方ずつ後ろに引く
③(キープ)両足を揃えて、目線は斜め前の床を見る
④頭頂から踵まで一直線上になるようにし、この姿勢で3~5呼吸キープする
⑤(アウト)両膝をつき、四つ這いの姿勢へと戻っていく
ポイント
①体幹を意識し、頭頂から踵まで一直線上になるようにし、頭頂とかかとで引っ張り合う意識を持つ
⇒体幹を意識するために大切なことです。
お腹が下がったり、お尻が上がったりしたまま、ポーズを取り続けても体幹は鍛えられません。しっかりとしたアライメントでポーズをとることで、正しい効果を手に入れましょう!
②肩の真下に手首をきちんと置き、手のひらで床を真下に押し続ける
⇒肩に体重を乗せると、体幹に力が入りにくいです。
手のひらで床を押すことによって、前鋸筋(+外腹斜筋)が働き、体幹の筋肉と連動します。手の親指の付け根を床に強く押すイメージを持つと手のひら全体で床を押しやすいです。(体験談です^^♪)
③両足のつま先は床を押し、かかとは後ろに蹴り続ける
⇒脚を強く使うために大切なことです。
④肘を伸ばしすぎない
⇒肘が伸びすぎて、過伸展という状態になってしまうと、肘を痛める恐れがあります。
脇を締めて、肘の過伸展を起こさないように注意します。
解剖学ポイント
〇手首の負担の軽減
…アームバランスのポーズでは、手首に負担をかけないようにしていきたいです。手首に負担をかけないためには、肩の真下に手首をきちんと置きましょう。その上で、手のひらの付け根に体重を乗せます。
バリエーション/軽減法/練習ポーズ
①膝をつく
⇒完全なプランクポーズがキツイ人、筋力不足の人への軽減法です。
②内ももにブロックを挟んでいく
⇒内ももに意識を向ける、体幹を意識するための練習法です。
③かかとを壁につける
⇒踵を後ろに蹴るイメージをつけるための練習法です。
④ドルフィンプランク
⇒さらに負荷をかけたい人へのUpperバリエーションポーズです。
リスク/禁忌事項
手首、肘、腰に違和感・痛みがある人は、注意しながらポーズをとっていきましょう。
まとめ
〇プランクポーズは、体幹を鍛える基本となるポーズ
〇お腹が下がったり、お尻が上がったりせず、頭頂から踵まで一直線上にポーズをとっていく
いかがでしょうか。
次回のポーズ紹介は、「チャトランガ・ダンダーサナ」を予定しています。
また、ポーズ紹介以外でも取材記事企画を進行しています!
待っていてくれたらうれしいです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました♪
Instagramもやっています。気軽にフォローしてくれたらと思います。
→@min__yoga
(_アンダーバーが2つです)
Min
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
