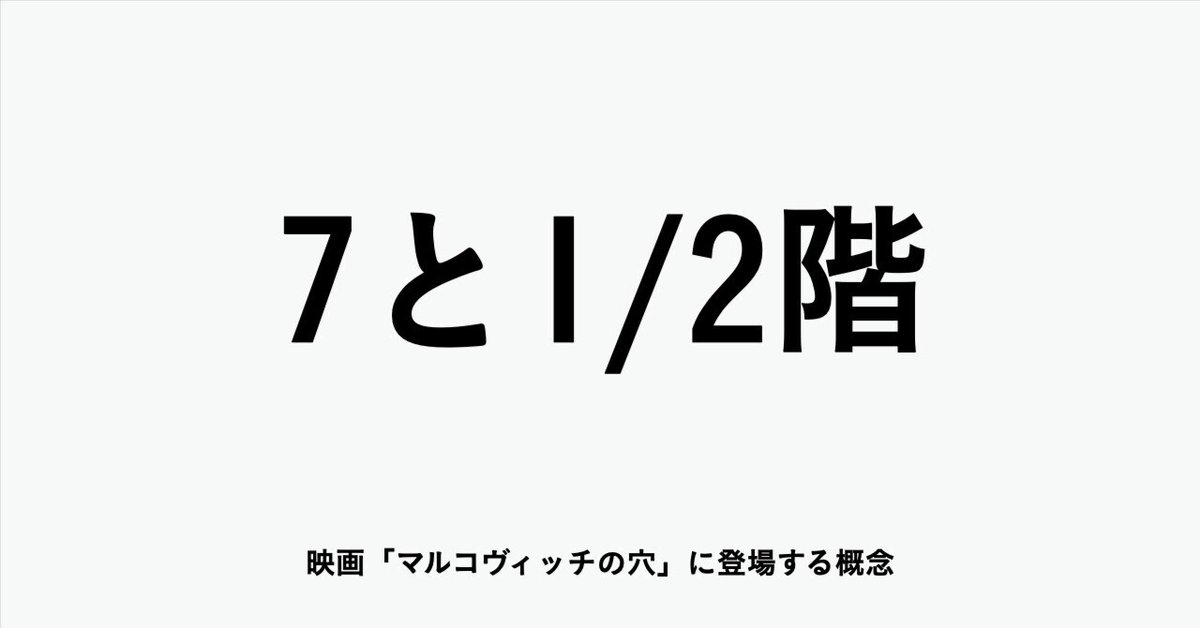
「あいだ」にひそむ欲望を見つける。
そこに何かがあるとは思わなかった
仲間内で「7と1/2階」と呼んでいるワインバーがある。正式な名前は「リーの厨房」。JR目黒駅から権之助坂を下って、さらにその脇道にある階段を下ったところにある屋根裏部屋のようなお店だ。もちろんお酒も料理も美味しい。汐留の会社に勤めていた時代、目黒方面に住む同僚たちと会社帰りに立ち寄るお気に入りの店の一つだった。階段を下って下って入店したら、こんどは店内の階段を上ってようやく席にたどり着く。この隠れ家でしかないロケーションを僕らは映画『マルコヴィッチの穴』になぞらえて「7と1/2階」と名付けた。もっともその外観は、どちらかというと『ジョーカー』のゴッサムシティに出てくる階段のようなのだが。

昔撮った写真で今更気づいたが公式にはB2階らしい
『マルコヴィッチの穴』は「とあるビルにある穴に入ると、誰もが俳優のマルコビッチになれる」という設定で人気になった1999年の映画だ。映画は見たことがなくてもスキンヘッドのマルコヴィッチが並ぶポスターを記憶している方は多いのではないだろうか(広告業界では一時期これのパロディが氾濫していた)。

100体メタルクウラ(1992年)の方が実は先
そんな狂った世界観の映画の、本筋とはあまり関係ない、だけどとても印象に残るエピソードとして7と1/2階は登場する。映画の冒頭、主人公がとある会社に面接を受けに行くのだが、その会社が7階と8階のあいだのフロアにある。そこは元々、ビルのオーナーが身長がとても低い妻のために作った専用の部屋だっという。世の中には、普通とされる規格が合わない人もいる。そんなことを思い、新しい規格を作ったという話である。
このコンセプトが素敵なのは、世界を測る物差しを変えたところにあると僕は思う。普通は7階と8階の間には何かがあると思わない。けれど1フロアというのは160~180cmぐらいの人に合わせてでできているから、130cmの人の基準で見ればそこには1/2階というのが存在している。いや、存在するべきだと、強く思ったのであろう。
コピーライターの仕事の現場でも、行き詰まりそうになったら(視点ではなく)視座を変えることを心がける。虫の目で見たら、つぎは鳥の目で見て。今ある単位を疑ってミクロとマクロを行き来する。そうすることで、新しい概念は見つけられる気がする。


多くのスキマは産業になる
実際にこうした物差しを変える発想で見つけたと思えるコンセプトが、世の中にはたくさんある。例えば「2.5次元」は、2次元キャラクターと3次元の俳優の文脈の交差を楽しむ新しいエンタメだ。「ハーフバースデー」は子どもの誕生日を少しでも早く、たくさんお祝いをしたい家族の気持ちを捉えた素敵な文化だと思う。
コロナ禍と時を同じくして世に出た「微アルコール」は、ノンアルコール飲料でもお酒でもない、飲食店の状況も鑑みた鮮やかな新マーケットの創造だった。対してノンアルコール飲料黎明期にあったキリンフリーの「ALC0.00%」は、「この小数点が見えているのは私たちだけ」という強いこだわりを感じる。
逆に物差しの目盛りを大きくしてみるとどうだろう。第四新卒。小学38年生。昭和99年。戦闘力53万。刃渡り2億センチ。見慣れた言葉の単位が狂っているだけで狂気を感じてとても良い。普通を積み重ねることで異常になった「いらすとや」のような例もあるが、何らかの異常値を含む概念の方が人は魅力を感じやすい。
コピーライターはうまい言い回しや面白いキャッチコピーを考えるよりも圧倒的に前に、あたらしい概念を見つけるべきだと強く思う。そのほうが10倍、いや100倍は世の中に価値ある提案ができるからだ。
こうして事例を眺めてみると、物差しを変える発想の中でも「あいだを見つける」のが特にオーソドックスな手法のように思う。そこに隠れている概念は何も数字に限らない。オフィスとカジュアルのあいだの「オフィスカジュアル」。新しい生活様式として広まったものでいうと、ワークとバケーションのあいだの「ワーケーション」や「リラックススーツ」もそうだろう。僕自身、とある空間にプライベートとパブリックの間のような「プライブリック」という概念を提案したこともあった。隙間産業とはよく言ったもので、ものごとが飽和した現代では、何かの「先」や「上」を見つけるよりも「あいだ」の需要を見つける方が良いのかもしれない。
あいだの気持ちを見つけてみる
思えば遥か昔から、人間には「あいだを見つける」感覚や発想があったように思う。それは主に宇宙や時間といった、とてつもなく広大なものとの関係において。
一年と雑に捉えるのではなく、春夏秋冬の4つに分けた「季節」という概念を作ること。さらにそれを6つに分けたて二十四節気と呼ぶこと。一生と雑に捉えるのではなく、寿命を3つに割って、1/3が終わる節目を元服とすること。それ以降を「大人」という概念で呼ぶこと。昼食と夕食の間に「お八つ」という時間帯を作り、エネルギーとこころの休息を摂ること。広大すぎる自然と世界。無限にも続くような時間を生きる中で、人は自然とそういった発想をしていったのだと思います。単位を刻むことで生活が豊かになる。体感の解像度が上がっていく。
翻って現代の事例の多くは、単なるマーケティングの産物なのかもしれない。けれどあたらしい物差しを持ち寄って、概念を作り変えることが生活を豊かにするのもまた事実。おそらく人間にはAともBとも言えない、白黒はっきりつかない「あいだ」の気持ちがとってもあるのだ。
複雑になりすぎた社会において、物事は様々な単位や言葉で規定されている。それをそのまま受け入れるだけでは、脱出口が見つからない時が多々ある。細かく刻んであいだを取るのか、逆に極限まで引いて大きくするのか。そのどちらでも良いのだけれど。行き詰まった時や生きづらさを感じた時。既存の単位を疑って物差しを変えてみると、世界は少し違って見えてくるのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
