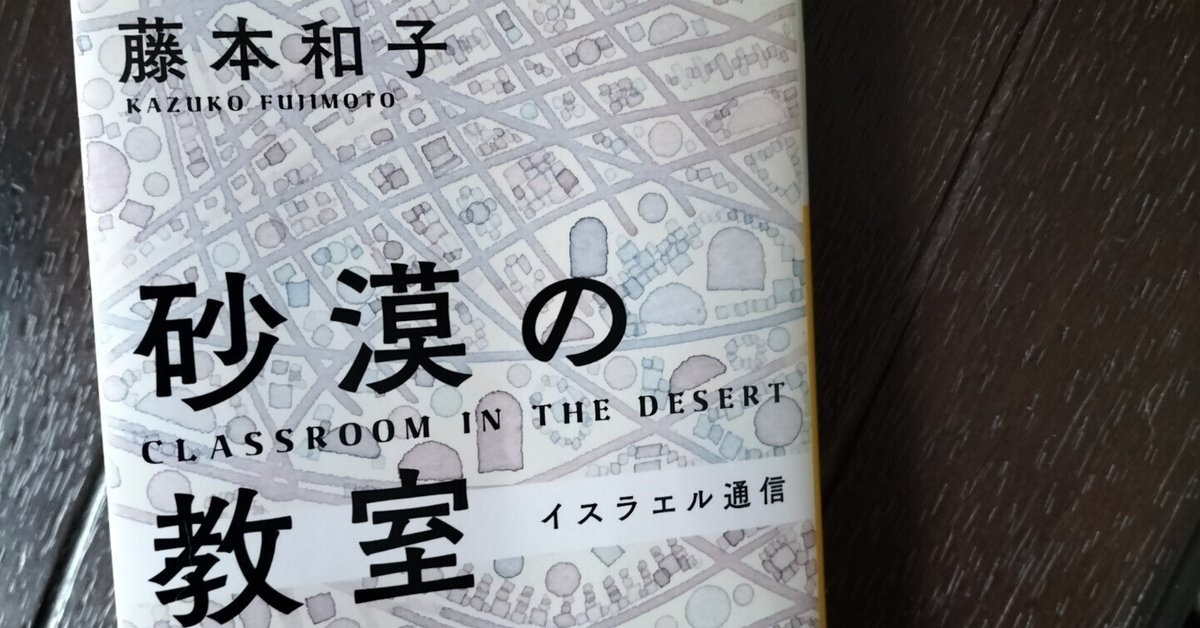
藤本和子『砂漠の教室―イスラエル通信』河出書房新社
ブローティガンやトニ・モリスンの名訳で知られる藤本和子がイスラエルに滞在したときのエッセイ。読む前から重い本だろうとある程度は予想していた。またイスラエルが狂気のような勢いでガザ侵略をつづけているいま、イスラエルについての本を読んでどう感じるのだろうという懸念も少しあった。
この本は大きく3つのパートに分かれる。最初の部分「砂漠の教室」は藤本がヘブライ語を学ぶためにイスラエルにある学校に短期で留学したときの体験記だ。粗末なホテルに滞在しながら、昼間はそこで開かれる教室に参加する。生徒は世界各国から来ていて、年齢もさまざまだが、出自や動機もさまざま。神経性の下痢になる女性やら、いつも手をつないでいる仲良しの夫婦やら、強制収容所を生き延びて腕に番号の彫りものがある老人やら。しかしこの学校での体験記は意外なほど短かったし、かなり軽かった。肩すかしされたように感じた。(また、あまり時間をかけなかったのか、名翻訳者のはずなのに文章がやや荒っぽいとも感じた。主語が何かわからない文があるなど。)
第2のパートはイスラエル滞在中のエッセイ。銀行で口座を開いたり(通帳をなかなか作ってもらえず、「銀行を信頼せよ」と何度も言われる)、小さい子どものいる家庭を訪問して自身の不妊治療の思い出がよみがえったりする。また、意外にもイスラエルの料理のレシピがいくつかあったりもする。
しかし最後のパート、「なぜヘブライ語だったのか」は重かった。学校の体験記が肩すかしなほど軽めだったが、ほんとうの重さはここにあったのだ。そもそもなぜ藤本がヘブライ語という、いまでは使われていない言語を学ぼうと思ったのか。彼女の夫はユダヤ系アメリカ人だからそのせいということもあるのだろうが、その理由は彼女自身の考えから出ていた。ここで何度も触れられるのが、朝鮮と日本とのことだ。引用されるのは、森崎和江の「二つのことば・二つのこころ」という文章だ。
森崎は朝鮮に生れて戦後、日本に来た在鮮日本人二世である。彼女にとっては日本に「来た」という感覚なのだが、日本人たちは彼女が「帰ってきた」と疑いもなく思う。なぜなら彼女は日本人だったから。朝鮮で生まれて育った彼女が自分たちとは違う精神構造を持っているなどとは想像もしない。つまり彼ら日本人は同化する・させるのは得意だが、異なるものを認めようとしない。想像できないのだ。
藤本はこの森崎の違和感に似たものを自分にも感じている。彼女はよその国に旅行者としているとき、「あってはいけないところに自分のからだがある」と感じてしまう。その国の言語も精神も自分はまったくわかっていないのにここにいる…と感じるのだ。彼女はホロコーストを体験したユダヤ人に対しても、同じように感じてしまう。旧約聖書以来の苦難の道を歩むユダヤ人のことを自分は理解できていない。少しでも理解したいと思った一歩がヘブライ語を学ぶことだった。
「わたしは、たとえば、朝鮮語を学ぶべきだと、頭では知っている。けれども、それはおそろしいことだ。学んだところで、いまのわたしになにができるのか。わたしたちのような歴史を背負うものが学びうるのか。学ぶことが、その言語を母国語とする相手を傷つけることにならないという保証があるのか。」
読者のわたしはこの感覚が少しはわかる。特に朝鮮語については、そのような躊躇いはたしかに自分にもある。「いつまでも過去にとらわれていてはいけない」とか、「人間って言葉や文化は違っても通じ合うところは多いよね」などという気楽な考えはとても持てない。藤本は、パートナーがユダヤ人であることを考えれば、ユダヤ人に関してのこのような葛藤は個人的にも強かっただろう。だから勇気を出して1歩を踏み出し、ヘブライ語を学ぼうとした。短期の語学留学などでは何も学べないということは覚悟の上で。その勇気と比べたら自分はまったくダメな人間であると痛感するばかりだ。そんな怠惰な自分ができるせめてものことが、この本を手に取って読むこと、この本を覚えておくこと、なのかもしれない。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
