
コンビニの魔女
少し前のことだけど、ミリーは自分が本当は魔女であったことを思い出した。
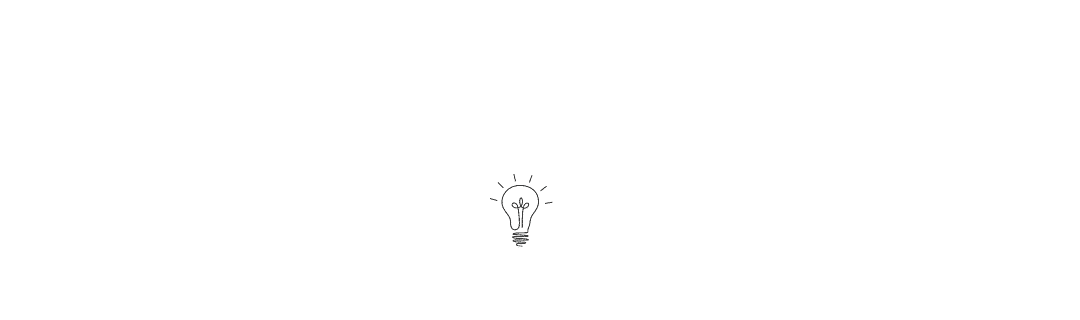
どこにでもいるような「普通の女の子」だったミリー。
毎朝、早すぎもせず遅すぎもしない時間に起き、満員の電車に乗って勤めに行く。 昼間はパソコンのキーボードをパチパチと打って、時間がくればパソコンを閉じ、ときどき大きな街に立ち寄って洋服屋や雑貨屋をのぞく。
そんな感じで、同じ日々が過ぎていく。
「どこか遠くの、別の場所に行きたいような気がする。だけど実際、私はどこに行きたいんだろう?」
大きな街の片隅で、そんな思いをぼんやりと抱いた、ごく普通の女の子。
それがミリーだった。

それが、ある日突然、ふと、なんの前触れもなく、自分が魔女であったことを思い出したのだ。
自分には、何か特別な力がある。
誰かにそんな風に言ってもらったことなんて一度もないけれど、
ひそかにそう思うことがあった。
「何よ、ばっかみたい」
そして、そんな風に思った後、ちょっとだけ自分が嫌になるのだった。
だけど、それはバカげたことではなかったのだ。
ミリーは、本当は魔女だった。
人生のどこを切り取っても平凡だったミリーだけど、これからは自分の魔法で人生を切り開いていける。これからの人生、なんだってできるのだ。
ミリーはすぐに勤めていた会社を辞めることを決め、そして本当に辞めてしまった。

「君には、何か特別な力があるね」
バックヤードの丸椅子にミリーを座らせながら、フクロウ氏はそう言った。
あれから、1ヶ月ほど経った。
この1ヶ月、本当に色々と考えたけれど、ミリーは自分の魔法を見つけることができなかった。
「魔女になる方法」とか「自分の魔法を見つける方法」なんて、インターネットで検索したってでてくるものじゃない。
どんな風に探せば良いのかも、まず何から始めれば良いのかも分からなかった。近所に「魔女やってます」って人でもいれば良かったのだけど。
焦り(なにせ魔法を見失った)と、生活の不安(なにせ仕事を辞めてしまった)で縮こまったミリーに声をかけたのが、フクロウ氏だった。
フクロウ氏は、高速道路の入り口の近くにあるコンビニエンスストア「よりどりマート」の店主だ。
私、本当は魔女だったんです。
ミリーは、この人になら言ってもいいかも知れない、と思った。
フクロウ氏なら、ミリーの魔法のことを、笑わずに聞いてくれるかもしれない。魔法を見つけるためのヒントをくれるかもしれない。
だって初めて「ミリーには何かある」ことを見抜いてくれた人なのだ。
真夜中に迫る時間帯。
店のあたりは確かに、夜の空のように静まりかえっていた。
だけどコンビニの中だけは、世間の空間から切り取られたみたいに、蛍光灯の明かりとせわしなさが人々を迎え入れる。
レジ音の「ピッピ」やレンジの「ピー」は絶えずなり続け、「ガサゴソ」とあちこちで商品が手に取られ、「ダンッ、ダンッ」と段ボール箱が開けられ、そこに「いらっしゃいませー」や「ありがとうございましたー」の声も加わる。
バックヤードの扉の隙間から、スタッフにあれこれと指示を出すフクロウ店主はまるで、それら全てを束ねる指揮者のようだ。
ミリーは、思い切って口を開いた。
「あの、私…」
「君はまだ、自分自身を模索しているね。君に何ができるか分からないけれど、それが見つかるまで、うちの店で働いてみなさい」
ミリーの言葉を遮り、フクロウ氏は、何か白い布のようなものを差し出した。
受け取ってみると、それは「よりどりマート」の制服の、白いジャンパージャケットだった。
「はい」
ミリーは小さく頷いた。
行くあてのない、孤独なアラサー女にとって、目の前に見える確かな道は、これしかないのだ。
自分の魔法を信じてくれる人が、一人でもいる。
郊外にある何の変哲もないコンビニエンスストア。
数多くある中の一軒にすぎないその店が、最初の足がかりだった。
サポートありがとうございます(*^^*)
