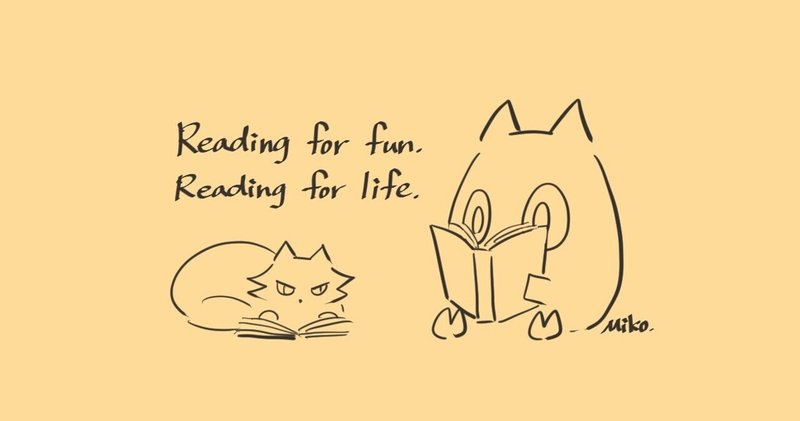
終わらない女たちの哀しみ エィミ・タン『ジョイ・ラック・クラブ』
人の苦しみ・悲しみを「なかったこと」にするのは意外と簡単だと思う。語らない、それだけでいいのだ。語ることによって過去に命が与えられ、受け継がれていく。エィミ・タン氏が描いたこの物語は1989年にアメリカで出版されるや否や、大ベストセラーとなったという。その要因の一つとして、フィクションではあるが、多くの女性がこう思ったからではないかーーー「これは私の物語だ」と。2012年公開の映画『少女は自転車に乗って』(※1)、2019年出版の小説『82年生まれ、キム・ジヨン』(※2)よりずっと前に、女たちの声が語られ、可視化され、命を吹き込まれた作品だった。
『ジョイ・ラック・クラブ(The Joy Luck Club)』は、1940年代終わりに中国からアメリカに移住した女性たちとその娘たちの物語。サンフランシスコに移り住んだ女性たちが現地で結婚し、それぞれ娘が生まれる。女性たちは祖国で苦しい生活を送っていたが、辛さを忘れて食事をし、麻雀をしながら語り合う小さな集まりを持っており、それを「ジョイ(喜)・ラック(福)・クラブ」と呼んでいた。その集まりをサンフランシスコでも行うようになり、そのメンバーとその娘たちが、それぞれの故郷や母親、結婚など、家庭のエピソードを語る構成となっている。
この本の感想をネットで拾い読みしていたとき、どなたかが「内容はブログのようだ」と仰っていた。その通りで、アメリカで育った娘たちの語りは「毒親」への苛立ちやへきえきを吐露したものである。迷信、ジンクス、偏見、無意味にしか思えない慣習の押し付け。今でこそそこら中で、ブログ、エッセイ等で取り上げられ、多くの人が「ああ、わかるわかる」と共感できる環境にあるが、出版当時にそれほど多くの人が共有できていたとは考えにくい。特にアメリカでの中国人というマイノリティなのだから。
中国は私にとって縁もゆかりもないが、ジョイ・ラック・クラブのメンバー(娘たちの母親たち)たち、またその母親たちのエピソードは凄まじく残酷だ。男たちの横暴。レイプ。セクハラ。子供ができないのは夫が妻に触れないからなのに、「わたしの息子と寝たくないというなら、こっちもおまえの衣食の面倒はみないからね」と妻を悪いと決めてかかって頬をぶつ姑。「女が結婚から逃れて復讐する道はただ一つ、自殺しかないっていいますから。」(307頁)
巻末の解説では、「実際、アメリカで生まれ育ったエィミ・タンから見ると、母親たちの物語は、神話かお伽話のように遠くに感じられるのだろう」(393頁)とか、「・・・富豪の妾となった後自殺するアンメイ・シューの母親の悲劇は、中国人が大事にする翡翠(ひすい)のような美しい透明感がある」(394頁)とあるが、美しいどころか悲劇であり、お伽話どころか日本でも現在も変わらない状況だ。「月の仙女」のエピソードで、インイン・セント・クレアは、子供の時、ずっと仙女にお願いしたかったことを告白する。「私を見つけてください・・・」と。少なくともアジアでは、ずっと女たちが声なき存在であったことをタン氏は知っていた。だからこそ30年経った今でも胸打たれるのだ。
本作には、アメリカの価値観と中国の価値観のぶつかり合い、母と娘だからこそのいさかいとそれでも失われない愛情、故郷の国への特別な思いなどたくさんの要素が盛り込まれ、理屈では説明できない心の機微が鮮やかに描かれる。作品は序章でジンメイ・ウーの不安から始まるが、ラストの展開にはカタルシスがあった。アメリカと中国のルーツを持つタン氏の傑作である。
『ジョイ・ラック・クラブ』引用は全て小沢瑞穂訳(角川文庫版、1994)より。
※1 チョ・ナムジュ著、斎藤真理子訳、筑摩書房。
※2 ハイファ・アル=マンスール監督作品。 ちなみにこの映画は劇場で観たが、エンドロールから涙が止まらなくなり、目の下が落ちたマスカラで真っ黒になって困ったことがある。
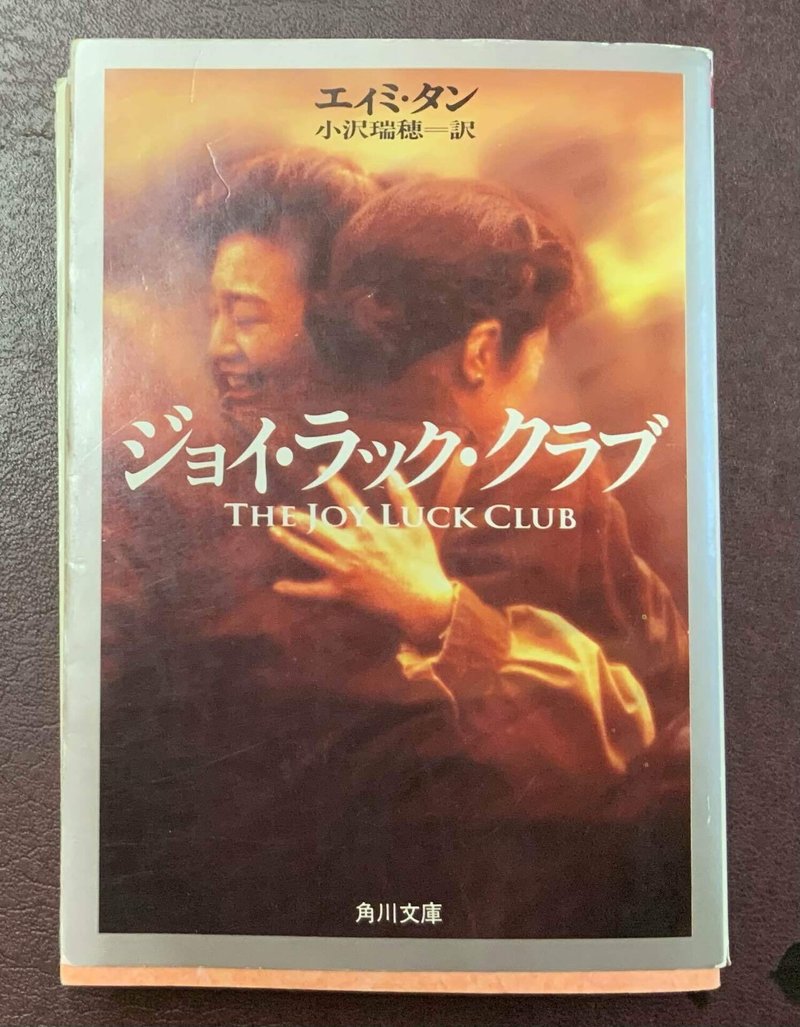
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
