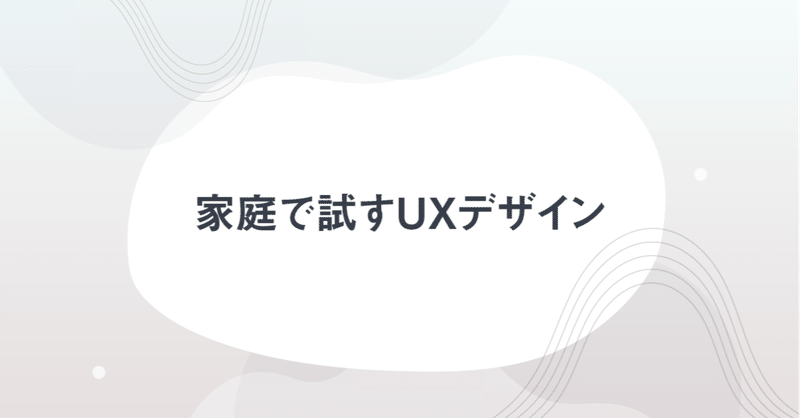
家庭で試すUXデザイン
体験の設計は特別なものではないと私は考えています。例え大学で学んでいなくても、業務として行っていなくても、それを実践する機会は日常のどこからでも得られるはずです。
例えばどんなことでしょうか?
* 家族が靴下を床ではなく洗濯籠に入れる設計
* 3-5歳のこどもが自分で配膳できる設計
* ホームスクーリングに慣れるための設計
わたしは小さな子どもがおり、家族で住んでいるためこのような例を挙げましたが、こういった事は一人暮らしでも、明日の自分のためにできる設計です。
思っているのと違いますか?
仕事に近いところで体験を設計する
ではもう少し仕事に近いところでの体験設計を見てみましょう。別にプロダクトに関してユーザーリサーチもカスタマージャーニーマップも作る必要はありません。まず自分のまわりの仕事に関するペインを自分の設計で快適にしてみましょう。
例えば
「在宅勤務で家の電気をつける作業で集中がきれる」
「オンラインミーティングに遅刻してしまう」
「メンバーに判断を仰ぐとき、早く返信してもらう工夫」
なども体験の設計です。
UXとはシステムを通した体験設計
「システム」というのは何もデジタルである訳でもないですし、また「ネットサービスでなければならない」訳でないハズです。ですよね?(不安)
11ページ参照のこと
実際にわたしが行った家庭での体験設計
ではここからは私がどのように設計したかを見ていきましょう。
わたし自身、正確にUXを学んだことはなく書籍や仕事の中で実践したり、専門家の人に話しを聞くなどして独学、独自解釈のオンパレードです。不安なところしかありません。しかし、免許を貰うまでその業務を行わない。ということもできません。やっていきましょう。
家族が靴下を床ではなく洗濯籠に入れる設計
子どもたちは帰宅したあと靴下を脱ぎたがるのですが、玄関やソファにぽーいと靴下を抜いだままにしてしまいます。
その度に「これは誰の?」「はーい」「じゃあ、洗濯機に入れてこよう〜」という流れを繰り返していました。
本筋とは違いますが、この時、親がかわりに洗濯機に入れる作業をしてはいけません。
本人の管理問題で被る不利益は、関係者が対処していては本人が課題と感じず根本的な対処をする動機がないからです。(アルコールなどの依存症に対しても関係者へのアドバイスでよく言われるそう)
ここでの不利益は「お気に入りの靴下が明日履けない」です。
しかし、もっとラクをしたいです。
わたしがソファでくつろいでいる時に靴下を発見することで、「モード母親」に切り替えるのは少し面倒なのです。
靴下を脱ぐときを分解する
When / いつ:帰宅時
Where / どこで:リビング周辺
Who / だれが:3-5歳の幼児
What / なにを:靴下を
Why / なぜ:未検証
How / どのように
この設計は非常に簡単ですので分解を雑に行ってもいいでしょう。Whyに至っては未検証です。
帰宅時のフローに組込む
我が家では帰宅時したとき、
1. 郵便物と荷物を降ろし
2. 靴を脱ぎ
3. 手を洗い
4. バッグ、コートや帽子をかけ
5. 荷物のアンパックとゴミ分類
6. そしておおまかな片付け
7. 自由時間へ
という流れを経ているケースが大筋です。子どもが行える範囲は主に1-4となります。この部分に靴下を洗濯機に入れる。というタスクを追加し一連のフローとしてしまうのです。
これであれば私はまだ「母親モード」ですので、スイッチングコストもありません。座ってもいないので活発なサポートも可能です。
1. 郵便物と荷物を降ろし
2. 靴を脱ぎ
3. 靴下を洗濯機に入れる ← NEW!
4. 手を洗い
5. バッグ、コートや帽子をかけ
6. 荷物のアンパックとゴミ分類
7. そしておおまかな片付け
8. 自由時間へ
洗濯機は洗面所と同じ部屋に置かれているので導線としても無理がありません。

フローを導入する
ではこれらを子どもたちに導入する施策はどうでしょうか。変えるのが簡単なのは「環境 > 自分 > 他人」です。今回は他人に行動を変化させるので少し大変そうです。
とはいえ、ここは母親という立場があるので簡単ですね。帰宅時に号令をかけるだけです。
「ただいまー(おかえりー)」
「はい、靴ぴったんこしよーねー」「上手ねー」
「靴下は洗濯機ね」
「はい、手を洗おうね」
「抜いだ服とリュックはどうするんだっけ?」
という声かけを一連の流れに合わせて行うのみです。
なるべく保育園(幼稚園)と設計を合わせておくのも子どもたちに混乱させず「靴を脱ぐ家屋に入る場合の習慣」として無意識下の習慣にしておくのが良いでしょう。
これまたUXとは別のテーマですが、子どもへの習慣定着は
* 自我が芽生えるまえに
* 適切な発達タイミングを知って
行うのが「教えやすい」タイミングだなと感じています。
指しゃぶりなどは自我が芽生えるまで放置していると「辞める事由」を本人が持つまでやめさせるのは困難です。(実体験)
またトイレトレーニングなどに顕著ですが、膀胱の容量、脳へ伝達できるだけの発達、そして発話可能であるという条件が揃わないうちに行ってもお互いがストレスを感じるだけという結果になってしまいます。(下記からの受け売り)
※ https://www.youtube.com/watch?v=BMRi2LN7OEg
ここまで行えば十分かと思いますが、もし、子どもがそれでも洗濯機に入れる行為を嫌がる(親に代行させる)などあれば、他に対策が必要です。
好子 / 嫌子の出現と消失とその強弱
この本は行動の理由を考えるのにとても役立ちました。何が作用してその行動を行うのか、また行わなくなるのかについて分かりやすいので、軽く目を通すだけでも行動や体験の観察に役立ちます。
話を戻して、では子が親に作業を代行させるケースはどのような状況でしょうか。我が家の場合は以下の二つです。
* 甘えたい ← お願いをききいれてもらう事で愛をはかりたい
* 面倒 ← 他にやりたい事があるなど、単純のその行為に対する動機がない
これらがやりたくない動機だとすれば、これ以上にやるべき動機を作ったり、解消してやる必要があります。それには子どもが対象(今回は靴下)に主体性を見出すことが必要です。
ぼやき:甘えたいだけの場合は無理に突き放さず、他の日に実践できていればば甘えさせてあげる事も良いと思います。
毎日好きな靴下を選べる
今のところはそれで主体性を作ることができるのではないでしょうか。と、すると好きな靴下を自分で選べる体験設計も適切か検討しなければなりません。
我が家ではこんな感じでその体験を提供しています。

100円ショップの紐付きのカゴに子ども二人分の靴下を入れ、玄関の荷物置きフックにかけるだけです。
これで、
✅ 子どもが靴下に主体性を持つことができ
✅ 好きな靴下が未洗濯で履けないという不利益を認識でき
✅ やりたくない動機を上回るやるべき理由を子どもが持つ
ことができたのではないでしょうか?
うちでは出来てるのですけど、オレオレ体験設計とその構造分解なので識者さまからの温かいご指摘をいただけますと嬉しいです。
高速でサイクルを回せて、しかも自分に多大なメリットがある
UXは本来、1個人だけが得られる体験のみではなく、その関係者やその他にシステムを利用する人も含めたものを指します。(で、あってます?)
しかし家庭内での体験設計はサンプリング対象が少なく、そういった意味では十分な実践とは言えないかもしれません。しかしそれはとくに問題ではないように思います。
家庭内での体験設計は、常に「カイゼン」する筋肉を養い、そしてそれが自分とその関係者に対して簡便さなど利益があれば十分ではないでしょうか。
ここでの仮説、検証、実地、考察、仮説〜を一人で行い、それを続けるという姿勢とその筋力は業務としてのUX領域でなくても幅広く役立つものだと思います。
「UXを学びたいのにその場がなくて困っている」という方は、まず自分のまわりの体験を自分でより良くする工夫をしてみるのはいかがでしょうか?
今後書くかもしれない体験周辺の設計
* 3-5歳児がこぼさず牛乳を注ぐための設計 ← 1票
* ソーダストリームのためのキッチン導線 ← 2票獲得🎉
* 脱衣所のUXD ← 1票
* 入浴中に切れたシャンプーを補充するUXD ← 1票
* こどものハミガキレッスン ← 1票
* おもちゃの所属と容量をこどもと一緒に考える← 2票獲得🎉
* バッグに絶対ハンカチを入れ忘れないようにする設計 ← 1票
* スマートスピーカーで作業を中断させない設計 ← 1票
* 仕事中に5秒で幸せになれる方法 ← 1票
* ホームスクーリングに慣れるための設計 ← 1票
* ひらがなを教える設計 ← 1票
* 幼児に対する片付けのアプローチ ← 1票
* 読み聞かせによる語彙の取得と、物語理解の使い分け ← 1票
* こどもは論理を理解できる ← 1票
* 3-5歳のこどもが自分で配膳できる設計 ← 1票
* 洗濯機で一度「すすぎまで」に設定してしまうと後から洗濯した人のタスクが完了できない問題 ← 1票
よろしければサポートお願いいたします。記事を書くモチベーションと頻度が上がります。
