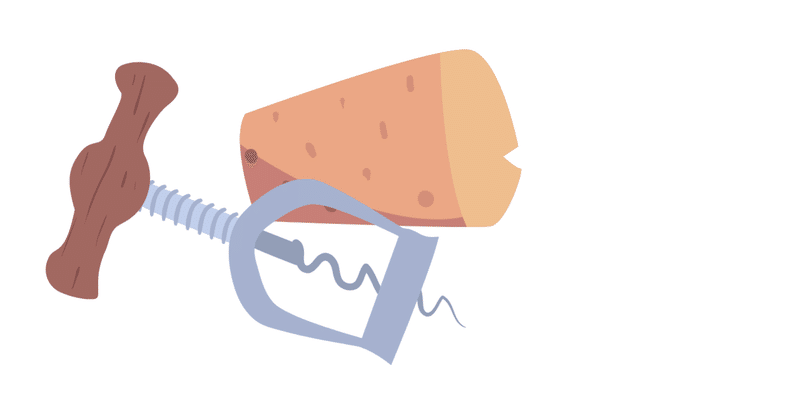
ワインコルクを再利用 箸置きに工作してみた話。 切断/断面加工で悪戦苦闘。
今回は、正月休みに?!工作してみた話です。
なんでそんなことしたの?
Amaz〇nセールでワインを大量購入しましてな。
そこで手に入ってしまった、ワインの栓:コルク。
捨てるには惜しい気がする なんか使えないかなぁ~
と思いまして。
これ。

あと、6個くらいあるんよ。
何作るの?
縦にまっぷたつに切って、箸置きにならないかなぁと。
いざ切断!

材料>
・ワインコルク1個
道具>
・カッター(刃が太めの方がいいかも)
・工作マット
あればよいかも>
・鉛筆/ペン
・定規
→切るところにアタリ(目印)をつけるため
切断 え?切れないんだけど
いざ!切断!

刃を押し込んで…ぐぎぎぎ💦
思ってた以上に、切れませんでした!!!!
刃を↓下に押しこんで切ろうとすると、コルクの弾力で押し返されて、刃が入っていきません。
困った。もう途中で投げ出そうかと思ったくらい切れませんでした💦
ぐぬぬ。そこで、試行錯誤・工夫してみることに。
切断の工夫1>のこぎりのようにカッターを動かす
刃を斜めにしつつ、前後にギコギコ動かすと、ちょっ〜っとずつ切れてきました。
だがしかし、刃がすっぽりコルクに隠れる程度まで切れたら、トラブルが。
今度は、カッターの刃がコルクの切断面に挟まっちゃって動かせなくなっちゃいました。
こんな感じ。
コルク→|刃|←コルク
コルクの圧力って、はんぱない。
刃がね、ビクともしないの。
新たな芸術作品が生まれてしまうところでした。
切断の工夫2>コルクをぐりぐりする。
パンが無ければケーキを食べればいいじゃない。
ならぬ、カッターが動かないなら、コルクを動かせばいいじゃない?!
ということで、
カッターを固定して、コルク側をぐりぐり動かす作戦に。
ぐりぐり作戦、効きます!
ぐりぐりやってるの図↓

切れた!!

表面ザラザラ💦
触ると、破片がポロポロと落ちます。
う〜む、このままだとポロポロし続けるよなぁ。断面加工した方がよさげですね。
断面加工実験1)火であぶる
ろうそくの炎🔥で断面を炙ってみることにしました。
なんでそうしたの?
・コルクの印字も焼印だし?!
・ポロポロ予備軍を焼いちゃえばいいんじゃ?
な〜んて。
道具>
・ろうそく
・マッチ(火をつけるもの)
方法>
・ろうそくに火をつける
・炎で切断面をあぶる
いざ!
🔥処理後1

🔥処理後2

あぶってると…
一部燃えました🔥
処理後2の角が黒くなってる部分が燃えた/焦げた所。
※火の取り扱いには十分ご注意ください。
あぶり加工で
・ポロポロは無くなった◎
・黒い燃えた/焦げた部分を触ると、触ると手が黒くなる💦
ですよねぇ〜。
コルクの黒い部分をティッシュで擦ったら、他にまで黒く汚れるのはおさまりました。

断面加工実験2)ボンド塗る
断面にボンドを塗って乾かすことにしました。
なんでそうしたの?
-ポロポロ部分を、コーティング、接着しちゃえばいいのでは?
なんでコレを最初にならなかったの?
-ボンド塗って、(ボンドの)表面が凸凹に固まってしまったら嫌だなぁ
と思って。
道具>
・ボンド
方法>
・切断面にボンドをぬる。
・乾くまで放置する
いざ!

塗り過ぎちゃった。
〜乾燥中〜

〜3時間後〜

なかなか乾かない💦
〜12時間後〜

もうちょい!
〜24時間後〜

乾きました!


あ… 浮いてる。
よく見ると、断面と机に沢山の隙間があります。
触るとカタカタもする。
恐れていた事態
-ボンド塗って、(ボンドの)表面が凸凹に固まってしまったら嫌だなぁ-
になってました💦
う〜む。
コルク切断面自体が凸凹+ボンド塗りすぎ かなぁ
まぁ使えなくはないから、いっか!
工作結果!

手前側→🔥あぶり加工のもの
奥側→ボンド塗り加工のもの
・🔥あぶり加工
焦げ、燃えてるの、使用時にもわかりますね。
まぁ焦げをコスコスしても、黒いの色移りしなくなったし、まぁ使えるかな。
・ボンド塗り加工
ガタツキはありますが、🥢箸置いてしまえば、固定されるので◎全然使えました。
おまけ1:コルクができるまで 調べてみた
「木の破片加工してんだろうなぁ~」程度の知識だったので、調べてみました。
原料:コルクガシという木の皮

オレンジ色部分は皮をぺローンされちゃったあと。
生息地:地中海沿岸
寿命:150~250年程度。
皮が取れる間隔:9年~12年に1回。
→1本の木から12回くらい皮が取れる。
特徴:木の皮か剝がされても木の生育に問題ないらしく。皮をはがれた木の方が二酸化炭素の吸収率がUPするんだとか。
・コルクガシの断面図
外側の凸凹部分をはがして作るんだそう。

・皮をぺローンしてる様子。

こんな大きくなる木なんだ~。
画像はWikipediaより
おまけ:コルク栓ができるまで 調べてみた
コルクの栓の作り方にも
・圧搾コルク栓
・天然コルク栓
の2つがあるんだそう。
ざっくりの見分け方としては、
つぶつぶがよく見える:圧搾コルク
つぶつぶ<木目がよく見える:天然コルク
といった感じ。
コルクマット、防音材等に使われてるのは圧搾コルクが多いんじゃないかな?知らんけど。
・圧搾コルク栓
コルクの木※の皮を粉砕して、接着剤+圧力かけてコルクの形にしたもの。
・天然コルク栓
コルクの木(コルクガシ(樫の木の一種))の皮をぺローン!ってして、コルクの形に型抜きカットしたもの。
さいごに
今回はワインのコルク栓を工作して、箸置きを作ってみました。
1番大変だったのは「切る」所。怪我等十分お気をつけくださいね。
「おまけ」にコルクの生産工程も調べてみました。
もし、コルクを見かけたら、圧搾/天然を見分けてみても面白いかもしれませんね。
ワイン買ったのに、そのコルクウンチクをこんな記事にするまでになるとは思いませんでした。
私、モノたちが「こんな工程を経て手元きたんだなぁ~」って、思いをはせるの好きなんですよね~。
お時間ある際は、原産地、生産過程を調べてみては?
まだコルクが余ってるので、次の作品もできるかも知れません?!
参考 ワインのコルク栓でアレコレ加工記事紹介
箸置きの他にも
メモはさみ、鍋敷き、コースター、観葉植物入れ? などなどありました。
ただし、コルク栓が大量に必要な作品もありますので、お手持ちの個数も考慮して選んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
