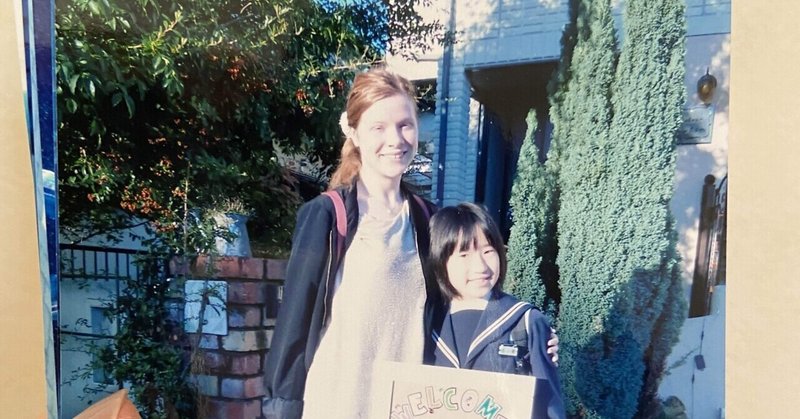
中学生が県知事賞を受賞した「ライティング術」とは?文章や読書が苦手な人でも簡単に身に付く方法をご紹介!
私はよく公言している通り、文章を書くことが大の苦手でした。
とくに中学生までは、本を読む習慣さえなかったため、文章に触れる機会はほぼ0……朝の読書タイムもふざけて絵本を読んだり、寝ていたりしていたような気がします……(本当に恥ずかしい)
そんな文章からはかけ離れた生活を送っていた私ですが、ちゃっかり夏休みの読書感動文だけは気合いが入っていました。気合い通り、毎年何かしらの章を受賞。中学3年生の時には県知事賞をいただきました。
いやいや。今振り返ると「なんで賞取れたねん」と思うわけですが、ライターになってみて考えると、自分なりに文章を工夫していたことがわかりました。しかも今の生活にも十分生きるなぁと。
そこで今回は、文章・読書嫌いな中学生がちゃっかり「県知事賞」を取った話をテーマに、過去の私が実践していたライティング術をシェアしたいと思います。
ポイント①とにかく人の真似をする

私は文章の「ぶ」の字も知らなかったため、文章を書く時は人の真似から始めました。
まずは読書感想文の優秀作品集がまとめられた冊子を読み込んで、優秀な人の書き方を真似ていました。文章の導入から、構成、締めくくり方まで。「こうやって書けば人の心が動くのか」や「悲しい時はこういう表現をするのか」などを見様見真似に真似していました。(もちろん丸パクリはしていません)
私は何かを学ぶ時、一番早い上達方法が真似ることだと思っています。スポーツでは憧れの選手の練習方法を真似たり、仕事でも仕事ができる先輩のコミュニケーション術を真似たり。
学ぶの語源は「真似ぶ」から来ているほど、新しいことを習得するには真似ることが一番早いのではないかと考えるのです。
ポイント②なんかいいの「何か」を分析する

人の文章を読んでいる時、なんかいいって感情誰にでも湧いてくると思います。私は幼いながらになんかいいの「何か」を常に分析していました。
文章の入り方がダイナミックでよかったのか。タイトルがキャッチーでよかったのか。書き手の経験が入っていて、感情移入しやすかったのか。各ページのよかったところに自分のコメントを付箋でつけて分析していました。(めちゃくちゃストイックw)
今思うとこの手法は、コピーライティングやタイトル案を作るときにも役立つ手法で、今でも文章のトレーニングに役立っています。
ポイント③FB を親身に受け入れる

読書感想文を提出して学年代表に選ばれると、何人かの先生からFBが入ります。時にはほぼ0からの書き直しを頼まれる時もありましたし、ものすごい数の赤字が入っていて泣きそうになる時もありました。(笑)
それでも、FBを親身に受け入れることを大切にしていました。
今ライターという仕事をしていても、赤字が入ることはよくあります。中には赤字がつらくてライターを辞めてしまう人もいます。しかし私は、赤字=期待されている・成長できる最高の機会だと考えるのです。
だからこそ、相手が伝えてくれた意図を真摯に受け取り、投げ出さずに受け入れてみる姿勢が大切だと思っています。
実際何度も書き直し、当時の先生と一緒に作り上げた読書感想文のおかげで、20万近く応募された読書感想文の中から1位を取ることができました。それくらい人の意見を聞き入れることは、大きな成果につながると感じています。
文章を通して皆さんの人生が少しでも好転しますように!

人生を歩む上で、誰にとっても文章は切っても切り離せない存在です。
いくら文章が嫌いでも仕事でメールは書かないといけないし、大学生なら2万字近くの卒業論文が待ち構えているでしょう。そんな時に少しでも、文章がうまくかけたら人生はきっと好転していくと思っています。
皆さんの人生が文章を通して少しでもいい方向に動くように。そんな思いを込めて、今日は生意気な中学生の私が文章のコツをシェアしてみました。少しでも誰かのためになれば幸いです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
