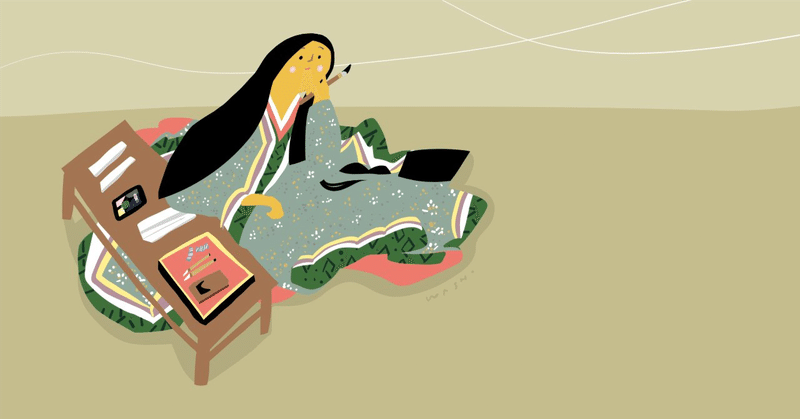
「大鏡」を読み直したくなっている~「光る君へ」のせい(いや「おかげ」だろ)。
大河ドラマ「光る君へ」。
予想以上に面白くてちゃんと消化してる(最新回の日は仕事だったのでまだ)。
「消化が早い」ってことは、それだけ「早く観たい」と思う作品ってこと。
惰性じゃあなく、本当に観たいから。
録画が溜まらないのはとにかく良い(笑)。
以前も書いたが、前作「どうする家康」が自分的にはすごくツボで、毎回楽しみにしていた。
自分史上大河トップ3に入ったくらいなので。
それもあって、正直「光る君へ」は
「まあ地味な平安時代だし。とりあえずちょっと観てイマイチだったら切るかぁ~」
くらいのノリで見始めた。
ところがどっこい……面白いのなんのって。
「史実がよく分からない」紫式部だからこそ、かなり大胆というか踏み込んだ脚色をしても許される余地がある。
そこは「みんなが(基本的な流れは)知ってる」戦国時代、というか家康の生涯を描いた前作とは正反対。
とは言え、それを(かなり力業だけど)説得力を持って成立させているのは、やはり脚本が大石静さんだからこそ。
話の進め方も、台詞回し一つとってもとにかく「手練れ」なんよ。
凡百の人には務まらない。
ラブロマンスと宮廷の権謀術数とのメリハリ。
前者は正直「ファンタジー/少女漫画/トレンディードラマ」のノリだが、それを(良い意味で)臆面も無くやりきるところがすごい。
だからこそ、ちょいちょい挟み込まれる「みんなが知ってる」エピソードが生きてくるし、その匙加減がとにかく上手い。
道長と伊周の「弓争い」とか、清少納言(ききょう)の「香炉峰の雪」とか。
どっちも「ここで来たかー!」ってニヤニヤした(笑)。
こうなると物語のどの辺で道長の「この世をば……」が来るか気になるわね。
高校の頃、「大鏡」にハマった。
比較で「栄花物語」も読んだけど、やっぱり「大鏡」の批判精神というか、少し斜めから切る視点が深い。
大学受けたときは、国文科に行って大鏡で卒論書いてその後は国語教師になる青写真を描いていたが……今では全然違う人生を歩んでる(苦笑)。
あ、高校国語教師の免許は意地で取ったけど。
そんなこんなで、「光る君へ」のおかげで、30年近くの時を経て「大鏡」を読み返したくなっている。
現代語訳でいいから、買うか図書館で借りてくるかなー。
うーん……図書館の方が「積ん読」にならなくて良い気がする(爆)。
ちなみに「源氏物語」の方は「原文では」全文読んでません(小声)。
現代語訳は誰で読んだかなぁ。
与謝野晶子、谷崎ではないはずなので円地文子だろうか(覚えてない。苦笑)。
寂聴さんも気になるが、今改めて読み返すなら角田光代さんだろうか。
そんな時間あるかなー(白目)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
