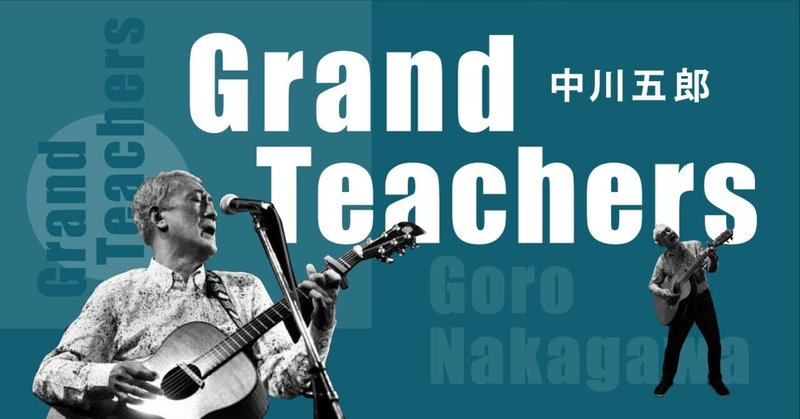
【アーカイブス#86】マイカ・P・ヒンソンが歌と音楽で届けてくれる奥深く刺激的な寓話の世界*2017年9月
この連載でマイカ・P・ヒンソン(Micah P. Hinson)のことを取り上げるのは二度目になる。最初は2014年8月、彼が通算7枚目となるアルバム『Micah P. Hinson And The Nothing』を発表した時に、「ほんとうに33歳? あまりにも渋くて老成したマイカ・P・ヒンソンの歌の世界」というタイトルで彼の音楽との出会い、彼の経歴のことなどを詳しく書いた。
その後マイカは2015年にT・ニコラス・フェルプスとのデュエット・アルバム『Broken Arrows』をBronson Recordingsから発表している。T・ニコラス・フェルプスは2006年の『Micah P. Hinson And The Opera Circuit』からマイカのアルバムや恐らくはライブにも参加し続けているマルチ・プレイヤーで、マイカにとって音楽上の重要なパートナーだと言えるだろう。『Broken Arrows』は全9曲すべてが二人で作られ、二人だけで演奏され、アメリカ各地でレコーディングされ、12インチ・レコードのアナログ盤だけでリリースされた。マイカのヴォーカルも1曲しか入っていない、ほとんどがインストゥルメンタルのアルバムなので、これをマイカのソロ作として数えるのは難しく、マイカとT・ニコラス・フェルプスの特別なデュエット作品と見るのが妥当だと思う。
『Micah P. Hinson And The Nothing』の発表から3年ちょっと、それに続く8枚目の新しいアルバム『Micah P. Hinson Presents The Holy Strangers』が2017年9月にイギリスのフル・タイム・ホビー・レコードからリリースされた。これがまたいつものマイカのアルバムと同じように素晴らしい作品なのだが、内容はいつもとはかなり違ったものになっていて、ちょっとびっくりさせられる。
ぼくがこの連載でマイカ・P・ヒンソンを紹介してから3年、この日本で彼のことが注目されたり話題になったりするような大きな動きは残念ながらまだ何も起こっていない。この素晴らしいシンガー・ソングライターが日本でももっともっと広く知れ渡る小さなきっかけになってくれることを願って、今回またマイカ・P・ヒンソンを、彼の最新アルバムのことを取り上げて書いてみたいと思う。
マイカ・P・ヒンソンが1981年2月3日、テネシー州メンフィスの生まれで、4歳の頃にテキサス州アビリーンに引っ越し、その後どんなふうに音楽の世界に足を踏み入れて行ったのか、彼のバイオグラフィー的なことは前回の文章で触れているので、まだ読んでいない方がいたら、まずはそちらを読んでみてほしい。
そしてぼくは前回の文章で、マイカはアルバムを発表するたびに、そのタイトルを『Micah P. Hinson And The Gospel of Progress』、『Micah P. Hinson And The Opera Circuit』、『Micah P. Hinson And The Red Empire Orchestra』、『Micah P. Hinson And The Pioneer Saboteurs』、『Micah P. Hinson And The Nothing』というように、『Micah P. Hinson And The ……』と付けていることに触れ、「彼が次々と新しいバンドを組んでいるのではないかとつい思ってしまうが、これは彼がその時々のレコーディング・セッションに参加した人たちにバンド名のような名前をつけているということなのだろう」と、書いた。
そして今回は『Micah P. Hinson And The……』ではなく、『Micah P. Hinson Presents The Holy Strangers』となっているものの、またまた新しいセッション・メンバーと一緒に作ったアルバムのように思える。
ところがアルバムのブックレットのクレジットを確かめてみると、「The Holy Strangers」の「Players」としてクレジットされているのは、登場順に、The Great Eyeball In The Sky、The Parents Of Either、The Man & The Husband、The Woman & The Wife、The 3 Children、The Prostitute、The Preacher、The Sons Of Manとなっている。そしてそれとは別にブックレットの次のページには「Musicians」として、Kormac(ピアノやドラム・マニピュレーション)、T.NicholasPhelps(ラップ・スティール)、Andrea Ruggerio(ヴァイオリン)、Ambrachiara Michangeli(ヴィオラ)、Ashley B. Hinson(ヴォーカル…2007年12月のロンドンのコンサートの最後でマイカが求婚し、2008年に結婚したマイカの奥さん)、Wiley T. Hinson(泣き声…きっとマイカたちの子供)など11人の名前が記されている。
つまり「Players」とは、演奏者ではなくて俳優という意味で、マイカの新しいアルバムは、さまざまな人物が登場して物語が進行していく、フォーク・オペラ、もしくはロック・オペラ的な作品、いわゆるコンセプト・アルバムとして作られている。マイカ・P・ヒンソンが「The Holy Strangers」という「オペラ作品」、「演目」をお届けするというわけだ。
『Micah P. Hinson Presents The Holy Strangers』には、マイカのオリジナル曲、トラディショナル・ナンバー、そしてインストゥルメンタルなど、全部で14曲が収められている。そして収録曲は「The Temptation」から「Micah Book One」までの前半7曲が第一幕(Act 1)、「The War(Volume One)」からラストの「Come By Here」までの7曲が第二幕(Act 2)に分けられていて、7曲目と8曲めの間にはご丁寧に幕間(Intermission)と表記されている。
そしてブックレットの曲名の下には短い筋書きのようなものも書かれている。まさにマイカの今回のアルバムは歌と音楽で綴られたお芝居だと言える。
マイカの筋書きによる「物語」を紹介しておくと、まずは大空の巨大な目玉(The Great Eyeball In The Sky)が水と水とを分かつ。そこに不妊に苦しむそれぞれの親(The Parents Of Either)が巨大な目玉に祈りを捧げ、彼らの祈りは叶えられる。そして生まれた男(The Man & The Husband)と女(The Woman & The Wife)は、共に育って大人になり、男は女に求婚して二人は結婚する。やがて結婚生活はうまくいかなくなり、男は暴力をふるったりするようになるが、奇跡が起きて二人の仲は復活し、三人の子供たち(The 3 Children)に恵まれる。その後男は徴兵され、家族を残して戦場に向かい、異国の人たちを殺戮する。男は人生の瀬戸際に立たされるが、そこで聖書と出会い、怒りと蔑みに満ちていた男の魂が救われる。
戦場で男は敵の兵士や無実の民間人までをも殺し尽くし、やがて兵役を終えて家路に着く。しかし彼の心は人を殺しまくったことで歪み、破壊されていて、途中で出会った売春婦(The Prostitute)をレイプし、彼女を殺してしまう。夫の帰りを待つ妻は地元で行われていた葬儀に参列して牧師(The Preacher)の言葉に耳を傾けていた。ふと窓の外を見ると、そこには血まみれでうわ言をまき散らしながらあたりをうろつきまわる夫の姿があった。錯乱し、わけがわからなくなった妻は、家に火をつけてすべてを終わりにしようとする。その火事で夫と三人の子供たちは亡くなったが、自分一人だけ無傷のまま生き残った妻は、列車の切符を買って自分が住むであろう最後の街へと向かう。そして男の子供たち(The Sons Of Man)が見下ろし、男の歌(The Song Of Man)が見上げて、共に最後の歌「Come By Here」が歌われる。
それぞれの歌はこの「物語」にぴったり合わせたものではなく、男と女の出会いの場面で歌われるのは「Lovers Lane」というトラディショナル曲だし、男に最初の子供が生まれた時に歌われる歌は「Oh, Spaceman」というものだったりする。そして女の最後の旅立ちに合わせて歌われるのは「The Lady From Abilene」と、マイカと関係の深いテキサスの街の名前が登場している。物語の最後を締めくくる「Come By Here」も、ぼくと同じ世代の古いフォーク・ソング・ファンにとってはジョーン・バエズやオデッタの歌でよく聞いた「クンバイヤ」と同じものだ。また「Micah Book One」では、マイカがアルバムの「物語」に合わせた散文を朗読しているし、アルバムのジャケットやブックレットには『伝道の書(Ecclesiastes)』の一節も掲載されている。
いつの時代のどこの国のどんな物語というよりも、聞く人それぞれが自由に解釈ができ、そしてさまざまなことに思いを馳せることができる、奥深くて刺激的な「寓話」を、今回マイカは歌と音楽で届けてくれたのだ。実に興味深い物語が、素朴な響きのギターやピアノ、それにヴァイオリンやヴィオラなどのストリングスで作り上げられたアコースティックなサウンドをバックに、マイカはいつものように渋く深く、どこまでも低い、「どこが36歳や!」と思わず突っ込みたくなるような老成した歌声で歌っていて、その世界の中にぐいぐいと引き込まれていってしまう。
このマイカ・P・ヒンソンの新境地を一人でも多くの人に聞いてほしいし、この異色の最新作からではなく、どのアルバムからでもいいから、日本でもたくさんの人に彼の歌の世界を堪能してもらいたいとぼくは切に願っている。
三年前にこの連載でマイカ・P・ヒンソンのことを初めて書いた時、ぼくはその記事を次のような文章で締めくくった。
「最新作の『Micah P. Hinson And The Nothing』が完成する前、彼はカタロニアへの旅の途中でひどい自動車事故にあって、今も杖なしでは歩けないと伝えられている。とても心配だ。一日も早い完全な回復を、そして精力的な音楽活動の再開を心から願っている」
彼のホームページを確かめて見ると、どうやらその傷も全快したようで、今は精力的にあちこちをツアーして回っている。そのうち日本にも絶対に歌いに来てほしいが、その前にとにかく一人でも多くの人にマイカ・P・ヒンソンのことを、彼の素晴らしい歌のことを知ってもらいたいと、ぼくはこれからも機会を見つけてせっせと書いていこうと思っている。
中川五郎(なかがわ・ごろう)
1949年、大阪生まれ。60年代半ばからアメリカのフォーク・ソングの影響を受けて、曲を作ったり歌ったりし始め、68年に「受験生のブルース」や「主婦のブルース」を発表。
70年代に入ってからは音楽に関する文章や歌詞の対訳などが活動も始める。90年代に入ってからは小説の執筆やチャールズ・ブコウスキーの小説などさまざまな翻訳も行っている。
最新アルバムは2017年の『どうぞ裸になって下さい』(コスモス・レコード)。著書にエッセイ集『七十年目の風に吹かれ』(平凡社)、小説『渋谷公園通り』、『ロメオ塾』、訳書にブコウスキーの小説『詩人と女たち』、『くそったれ!少年時代』、ハニフ・クレイシの小説『ぼくは静かに揺れ動く』、『ボブ・ディラン全詩集』などがある。
1990年代の半ば頃から、活動の中心を歌うことに戻し、新しい曲を作りつつ、日本各地でライブを行なっている。
中川五郎HP
https://goronakagawa.com/index.html
midizineは限られたリソースの中で、記事の制作を続けています。よろしければサポートいただけると幸いです。
