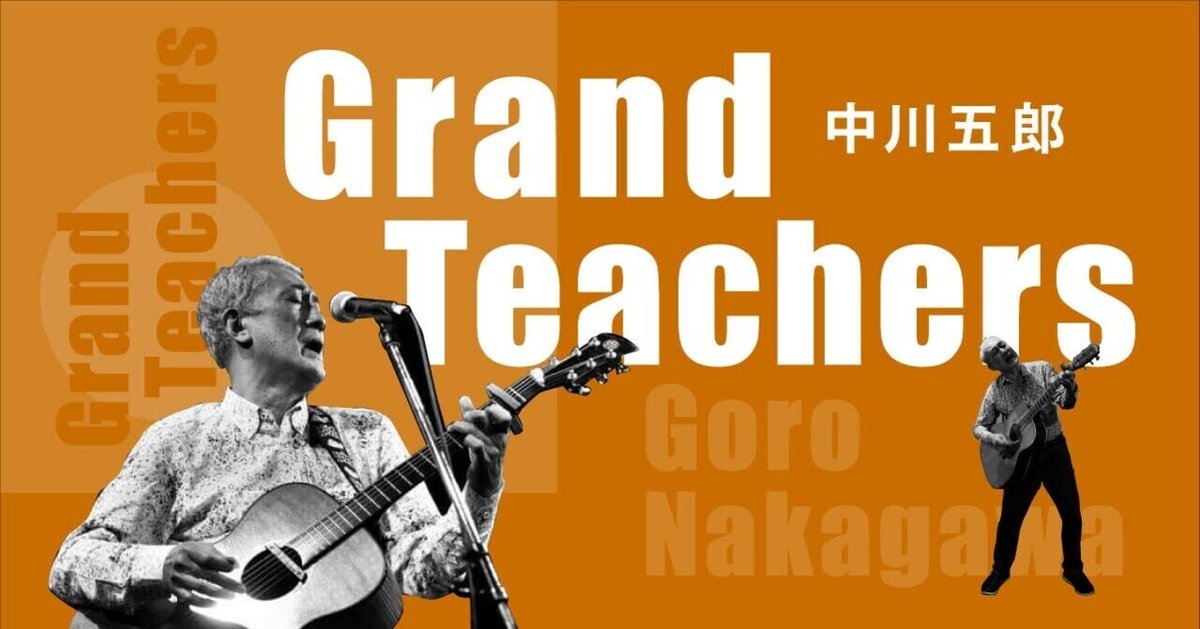
【アーカイブス#33】レナード・コーエン Old Ideas *2012年2月
ぼくにとっての音楽のティーチャー、だからぼくの子供の世代、あるいはもっと若い世代にとってはグランドティーチャーとなるミュージシャンを取り上げていろいろ書くというのがこの連載のメイン・テーマなので、やはりこの人のことは避けて通ることはできないだろう。レナード・コーエン(Leonard Cohen)。1934年9月21日、カナダのモントリオール生まれで現在77歳。本格的に歌い始めてから45年以上。そのレナードが今年の1月の終りに新しいアルバム『オールド・アイディア/Old Ideas』を発表した。今回はそのアルバムのことを書いてみたい。
ソニー・ミュージック・ジャパンから発売されたこのアルバムの日本盤(SICP-3425)のライナー・ノーツで菅野ヘッケルさんが書かれているように、レナード・コーエンはアルバムの発表ということでいえば、驚くほど寡作なミュージシャンだ。1968年の初めに『Songs of Leonard Cohen』でアルバム・デビューしてから44年目、今回の『Old Ideas』が12枚目のスタジオ録音アルバムということになる。44年間で12枚。平均するとほほ3年半に一作ということになるが、もちろんレナードは同じ間隔で新作を発表しているわけではなく、続けて登場して来る時もあれば、うんと長いインターバルの時もある。『Old Ideas』は、前作となる2004年の『Dear Heather』以来8年ぶりだ。レナードはベスト・アルバムだけでなくライブ・アルバムも最近立て続けに発表しているので、それほど久しぶりのアルバムという気がしない。
8年ぶりのスタジオ録音アルバム。そのインターバルの長さはレナードがいかに曲作りに、そしてアルバム作りに時間と労力を注ぎ込んでいるのかを証明している。一方ではまるで義務のように毎年新作アルバムを発表するミュージシャンもいて、その人はミューズの閃きや新しい音楽のアイディアに事欠かないのだろうし、それはそれでまったく文句を言う筋合いはないのだが、しかし『Old Ideas』のように、時間に時間をかけ、詩や曲想、アイディアを練りに練り、推敲に推敲を重ねて丁寧に作られた作品を耳にしてしまうと、音楽やアルバム作りに対する姿勢の違いというか、志の高さの違いのようなものをどうしても感じずにはいられなくなる。
再び菅野ヘッケルさんの日本盤のライナー・ノーツによると、レナードが2004年の『Dear Heather』に続く新しいスタジオ録音のアルバム制作に着手しという情報が流れたのは、2006年のことだったと書かれている。もちろんその時にはアルバムの収録曲もじっくりと書き上げられて、大部分揃っていたのだろう。そしてレナード自身も2007年9月に新しいアルバムを発表する予定だとあるインタビューで語っていた。アルバムの録音がどこまで進められたのかはよくわからないが、結局そのアルバムが登場してくることはなかった。その後2008年からスタートしたワールド・ツアーのバンド・メンバーと一緒にレコーディングをし、いったんはそのアルバムを完成させたが、それも日の目を見ることはなかった(ただし今回のアルバムにはレナードがツアー・バンドのザ・ユニファイド・ハート・ツアリング・バンドと一緒にレコーディングしている「Darkness」という曲が1曲だけ収められている)。
『Dear Heather』の後、レナードが新しいアルバムのためのレコーディングを行なってはそれを反故にし、やり方を変えて再度挑戦しては、またまたそれを反故にしてやり直すなど、大いに苦闘したであろうことは『Old Ideas』のプロデューサー・クレジットからも窺い知ることができる。
アルバムには10曲が収められているが、ブックレットには「OLD IDEAS A Record by Leonard Cohen with PATRICK LEONARD, ANJANI THOMAS, ED SANDERS and DINO SOLDO」と書かれていて、レナードと一緒にアルバムを作ったプロデューサーとして、4人の名前が挙げられている。それぞれの参加が重なっている部分もあるが、パトリックが4曲、アンジャニが1曲、エドが4曲、そしてディノが1曲をブロデュースしている。
『Dear Heather』も曲ごとにブロデューサーが異なっていたが、今回もレナードはそのやり方を踏襲し、それこそ曲作りの段階からその曲にいちばんふさわしいパートナーを見つけることに彼は腐心していたのではないかと思える。
しかし4人のプロデューサーがそれぞれ担当を分けあってレナードと一緒に曲を造り上げているとはいえ、『Old Ideas』には寄せ集めの作品集といった印象は微塵もない。首尾一貫したとても統一感のあるアルバムに仕上がっている。これはベーシックな部分のアイディアの多くがレナード自身によって出されていることもあるだろうし、誰がプロデュースを担当しても、ガット・ギターに女性コーラス、そして時にはチープにも聞こえるキーボードの音をレナードのサウンドの基調にしているからだろう。
とりわけ女性コーラスの起用はデビュー・アルバム以来のレナードのサウンド作りのトレード・マークと言ってもよく、三たび菅野ヘッケルさんの日本盤の解説によると、その理由をレナードは「陰鬱な自分の声を女性バックヴォーカルが和らげてくれる」と発言している。ぼくは個人的にはレナードのソロ・ヴォーカルでも全然かまわないし、曲によってはその方がいいようにも思えるものもある。しかしレナードのアルバムやライブにとって女性バック・ヴォーカルは、もはや切っても切り離せない必要不可欠な要素になってしまっているので、女性バック・ヴーカルのないレナードの歌だと物足りない、あるいは不自然だと思う人たちもきっといることだろう。
『Old Ideas』では、ジェニファー・ウォーンズやシャロン・ロビンソン、ザ・ウェブ・シスターズといった以前からレナードと関係のある女性ヴォーカリストたちに混じって、2002年にロビー・ロバートソンに認められ『Testimony』というアルバムを発表したシンガー・ソングライターのダナ・グローバーがレコーディングに初参加している。誰もがコーラスのアレンジとヴォーカルを担当しているのだが、初顔合わせということもあるのか、今回はダナがいちばん印象的な女性バック・ヴォーカルを聞かせてくれているようにぼくには思える。
しかし何といっても『Old Ideas』でいちばん強烈なのはレナード・コーエンの書く詩の世界だ。もともと詩人としてスタートした人だけに、歌の詞を書いても、それらは単なる歌詞以上に深く大きく重く鋭いものを抱え込んでいる。それらの厳選された、研ぎ澄まされた言葉やフレーズを、レナードはこれまで以上に低く深い声で歌い上げている。その声の表情もとんでもなく豊かだ。そしてどこまでも奥行きと広がりのある言葉だけに、逆にシンプルで素朴なメロディや単純なブルースのスタイルが、ぴったりと合っているように思える。
『Old Ideas』に収められている新しい曲のレナードの詩は、すでに70代の後半を迎えているということもあって、老いや死、そしてこの世を去った後に待ち受けている世界、すなわち神のことが歌われているものが多い。例外的に「Anyhow」や「Crazy To Love You」のようなちょっと聞くと世俗的に思えるラブ・ソングもあって、「Anyhow」では「許してもらえないことはわかっているけど何とか許してくれないか」と懇願しながらも、「負うべき責めは、両方にある」と開き直ってもいる。レナードはまだまだ恋の現役というか、永遠のドン・ファンなのだと、恐らくアルバムの中ではいちばん暗くて陰鬱なムードの曲なのに、聞いていると何だかにんまりさせられてしまう。
『Old Ideas』のソニー・ミュージックからの日本盤には、三浦久さんの素晴らしい対訳が付いていて,今回のレナードの歌詞を日本語に訳すにあたっての苦労話や解釈の仕方などが綴られた「訳者ノート」も掲載されている。アマゾンなどで買う輸入盤と違って日本盤はそれこそ1000円ぐらい値段が高かったりするが、丁寧な解説や見事な対訳が付いていれば、その差額は当然というか、それだけの価値があるのではないかとぼくは思っている。特にこれまでレナード・コーエンの歌詞の対訳を手がけられて来た三浦久さんの対訳は、言葉の世界にまで分け入って、『Old Ideas』にじっくりと耳を傾け理解するための最高の手引きとなることだろう。
ここでその対訳もいくつか引用してレナード・コーエンのいちばん新しい詩の世界のことにも触れたいのだが、引用はいろいろと差し障りがあるので、ここではとにかく『Old Ideas』はぜひ日本盤を手に入れてほしいと書くだけにとどめておこう。
レナード・コーエン、77歳。歌い続けて47年。ぼくの音楽のティーチャー、あなたの音楽のグランドティーチャー。
一度は日程まで決まっていながら実現することのなかった来日公演。この新しいアルバム『Old Ideas』の発売と共に、日本に歌いに来てくれることを少しは期待してもいいのだろうか? いや、そもそもアルバム発売に合わせたワールド・ツアーの計画などあるのだろうか。
ちなみにレナード・コーエンの『Old Ideas』は、さまざまな国でチャートのトップとなる売り上げを記録しているらしい。こんな「本物」の音楽が高く評価され、しかもアルバムがちゃんと売れているというのは、まだまだ世界は見捨てたものではないと思う。さて、日本ではどう受け入れられるのだろう?
中川五郎(なかがわ・ごろう)
1949年、大阪生まれ。60年代半ばからアメリカのフォーク・ソングの影響を受けて、曲を作ったり歌ったりし始め、68年に「受験生のブルース」や「主婦のブルース」を発表。
70年代に入ってからは音楽に関する文章や歌詞の対訳などが活動も始める。90年代に入ってからは小説の執筆やチャールズ・ブコウスキーの小説などさまざまな翻訳も行っている。
最新アルバムは2017年の『どうぞ裸になって下さい』(コスモス・レコード)。著書にエッセイ集『七十年目の風に吹かれ』(平凡社)、小説『渋谷公園通り』、『ロメオ塾』、訳書にブコウスキーの小説『詩人と女たち』、『くそったれ!少年時代』、ハニフ・クレイシの小説『ぼくは静かに揺れ動く』、『ボブ・ディラン全詩集』などがある。
1990年代の半ば頃から、活動の中心を歌うことに戻し、新しい曲を作りつつ、日本各地でライブを行なっている。
中川五郎HP
https://goronakagawa.com/index.html
midizineは限られたリソースの中で、記事の制作を続けています。よろしければサポートいただけると幸いです。
