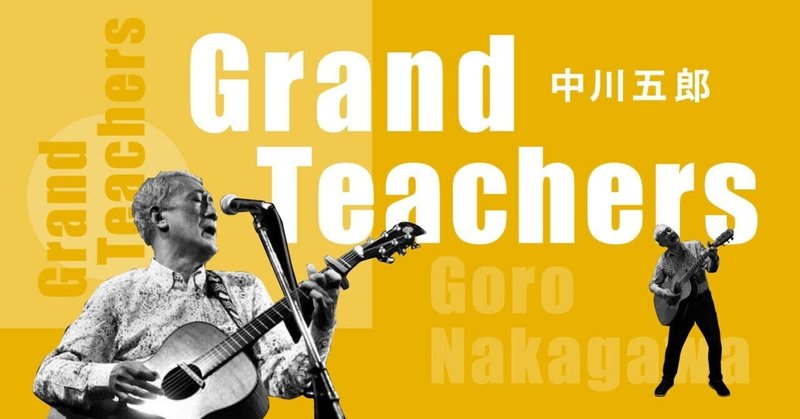
【アーカイブス#45】スティーブ・フォーバート *2013年2月
スティーブ・フォーバート(Steve Forbert)がこの3月の終りから4月の初めにかけて日本に歌いにやって来る。3月29日横浜、30日鎌倉、4月1日東京、2日名古屋、3日大阪と5か所を歌って回る。彼を招聘するパッファロー・レコードの告知を見ると「33年ぶりの奇跡の来日決定! It’s been a long time」という言葉が躍っている。そうか、もうそんなになるのか。
1978年の彼のデビュー・アルバム『Alive On Arrival』は、アメリカでの発売からそれほど間を置くことなく日本でも発売され、ハスキーな声で放浪や孤独を歌うその歌や、激しく吹き鳴らされるハーモニカに、多くの人たちが心を鷲掴みにされ、たちまちのうちに話題の存在となった。1979年のセカンド・アルバム『Jackrabbit Slim』や80年のサード・アルバム『Little Stevie Orbit』も日本発売され、80年には初来日公演も行って、会場に足を運んだ人たちは彼の熱いライブに興奮もすれば感動もし、大いに盛り上がったことをよく覚えている。あれからもう33年なのか。
恐らくは来日記念盤となったサード・アルバムの『Little Stevie Orbit』の後も、スティーブは82年にもう1枚『Steve Forbert』というアルバムをデビュー・アルバムからのレーベル、ソニー・ミュージック傘下のネンペラー・レコードからリリースし、それから6年間という長いインターバルを挟んで88年にはソニーと同じくメジャーのゲフィン・レコードに移籍して5枚目のアルバムとなる『Streets of This Town』を発表。その後もゲフィンやゲフィンと同じくワーナー系列のジャイアント・レーベルからアルバムを出し続けたが、全米チャートのトップ10直前まで行った「Romeo’s Tune」のような大ヒット曲も生まれたソニー時代に比べると、新しい歌の数々は高く評価されたもののあまり話題にはならず、寂しいことに日本でも彼の新しい歌は以前のように熱心には聞かれなくなってしまった。今となってはよく覚えていないが、『Streets of This Town』を最後に彼のアルバムは日本盤で発売されなくなってしまったのではないだろうか。
2000年代に入ると、スティーブはKochや429 Recordsといったインディーズ・レーベルからスタジオ録音の新しいアルバムを発表するようになり、それと同時にニューヨークのボトム・ラインなどさまざまな会場で行なったコンサートのライブ・アルバムも数多く登場した。
1954年12月13日にミシシッピ州のメリディアンという街に生まれたスティーブは、ティーンエージャーになった頃にはギターを抱えて歌い始め、やがて仲間とバンドを組んで、同じメリディアン出身の偉大なカントリー・シンガー、ジミー・ロジャースからブルースマンのロバート・ジョンソン、それにエルヴィス・プレスリーやチャック・ベリー、ビートルズにフォー・トップスなどどんな音楽にも挑戦し、1972年頃からは自分でも歌を書くようになった。そしてシンガー・ソングライターとして一旗揚げようと70年代半ばにはニューヨークへとやって来た。その頃から現在に至るまで、まさにライブこそがスティーブの音楽活動の中心に位置するものであり、ライブこそどんな状況の中でも彼がひたむきにやり通して来たことなのだ。
スティーブ・フォーバートのオフィシャル・ホームページ、のディスコグラフィーのページを見ると、幾つかのレーベルから発売されたいわゆる「正規」のライブ・アルバムのほかにも、ホームページからの独占リリースとして10枚ものライブ・アルバムが発表されていて、その多作さに驚かされてしまう。
ところでこの春のスティーブ・フォーバートの「33年ぶりの奇跡の来日」は、ぼくにとっては青天の霹靂のようでもあったが、それと同時に起こるべくして起こったというか、必ず実現するような予感がどこかでしていた。というのも、日本の多くのかつてのスティーブ・フォーバート・ファンと同じように、ぼく自身1990年代半ばあたりからは彼の歌にほとんど耳を傾けなくなってしまっていたのだが、この1,2年、彼は元気で歌っているのだろうか、いい歌を作っているのだろうかと妙に気になり始め、最近の彼のアルバムを手に入れてまた熱心に耳を傾けるようになっていたのだ。
そして「おっ、最近のスティーブは実にいいぞ」とひとりで嬉しくなり、こんなにいいのだからぼくと同じように今のスティーブを気に入って、何とかもう一度彼に光を当てたいと考えている人が日本には必ずいるはずだと思っていた。そんなことを思いながら昨年リリースされた彼の最新アルバム『Over With You』に繰り返し耳を傾けていた。そんなところにバッファロー・レコードがスティーブ・フォーバートの日本公演を行うという何とも嬉しいニュースが飛び込んで来たのだ。万歳!!
ぼくはまずはスティーブ・フォーバートが2004年にKochから発表した『Just Like There’s Nothin’To It』からスティーブの聞き直しを始め、2007年の『Strange Names & New Sensations』(429 Records)、2009年の『The Place And The Time』(429 Records)と聞いて行き、最近のスティーブの歌の虜にすっかりなってしまった。
そこには50代になって深みも増せば、肩の力も自然に抜け、どこか飄々としてユーモアも感じさせる、実に人間味溢れるスティーブの歌があった。1978年、20代前半のデビュー・アルバム『Alive On Arrival』での、突っ張って、傷ついて、孤独に苛まれている、それこそ心の襞を掻きむしるかのようなひりひりと痛い歌も凄かったが、熟成した彼の歌もほんとうに素晴らしい。
1982年のソニー・ミュージック傘下のネンペラー・レコードでの『Steve Forbert』から88年のゲフィン・レコードに移籍しての『Streets of This Town』まで、6年間という長いインターバルがあったと前述したが、『Steve Forbert』の後、今度こそは「Romeo’s Tune」に続く大ヒット曲を何とかと期待するレコード会社のもとでスティーブは5枚目のアルバムを完成させたが、レコード会社はその内容に満足せず、発売を拒否してしまった(このアルバムは2009年に『Down In Flame』という3枚組のCDで日の目を見ている)。加えて彼を見出したマネージャーとの関係も悪くなり、いずれも契約問題がこじれて裁判沙汰となり、それで6年間も新しいレコードを発表できないという苦境に彼は追い込まれてしまったのだ。
確かその当時、トラブルにすっかり嫌気がさしたスティーブは酒などに溺れてしまい、荒んだ生活を送っているという話をどこかで聞いたような気がする。しかもこの長いブランクのせいで、彼の歌から離れて行ってしまった人たちもいたことだろう。しかしスティーブはこの人生の難関を何とか乗り越え、それを歌の糧にもして、以前にも増して豊かで逞しく、そしてしなやかな歌を作り、歌うようになった。とりわけ2000年代半ば以降、50代になってからの充実ぶりは素晴らしく、まさにそんな時に「33年ぶりの奇跡の来日」とは、ぼくにとってはほんとうに狂喜乱舞のできごとで、感無量でもある。
スティーブ・フォーバートの最新アルバム『Over With You』(Blue Corn Music)は、ほんとうにぼくのお気に入りで、改めて彼の新しい作品を聞き始めてからのいちばんの傑作、1978年のデビュー・アルバムから数えて全部で15枚になる彼のスタジオ録音アルバムの中でも、恐らくは最良の作品のひとつと言えるのではないだろうか(全作をきちんと聞いていないので、ごめんなさい)。
オープニング・ナンバーの「All I Asked of You」を聞くと、「うわっ、『Alive On Arrival』の頃のスティーブが戻って来たみたいだ」と、ちょっとどきどきさせられてしまうが、アルバムを聞き進むうちに、あの頃の少年のような輝きや瑞々しさはそのままに、人生の酸いも甘いも噛み分け、喜びも悲しみもふんだんに味わい、悟りもすればより深い洞察力も身につけた、還暦に近づいたスティープのまさに今の歌を堪能することができる。
この連載ではお馴染みのシンガー・ソングライター・チェリストのベン・ソリーがチェロやエレクトリック・ベースで3曲に参加しているのも嬉しいかぎりだし、べン・ハーパーがやはり3曲でギターを弾いているのにもちょっとびっくりさせられる。ベンとベン。ベンにベン。特にベン・ソリーのようなうんと若い世代のミュージシャンとスティーブが積極的に交流しているのが素敵だが、1983年生まれのベン・ソリーにしても1969年生まれのベン・ハーパーにしても、自分たちの大先輩の不屈のミュージシャンに対して強いリスペクトの気持ちを抱いてレコーディングに参加したに違いない。
レコーディングにはほかにもキーボード・プレイヤーやドラムスとベースのリズム・セクションが参加しているが、はてさて、33年ぶりの来日公演はスティーブのソロなのだろうか、それともバンドを引き連れてのステージなのだろうか。いずれにしてもミュージシャンとしていちばん充実した時期を迎えている絶好のタイミングでの来日公演、それは奇跡であると同時に、とんでもなく素晴らしいものになることは確実だ。残念なことに大阪公演はソールド・アウトになってしまったようだが、ほかの四回のステージ、ぜひともお見逃しなきように。
中川五郎(なかがわ・ごろう)
1949年、大阪生まれ。60年代半ばからアメリカのフォーク・ソングの影響を受けて、曲を作ったり歌ったりし始め、68年に「受験生のブルース」や「主婦のブルース」を発表。
70年代に入ってからは音楽に関する文章や歌詞の対訳などが活動も始める。90年代に入ってからは小説の執筆やチャールズ・ブコウスキーの小説などさまざまな翻訳も行っている。
最新アルバムは2017年の『どうぞ裸になって下さい』(コスモス・レコード)。著書にエッセイ集『七十年目の風に吹かれ』(平凡社)、小説『渋谷公園通り』、『ロメオ塾』、訳書にブコウスキーの小説『詩人と女たち』、『くそったれ!少年時代』、ハニフ・クレイシの小説『ぼくは静かに揺れ動く』、『ボブ・ディラン全詩集』などがある。
1990年代の半ば頃から、活動の中心を歌うことに戻し、新しい曲を作りつつ、日本各地でライブを行なっている。
中川五郎HP
https://goronakagawa.com/index.html
midizineは限られたリソースの中で、記事の制作を続けています。よろしければサポートいただけると幸いです。
