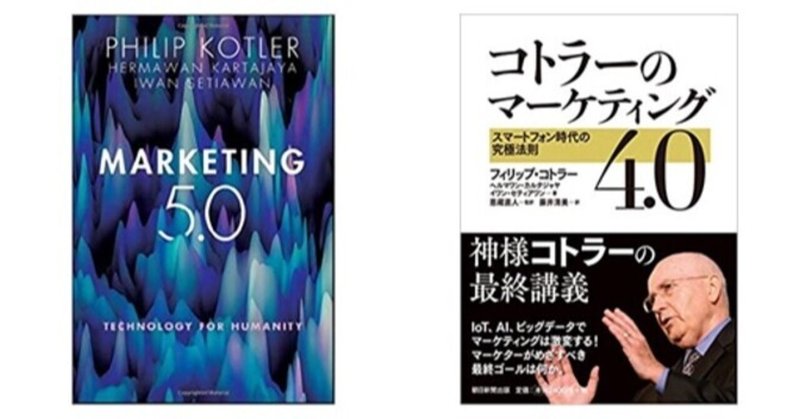
マーケティング5.0を読む前に現在の視点からマーケティング4.0を振り返る
michinaru株式会社の若林です。ファーストペンギンを紹介してきた記事をいつも読んでいただきありがとうございます。今週からは少し角度を変えて、読者の皆さんの背中を押す知見をお伝えできる記事を書けたらと思っています。
ご存知の方も多いかと思いますが「近代マーケティングの父」と称されるフィリップ・コトラー氏の『マーケティング5.0』が今年の2月3日に出版されました。
コトラー氏はマーケティングの概念をアップデートさせることで「マーケティング x.0」シリーズを書いています。そのため、前作である「マーケティング4.0」をしっかりと振り返ってから読むことで、『マーケティング5.0』の理解の仕方も変わると思い、この記事を書かせていただきました。
マーケットのトレンドを知ることは、マーケターに関わらず、ビジネスに関わる全ての人にとって役立つ事だと考えています。
「マーケティング4.0」の中でもコトラー氏の市場に対する考え方が最も色濃く表れている第一部「マーケティングを形作る基本的なトレンド」をピックアップして読み返していきたいと思います。
第一部は
第1章 つながっている顧客へのパワーシフト
第2章 つながっている顧客に対するマーケティングのパラドックス
第3章 影響力のあるデジタル・サブカルチャー
第4章 デジタル経済におけるマーケティング4.0
の4部構成でそれぞれスマートフォンが普及した時代に変化している重要なマーケティングのトレンドを解説しています。
第1章 つながっている顧客へのパワーシフト
第1章ではソーシャルメディアにより、地理的・人口動態的障壁を関係なくコミュニケーションを取れるようになった人々は縦の繋がりではなく、横の関係を重視していることについてコトラー氏は言及しています。
それを象徴する端的な説明として、
"ブランド発のマーケティング・コミュニケーションをますます警戒するようになり、代わりにFファクターに頼っている。"
と書いています。Fファクターとはfriends友達、families家族、Facebook fansフェイスブックのファン、Twitter followersツイッターのフォロワー、のことです。そして、購買プロセスは個人的なものではなく、社会的なものになってきている。と記しています。
コトラー氏の説明はまさに書かれてから5年ほど経過している現在の購買活動を表していますよね!企業ではなく、友達や親しみのある芸能人が使用しているものを欲しくなるし、不透明な会社の商品は、機能や価格面をいくら売り出しても宣伝効果があまりない。
amazonや楽天市場で何かを購入するときも、口コミを気にする人がほとんどなのではないでしょうか。
コロナウイルスの影響で、オフラインでスタッフの声を聞いたりや実物を見たり触ったりすることが難しくなっている現在では、購入プロセスの社会性は上がってきていると考えられます。
第2章 つながっている顧客に対するマーケティングのパラドックス
第2章では移動性と接続生の高い、中流階級の若い都市住居者をマーケターが狙うべき魅力的な市場だと伝え、その市場が抱えるパラドックスについて説明しています。
第2章で述べられているパラドックスは
1.オンライン交流 対 オフライン交流
2.情報を持っている顧客 対 注意力散漫な顧客
3.批判的な意見 対 好意的な意見
の3つです。「対」という表現がされているので、誤解を生みやすいですが、それらは相反するものではなく、互いに影響をし合っているものであると説明されています。それぞれ下に説明を加えました。
1.オンライン交流 対 オフライン交流
オンライン・ビジネスが市場の大きな部分を占めているが、完全にオフライン・ビジネスに取って代わるものではない。
ハイテク化が進む世界では、コールセンターや実店舗での接客など、ハイタッチの交流が新しい差別化要因になり、オンライン経験とオフライン経験の要素を統合して、総合的な顧客景観を作り上げる必要がある。
2.情報を持っている顧客 対 注意力散漫な顧客
デジタル技術の発展により、誰もがブランドに対する情報を積極的に求めるようになってきている。しかし、接続性は、いくつもの機器やスクリーンが存在することとあいまって、気を散らせるものともなっている。結果として、多くの顧客がクチコミなどの集合知に従い決定を下している。
3.批判的な意見 対 好意的な意見
デバイスを持つことによって、顧客が意見を表明し、他者がそれに耳を傾けることが可能になっている。ブランド推奨の最も有名な測定基準とされている、「ネット・プロモーター・スコア(正味推奨者比率)」では、批判的なクチコミの悪影響は好意的なクチコミの好影響を弱めるとされている。
しかし、ブランド推奨は、批判的な顧客による質問や意見によって活性化される側面がある。そのために、好意的な意見と批判的な意見の両方があることによって初めて、ブランドに関するカンバセーションは面白みのあるものとなり、人々を魅了する。
デジタル技術は情報収集やコミュニケーションを速く行えるようにしただけでなく、人々の行動様式を根本的に変えてしまった。行動様式に変化が生まれ、新たな選択肢が生まれるからこそ、前からあった選択肢の意味合いも変わってくる。ということを的確に説明してくれていると思いました。
新たな選択肢が生まれることで、既存の選択肢の意味合いが変わってくる。
この観点は多くの場面で変化求められている現在のマーケティング活動において、とても大切だと感じました。
第3章 影響力のあるデジタル・サブカルチャー
第3章ではデジタル界においてマーケターが力を集中すべき顧客を、若者(youth)と女性(women)とネティズン(netizen)を意味するYWNとしてその理由について説明しています。ネティズンとは(network+citizen)を掛け合わせた言葉で、ネットワークを自分のコミュニティとして積極的に関わっている人のことを指しています。
YWNの顧客層が重要な理由は、それぞれこのように説明しています
若者は
1.アーリーアダプター(早期採用者)2.トレンドセッター3.ゲームチャンジャーという3つの役割を持っている。これらの役割から、若者はマインドシェアを獲得するためのカギである。
女性は
1.インフォメーション・コレクター(情報収集者)2.ホリスティック・ショッパー3.ハウスホールド・マネジャー(家庭管理者)という役割を持っている。これらの役割を担う女性の意思決定プロセスを通り抜けることは、デジタル経済において市場シェアを獲得するためのカギである。
ホリスティック・ショッパーとは、「全体を見て判断する買い物客」を意味する用語で、男性よりも女性のほうが、あらゆることを 〜機能的利点、感情的利点、価格など〜 を考慮してから製品やサービスの真の価値を判断する可能性が高いと考えられている。そのため、自分の選んだブランドに男性よりもロイヤルティを有し、当該ブランドを自分のコミュニティに推奨したいという気持ちも強い。
ネティズンは
1.ソーシャル・コネクター2.熱烈な伝道者3.コンテンツ投稿者という役割を持っている。ネティズンのコミュニティーはこのような役割から、ブランドのハートシェア(ブランドに対する心情内で交換が占める割合)を拡大するカギになる。
つまり、デジタル時代では情報の収集や発信が容易になり、コミュニケーションの様式が変化したことによって、YWNがもつ影響力がどんどん大きくなってきていることを説明しています。
感染対策の観点からもオンラインでの活動が推奨されている現在は誰もが、ネティズンなっている時代だと言えると思います。
ネティズンを効果的にセグメンテーションして、自分たちのメッセージを適切な相手に届ける工夫がより重要視されてきていますね。
マーケティング5.0では、どの顧客に力を集中すべきだと述べるているのか気になります。
第4章 デジタル経済におけるマーケティング4.0
第4章ではマーケティング4.0が企業と顧客のオンライン交流とオフライン交流を一体化させるマーケティングアプローチであることを発表します。そして、伝統的マーケティングとデジタルマーケティングの統合が重要であると解説しています。
伝統的にマーケティングはセグメンテーションから始まり、ターゲティングをして売り込む。
縦の関係 ー ハンターと獲物のような関係 ー で表すものであり、マーケティングミックスでは、4P製品(Producut)価格(Price)流通(Place)プロモーション(Promotion)の四つが最適に設計されることが販売へ結びつくとされてきました。
しかし、接続された世界では4Pは4C(co-creation=共創、currency=通貨、communal activation=共同活性化 、conversation=カンバーセーション)に改められるべきだと主張しています。
企業と顧客、そして顧客同士が常にコミュニケーションを取ることが当たり前になったデジタル経済。
それによって、企業と顧客は共に商品を作り(co-creation=共創)、それぞれの顧客に対して動的な価格設定をし(currency=通貨)、他者の所有している製品・サービスを簡単かつ即座に利用、購入し(communal activation=共同活性化)、立場関係なく会話をすることが出来る。(conversation=カンバーセーション)
この4Cをうまく設計することで、企業がデジタル世界で生き残る可能性を上げることが出来ると述べています。
しかし、コトラー氏はこの新しいトレンドを伝統的なマーケティング手法に取って代わるものではなく、顧客のカスタマー・ジャーニーによって役割を交代しながら共存すべきものであると主張しています。
下の図のように、企業と顧客の交流が初期の段階では伝統的なマーケティングの考え方を用いて、顧客の認知と関心を構築する。
そして、交流が進み、顧客が企業とのより緊密な関係を求めるようになった段階では、デジタルマーケティングを用いてアプローチをすることが重要になると述べています。
そして、デジタル・マーケティングと伝統的なマーケティングは顧客の推奨を勝ち取ることを最終目標として、共存をしていかなければならないと4章をまとめています。
現代の視点から4.0を読み直してみて
最後まで読んでいただきありがとうございます。「マーケティング4.0」の第一部を読み直し、まとめさせていただきました。読者のみなさまの活動を少しでも助ける知見を共有できていたら嬉しいです。
読み返して思ったことは、5年前に書かれていることもあり、現在にそのまま当てはめられないものもあるなということです。コロナウイルスの影響により、世界的に企業と顧客のオフラインのタッチポイントが減り、オンライン交流の頻度や自由度が上がってきています。そんな現在においては、オフライン交流 対 オンライン交流 という分け方で考えることは難しくなってきているのではないでしょうか。
そして、オフライン交流の意味を改めて、問い直す必要があります。
このことについて、コトラー氏も本の中で”新しいタイプの顧客の特性は、マーケティングの未来がカスタマー・ジャーニー全体にわたってオンライン経験とオフライン経験のシームレスな融合になることをはっきり示している”と書いています。
シームレスな融合を半ば強引にさせられた、現代社会では新しい顧客交流の考え方が求めれており、誰もが明確な答えを持っていない状態だと思います。
この状態は不安定で悩むことも多いですが、新しい挑戦をする人にとってはチャンスだと捉えることも出来ると思います。
この記事が読者のみなさんの活動のヒントになり、そんな新しい挑戦をする人の背中を少しでも押せていたらとても嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
最後に一つお知らせをさせていただきます。
2月19日(金)15:00〜で「新規事業を生み出す挑戦者の創り方」というテーマで無料セミナーを開催します。
「コロナウイルスの影響で急速に変わりゆく市場の中で、新規事業に挑戦する社員を育成するにはどうすれば良いか。」ということについて、お話をさせていただく予定です。興味のある方はご参加いただけると嬉しいです。
michinaruのHP https://michinaru.co.jp/
michinaru公式Twitter https://twitter.com/michinaru0430
michinaruメルマガ https://michinaru.lmsg.jp/form/23979/llJS8KAv
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

