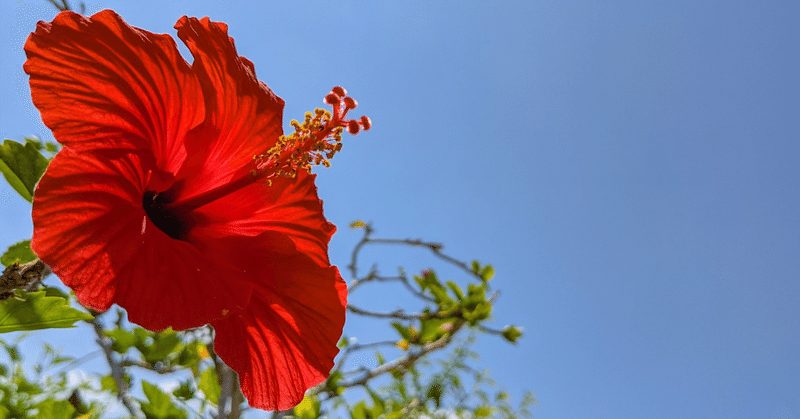
#56 慰霊の日
今日は、慰霊の日です。沖縄戦から78年が経ちました。現地では遺族などが平和への祈りを捧げたようです。
戦時中に亡くなられた方には、心からのご冥福をお祈り申し上げます。
沖縄は23日、太平洋戦争末期の沖縄戦から78年の「慰霊の日」を迎え、最後の激戦地となった糸満市の平和祈念公園では朝早くから遺族などが平和への祈りをささげています。戦争を実際に体験した県民は全体の1割を下回っているとみられていて、沖縄戦の記憶を次の世代がどう継承していくのか、問われています。
僕は戦争経験者ではないですし、残念ながら沖縄を訪れたこともなく、この国で実際に行われていた戦争というものを追体験したことがありません。ですが、戦争の災禍は今も世界のどこかを襲っているというのも疑いようのない事実でしょう。
実際に、当時の沖縄では20万人以上、4人に1人の県民の方が亡くなられたと伝えられています。
法学専攻の僕としては、戦時中には平時法と異なり、戦時法が適用されることが大きな特徴だと思っています。法治国家を標榜する国では、もしかしたら今のバイブルは六法全書なのかもしれない、というように考えていますが、そのバイブルを変貌させる引き金の一つが戦争なのでしょう。この国も、戦前、戦時、戦後では外的には同じ国でも、内的にはもはや異国と言えるかもしれません。申し訳程度の知識しかないですが、素人ながらに肌感覚ではそのように感じられます。
草野心平も終戦後のとある詩で「おれのこころは。どこいつた。おれのこころはどこにゐる。」(原文の改行は筆者省略。)と書いています。「おれのこころ」は戦前の日本に取り残されたままなのかもしれません。この詩については、別の記事で後日触れる予定です。
あまりこのタイミングで言及することではないかもしれませんが、どうしても寿命がある以上、世代が変わっていってしまうことは仕方のないことと思います。風化させずに、後世に伝えていくことはもちろんですが、戦争を全く経験していない(やや侮蔑する意味を込めて平和ボケと言われることもありますが。)僕たちに、今何を期待されていて、何ができるのか、ということについて、この機会に考えてみたいと思います。
