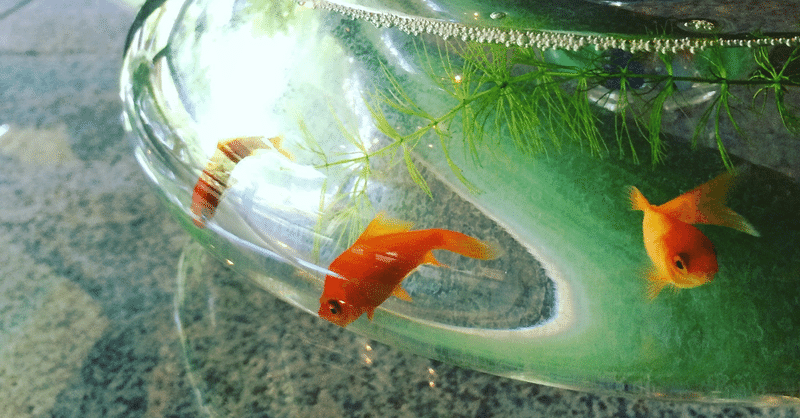
#60 本当の自分・・本物と贋作の自分
真正性という。本物という意味。英語でauthenticiyty.
客の持ち込んだ品が本物かどうか質屋が見分けることができるのは、質屋が本物しか見続けないからだ。贋作とは本物と見分けがつかないくらい精巧につくりあげられた偽物である。
商品が多様にでまわり、自分に「あった」商品を選択する。「商品」に自分をあわせているわけで「自分」が商品を選択しているというのは幻想がある。自分にあった服を選ぶとき、自分を服にあわせている。そこでは自分が贋作になってしまう。
学校の授業で教科がある。世の中にはたくさん知恵や知識があって、それをなにかの都合のいい分類基準でわけて、体系性をもたせて、教育という固有のシステムと方法論で構成したのが教科である。それを習得することで社会に参加できるという国家のお墨付きをもらえる。そのお墨付きは他者評価であって自己評価ではない。自分が本当に満足しているわけでもない。自分が教科にあわせていることだってありうる。
体のいいいいかたではそれを適応という。適応しすぎると過剰適応になり自分がわからなくかってしまう。アイデンティティの拡散。自分探しというのは、そういう意味である。
学校で学ぶときの真性性とはなにか。それには2つの側面がある。ひとつは、いうまでもなく、教科のアカデミズムの真正性である。あと一つは自分自身の真正性である。
教科の内容に真正性がともなわないとき、意味なく言語や記号の情報処理をしている自分がいる。スキルをみにつけるだけに終始する。閉じた領域で部分の習得をするのは、あたかも分業によって製品の一部を担当する工場労働者のようである。つまり労働の疎外。学習から疎外されている。
物理学の本物にであっていない。音楽の本物にであっていない。物理学の音の波長と音楽の楽理が共鳴して越境性する魅力を備えていない。学際性を持っていない。閉じた孤立主義の教科学習は学習から自分を疎外する。その疎外感が自己肯定感を低下させ、虚無主義に結びつき、外部依存をたかめて他罰主義に陥る。
その克服が総合的な学習・探究の理念である。総合的というのは言い方が誤解を与えている気がする。越境性である。
自分とは何か?自分を自己といってもよい。学習する教科は誰かさんがつくったもので、自分が作ったものではない。その誰かさんも抽象化された匿名性の誰かさんである。この誰だかわからないけれど誰かではあるその誰かの作った内容を誰かにあわせて習得するのみの時、誰か自体を疑うことはなくなる。それは知ではなく情報である。
疑うときには疑う自分がありそれを吟味する自分がある。複数の自分が自分を吟味し本当の自分を形成しようとする。わからない、というのはそういうことだ。理解できないということではない。真正性とは本当の自分(自己)の内なる声を聴くことである。知識とは過去の先人がそのようにして集積したものである。とすれば、その過程そのものの方法を辿ることでしか自己を知ることはできない。
