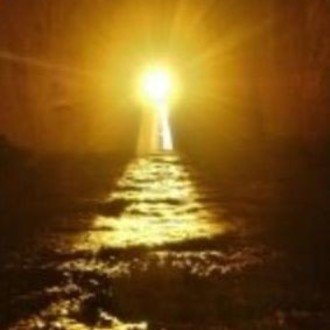[英詩]Louise Glück, 'The Magi'
※ 旧「英詩が読めるようになるマガジン」(2016年3月1日—2022年11月30日)の記事の避難先マガジンです。リンク先は順次修正してゆきます。
※「英詩のマガジン」の副配信です。
2020年ノーベル文学賞を受けた米国の詩人ルイーズ・グリク (Louise Glück, 1943- ) を扱うのは3回めです。過去2回は次のとおり。
・[英詩]Louise Glück, 'Nostos' (詩集 'Meadowlands' [1996])
・[英詩]Louise Glück, 'Hesitate to Call' (詩集 'Firstborn' [1968])
今回は 'The Magi' を取上げます。詩集 'The House on Marshland' (1975, 下) の詩です。

*
グリクについては、朝日新聞 (2020年10月14日) に北海道武蔵女子短大名誉教授・木村淳子氏 (米文学者) の インタビュー が載っていました。グリクのひと世代上の「告白詩」といわれる、〈病歴でも家庭生活でも体験を明け透けに詩に書く〉女性詩人たちとの比較から語ります。〈それも怒鳴るように[書く]。私はあまり好みではなかった〉といいます。
米詩で告白詩の女性詩人といえば、Sylvia Plath (1932-63), Anne Sexton ( 1928-74) らの名が思いうかびます。グリクより10−15歳くらい年上です。
〈ところが、グリュックさんの作品は体験をうたっていても、抑制が利いていて静かなんです。〉
*
なぜ、このような違いがあるのでしょう。グリクは、つらい体験でも、告白詩人たちとは受止め方が違うようです。
〈生い立ちを調べると、10代のころ拒食症になって20代になるまで治療を受けて、つらい、大変な思いをしたようです。でも、「苦しい、苦しい」と声高に訴えるのではなくて、暗い地中でジーッと耐えていた球根が芽を出し、花を開いていく、と。そんなうたい方です。花とか植物とか木になぞらえる。メタファー=隠喩ですよね。個人の体験をメタファーによって、ほかの人にも理解できるように表現して公のものにする。ノーベル委員会が「個人の存在を普遍化した」と評したのは、そんな意味ではないでしょうか。〉
ノーベル委員会の授賞理由は 'for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal' というものでした。この 'makes individual existence universal' が「個人の存在を普遍化した」に当たります。
*
〈ノーベル委員会は「飾り気のない美しさ」ともおっしゃっていますね。言葉は非常に簡潔で、すっきりしている。難しい単語がない。日本の中学生、高校生も読めるはずです。〉
「飾り気のない美しさ」は 'austere beauty' に当たります。難しい単語がないから、中学生・高校生でも読めるだろうというのですが。
*
確かに、単語は難しくないので、読めるとは思いますが、本マガジンで取上げた2篇を見ても、読み手が考えるべきことは相当ありますね。
〈だけど、内容は深い。人間存在の根本にかかわるテーマをとり上げている。死と蘇りについてうたった詩がたくさんあります。〉という木村氏の言葉はそのあたりに関ります。
一見、難しくない単語で、深い内容をうたう詩人は、実は米国には多いのです。典型例はアシュベリ (John Ashbery, 1927- ) でしょうか。過去50年間で最大の米詩人でしょう。20世紀で考えても最高の米詩人の一人です。アシュベリはあまりにも言語的に難しいので、中学生・高校生が読むのはおそらく無理です。ある意味で言語の力の極北を志向する詩人です。読み手は自分の持っている言語能力を極限まで試されます。
*
話がそれました。ノーベル委員会がグリクに賞を贈った理由について木村氏はこう考えます。
〈春先、夜が白々と明けていく。その中に引き込まれるような詩の世界を彼女はつくり上げた。新型コロナやら分断やら、そんな世界にあって、ノーベル委員会はこの人の詩の持つ「癒やす力」に目を留めたのではないかと感じました。〉
この「癒やす力」は、同じノーベル賞詩人のアイルランドのヒーニ (Seamus Heaney, 1939-2013) にも感じられます。'the cure by poetry'「詩による治療」というふうに、はっきりと詩の治癒力を意識しています (詩 'Out of the Bag' に現れる言葉)。
*
木村氏はグリクの好きな詩を引用します。
〈私の好きな1編は最初に読んだ「野生のアイリス」['The Wild Iris' (1992)]の表題作です。冒頭に 'At the end of my suffering there was a door.' とあるんです。「苦しみの終わりに 扉があった。」と。「苦しい、死んでしまおう」ではなくて、そこから出て生へ向かう扉です。彼女の詩には必ず光が見えるんですね。明かりの方向へ進んでいく、そういう姿勢は一貫しています。〉
「彼女の詩には必ず光が見える」——おぼえておきたい言葉です。
_/_/_/
原詩
The Magi
Louise Glück
Toward world’s end, through the bare
beginnings of winter, they are traveling again.
How many winters have we seen it happen,
watched the same sign come forward as they pass
cities sprung around this route their gold 5
engraved on the desert, and yet
held our peace, these
being the Wise, come to see at the accustomed hour
nothing changed: roofs, the barn
blazing in darkness, all they wish to see. 10
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?