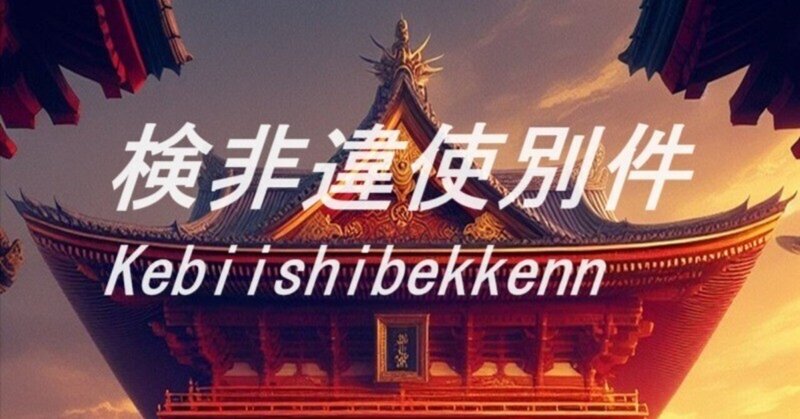
検非違使別件 七 ⑭
「恐ろしい光景を思い出させてすまないが、詳しく聞かせてくれ」
「……はあ、伎楽殿ではすでに一人が倒れていて、メラメラ燃える几帳にくるまって、ピクリともしなかったのですよ」
(それは、すでに刺されてこと切れていたということか)
わずかでも息があれば、炎にあぶられてのたうち回るのではないだろうか。
(殺害された女……雑仕女と届けが出されたが、本当はそれが能原門継の言う舞姫なのではないか?)
仁木緒は質問を重ねた。
「炎の中で、苦しんでいる三人が何者だったのだ?」
「……恐ろしいことで……恐ろしいのなんの……。たもとも何もかも、炎を吹き上げておりまして、顔なんか、確かめられるもんじゃありません……水をぶちまけたものの、お三方には届かず……ただもう、立ち尽くしていたところ、亥の刻を知らせる寺の鐘の音が、耳の奥に響いてきたように思います……」 曖昧な言い方ではあるものの、これで刻限の見当がついた。
「仲間の使用人で、火事を境に行方不明になった者はいなかったか?」
「一人として欠けておりません」
「女も男も?」
「はあ」
「焼死者の様子はどうだ。袴は身に着けていなかったのか? あるいは、烏帽子はどうだ?」
「うう……思い出すのも辛うございます。……ご容赦を」
いまや全身を震わせて、千歳丸は両手でおのれの頭を抱えている。額に汗がにじみ出て、顔色は青い。あまりに恐ろしい光景を見たことで、千歳丸が心に大きな傷を負っているらしかった。
「わっしは間違ったことはしておりませんよね? あのとき、取って返して、他の連中にすぐ火を消すようにと頼んで、わっしはもう夢中で門を出た。このまま火が大きくなれば、ご近所に延焼しちまう。だから、あちこちのお邸の門番に『火事だ火事だ』『手を貸してくれ』ってわめいて回りまして……」
「そうか、お前が騒いだおかげで、この事件がもみ消されずに検非違使庁に届けられたというわけか」
「……ところがそれで、伴家継さまらに『下郎が、差し出たことをした』とずいぶんなお叱りを受けてしまいまして……殴る蹴るの乱暴をされた挙句に、放逐されてしまいました……」
頭部の包帯に手をやった。
「客人と言ったな。客はどうだ? 客が連れて来た武士、あるいは遊び女が焼死したのではないのか?」
「いえ、それは……その……」
「なんだ?」
「……も、申し上げます」
何度も唾液を飲み込んで、震えながら千歳丸が平伏した。顔を床板に向けたまま言葉を続ける。
「これは、わっしだけじゃなく、そのころ勤めていた使用人仲間も、ささやいていたことなんですが……」
「うん?」
「焼死した四人のうち、二人は……おそらく、任尊さまと実覚さまではなかったか……と」
「なんだとっ」
思わず仁木緒は片膝を立てた。前のめりになり、千歳丸の肩をつかむ。
「詳しく話せ」
前後にゆすぶられながら、千歳丸は言葉を続けた。
「じ、実は、お二人はその二日前に邸へいらっしゃいまして……いつものごとく、父君の登任さまをおいさめしているようでございました。ですが、僧籍にあるご子息お二人とは別に、登任さまは、伴家継さまを通じてお客人を招いていらして、舞の上手なさゆりと申す女を伎楽殿に召したのでございます」
「さゆり……」
仁木緒は千歳丸の肩から手を放した。
「邸内に曹司を与えられ、登任さまの無聊をなぐさめる女でして……。いつものごとく、伎楽殿で宴席が張られ、さゆりが舞い始めたようです。火事のあとで伴家継さまは仰せになりました……『さゆりが宴席で舞う少し前に、任尊さまと実覚さまはお帰りになった』……と」「だが、僧二人は帰ってはいなかった」
「はあ、たぶん……」
「出家したとはいえ、その家の子息が二人そろって寺へ帰るのだ。誰かが必ず見送りをしたはずだが」
「ところが、誰も気づかなかったと言うんです。……そりゃあ、あの夜は十人ばかりガラの悪い客人が一度にいらっしゃって、酒肴を運ぶのに忙しく、牛飼いのわっしですら用事を言いつかっておりました。おまけに邸の敷地は広い。門は四つもある。それでも、人目を避けて任尊さまと実覚さまが邸から出たとは思えません」
「ガラの悪い客?」
「はあ、数年前からちょくちょく出入りしている客人たちでございますが……目つきや声色、衣の着こなしがくずれておりまして」
「首の名は」
「備前に領地を持つ、能原門継というお方だそうで」
仁木緒は自分でも、顔色が変わるのを感じた。膝の上で拳が固くなる。多紀満老人が食い入るように千歳丸を見つめている。
気持ちがはやるのを押さえつけ、仁木緒は荒々しく鼻孔から息を吐き出した。「能原門継……その男は左右の眉の上と眉間の三か所にほくろがある、髭の濃い巨漢だったか?」「ええ、もともと家司の伴家継さまとお親しかったとか。そのうち、主人の登任さまに取り入って、数年前からちょくちょく出入りするようになったのでございますよ」
千歳丸が大きくうなずく。もう震えてはいなかったが、潤んだ目から再び涙がこぼれ、それを右の袖口でぐいとぬぐった。
「……ずっとあの火事が、胸の奥に重くのしかかっておりました……。寝ても覚めても悪夢ばかり見て………」
そんなささやきを耳に止めながら、仁木緒は忙しく脳裏に一つの構図を描いていた。
かつて陸奥国守だった藤原登任である。失脚し、出家したとなれば収入は途絶える。それでも陸奥から引き上げるとき、多くの財を自邸へ運び入れたはず、という風聞があった。
(能原門継は備前国を足場に、海賊団を率いて瀬戸内海を荒らしていた。登任さまは蓄えていた陸奥の物品を売りさばくため、伴家継を通して門継を頼ったということだろうか? ……それともまた別のつながりがあるのだろうか)
散位(無職)であれば蓄財は減る一方だ。手っ取り早く財貨を得る手段なら賭博が思い当たる。もし、藤原登任が邸のどこかに賭場を設けていた場合、金の匂いに凶賊たちが引き寄せられたとしても不思議はない。
(藤原登任さまの邸内で賭博が行われていたとすれば、二人のご子息に証拠をつかまれ、賊たちが口封じに命を奪うこともあり得る)
放火は殺人だけでなく、賭博の証拠を消すための工作ではなかったか。
瞬間的にそこまで思いつめたものの、ただの憶測にすぎぬと仁木緒は自分に言い聞かせた。
「その火事だが、遺骸四体が男女の区別もつかぬほどだったという割に、延焼がなく伎楽殿のみ焼け落ちるとは奇妙だ。油か松脂を思わせる匂いでも嗅いだ記憶はないか?」
「……はあ、言われてみれば……油壷がなくなっている、盗まれた、などと雑仕女が三人しゃべっておりました」
「その油壷を荒彦が盗んだと疑われたのか?」
「いえ、あいつはそんなことをするヤツじゃありませんよ」
千歳丸は首を横に振った。
「荒彦は牛飼いじゃありません。登任さまが十年前に陸奥から連れて来たヤツで。都の邸に入ったときはまだ……六つくらいの小僧でしたよ。俘囚の出身ですが、笛や太鼓が上手でした。舞姫のさゆりの倅だと聞いています。さゆりもまた、陸奥から連れて来た女でして」
「……さゆりの、子だと?」
仁木緒は混乱した。
たったいま、千歳丸の口から「さゆりは藤原登任の無聊をなぐさめる女」と聞いたばかりだ。貴族が親子ほども歳の差がある女を側室にすることは珍しくない。舞姫のさゆりもそういう立場に置かれていたのだと納得し、納得しながらも少々苛立ちを感じてはいた。苛立ちは嫉妬に近い。
(だが、十七、八の荒彦が、あのさゆりの息子だと?)
おれの見た舞姫さゆりは何者だ。あれはどう見ても二十歳そこそこにしか見えなかったぞ。
頭をかきむしって、仁木緒はうめきたくなった。
千歳丸の言葉を信じるなら、さゆりと荒彦は母子であり、陸奥の俘囚。
俘囚……。仁木緒は膝の上のおのれの拳をさらに強く握った。
大和朝廷は陸奥国に住まう人々を「蝦夷(野蛮な異民族の意味)」と蔑称し、律令国家の中に組み込もうとしてきた。しばしば大和朝廷と蝦夷との戦いはあったものの、本格的な侵略を意図したのは平安京に都を定めた桓武帝の御代である。
蝦夷征伐の名のもとに陸奥国(東北地方)への出兵がされ、帝に従わぬ「まつろわぬ民」は捕虜として都へ送られてきたのだった。戦火に追われ、家族を殺され、捕虜となった蝦夷たちは朝廷の権威に服した囚人という意味で「俘囚」と呼ばれた。
俘囚(蝦夷)が強兵であることに目をつけた朝廷は「新羅が攻め入る九州の防衛に俘囚を配す」と決定。四国や九州に移住させられ、その地方を開拓しながら俘囚は軍兵として養われたのである。
仁木緒の一族、佐伯が国造として威を振るっていた讃岐にも、俘囚が入植を強制された歴史がある。その地方ではすでに混血が進み、仁木緒にかぎらず多くの者たちに俘囚の血が混じっているはずであった。
むろん、故郷の陸奥国にそのまま住まわせられた俘囚もいた。
「ちょっと待て、千歳丸」
仁木緒はやや手に余るものを感じながら、咳ばらいをしてのどの通りをよくした。
「異国の舞を心得た女が俘囚で、しかも荒彦と母子だというのだな?」
念を押しながら、文屋兼臣の言葉を脳裏に思い出していた。
……都では陸奥国を辺境の地と侮っているが……あそこは産出する黄金で、異国と秘かに交易しているという……
天上の彩雲にも似た長い袖布を自在にあやつり、自分の目の前で荒彦を連れ去った舞姫。荒彦の身代わりに、極悪人の能原門継を出現させた舞姫である。
深い緑の山河に囲まれた陸奥国に生まれ、その出身だという理由で「俘囚」と蔑まれながらも失脚した男の夜伽をしてきた女だからこそ、我が子を取り戻すために一世一代の舞踏を踏んだのかもしれない。
(では、能原門継が『あの女は、殺したはずだ……死んだ、はず』と自供したさゆりが、伎楽殿で炎に包まれて倒れていたのだという、おれの推測は間違っているのか? 四人の焼死体のうち、二人が僧侶だとして、もう一人がさゆりだと考えていたのだが……。それでも遺骸はまだ一人残っている。何者が焼死したのか……)
死せるさゆりの魂が息子の荒彦を連れ去ったとは思えなかった。
その舞をこの目で見たし、声も聞いた。笛吹童子に扮していたゆずかもまた「さゆりさま」と呼びかけている。
(あれは、生身の人間の女だ。そして、謎そのものだ)
そんな葛藤などお構いなく、千歳丸が首をかしげる。
「へえ、荒彦は名前に似ず、体は華奢で顔立ちも女みたいなきれいなヤツでね。さゆりから舞も教授されていたようだし、いつも伎楽殿の掃除や音曲の稽古をして、唄もうまかった。いい声をしておりましたね」
「声、か……」
「だからね、わっしら使用人は荒彦が人殺しで火を放ったなんて、信じちゃいません。きっと客人の誰かが、舞姫に夜伽を拒まれて腹いせにやったことだろうとささやき合っていまして……そういう風聞が立つのを恐れて、みんな解雇されたってわけですよ」
仁木緒は深々と吐息をついた。
頭にひっかかっていた能原門継の言葉がよみがえってきた。
……これではっきりしたぜ。脱獄した荒彦はやってもおらぬ罪に問われる天命だということがな……
やってもおらぬ罪に問われる天命。そう言ったのだ。つまり藤原登任の家司・伴家継は荒彦を捕らえ、濡れ衣を着せて検非違使庁に突き出したということか。
(やはり荒彦は、罪を否定できぬよう、のどをつぶされて庁に差し出されたのだ……)
「千歳丸、お前さま……いままで辛かったねえ……」
いつのまにかとよめが千歳丸の隣にすり寄っていた。事件について物語り終えた千歳丸の肩を抱き、とよめが鼻をすすった。
「怪我を負わされた上に、そんな恐ろしいことを胸に秘めて……あたしゃお前さまが気の毒で気の毒で、叫びだしそうだったよ」
「うんうん、わっしもお前という女がいたから、つらい思い出を堪えてこられたんだ」
手を取り合い、千歳丸がとよめのふくよかな体を抱きよせている。夫婦のそんな様子を横目でながめ、多紀満老人が数珠をまさぐりながら仁木緒に首を伸ばした。
「ここに、ゆずかをお呼びしましょうか?」
「そうですね……泥蓮尼どのもご一緒にお願いします」
とよめ千歳丸夫婦が肩を寄せ合って板の間から去ると、それと入れ違いに稲若が柱の影から顔を突き出した。
前のめりの姿勢で手招きする。仁木緒はその廊下に出た。
「佐伯さま、ゆずかを問い詰めるのはやめてくださいっ。あの子、何にもわかっちゃいねえんだ」
「稲若、これはおれの仕事なんだぞ。真実を明らかにしなくてはならない」
少しムッとして仁木緒が腕を組む。稲若は相手の不機嫌などお構いなしに早口でまくしたてた。
「ゆずかはかわいそうな子なんだ。瀬戸内海で両親を海賊に殺されて、多紀満じいさまと肩寄せ合って暮らしている。泥蓮尼さまに笛を教えてもらうのが嬉しくて、あの日、あの場所で舞姫のために奏でただけなんだって」
「その舞姫について、ゆずかは何か知っているはずだ」
「だめだよ! とにかく、ゆずかを怖がらせないでくださいっ」
「稲若、押し問答をしている場合じゃないんだぞ」
そう言い放ってから、多紀満老人を仁木緒は振り返った。
多紀満老人はぼうぜんと立ち上がっている。
板の間に戻り、多紀満老人に向けて仁木緒は強い口ぶりになった。
「ゆずかの両親は、海賊に殺されたのですか?」
「はい、倅夫婦はここで収穫した豆を布に代えるため、瀬戸内海へ……」「二人を襲った海賊とは、もしや能原門継では?」
白髪の髷を包んだ烏帽子が、がくりとうつむいた。仁木緒はたたみこんだ。
「能原門継の所業なら、船荷のみならず、その船に乗っていた人々の命すら強奪されます。女子どもといえど、命乞いのいとまもなく。それがやつらのやり方です」
「……倅たちは幼いゆずかに、櫛や鈴を土産にしてやる、楽しみに帰りを待っておいで……と。それが、今生の別れでした……」
「あなたは能原門継への恨みを晴らすため、ゆずかの笛の才を利用して舞姫と結託し、荒彦と能原門継を入れ替わらせたのではありませんか?」
そう言ってはみたものの、能原門継のような男に近づき、どうやって意識を奪ったのかは分からない。確かなことは能原門継が「尼僧(アマ)にはめられた」と無念がっていたことだ。それが泥蓮尼だと明かしてもいる。
「舞姫のために笛を奏でるよう、あなたならゆずかにさとすのは容易だった。それとも、親の仇を獄中へ送るため、と説き伏せて孫娘に笛を吹くよう命じたのですか? 泥蓮尼どのはどうなのです。あの人こそ、能原門継をはめる策略を弄したのでは……」
ハッとなった。稲若を押しのけてすぐ廊下へとって返した。玄関土間に置いた藁沓に足を入れて庭先に出る。
振り返ると仁木緒を追って来て立ち尽くしている稲若が視界に入った。その肩をつかんだ。
「泥蓮尼どのはどこだ。まさか、ゆずかと一緒に逃げたのか?」
「に、逃げたなんて……。あの人はゆずかが緊張しているから、少し一緒に散歩してくるって……すぐ戻るからって……」
「ばか! それが逃げたというんだっ」
そのまま仁木緒は稲若を伴って、しおり戸を抜けた。そのあとを多紀満老人がついてくる。
広がる葦原の上を風が通り過ぎていく。葦の葉がざわめいて波打っている。そのさまをながめ、それから都へと延びる路地を振り返った。
尼僧と少女の影は、どこにも見当たらなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

