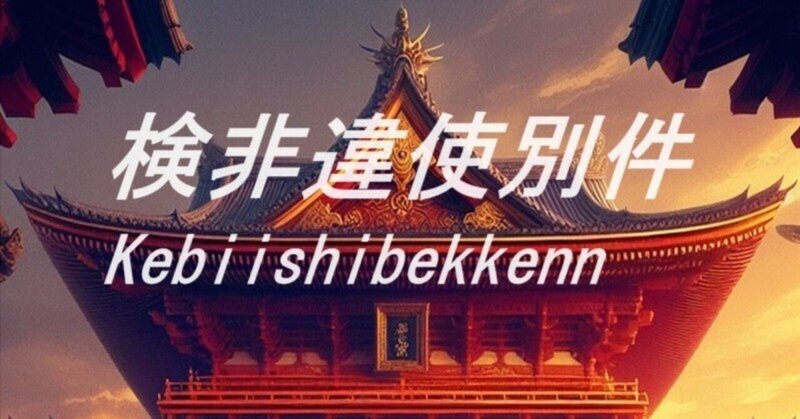
検非違使別件 二 ③
源経成の邸門前では、五月の風を受けて幄舎(テント)の幕が波打っている。
天幕の日陰に備えられた席に別当以下、佐(次官)、尉(警部クラス)といった検非違使庁の官人たちが座った。儀式での衣装も決まっており、頭に冠、足を包むのは草で編んだ襪、尉より上の階級はみな、一斤染めの束帯を身に着けている。
彼らと儀式用の覧筥を置いた台などを取り囲んで、ここでもすでに野次馬の人だかりができていた。
検非違使庁の役人と獄囚らを囲む群衆は、身なりも階級も実に雑多な顔ぶれだった。
すそを短く着つけて袖をまくりあげ、頭に荷を載せている女もいれば、すすけた烏帽子をかぶった髭面の男もいる。壺装束に虫垂れぎぬをつけた市女笠で顔を隠した女とその侍女、荒縄を帯に使っている汚れた顔の子どもたち。蓬髪をふりみだしたみすぼらしい老人もいれば、噂を聞き付けて、わざわざ牛車をしたてて見物にやってきた身分高い人物とその従者たちもいる。
毎年五月と十二月に行われる「着鈦の政」である。
刑罰権が検非違使庁にあることを示す儀式で、かつては市、あるいは罪人の首をさらす獄門の前といった人々の耳目を集める公の場で行われていた。
いまだ地方においては国司が刑罰権を握って死刑の執行が行われているのだが、この平安京においてはかつて嵯峨帝が「死する者、再びかえらず、遠流不帰の罪は死罪と同じき」として死刑は免じられて流刑とされるのが常だった。
右兵衛監藤原仲麻呂にそそのかされた兄・平城太政天皇が謀反を起こし、それを制した嵯峨帝である。兄の権威を吸収し、自身を徳の高い聖帝として確立するために「罪は死をもって代償としなくてよい」としたのである。
もっとも、平安京では死刑がないというのは表向きのことだ。
東国で「新皇」を名乗って反乱を起こした平将門をはじめとして、藤原純友など反逆者たちの首が平安京の東市のイチイの木にさらされている。討伐した国司らから賊徒の首を受け取り、鉾に差して練り歩き、樹木の枝に生首の髷を括り付けてさらすのも検非違使の仕事の一つだった。
御所で華麗なる王朝文化が花開く一方で、弓矢、鉾で武装した強盗団が都を荒らしまわらぬ日はない。
人質をとって貴族の邸に立て籠もることもあれば、権門の家に仕える武士たちが、それぞれの主人のために路地で合戦に近い小競り合いを起こすこともある。そうした場に急行して乱闘を鎮め、賊を切り捨てるのが検非違使だった。
かつて律令制下で司法、刑罰権を掌握していた「刑部省」と治安維持の職務機関であった「京職」だが、桓武帝の遷都とその後の平城太政天皇と嵯峨帝の二重政治で混乱をきたして弱体化。
嵯峨帝の補佐役として「蔵人」という令外官が発足。続いて治安を担う役所・検非違使庁が成立した。官人の検非違使もまた令外官である。
検非違使たるべし……という帝からの宣旨を下されて検非違使庁に詰める官人は限られている。
検非違使として正式に宣旨を受けるのは「佐(次官)」「尉(警部クラス)」「志志」そして「府生」の四つのみだ。
長官の別当は衛門督あるいは兵部督を兼ねていた。
貴族の中でも公卿と呼ばれる一握りの上流貴族であり、いわば、検非違使の長官は正確には検非違使ではない。
左右衛門府の衛士(兵員)でも腕の立つ者を「火長」と呼び、その火長の中から検非違使庁の看督長(看守)や案主(事務方)が選出される。
佐伯仁木緒が火長に任じられたのは二十歳のときで、翌年には検非違使庁の看督長をも兼務するようになった。
もともとは看守にすぎぬはずが、いつのまにか賊徒の捕縛までを職務とする看督長だが、宣旨を受けているわけではなかった。したがって正式な検非違使ではない。目覚ましい活躍をすれば看督長が府生に出世する特別な例もあるが、府生は一生を検非違使で終わるのが常だった。
看督長の下には、罪をゆるされて検非違使の仕事を手伝う「放免」がいる。
窃盗、強盗、殺人、乱闘、博打、強姦などを取り締まる検非違使は、犯罪の一つ一つをはじめのうちは刑部省へ届け出ていたのだが、その手続きをやめて罪人に足枷をつけて懲罰場で懲役につかせる役目までを掌握するようになっていた。
いまでは獄から未決囚を引き出して、検非違使別当(長官)の邸前で衆人環視の中で刑を定め、鉄の枷を着ける儀式「着鈦の政」が行われるのである。
「看督長・佐伯仁木緒、版木を置け」
上役の衛門志・坂上定成があごを上げた。
「はっ」
一礼すると、幄舎から二丈ほど距離をとった場所に仁木緒は手にした版木を置いた。
手が震えている。動揺を隠して面を伏せ、そのまま持ち場に戻る。
そうする間にも、紀成房は木簡に記した囚人過状を入れた覧筥を、うやうやしい手つきで右衛門権佐・藤原隆方に差し出している。
囚人たちは東西の二方向から引き連れてくる手はずになっていた。
仁木緒は東側から。もう一人の看督長・石川彦虫は西から。
顔を上げると、石川彦虫の視線とぶつかった。一瞬だけ、ニヤと口をゆがめた。
仁木緒は反発を感じた。一族を「斜陽」と嘲笑されたことが、いまだに胸に突き刺さっている。こいつにだけは負けるまい、と誓ったはずだ。
だが、いまは負い目から顔を伏せるしかない。
……脱獄した荒彦と能原門継を入れ替え、儀式の場で正式に足枷をつけてはどうじゃ。
そう言いだしたのは紀成房だ。真っ先に同調したのは石川彦虫である。
仁木緒は荒彦脱獄を許した当事者として、職務怠慢を責められて自身が罪人となる覚悟をつけていた。
……とにかく、このことを佐さまや尉さまへ連絡しなければなりません。
駆けだそうとする仁木緒の肩を石川彦虫が押さえた。
……よせよせ。儀式まで時がないというのに、上役を困らせるつもりか? ま、囚人の列の監視役をおおせつかったおぬしだ。失点を解消するため、いずれ脱獄した荒彦を追跡し捕縛する許しを求めるのは当然だが、これからすぐに儀式が始まるのだぞ。
もっともらしく石川彦虫は言ったが、内心では仁木緒が困惑していることを面白がっているに違いない。一方の紀成房は明らかに仁木緒の身の上を案じていた。
……いまここに長年のあいだ捕縛できずにいた能原門継がいる。この能原門継をまずは押さえておくのが大事。荒彦の身代わりに、儀式で足枷をつければ上役さまらの心証もよろしかろう。なにより、おぬしの父上・周宜どのは半身が動かぬ病人ではないか。心労をかけてはいけない。この場しのぎであっても、ひとえに儀式のためでありましたと、上役さまにわしからも口添えいたすぞ。
追い詰められた焦燥感から、やむなく仁木緒は能原門継を無理やり立たせ、肩に縄目を食いこませて列に加えたのだった。
#創作大賞2024 #ミステリー小説部門
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

