MMGB - CYNIC
本稿は、2023年12月のCynic来日公演に向けて書かれたものである。Cynicは“プログレッシヴ・デスメタル”の代表格として語られることが多いが、その音楽性はメタルとしてはきわめて特異で、どちらかと言えば近年のジャズや黎明期のポストロック、Radioheadやblack midiのようなバンドが好きな人にこそアピールする側面も多い。もちろんメタルの歴史が生み出した最高のバンドの一つではあるのだが、メタルファンの間だけで知る人ぞ知る名バンド扱いされ続けるのはあまりに勿体なさすぎる。また、メタルシーン内の定評を知らずに接した音楽ファンが新鮮な切り口で語る機会も増えてほしい。というわけで、以下の作品評はむしろメタルファンでない人を想定したものになっている。お楽しみいただければ何よりだ。
なお、12月の来日公演は、『Focus』30周年を記念してその全曲が演奏される。なのでまずは本作を聴いてみて、そこで興味を持てたのなら次に『Traced in Air』も聴いてみるのがいいと思う。この二つの作品における飛躍と共通点こそがCynicの面白さであり、関連する音楽ジャンルを理解するにあたっての糸口になる部分でもある。この最高のバンドを生で体験できる人をひとりでも増やせれば幸いだ。
Cynic 『Focus』
1993 USA(Roadrunner Records)
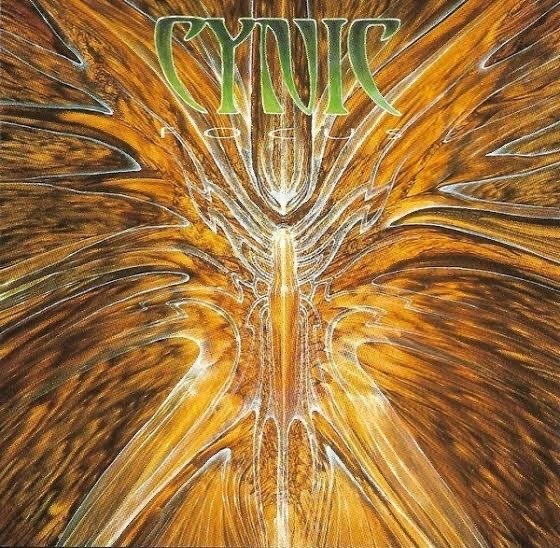
1stフル。いわゆる“プログレッシヴ・デスメタル”の原点にして頂点、孤高の存在感を保ち続ける傑作である。こう書くとマニア以外お断りの取っ付きづらいメタルに見えるかもしれないが、実際の音は非常に聴きやすく間口が広い。中心人物のポール・マスヴィダルが“人生を変えたアルバム”にブライアン・イーノの『Ambient 1: Music for Airports』を挙げていたり、ブックレットにThe Chick Corea Elektric Bandやアラン・ホールズワース関連の名前が並んでいるのを見てもわかるように、本作の音楽性は典型的なメタルよりもどちらかと言えばジャズロックに近い。その上で、アンビエント〜ニューエイジやフュージョンの要素を元文脈から切り離して用い、全く新しいニュアンスを生み出す創意が凄まじい。参照元をしっかり示しているのにこれほど突き抜けた個性を確立した音楽も稀だろう。Talk Talkをはじめとした黎明期のポストロックや後のRadioheadなどと併せて聴くと成り立ちを掴みやすくなるし、即興を多用する近年のバンド(black midiなど)に通じる要素も多い。そうした音楽が好きな方には特にお薦めの逸品だ。
『Focus』に初めて触れた人は「こんな音楽聴いたことない!」と驚くだろうが、実は既存の音楽語彙がそのまま使われている場面も少なくない。例えば「Sentiment」では、イントロのポリリズミックなドラム&ベース(21拍ループ、一部で23拍)に続くギターリフは70年代フュージョンによくあるフレーズからなる。また、中間部のアンビエントなソロもそこだけ切り取ってみれば確かにイーノ的でもある。しかし、そうした要素が本作特有のグルーヴや神秘的な雰囲気のもとで用いられると、元のジャンルとは全く異なる味が生まれる。続く「I’m But A Wave To…」イントロの不穏なシンセ(全てギターシンセで構築しているとのこと)や、名インスト「Textures」におけるポリリズミックなフレーズ(どこかパット・メセニーに通じる)も同様で、このような仕掛けは枚挙に暇がない。こうしたアレンジセンスはKing Crimson〜Voivodの影響が強い“プログレッシヴ”なスラッシュ/デスメタルの主流とは一線を画しているし、発想としてはヒップホップをはじめとしたサンプリング音楽に近い。後続に絶大な影響を与えたのに直接的なフォロワーが現れない理由は、表面をなぞっただけでは再現できないこうした成り立ちにもあるのではないかと思われる。
その上で、本作最大の妙味になっているのはやはり唯一無二のアンサンブルだろう。ショーン・レイナート(ドラムス)とショーン・マローン(ベース)というメタル史上屈指のリズムセクション(演奏スタイル的には一般的なメタルの枠を大幅に逸脱)もさることながら、ポール・マスヴィダルとジェイソン・ゴーベルのギターが素晴らしい。ファンクや中南米音楽のリズム構成を入り組んだリフ(どこかYes風でもある)に改造し、それをスラッシュメタル系譜の硬く速い刻みで料理したようなリズムギターは、以降の作品にも引き継がれるCynic最大のシグネチャー・サウンドとなった。こうした出音が絡み合って生まれるグルーヴは、溶けかかった金属のスープが蠢くような不思議な質感で、音楽史上を見渡しても似たものがない。ヴォコーダーを通した歌メロ(2010年代以降は当たり前のように用いられるようになったが、この当時はメタルに限らず稀だった)との相性も抜群。すべての音楽ファンに聴いてほしい、永遠の名盤だ。
Cynic 『Uroboric Forms – The Complete Demo Recording』
2017 USA(Century Media Records)
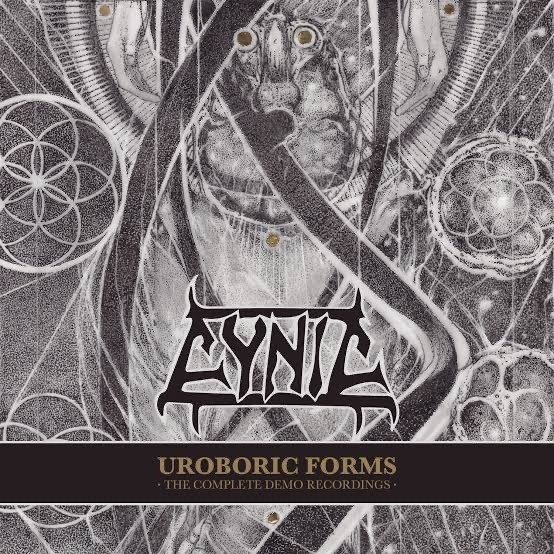
1stフル発表前のデモ音源を集めたコンピレーション。『Demo 1988』『Reflections of a Dying World』『Demo 1990』『Demo 1991』の4作に加え、ボーカリストのオーディションを兼ねて制作された「Uroboric Forms」「The Eagle Nature」の1991年音源が収録されている。基本的には当時のシーンからあまり乖離していない音楽性で、マスヴィダルとレイナートが参加し注目されるきっかけとなったDeathの名盤『Human』(1991年)や、伝統的メタルの最終進化形とも言えるAtheistの傑作『Piece of Time』(1990年)および『Unquestionable Presence』(1991年)、そしてPestilenceの『Testimony of the Ancients』(1991年)と同様に、スラッシュメタルからデスメタルが確立されていった黎明期のスタイル(ギターリフの並びで曲の大部分を構築する)を基盤としつつ、そこに収まらないアイデアが漏れ出ている、というくらいの仕上がりになっている。
最大の聴きどころは上記の2曲だろう。『Focus』収録の完成形と比べると、ギターリフをはじめとした基本的な展開は概ね出来上がっているが、ドラムスやベースのフレーズは異なる部分も多いし、何より印象的な歌メロがほとんど入っていない。ここにヴォコーダー付きのクリーンボーカルが入ることでポップソングとしてどれだけ洗練された(ギターソロも含めリードフレーズが適切に配置されたことで曲としての進行軸が定まった)のか、ということが非常によくわかる。こうして聴き比べると、『Focus』における音楽的達成の秘訣はリフ主導構造からの脱却にあることが見えてくるし、その上でデモ期に培った優れたリフ構築力も活かされていることもわかる。この時期の音源は正直言ってマニア向けだが、初期デスメタル(OSDM)や黎明期の“プログレッシヴ・デスメタル”が好きな人はマストだし、1990年と1991年のデモでベースを担当しているトニー・チョイ(AtheistやPestilenceの名盤にも参加)も含め、当時のシーンの凄さがよく示されてもいる。『Focus』が気に入った人はぜひ聴いてみてほしい。
なお、『Demo 1991』収録の「Pleading for Preservation」は、アウトロの叙情的なツインリードギターが『Focus』最後の曲「How Could I」に引き継がれている。『Focus』全体のジャンル越境的な音楽性がこういう様式美メタル的なフレーズで締められる展開は唐突にも思えるが、出自の表明として重要な表現になっているし、そこも含め作品全体の完成度は非常に高い。こうした理解を深めてくれる点においても、とても良い音源集である。
Portal 『The Portal Tapes』
2012 USA(Season of Mist)

『Focus』の路線を踏まえて制作された、別名義バンドPortal唯一のフルアルバム。1994年に解散したCynicとほぼ同一メンバーで1994年から1995年にかけて録音されたがお蔵入りとなり、再結成後のCynic(2006年〜)が高く評価されたのをうけて2012年にリリースされた。最大の特徴はアルーナ・エイブラムズ(ボーカル、キーボード)の参加だろう。マスヴィダルとのツインボーカル体制は、同時期に確立されつつあった男女混声歌唱のゴシックメタル(My Dying BrideやAnathemaなど)を想起させるが、Cocteau TwinsやDead Can Danceに通じるニューウェーヴ〜ゴシックロック系譜の音楽語彙はこちらの方が遥かに前面に出ている。これは、『Focus』で示されたアンビエント〜ニューエイジやフュージョンの要素が発展的に引き継がれているからこそやりやすくなったことでもあるだろう。こうした80年代的な音楽要素は長く敬遠される対象だったが、それが一転して歓迎されるようになった2010年代以降の感覚で聴くと全面的にアリに思える。『Focus』でさえ歓迎されなかった当時のシーンの感覚では確かに厳しい内容だが、今なら抵抗なく聴ける人も多いのではないだろうか。
実際、本作は優れたアルバムだ。どの曲も非常に出来が良く、全体としてはやや間延びしているように感じられる曲順構成も、緩慢に漂い浸る曲展開には合っている。再結成後の路線にそのまま繋がる内容だし、AtroxやRam-Zet、Unexpectのようなテクニカルなゴシックメタルの先駆けとしても聴ける要素を含みつつ、Dream Unendingなど近年の尖鋭的なメタルに通じる部分も多い。再評価されるべき作品だ。
Cynic 『Traced in Air』
2008 USA(Season of Mist)

2ndフル。1994年に一度解散してから2006年に再結成、実に15年ぶりにリリースされた作品だ。Cynicの知名度は当時も低いままだったし、『Focus』を高く評価していたファンも新譜の発表は寝耳に水。嬉しく思いながらも、伝説的なキャリアに見合った作品を期待していいのかと懐疑的にみていた人も多かった。しかし、蓋を開けてみれば新譜の出来は圧倒的で、予測を裏切りつつ期待を超えてくる内容に誰もが納得させられたように思う。演奏も楽曲も全編素晴らしい。今に至るCynicの音楽性を完成してみせた傑作である。
Cynic解散後のポール・マスヴィダルとショーン・レイナートはÆon Spokeを結成し、Portalをインディロック/オルタナティヴ方面に推し進めた音楽性を追求していた。1stフル『Above the Buried Cry』(2004年)が2022年に再発された際のインタビューでは、マスヴィダルの影響源が具体的に述べられている。最大のインスピレーション源と公言するJ.S.バッハに加え、Bread、サイモン& ガーファンクル、キャット・スティーヴンス、ハリー・ニルソン、エリオット・スミスといったフォーク方面のシンガーソングライター(SSW)が多数。そこにニール・ヤングやWilco、My Bloody Valentineなどの名前も並ぶ(自分よりも後にデビューした人も多い)様子は、メタルシーン屈指の技量を誇るギタリストという一般的なイメージからはかけ離れているようにもみえる。しかし、表現力や求める雰囲気の面ではこちらこそが本領なのだろうし、実際Æon Spokeではこのような持ち味がよく示されていた。そうしたキャリアを経て発表された『Traced in Air』は、上記のオルタナ/フォーク路線をCynicのシグネチャー・サウンドで彩り(比較的知名度の高いスタイルで化粧を施し)強引にメタルに落とし込んだ、ある意味ではセルアウトとさえ取れる作品なのだが、それが素晴らしい成果をもたらしているのだから面白い。マスヴィダルの歌唱力が飛躍的に成長したこともあってかソングライティング(特に歌メロまわり)は更に冴え、それを最高の演奏表現力が支える。メタル的な硬さとインディロック的なローファイ感覚を特有の粘るグルーヴで繋いだサウンドも素晴らしい。名曲「King of Those Who Know」をハイライトに据えた曲順構成も完璧。『Focus』とは全く別の方向性を示しつつ、クオリティの面では並んでみせたアルバムだと言える。
『Traced in Air』は、メタルにおけるインディ/オルタナ的な要素の導入を最もうまく推し進めた作品の一つであり(そういう評価がメタル内からいまだにほとんど出てこないほど自然になされていることも含め)、そちら方面にあまり興味のないミュージシャンがこれ以降のCynicから影響を受けてそうした要素を伝播させていく取っ掛かりにもなっている。本作に参加したギタリストTymonが率いるExiviousがプログ・フュージョン的なバンドの系譜を更新するなど、文脈的な繋がりも重要。同時期のRadioheadなどにも勝るとも劣らない傑作だと思われるし、広く聴かれてほしいものである。
Cynic 『Re-Traced』
2010 USA(Season of Mist)

1st EP。『Traced in Air』収録の4曲をインディロック〜トリップホップ的なスタイルで再構築、そこに新曲「Wheel Within Wheel」を加えた作品である。と書くと別に聴かなくていい企画ものに見えるかもしれないが、各曲の仕上がりは元ver.と同等以上に素晴らしい。Cynic流の目まぐるしいアレンジを取り除いたぶん、各曲の悲痛で温かい表現力が丸裸になっていて、マスヴィダル特有のメロウかつシリアスな雰囲気は本作が最も顕著に出ているように思う。それだけに、聴き手に刺さる力は良くも悪くも非常に強く、Cynic流のアレンジはそれを中和する意味でもうまく働いていたことがよくわかる。超一流のオルタナティヴ・ソウルとしても聴けるSSW作であり、「Integral」などはGastr del Solのようなポストロック〜フォークにも通じる。メタル的な鳴りにこだわらない人ならこれを入門編としてもいいのではないかと思う。
新曲「Wheel Within Wheel」もとても良い。スタイルとしては確かに『Traced in Air』の延長線上にあるが、メタルにおける “ジャズ”の参照対象が80年代までのフュージョンから同時代のジャズに移行している感じが示されていて、とても新鮮な印象が生まれている。これは、マスヴィダルがベン・モンダー(2000年代以降のジャズギターを代表する名手で、ECMからも作品をリリースする一方、プログレッシヴなメタルから大きな影響を受けている)など、自分より後の年代に頭角をあらわしたミュージシャンからも積極的に学んでいるからこそ可能な進化なのだろう。この時期、Animals As Leaders(1stフルを2009年発表)やPeriphery(1stフルを2010年発表)など、メタルにおけるジャズ要素の活用を更新するバンドが台頭してきたが、Cynicはそうした新たな世代に大きな影響を与えつつ、自身もそれらに並ぶ現代性を獲得している。このような観点からもさらに評価されるべきバンドだと思われる。
Cynic 『Carbon-Based Anatomy』
2011 USA(Season of Mist)

2nd EP。ギターとグロウルを担当していたTymonが離脱、前作には不参加だった名ベーシストのショーン・マローンが復帰した作品で、デスメタル由来の要素を完全に排除(これは以降のアルバムも同様)。音楽性としては、スピリチュアリズムへの傾倒が増した歌詞に応じるかのように、『Focus』期にもあったニューエイジ風味が特濃で復活。その上でメタル的に勇壮な展開も増えていて、良くも悪くもとても刺激の強い雰囲気が生まれている。個人的な相性としてはなかなか難しい作品で(主に雰囲気の面で)、クオリティは申し分なく高いものの、EPの尺で簡潔に済ましてしまうには惜しい内容ではないかと思う。とはいえ、23分の短さでニューエイジ的な(ロングスパンで浸らせるのが一般的な)サウンドスケープを違和感なく複数配置してしまえるのも凄いし、どのようにして成立しているのか吟味するのが面白い一枚でもある。過渡期の作品だが、バンドの変遷を考えるにあたっては重要かもしれない。
Cynic 『Kindly Bent to Free Us』
2014 USA(Season of Mist)
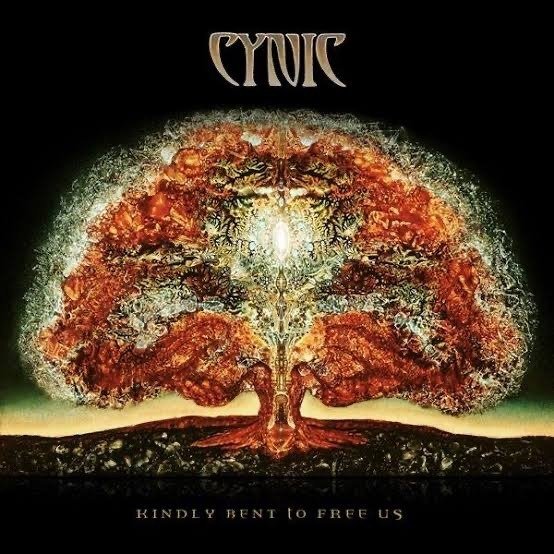
3rdフル。前EPの路線を引き継ぎつつうまく軌道修正した感のある作品で、Æon Spokeに違和感なくメタル的なエッジを加えつつ、ローファイ&サイケデリックなインディロックに寄せた印象がある。マスヴィダルはこの当時のインタビューでTame Impalaの『Lonerism』(2012年発表)やカエターノ・ヴェローゾをよく聴いていたと発言しており、仄暗くぼやけた音響は確かに通じる部分が多い。面白いのはそこにCynicならではの分厚く粘ったグルーヴが加わっていることで、RushとAnimal Collectiveの間にあるような不思議な音像が生まれている。楽曲の出来も良く、他作品のような明快さには欠けるものの、いずれも渋くキャッチーに仕上がっている。個人的にも、リアルタイムではピンとこない部分も多かったのだが、インディロック的なものをよく聴くようになってからはしみじみ良いと思えるようになった。マスヴィダルが影響を受けたというキューバ音楽の要素(『Focus』の頃からギターリフのリズム構造に活かされていると思われる)もうまく映えている。複雑な滋味が好ましい、燻し銀のように奥深いアルバムだ。
Cynicは本作に伴うツアーの一環で2015年に来日。自分は東京2公演を観ることができたが、いずれもきわめて素晴らしい内容だった。しかし、この直後にバンドは空中分解。ショーン・レイナートは2020年1月に亡くなり、ショーン・マローンも同年末に亡くなったことで、本作までのラインナップで再始動することは不可能になってしまった。早逝が本当に惜しまれる。
Cynic 『Ascension Codes』
2021 USA(Season of Mist)

7年ぶりのリリースとなった4thフル。過去作で重要な役割を担ってきたこのジャンルを代表する達人、ショーン・レイナート(ドラムス)とショーン・マローン(ベース)が2020年に相次いで亡くなり、バンドとしての活動が危ぶまれていた中で発表されたアルバムで、ファンからの期待とハードル設定は非常に高くなっていたのだが、蓋を開けてみれば概ね満足されているというか、基本的には絶賛とともに迎え入れられているように思われる。
そもそもCynicは2006年の復活以降は実質的にポール・マスヴィダル(ギター・ボーカル)のリーダーバンドで、マスヴィダル特有のメロウかつシリアスな音進行感覚を各プレイヤー特有のフレージング(1993年の歴史的名盤1stフルにもあった、まどろっこしく蠢くようなギターリフや、既存のメタルやジャズロックの枠を大きく超えた創造的なドラムアレンジ)によりCynic的に料理する活動を続けてきた。ここまでの各項で述べてきたように、マスヴィダルの音楽志向はメタルやプログレッシヴロックよりもインディロック寄りで、それをメタルファンにも納得しやすい形に整理したのが2008年の歴史的名盤2ndフルだったのだ。そうした経歴を踏まえてみると、本作4thフルは上記のような持ち味を見事に発展させ、過去最高の形でまとめ上げた傑作だといえる。9つのソングと9つの短いインタールード(数個の主題による変奏と思われる)からなる構成は、冒頭の「The Winged Ones」と真ん中の9トラック目「DNA Activation Template」で同一展開(一見5拍子に思われるが全部4拍子)を持ってくるなど、アルバム全体のまとまりが緻密に考え抜かれており、それが各曲のやや歪な展開と絶妙なバランスを生んでいる。マスヴィダル特有のフレーズ&コードも実に良い感じで、柔らかくもどこまでも沈んでいくような展開(『Re-Traced』に顕著、繰り返し接しているとしんどくなるので個人的には惹かれつつも苦手だった)が絶望一辺倒でない前向きなまとめ方をされているのが好ましい。2017年からドラムスを担当しているマット・リンチの演奏も素晴らしく、レイナートとは異なるタイプの変則的なフレーズ構成とメタルコア以降のグルーヴ感覚をもってこのバンドの質感を現代的にアップグレードしてくれていると思う。また、プロ奏者によるシンセベース(客演のデイヴ・マッケイが担当)を全面的に駆使したほとんど初めてのメタル作品であり、それだからこそ可能になるアンサンブル表現を最高の条件で達成したアルバムだとも言える。
個人的には、2ndフル以降では本作が最も肌に合う。インディロック方面とメタルの融合の尖端部としても評価されるべき傑作だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
