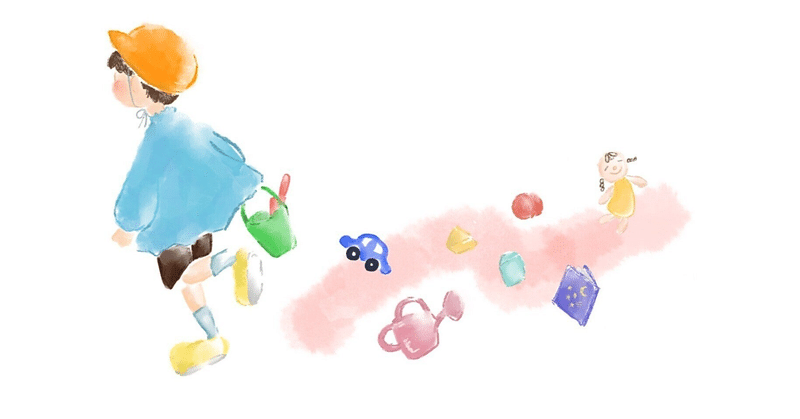
発達障害児の保育園の探し方
保育園を決めるにあたって助言をもらい、実際におこなったことをまとめました。
1 保活の心得

障害を抱えた子供の入園にあたっては、「園の迷惑にならないだろうか」「他の子供達と楽しく過ごせるだろうか」「この園でいいのだろうか」と悩みは尽きません。
▶︎園見学をして思ったこと
理想とする完璧な園というのは残念ながら存在しないと言うことでした。
どの園も「対応は良いんだけれど、通勤距離がちょっとなあ」「人気だから人数が多すぎるなあ」と悩みます。
園を決めることについて「自分がやれることはやった。この後のことは分からないけれど、その時々で判断するしかない」と言う気持ちが大切だと思うようになりました。
▶︎地元の情報は地元にある
最近は発達障害について書籍やメディア、ネットなど多くの情報を目にする機会に恵まれています。とてもありがたいです。
同時に地元の情報は地元で情報収集するしかありません。
医療も福祉も教育も地域格差があります。地元の情報に詳しい信頼できる支援者の複数の意見を聞くのが良いのではないでしょうか。
▶︎親のメンタルケアが大切
最後に保育園探しは心身ともに疲れます。
私が家は厳しい言葉を投げられたわけではないですし、実際の園見学は3園にしぼりました。
それでも事前の情報収集の焦り、園見学の緊張や疲労、園の決定が出るまで祈る気持ちがありました。
園見学の後は、自分への労いとしてご褒美を作っておくことをお勧めします。(私はちょっと良いチョコを食べました)
2 事前の情報を整理する

▶︎主治医の意見について
疾患や障害の特性から、園生活について注意する必要があることを聞きました。
「受診の目安」や「怪我に注意」など園と安全配慮上、共有しておいた方がいいことについて助言がありました。
また我が家は入園前に診断が降りていたので、加配保育士の申請のための診断書も書いてもらっています。
▶︎行政(保健師や言語療法士)の意見について
候補となる園をいくつか挙げて、優先度をどのように決めるか助言をもらいました。公立と私立、大人数と少人数で我が家が判断に迷っていたためです。
共通した意見は、「少人数の方が目は届きやすい」でした。
一方、「公立は保育士の質が一定は担保されているので、公立の優先度を上げる方が良い」と言う意見と「私立保育園も行政との風通しが良く人数もほどほどで、連携が取れやすい園のため優先度を上げて良い」との意見があり、甲乙つけ難い様子でした。
また行政職員は名指しで「この園が良い/悪い」と言うことはできませんが、「この園の雰囲気や環境は、我が子の◯◯な特性を見ると合いそうでしょうか。本人が辛くなることは何かありそうでしょうか?」と尋ねると、我が子にとってどうかを教えてくれる時があります。
例えば「ルールや決まりが明確で、その中にいる方が安心するタイプに合う園」と「あまり決まり事がなく、自分でやりたい気持ちが強くて見守ってもらえる方がイキイキするタイプに合う園」は違います。
このあたりは長年地域に関わって各保育園の情報を持っている行政の強みです。
総じて公立/私立にかかわらず、行政との連携がとりやすい園は、何かあった時に外部からの知識や意見を取り入れて問題解決を図れる土壌があると判断し、我が家では保育園決定の判断材料の一つとして大切にすることにしています。
▶︎市立子育て支援センター(保育士)の意見について
小さい頃から市立の子育て支援センターを頻繁に利用していました。そのため子供の成長具合を先生方はよくご存知でした。
市の保育士さんは、公立の各保育園に移動します。実際に働く側として園の多忙具合や一緒に働いた園長先生のことなど、教えて頂きました。
▶︎ホームページについて
市が公開している園の情報(住所、定員、時間外保育、病児保育)を確認します。
3 園見学の準備

園見学は4月や5月は避け、6から8月頃に連絡することをお勧めします。
子供も学年が代わり、保育士さんも新しく異動されたばかりの人もいます。環境が変わったばかりの春先は避けたいです。
事前に電話で「入園希望であること」「障害児の受け入れについて相談したい」「いつ頃、園見学が可能か」について伺います。
4 園見学で見ること

園見学では園内の各教室の案内をして頂きました。
張り紙や視覚支援は実際にお子さんたちのいる教室をまじまじと見ることはできないので、遠目での見学にはなりますが確認できます。
電話や訪問時、「すぐ応対してくれるか」「保育士さんに笑顔があるか」は、先生方の余裕を見る目安として大事だと思います。
どんなに優秀な保育士さんであっても、余裕がないと力を十分発揮することはできません。
笑顔は精神的・肉体的に余裕がないと難しいです。
また過去の障害児への受け入れ経験について伺うことをお勧めします。
その時の反応で園が受け入れに前向きか後ろ向きか感じることができます。
特に園長先生や園長代理の先生方のリアクションは、その園の雰囲気を反映することが多いです。
周囲の交通量やパニック時のクールダウンの場所についても、可能性として高い場合には確認が必要だと思います。「この場所で気持ちを落ち着かせようとする子供が多いです」とさっと教えてくれる園は、経験豊かである可能性が高いです。
また運動会などの園行事の見学も可能であればお勧めします。園の先生方と子供達の実際の関わり方を目にする貴重な機会です。
5 園見学で伝えること

「診断名」「療育の頻度」「内服」「普段の様子や園生活で心配していること(偏食、多動、言葉の遅れ、他害や自傷など)」や「加配の手続き」について話しました。
家や療育施設での姿と園生活での姿は、良くも悪くも異なることがあります。当時はなかった課題が成長するとともに出てくることもあります。
入園後も家庭と保育園の情報をやりとりすることは欠かせません。
現在、保活に取り組んでいる皆様が良い園とのご縁があるよう願っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
