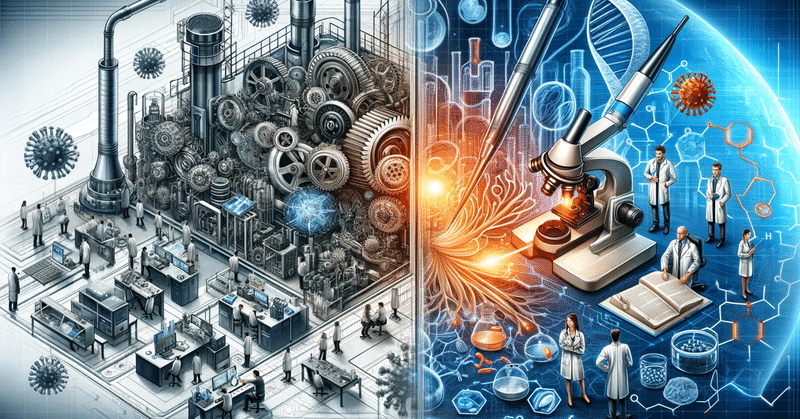
医工産学連携の基礎:(1) 医工連携における医療と医学と工業と工学と 〜 学の視点から
このシリーズでは、研究者として医療機器・ヘルステックの研究開発と事業化、人材育成に関わった経験から、医工連携・産学連携で考えておくべき基礎的な事柄を自分の視点でまとめてみます。
※本シリーズは
北海道大学病院 医療機器開発推進センター医療機器開発人材育成プログラム(2021年11月)
「医工連携による医療機器開発:医療と医学と工業と工学と」名古屋工業大学―名古屋大学医学系研究科合同シンポジウム(2023年10月)
「共感とデザイン思考に基づく医療製品開発 〜実例によるデザイン思考・オープンイノベーションの理解とその功罪〜」
の講演内容をベースに、再編・加筆して構成する予定です。
医工連携と産学連携
医工連携とは、医学・医療分野と工学・技術分野が連携することで、医療技術の革新や医療サービスの向上を目指す取り組みです。この連携は、医療現場のニーズと技術的な解決策を組み合わせることで、新しい医療機器の開発、診断技術の向上、治療方法の革新などを実現することを目的としています。
医工連携と似たような異業種連携共創の取り組みとして、産学連携があります。産学連携は大学や研究機関などの「学」と、企業や産業界などの「産」が連携し、共同で研究開発などを行う取り組みです。その目的は、学術的な知見や研究成果を実社会の問題解決や新技術の開発に活用し、新たな製品やサービスを市場に提供することです。
この産学連携には様々な形態、例えば共同研究、委託研究、技術ライセンスの提供などがあります。基本的には企業のニーズに答える形で、大学・研究機関が保有するリソース、知識・研究・知財等のシーズを提供する形です。

経済産業省の産学官連携の系譜を見ると、大学等でのTLO(技術移転機関)の整備、大学の役割に産学官連携を明文化、国立大学からのVCへの投資を許可、税制改革、ガイドライン・ファクトブックの整備など、平成7年(1995年)から30年に渡る学術研究を起点とした産業振興・イノベーション創出の道のりが見られます。大学のリソースを学術だけでなく産業でも積極的に活用しようという活動です。
一方、逆に産業界のリソースを大学に導入することで、大学での高等教育の幅を広げる産学連携もあります。例えば企業でのインターンシップや、企業人材による講義・演習などです。「学」の教育機関としての役割を強化するための産学連携ですね。
医工連携における注意点:医療と医学と工業と工学と
医工連携では大学の医学部・病院と企業が連携するパターンも多いことから産学連携と似たようなニュアンスと捉えられることもありますが、「医療分野での産学連携 ≒ 医工連携」ではなく全くの別物です。
まず医工連携で注意したいことは、医工連携の医・工にはそれぞれ産・学の医・工があるということです。
すなわち、産の医とは「医療」、学の医とは「医学」。産の工とは「工業」、学の工とは「工学」。それぞれ同じ医・工でも学術的な医工とビジネスとしての医工があります。
一般的に世間で言われる「医工連携」は、最終的な医療機器・サービスを産み出す産業としての医工連携であり、中心的なパターンは「医療」の現場に存在する課題、ニーズに対して「工業」技術でその解決をはかり、製品サービスとして臨床に届けるパターンが多くみられます。
近年いろいろな自治体や学会、病院等で盛んに行われている医療ニーズ発表会で医療従事者と製造業がマッチングして製品開発を行うパターンなど。これは基本的には産しかいない、医療と工業による「産の医工連携」です。

一方、私は工学者(医工学者なので医学者でもあります)です。上記の医工連携には出る幕がありませんが長年医工連携に携わってきました。大学等研究機関では、医学者と工学者が学術的なアプローチで新たな診療技術を創出する「医工連携研究」が多く行われてきました。ニーズ・シーズについて医・工で協力して考えます。これは基本的には学しかいない、医学と工学による「学の医工連携」です。

(スタート時には医療ニーズは必ずしもない場合も)
このように医工連携の典型的な形態では「産の医工連携」か「学の医工連携」か。いずれも産学の連携ではない連携になります。
一方でこの形では収まらない医工連携ももちろん存在します。特にイノベーティブな新規医療技術・製品サービスや複雑で大掛かりな医療機器・システム、ハイクラスの新規医療機器等を創出するためには、産学連携としての医工連携の要求が高くなります。
産の医工連携では革新的な新技術を創出・導入することは難しく、学の医工連携では実装して製品化しユーザーに届ける過程を行うことは不可能です。片方だけではなく医工・産学、双方が必要になってきます。
※産の医工連携でもイノベーティブな製品実現が全く出来ないわけではありません。モジュール技術の革新(新規技術の創造)でなくアッセンブル技術の革新(既存技術の新規な擦り合せ)による価値獲得・付加価値創造を実現した製品は多くの工業製品で見られます。
医療機関と大学・研究機関と企業が関わって高度で実用的な新規医療技術を創出する医工連携、「医工産学連携」では、その連携が医療と医学と工業と工学の絡み合う複雑な関係の中での共同開発になることを考えておく必要があります。

(大分簡略化しています)
※実際にはビジネスを成功に導くために他の戦略に関わるプレーヤーももちろん参画あるいは枠外協力します。まず少なくとも行政支援と投資家・VC・アクセラレータ、問屋商社などが関わる「医工商産学官連携」にまではなるケースも多いでしょう。あと法・理・芸・歯・文あたりまで入るかも…総合大学ですね。
企業が医工産学連携で注意すべきは、学との付き合い
このように、産学連携としての医工連携、「医工産学連携」は医と工、産と学が絡みあい、様々なアイデアと技術、ニーズとシーズが行き交います。一般的な産学連携のように産業界のニーズを学のシーズで解決する、ではなく、医療のニーズに対してシーズを作り出すのは工業だけでなく医学と工学も関わります。参加するメンバーによって、技術・サービスの生み出し方には様々なパターンがあります。
製造業が新たに医療に参入する時や、ベンチャー・スタートアップを起業してイノベーティブな医療製品の実現に挑戦するときなど、医工連携に関わる際にまず注意すべきは、相手の医が単なる医療か、それとも医療+医学(あるいは+工学)か、学が関わるか、ということです。医者と医学者は別物です。
一般的な「産の医工連携」ならば基本的に医療従事者の役割はニーズを出す人で、ニーズは技術ではありませんので共同開発にはなりません。重要な「お客様の声」です。
一方医学or工学として学と共同でシーズを創出するならば、共同開発上での知財やその他いろいろ考慮しなければならないことが生まれてきます。これは最初に紹介した学術側のシーズを企業に導入する一般的な産学連携とも違うプラットフォームです。
医工連携では相手が医者なのか、医者かつ医学者なのか。医療従事者なのか、医療技術者・医療研究者でもあるのか。どういう立場で共創をおこないたいのかを見極めてからスタートすることが肝要です。
次は学との付き合いで知っておいてほしいこと
ということで、次の記事ではその「学」とはどういう生き物なのか。昔は「象牙の塔」に住むと言われた、その仕事の様子がわかるようでよくわからない職業について紹介します。
なぜ上述のように学との付き合いに注意しなければならないのでしょうか?医工産学連携で学者と付き合う時、学者は研究費以外に何を必要としてくるのでしょうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
