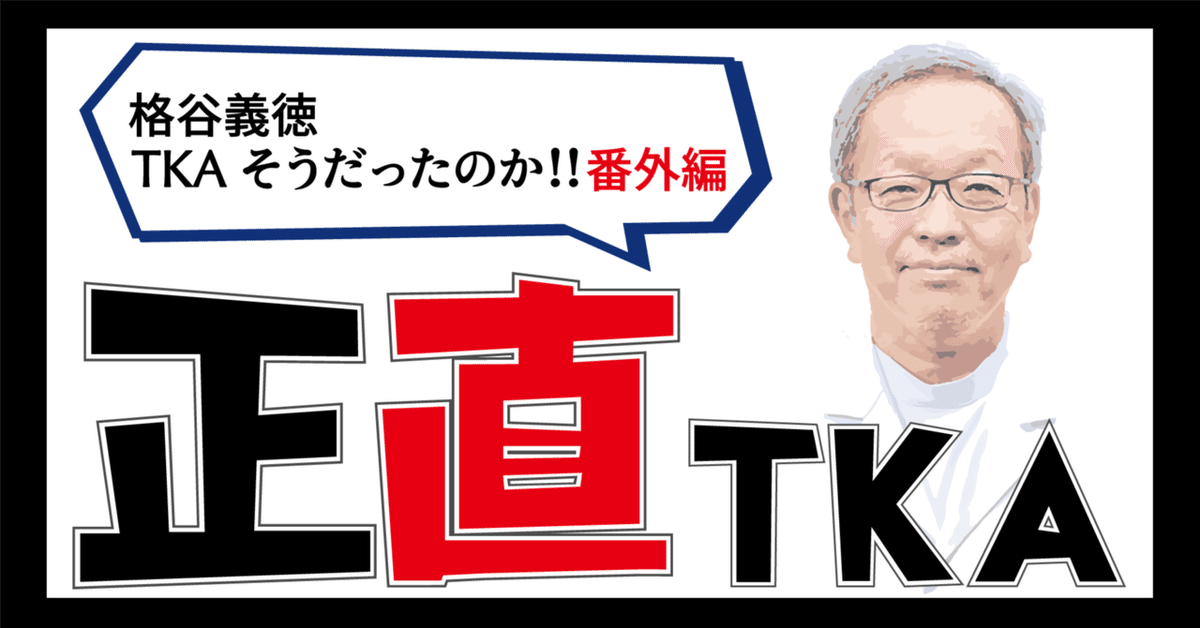
【第25回】正直TKA,過去-11:TKA手技の混迷の時代
阪和第二泉北病院 阪和人工関節センター 総長
格谷義徳
私が近藤先生とお会いした2000年代初頭は手技に関しても混迷期だった。それより少し前の1990年代終盤に,わが国でCR→PS,セメントレス→セメント固定への転換が起こったことは先に述べた。本来なら,これと同期してMeasured resectionからGap techniqueへの回帰が起こって然るべきだったのだ。なぜなら,その成り立ちから見てCRはMeasured resectionと,PSはGap techniqueと組み合わせられるべき(精一杯控えめに言っても“そのほうが相性のよい”)手法なのだから。しかし現実には,大多数の症例でMeasured resectionがそのまま行われることが多かった。
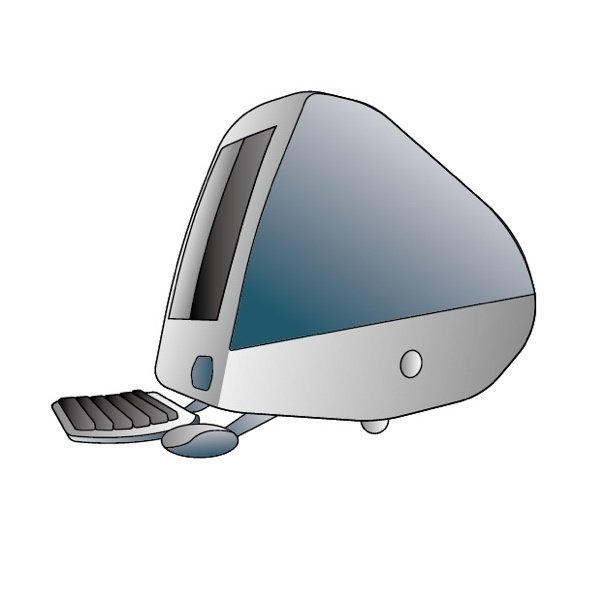
斬新なデザインと色使いの製品を次々に発売。新時代の到来を感じさせた。懐かしい。
その背景としては歴史的・理論的背景の理解不足が一番大きい。TKAに関わる人すべてのレベルが低かったのだ。だからコマーシャリズムの影響を強く受けてしまって,正しい判断ができなかったといえる。その意味で私がnoteで発信する最大の目的はTKAの民度みたいなものの総底上げなのだと再認識する。主体性を持った一般的凡人整形外科医が一人でも増えて,その人たちが自分なりの信念に基づいた判断ができるようになってくれればとても嬉しい。そして,結局それこそが患者さんの利益に一番かなうのである。
インプラント会社としては売り上げさえ上がればよいので,すべての症例が適応になり,CRからPS型への術中転換が可能なことをアピールする。“PCL温存を試みる際,もし機能不全であれば,術者の判断でPS型に移行していただければ・・・”という論法である。そこで手技書にはまずMeasured resectionによる手術法が記載されることになり,結局PSを使用する場合もMeasured resectionになってしまう。そして肝心のGap techniqueについては触れられることがない。元来PCLを切除するならそれなりの(理論的に整合性のある)やり方があるのだから,そのような妥協案に安易に乗せられてしまう術者のほうにこそ,おおいに問題があるのだ。つまるところ,“TKAの民度”が低かったのが根本的な問題だったといえる。

とはいえ,メーカーの手技書(たいていは英語版を訳しただけだが)にそう書いてあるのだから,よほどの知識や信念がない限り,それを踏襲することになる。ちなみに,メーカーが配布する手技書というものは総じて難解であり,無用の長物といってもよい。読んでみれば分かるが,TKAがとてつもなく難しい手術のように思えてくる。本質的には保険の約款と同じで免責条項の羅列(術者への責任転嫁である)になっているのだから,ある意味仕様がないともいえる。
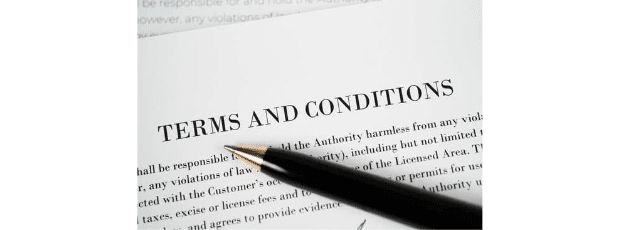
機種名のあり方も当時の混乱に拍車をかけていた。もともと機種名と手技は表裏一体であった。例えばIBIIであればPCL 切除のPS型でセメント固定,MGやPCAといった機種であればCR型でノンセメント固定という風に一対一対応していた。すなわち機種名が手術手技・コンセプトと直結しており,機種を選択することイコール,コンセプト・手術手技を選択することになったのである。しかし,後に導入されたLegacy, Persona, Vanguard Attuneなどの名前は単なるブランド名であり,さまざまなデザイン(PCLの処理,関節面の形状,セメントの使用・非使用など)のものが“術者のお好みで” (surgeon’s choiceまたはdiscretion)という名目で網羅されている。術者の幅広い要望に応えるというのが謳い文句なのだが,要するに適応症例を増やしてインプラントを多く売りたいという企業側の戦略にすぎない。このことは一般的整形外科医,特に方針の定まらない初心者にとっては迷惑な話である。
重要なことなのでもう一度(何度でも)言っておくが,PSとCRの選択は単にPCLを切離するか否かの問題ではなく,手術手技(Gap theoryとJoint line theory)やデザイン(関節面形状やカム-ポスト機構)を含めた基本的なコンセプトの選択と深く関連しているのだ。だから症例の特徴も考慮に入れたうえで,各自の信念に基づいて手術に臨むべきであり,“CRからPS型への術中転換”などという折衷案はとうてい合理的とはいえない選択なのだ。

根っこのところで相容れない人とは関わってはいけない。
前置きが長くなったが,当時(2000年代初頭)はPS型をMeasured resection法で手術するのはごく一般的な手法になって(しまって)いた。そうすると色々問題が起こり,手術が難しくなる。繰り返すが“根本的な理念に相違があり,相性の悪いものを組み合わせる”のだから当然である。具体的には屈曲ギャップが大きくなるのが最大の問題であり,その結果インプラントサイズが大きくなってoverhangが起こったり,屈曲拘縮が残存したりする。自分の技術が未熟だったせいもあるが,ずいぶん苦労して手術していた記憶があるし,それをネタにした論文も書いている。
Y. Kadoya et al. Effects of Posterior Cruciate Ligament Resection on the Tibiofemoral Joint Gap. CORR 2001; 391: 210-7.

この論文については,当時北大教授であった故松野誠夫先生からずいぶんお叱りをいただいたが,反面,影響力のあった論文だとの評価もいただいた。若干の自戒を込めてcoming outすると,“内側の軟部組織剥離を最小限にしておけばPCLを切除しても屈曲ギャップの開大は起こらない(少なくとも最小限である)”というのが本当である。この辺りの “PCL切除と屈曲ギャップの関係”は私のTKA関連の研究の原点であり,その後興味深い論文もいくつか出ているので,また項を改めて考察してみたい。
そんな2000年代初頭の混沌とした状況の中で近藤先生とお会いしたのだが,実際話を聞いて手術を見せてもらうと,目からうろこ,なるほどと思うことがたくさんあった。私が学んだことを羅列してみると,
1. 骨切りの順序(Tibia first or Femur first)は問題ではない
2. 伸展ギャップを構成する骨切り(大腿骨遠位&脛骨近位)は術前に決められる(術前計画で正確に作図可能)
3. 屈曲ギャップを構成する骨切り(大腿骨後顆部)は術中にしか決められない (術前計画では作図は不可能)
4. そのため,正確に決定できる伸展ギャップをまず作成し,それに合わせて屈曲ギャップを作成する方法のほうが理にかなっている
5. DependentとIndependent cutとは屈曲位での大腿骨後顆の骨切り位置の決め方の問題であり,Dependentがgapに,そしてIndependentがmeasuredに該当する(DependentとIndependent cutという呼び名は帰国後よく耳にしたが,留学中は一度も聞いたことがなかった。このあたりも10年遅れていたことの証左なのだろう)
総括すると,伸展ギャップに合わせて屈曲ギャップ“を作成するReversed gap techniqueなるものを提唱していたのであるが,これを誰に教わった訳でもなく作り上げたというのが驚きである。実際ご本人にその経緯を聞いてみたが,確かに誰に習った訳ではなく,自分で試行錯誤して辿り着いた方法だと言っていた。そもそも手術手技を自分で作り上げるのはごく限られた人(天賦の才に恵まれた人)が人一倍努力しないと成しえないことである。この近藤変法(新垣晃先生がこう命名された)がModified gap techniqueあるいはGap balancing techniqueとして広く(少なくとも本邦では)世間に認知されていくことになる。

近藤変法においては,伸展及び屈曲ギャップを形成する大腿骨遠位と後顆部の骨切りを“術前計画が可能か否か”で特徴付けた点がユニークであり,かつ実際的である。これは術前計画を入念にやる人しか気付かないことなので,私には出てこない視点である。しかし,逆説的ではあるが,大腿骨遠位&脛骨近位の骨切りを術中に正確に誘導できるテクノロジーを使用すれば(ポータブルナビのKnee align 2がそれに当たる)術前計画は必要ないという論理も成立することになる。これは,私がそれ以降の手術手技を考えるうえでの大切な気付きであった。
その後,われわれが“近藤変法”を誰もが再現性よく行えるようにと開発した器械がEquiflex™(現在のProflex-G)である。その経緯や背景を,さらに深く理解してもらうために,ここでTKA手技の歴史のおさらいをしておくことにしよう。

(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
