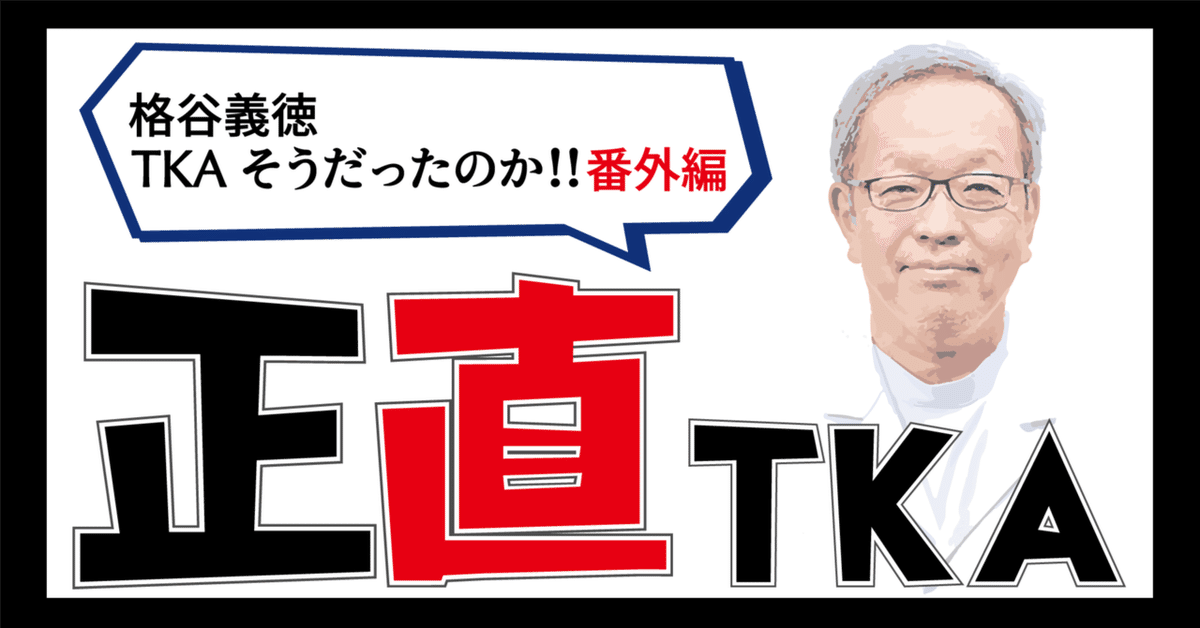
【第26回】正直TKA,過去-12:TKA手技の歴史(今こそ原点を見直してみよう)
阪和第二泉北病院 阪和人工関節センター 総長
格谷義徳
黎明期におけるFreemanの貢献
TKAの基本的手技を確立したのは誰かご存じだろうか? 基本的な考え方や手技が確立されたのは,1960年代後半から1970年代初めにかけてである。この熱気にあふれたTKAの黎明期については,自身の体験とインタビューを基にしたMr. Robinsonの論文に詳しいので興味のある方は是非一読をお勧めする。
Robinson RP. The early innovators of today's resurfacing condylar knees. J Arthroplasty 2005; 20: 2-26.
歴史的に言えば,今では金科玉条とされるMechanical alignmentや軟部組織バランスの概念を確立したのは他ならぬFreemanなのである(私の師匠だと思うとなんだか誇らしい)。同時にこんな“TKAの超大物”の所に,“何も知らない”だけでなく“THA surgeon”だと思って留学した自分を改めて恥ずかしく思う。
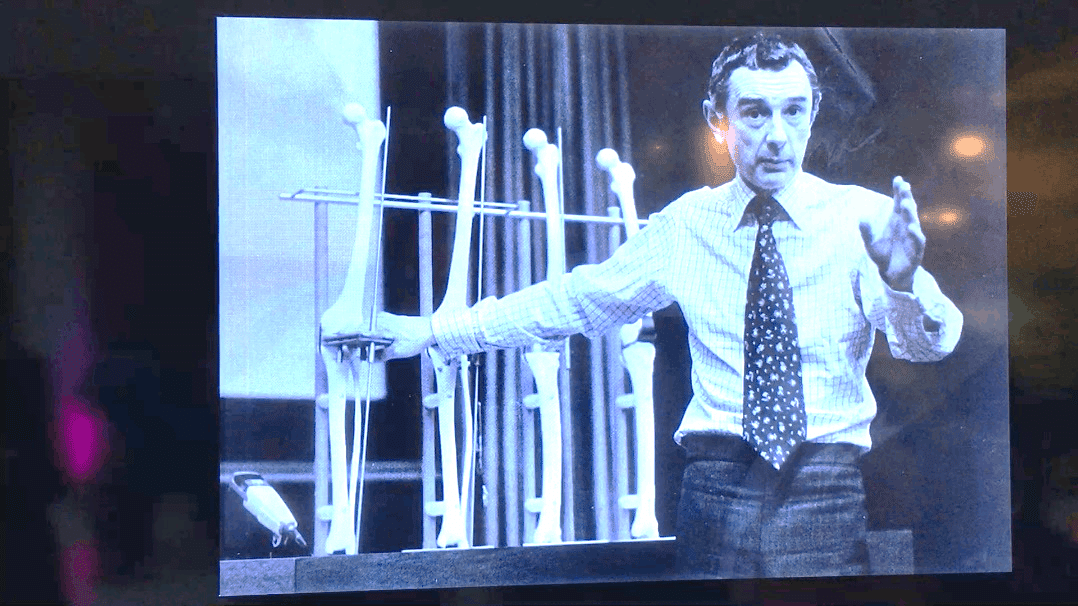

彼は議論にめっぽう強かったので,若干のやっかみを持って”Great debater”と呼ばれたが,何よりも“Scientifically honest”であったのだと思う。だから“dishonest”な人には厳しかったのだろう。
この分野でのFreemanの貢献については,TKA界のLegendの一人であるInsallも最大級の賛辞を贈っている。
“Although the Gunston polycentric prosthesis was the first cemented surface arthroplasty of the knee joint, the work of Freeman and colleagues has had an even greater influence on the direction of both prosthetic design and surgical technique”
“最初の表面置換型TKAはGunstonのpolycentric kneeではあるが,Freemanらの業績が以後のTKAデザイン及び手技,両方の方向性により大きな影響を与えた。”
他のどんな教科書や論文を見ても,彼の名前はTKAのパイオニアとして必ず出てくる。歴史をひもといてみると,TKAの基本的なデザインと手技を確立したのがFreemanであることは間違いなかろう。

なんとなく日本人には醸成しにくい関係に思えて,ちょっとうらやましい。
Freeman-Swanson Knee Prosthesis
それでは最初のTKAデザイン及び手技の方向性とはどのようなものだったのか見てみよう。さまざまなデザインや手技が乱立して混迷を深めつつある現在,原点となる考え方を知っておくことには大きな意味がある。これについてはFreeman自身によるTotal Replacement of the Knee Using the Freeman-Swanson Knee Prosthesis. CORR94:153-17, 1973に詳しいので,それを見ていくことにしよう。


解剖をばっさりと切り捨てた,Functional approachとしての“潔さ”を感じさせるデザインである。 左側が前方であり,PF関節は非置換というよりフランジ自体が存在しない。 大腿骨後顆部(右側)は円筒形であり,同一径のPEと関節する(roller in trough)。
彼がその論文中でデザイン上の要件として挙げているのは,
1. Salvageが容易であること:関節固定術に移行できるための骨温存がなされること
2. Looseningの可能性を最小限にすること
(ア) 関節面の適度な拘束性を持つ(incompletely constrained):ヒンジ型でないという意味であろう)
(イ) 摺動面の摩擦係数が小さい
(ウ) 過伸展の制限が緩徐である(これもヒンジ型との比較であろう)
(エ) 骨への応力集中を避けるため十分な固定面積を得ること(セメントを推奨)
3. 摩耗粉の産生を最小限にすること:接触面を大きくし,表面は平滑にする
4. 摩耗粉の生物学的影響を最小限にすること:MetalよりPEの影響が少ない
5. 感染の可能性を最小限にすること:インプラントはコンパクトに,死腔を小さく,軟部組織インピンジメントを最小限に
6. 感染が起こった際の影響を最小限にすること:長い髄内ステムや髄内セメントを避ける,インプラントはコンパクトに
7. 挿入のための標準的な手技が用意されていること
8. 5度過伸展~最低90度屈曲可能であること(120度以上は有用とは考えない)
9. 適度な回旋許容性(特に屈曲位において)と内外反許容性を持つこと
10. どの方向の運動に関してもLooseningやインプラント破損が起こらない範囲内で軟部組織(特に側副靱帯)よって制動されること
11. 適応となる膝の状態を考えれば,十字靱帯に機能的に依存するのは賢明ではない
12. 十字靱帯を切除しても,その機能が保たれている(代償されている)こと
13. 理論的にはPF関節も置換すべきだが,非置換でも許容できる結果が得られる
14. コストを最小限にすること
上記を読み通して,皆さんはどのように感じられただろうか? ヒンジ型から脱却して表面置換型に移行しつつある時期の記載だから若干の違和感がないではない。特に可動域に関する要求度は低いし,PF関節に関してはその後フランジが追加され,Freeman自身も置換派に転向している。とはいえ,この最も古い(であろう)TKAのデザインコンセプトの大部分が現在でも当てはまる(そしてしばしば忘れられている)ものなのには驚かされる。とりわけLooseningと拘束性(incompletely constrained)の関係や,摩耗粉の産生とその生物学的影響に関しては,21世紀にも通じる慧眼であったといえるだろう。

デザイン的には,Freeman-Swanson型(こそ)が”Functional approach”の原型であることを改めて認識させられる。補足しておくと,Functional approachとは“こういう形でないとポリエチレンがもたない”という材料工学的見地からの設計である。その視点からFreeman-Swanson型を見てみると,解剖をばっさりと切り捨てた,潔ささえ感じるデザインである。もちろん,それが気に入らない(膝関節の形状はこうあるべきだ)というロマンチスト(?)もいるだろうし,それはそれで否定はしない。さまざまな感受性や意見があることはむしろ健全である。それでも膝関節を手持ちの材料(現実的にはごく限られている)で表面置換しようとするなら,材料の特性・耐久性から逆算してデザインが決まってくるのも道理(必然)である。機能の向上を追求するにしても,あくまでも材料学的な耐久性(耐摩耗性)を担保したうえで行うべきであるという原則を,このTKAの原点ともいえる論文を通じて,今一度肝に銘じておきたい。

(つづく)
※TKAの手術手技に関する書籍の購入はこちらから↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
