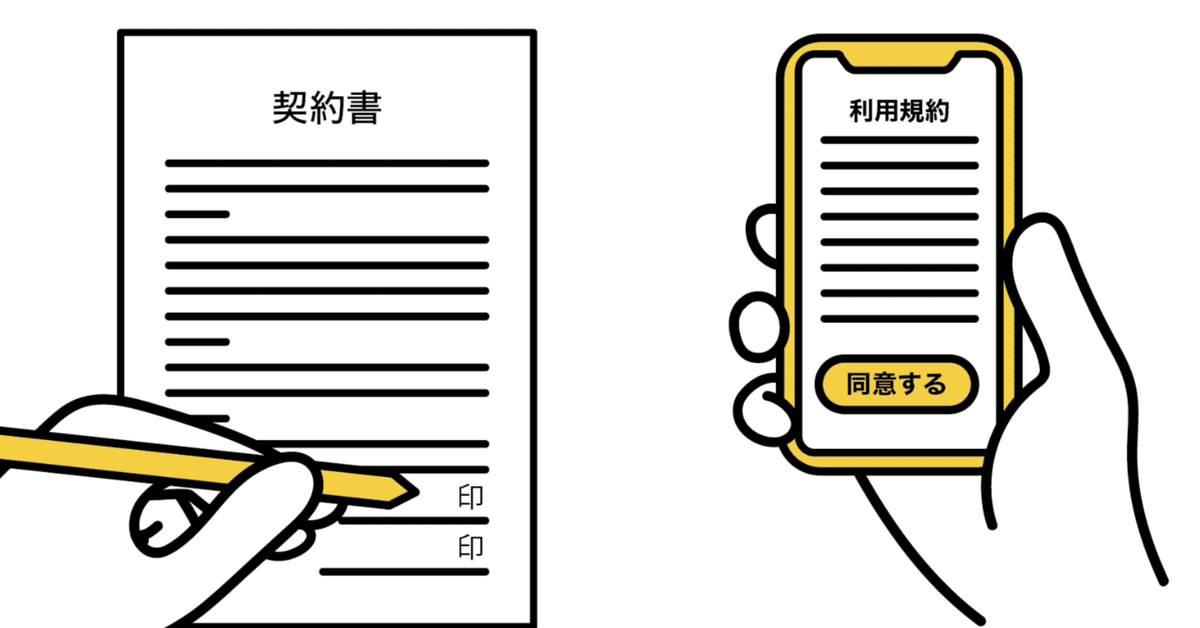
採用ついて
こんばんは、ももんがです。
ぼくは20数年前に某県の公立高等学校の新規採用職員として採用しました。その際に提出した書類は、通勤経路、自分の個票、共済組合登録、自家用車登録と「同意書」くらいでした。「同意書」には「某県の教育公務員として、しっかり働きます(要約)」です。
しかしながら、勤務条件や給与についてなどについての説明文書もありませんでしたし、ぼくは講師経験者でしたが、「基本給」がどのように決まったのかも説明はありませんでした。
もちろん、配属された学校での服務規定や某県教育委員会がさだめた含む規定も提示されていません。その上で例えば「座学はスーツで行う」「実習は必ず実習服(作業服)」「職員会議は必ず出席、時間外でも基本は出席する」などありました。職員会議の勤務時間外の出席については、ある時期から管理職も気をつけていました。会議の設定が会議が時間外にならないようになったり、時間外に及びそうな際には会議中に退席のアナウンスもでるようになりました。
20数年を某公立高等学校の職員としてやってきて不思議に思うのは、よくこれだけ情報をあいまいにして「公の機関」としてやっているなということです。
まあ公務員なので、条例等は公開されているのでそれをみろということだと思いますが、それであれば条例になっていないことは本人の自由だといことだと言えるのではないでしょうか。授業をする際の服装もスーツである必要があるとは思えませんし、そもそもすべての教員が座学でスーツを着ているわけでもないのです。それを目についた職員のみ管理職が個別に圧力をかけていくというのは、どういうことなんでしょうか?
最近小学校でも授業参観のときにスーツなどで着飾っている先生をみて、「授業参観」の本来の意味とはなんだろうかと思います。「授業参観」は自分の子供が、その友達が普段学校でどのような活動をしているのかを見る場面です。それを普段していない格好をしている先生の授業で、子どもたちの普段の様子って見れるんでしょうか。
スーツ着て子どもたちと活動しれくれない校長より、ポロシャツ・ジャージでこどもたちと活動している校長のほうが、子どもたちにはいい影響があるんではないかと思います。
そもそも服装にこだわるのであれば、きちんと服務規定にするべきです。それを管理職が各個人の教員に「お願い」するのは、ぼくは「パワハラ」だと思います。
教員の働き方改革で、すべてがかわるとは思えませんし、すべての先生、これから未来の先生が納得することはできないと思います。それはほとそれぞれの理想や考え方があるからです。しかし明文化されていないことがらを「あたり前」のように求めてくるのは、だいぶ違うと思います。
みなさんはどう思いますか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
