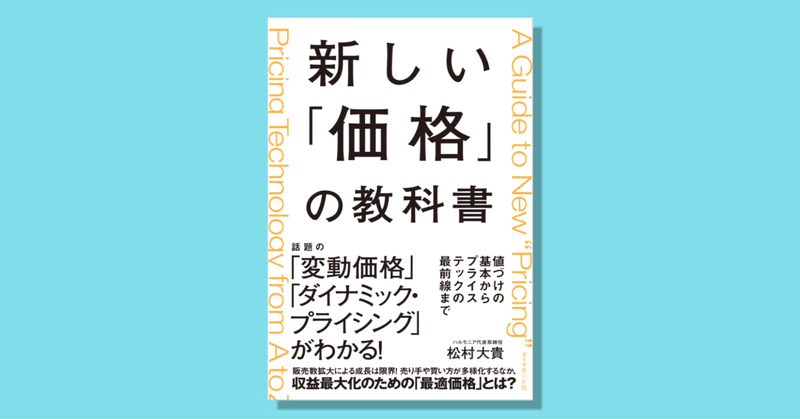
初めての本 『新しい価格の教科書』が12月14日に刊行! 冒頭の一部をご紹介
こんにちは、松村大貴です。ハルモニア株式会社の代表として、企業のプライシングを支援しています。この度、ご縁があってダイヤモンド社から『新しい「価格」の教科書』という本を出していただくことになりました。12月14日刊行で、翌15日頃からAmazonや書店に並んでいく予定です。
2日に1回は書店か図書館に足を運び、住む街を選ぶ条件は良い書店にアクセスできること。そんな自分にとって初めての執筆というのは感動的でもあり、ドキドキと苦悩の連続の体験でした。(2020年11月に書き始めて、「おわりに」を書き終えたのは2021年8月!きっと3ヶ月くらいで書けるだろうと思っていた自分がアホでした・・・。)
ともあれ、何とか出版までこぎ着け、こうしてご案内できるようになりました。自分とハルモニアが6年以上かけて学び、考察してきた「価格とはなにか」を1冊にギュッとまとめた『新しい「価格」の教科書』、ぜひお手にとっていただければと思います。
今回はそんな『新しい「価格」の教科書』から、内容や全体の構成がわかる「はじめに」の一部を紹介します。
ーーー
はじめに
古今東西、あらゆるモノやサービスの売買には価格がつけられてきた。
つまり、すべての企業や個人は価格に関わって生きている。
例えば、この本を書店で開いているあなた。あなたの周囲にはいったい何冊の本があるだろうか。それら一つひとつに固有の価格がつけられていることを想像してみてほしい。
そして、この本を買ってから「はじめに」を読み始めたあなた。あなたは本から得られる価値が価格以上だと期待して、購入を決めたはずだ(ありがとうございます)。
お金を使う以上、すべての人が関係するこの「価格」について整理して、最新の視点へとアップデートすることを目指したのが、本書『新しい「価格」の教科書』だ。
新しい形の「お金」や「決済方法」が登場するのに合わせて、「価格」も進化している。新しく多様な「価値観」が生まれれば、それに合わせて「価格」も多様になる。
この本を読むと、価格について大きく三つの視点が得られるよう心がけた。
一つ目は、固定的な価格から、動的な価格への変化について。商品に値札や定価がつけられる一律価格と、状況に合わせて変わっていく変動価格の変遷を、歴史の流れから考察する。
二つ目は、アナログから、デジタルな方法論への変化について。より良い取り引きを目指して、価格に関するデジタル・テクノロジーは進化している。プライステックやダイナミック・プライシングといったキーワードと、その本質を考える。
三つ目は、狭義のプライシング(価格づけ)から、広義のプライシングへの拡張について。より良いプライシングを目指すために、できることは実は幅広い。価格をより広い概念として捉え直し、さらには社会課題解決への適用可能性を考える。
本書の構成は、次のとおりだ。第1章が価格の基本。第2章から第4章が価格の過去〜現在、そして実践編。第5章が価格の未来。
時系列の構成だが、どこからでも読み進めていただいて構わない。そもそも価格とは何かを知ることに興味のある人は、第1章や第2章から順番に。プライステックと呼ばれる技術や、実践・実装の方法を学びたい人は第3章や第4章から。価格のもたらす社会課題解決や未来へのポテンシャル、筆者の見据える世界観については第5章にまとめた。
第1章 価格の基本
「価格」とは、売り手と買い手の合意によって決めた商品の価値のことであり、「プライシング(価格づけ)」はそのプロセスである。狭義のプライシングとは、買い手の「払ってもいい額の範囲」と売り手の「売ってもいい額の範囲」が重なる範囲を見極めて、価格を設定することだ。
第2章 価格の歴史
価格の歴史は、個別交渉をしていた「価格1.0の時代」、一律価格がつけられる「価格2.0の時代」、変動価格とテクノロジーが採用される「価格3.0の時代」の三つに大別できる。価格3.0の時代においては、個人はフットワークを軽く、柔軟なライフスタイルで過ごすほど得になる。
第3章 価格3.0を象徴するプライステック
プライステックとは、プライスとテクノロジーを組み合わせた造語で、その名のとおりプライシングを行うための技術やサービスの総称である。価格を決める主体者やタイミングによって、主に三つのカテゴリーがある。プライステックの広がる背景には、「Eコマース」「電子決済」「データ分析」という三つのテクノロジーの普及がある。
第4章 ビジネスを大きく変えるこれからのプライシング
新しいプライシングの成功確率を高めるためには一定のフレームワークがある。複雑度の高いテーマだからこそ、目的を失わないために適切な順序で進めるのがよい。プライシングをコミュニケーションと捉え、顧客をセンターにおいて構想することで、有効かつ顧客にも納得感のある価格をつけることができるだろう。売り手の独りよがりや技術偏重のプライシング戦略となってしまうのは防ぐべきだ。
第5章 価格の未来
価格は個人や企業の行動を変え、資源とニーズのマッチングを調整する。うまく活用することができれば、食品ロス、エネルギー消費、商品の廃棄問題などを抑制し、社会課題解決につながる。企業や個人のマインドセットが変わり、私たち一人ひとりの行動が変わっていくことで大きな変化が生まれていく。
本書は直接的に価格決定に関わる人だけでなく、すべてのビジネスパーソンに向けて、新しい考え方や捉え方を共有することに重きをおいて書いた。経済学の難しい言葉も極力避けるようにしているため、特別な前提知識なしで読んでもらえるはずだ。価格に関する先入観をなくし、新しい価格の仕組みや戦略を読者が描くための土台を用意したつもりだ。
この本を片手に、新しい価格の実践へと踏み出してほしい。
ーーー
『新しい「価格」の教科書』、ぜひお読みください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
