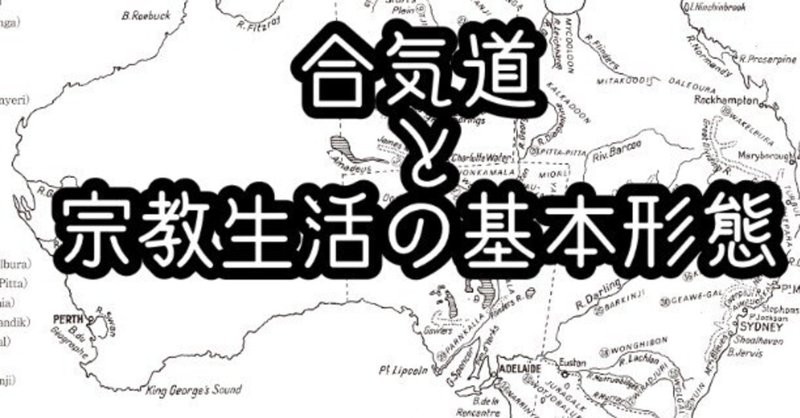
信仰とは何からはじまるのか?矛盾について【宗教の基本形態と合気道③】
前回のデュルケームは「聖なるもの」こそが宗教のはじまりだとした。
では人は何を崇拝するところから宗教を始めたのだろうか?というのが今回からのお話。
霊的な体験なのか、自然の偉大さからなのか? 内側からなのか外側からなのか?
デュルケームが持論を押し倒すために、他の崇拝対象の穴をついていく一方的なトーナメントが開催される。
VSアニミスム(霊魂崇拝)
アニミスム(霊魂崇拝)とは、どんなものにも霊魂が宿っているからそれを崇拝するという考え。
これには死と睡眠の混同、寝た時に夢で霊体になって肉体から離れるのだと思いこんだことから始まったという説がある。

要するに昔の未開な人間はどうせ夢と現実の区別なんかそんなにつかんやろ、ということだ。
これに対してはデュルケームも「いやいやいや、未開人ってそんな賢くないやろ」というさらに酷い反論を入れている。

一応フォローすると、死者崇拝がない段階から霊魂を崇拝するのはあり得ないというちゃんとした指摘もあった。
死者への崇拝は文明がかなり進歩しないと出てこないらしい。

デュルケーム曰く「人類の文明や祈り、儀礼や儀式が夢から生まれるわけないじゃん」とのこと。
参考:第二章 アニミスム
VSナチュリスム(精霊崇拝)
ナチュリスムは人よりも先に自然現象や動物に崇拝が行われた!という説。
実際にマックス・ミュラーはヒンドゥー教の聖典ヴェーダから神々の名前に色んな言語の共通点を見つけた。
火の神アグニ(Agni)はラテン語のイグニス(Ignis)、リトアニア語のウグニス(ugnis)、古代スラブ語のオグニ(ogny)といった感じで火について似通った呼び名を与えている。

こうした単なる火などの自然を意味していた言葉に「動く」とか「増える」とか動詞で呼んでいる内に、霊的な存在へと昇華され崇拝されるようになったのではないか?って説。
これに対してデュルケームは「え?言葉遊びで宗教って生まれるかなぁ??」などとコメントしていた。
おわり。
参考:第三章 ナチュリスム
トーテミスム爆誕
アニミスムもナチュリスムも退けたデュルケームによる推しの崇拝対象はトーテミスムだ。
なにしろ研究の量が段違いらしい。
実はトーテミスムがすげぇぞという話だけで第四章は終わる。
しかもこれで「第一部・完!」
トーテミスムの実態は次回!
陰と陽の外から考える
アニミスムとナチュリスムも単に起源ではないというだけで宗教を考える上で重要な位置を占めている。
この関係は内と外、陰陽の関係にある。ナチュリスムは自然、人類の外にずっとあったものであり、アニミスムは霊魂、人類の内にあった。

デュルケームのアプローチはこの陰陽が対立した時に別の視点から回答を用意しようというものだと思う。
新しいものの考え方、矛盾を成立させる方法を考えるヤヌス的思考法なんかがあるように、アプローチとしても合気道的で面白い。
関連記事
マルセル・モースの『贈与論』と考える合気道と贈与
レヴィ=ストロースの『野生の思考』から考える合気道と人類の構造
エミール・デュルケームの『宗教生活の基本形態』から考える合気道と宗教
マツリの合気道はワシが育てたって言いたくない?
