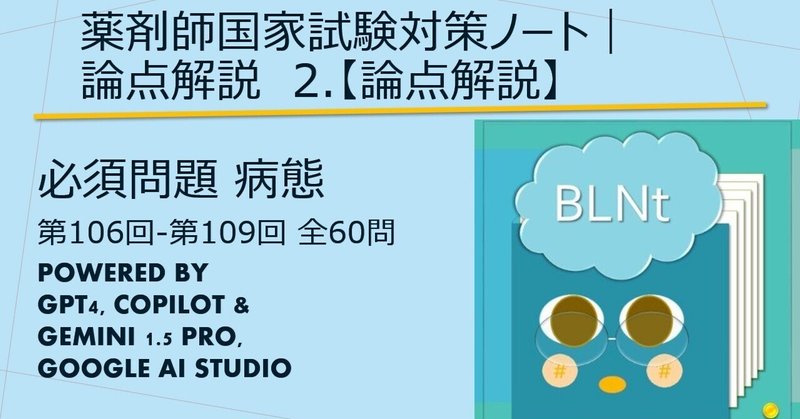
薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 病態 第106回-第109回 全60問 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot
こんにちは!Mats & BLNtです。
matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。
苦手意識がある人も、この機会に、必須問題【病態】 を一緒に完全攻略しよう!
今回は、2024年2月に実施された最新の薬剤師国家試験までの4回分、第106回薬剤師国家試験-第109回薬剤師国家試験 必須問題【病態】全60問の論点解説を powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot との対話を基盤にして一挙公開します。
GPT4, Copilot との対話を基盤にした論点解説と Gemini 1.5 Pro との対話を基盤にした論点解説を両方掲載していますので、追加の情報を得られ、また、両者の回答を比較することも可能です。
薬剤師国家試験の勉強法は色々ありますが、必須問題を一通り解いてみて、そこから自分に合った勉強法の傾向と対策を立てることは効率的な方法のひとつです。
Matsunoya品質の論点解説でサクッと学べば、それはそれで、薬剤師国家資格取得に向け走り出すきっかけになると思います。
薬剤師にしかできない仕事がある。
さあ、はじめよう。
Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n92a81f3546a9
薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 病態 第106回-第109回 全60問 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot
1. 論点一覧 全60問 必須問題【病態】
問番号は[試験の回]-[問番号]です。問番号順に並んでいます。
まず、論点を確認しましょう。
薬剤師国家試験問題 必須問題【病態】第106回 - 第109回

論点:
■■Gemini 1.5 Pro
⇒ Copilot で校正 ⇒ 最終校正(Yukiho Takizawa, PhD)
病態 論点リスト (問106-056 から 問109-070)
問番号 |論点 |正答 |正答の選択肢
問106-056|ビリルビン代謝 / 疾患|溶血性貧血|3
問107-056|自己免疫疾患 / 特異的抗体|抗二本鎖DNA抗体|2
問108-056|頭痛の種類 / 特徴|群発頭痛|3
問109-056|自己免疫性神経筋疾患 / 症状|重症筋無力症|2
問106-057|肝機能検査 / タンパク質合成能|コリンエステラーゼ(ChE)|2
問107-057|間質性肺炎の指標 / 特異度|シアル化糖鎖抗原(KL-6)|5
問108-057|血液凝固異常 / 疾患|播種性血管内凝固症候群(DIC)|3
問109-057|てんかん発作/ 種類・特徴|ミオクロニー発作|4
問106-058|遅発性ジスキネジア / 症状|無意識に口をもぐもぐさせる|3
問107-058|重症筋無力症 / 初発症状|眼瞼下垂|4
問108-058|血栓性血小板減少性紫斑病(TTP) / 薬剤|クロピドグレル硫酸塩|2
問109-058|メチルフェニデート塩酸塩 / 適応疾患|ナルコレプシー|5
問106-059|パーキンソン様症状 / 識別|小刻み歩行|3
問107-059|レム睡眠 / 特徴|急速な眼球運動が特徴|1
問108-059|パーキンソン病 / 症状|無動|5
問109-059|高ナトリウム血症 / 治療薬|トルバプタン|1
問106-060|続発性副甲状腺機能低下症 / 治療薬|アルファカルシドール|1
問107-060|機械操作に注意が必要 / 薬剤|タムスロシン塩酸塩錠|1
問108-060|フェニトインの代謝 / 遺伝子多型|CYP2C9|1
問109-060|スプーン状爪 / 関連疾患|鉄欠乏性貧血|1
問106-061|急性前骨髄球性白血病 / 治療薬|トレチノイン|4
問107-061|閃輝暗点を伴う / 頭痛|片頭痛|1
問108-061|間欠性跛行を特徴とする / 疾患|閉塞性動脈硬化症|1
問109-061|QT延長 / 不整脈|多形性心室頻拍|5
問106-062|前立腺肥大症 / 治療薬|デュタステリド|5
問107-062|依存性の少ない / 薬剤|グアンファシン|3
問108-062|急性膵炎 / 典型的な所見|心窩部痛|4
問109-062|副腎皮質ステロイド薬の適応 / 腎疾患|特発性膜性腎症|5
問106-063|急性膵炎の診断 / 血液検査|リパーゼ活性|5
問107-063|子宮内膜症 / 治療薬|リュープロレリン酢酸塩注|4
問108-063|アジソン病 / 特徴的所見|色素沈着|4
問109-063|ポリカルボフィルカルシウム / 適応疾患|過敏性腸症候群|3
問106-064|動揺病 / 治療薬|ジメンヒドリナート|5
問107-064|急性胆管炎 / 特徴|血清ALP(アルカリフォスファターゼ)活性上昇|4
問108-064|慢性副鼻腔炎 / 治療薬|クラリスロマイシン|5
問109-064|尿路結石を有する痛風患者 / 尿酸降下薬|トピロキソスタット|4
問106-065|空気感染 / 病原体|麻しんウイルス|5
問107-065|原発性アルドステロン症 / 臨床所見|低カリウム血症|3
問108-065|光線過敏症/ 原因となりやすいテープ剤|ケトプロフェン|2
問109-065|手術非適応のクッシング症候群 / 治療薬|ミトタン|2
問106-066|帯状疱疹 / 治療薬|バラシクロビル塩酸塩|3
問107-066|活性型ビタミンD3外用薬 / 適応疾患|尋常性乾癬|5
問108-066|メトトレキサート・ホリナート救援療法 / 副作用回避|アセタゾラミドナトリウム注|1

問109-066|褥瘡治療薬 / 壊死組織除去|ブロメライン|2
問106-067|乳がん発症 / 危険因子|初経年齢が早い|1
問107-067|がん終末期 / 呼吸困難治療薬|モルヒネ|5
問108-067|マイコプラズマ肺炎 / 治療薬|アジスロマイシン錠|4
問109-067|日本における肝硬変の原因 / ウイルス性肝炎|C型肝炎|3
問106-068|甘草の副作用 / 電解質異常|低カリウム血症|2
問107-068|組換え体医薬品 / 識別|ソラフェニブ|3
問108-068|脳梗塞後遺症の興奮症状に用いる / 漢方薬|抑肝散|3
問109-068|組換え体医薬品 / 生産プロセス|タンパク質|4
問106-069|医薬品安全性情報 / 入手方法|DRUG SAFETY UPDATE|2
問107-069|厚生労働省発行 / 医薬品情報資料|医薬品・医療機器等安全性情報|4
問108-069|「使用上の注意」改訂 / 情報源|医薬品安全対策情報(DSU)|4
問109-069|非劣性試験 / 結果の解釈|4|4

問106-070|パラメトリック法 / ノンパラメトリック法|t検定|2
問107-070|ヒストグラム / 箱ひげ図|3|3

問108-070|パフォーマンスステータス / データ尺度|順序尺度|4
問109-070|生殖細胞系列遺伝子 / コンパニオン診断|BRCA1/2遺伝子変異|3
2. 試験問題 全60問 必須問題【病態】
論点を確認し終わったら、問題を解いてみましょう。
2. 試験問題 全60問の後に、3. 論点解説 全60問があります。
わからなかった問題に関して、論点解説を読み、重点的に復習してみましょう。正解だった問題も、時間があったら、解説を確認するとよいです。
薬剤師国家試験問題 必須問題【病態】第106回 - 第109回

・正答の選択肢を一つ選んでください。
病態|問 106-056
血中間接ビリルビン値が血中直接ビリルビン値に比べて優位に上昇する疾患はどれか。
■選択肢
1. 肝硬変
2. アルコール性肝障害
3. 溶血性貧血
4. 胆石症
5. 膵頭部がん
病態|問 107-056
全身性エリテマトーデス(SLE)に特異性の高い抗体はどれか。
■選択肢
1. 抗チログロブリン抗体(抗サイログロブリン抗体)
2. 抗二本鎖DNA抗体
3. 抗CCP抗体(抗環状シトルリン化ペプチド抗体)
4. 抗Jo-1抗体
5. 抗GAD抗体(抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体)
病態|問 108-056
眼窩部の激痛を特徴とする頭痛はどれか。
■選択肢
1. 筋緊張性頭痛
2. 片頭痛
3. 群発頭痛
4. くも膜下出血による頭痛
5. 脳腫瘍による頭痛
病態|問 109-056
神経筋接合部のアセチルコリン受容体に対する自己抗体が産生されることにより、筋力低下をきたす自己免疫疾患はどれか。
■選択肢
1. イートン・ランバート症候群
2. 重症筋無力症
3. ギラン・バレー症候群
4. 進行性筋ジストロフィー
5. 筋萎縮性側索硬化症
病態|問 106-057
肝臓のタンパク質合成能の指標となるのはどれか。
■選択肢
1. アルカリホスファターゼ(ALP)
2. コリンエステラーゼ(ChE)
3. クレアチンキナーゼ(CK)
4. γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)
5. 乳酸脱水素酵素(LDH)
病態|問 107-057
間質性肺炎の指標として、特異度が高いのはどれか。
■選択肢
1. アミラーゼ(AMY)
2. 脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)
3. クレアチンキナーゼ(CK)
4. グリコヘモグロビン(HbA1c)
5. シアル化糖鎖抗原(KL-6)
病態|問 108-057
プロトロンビン時間が延長する疾患はどれか。
■選択肢
1. 鉄欠乏性貧血
2. 抗リン脂質抗体症候群
3. 播種性血管内凝固症候群(DIC)
4. 血友病A
5. 腎性貧血
病態|問 109-057
身体の一部又は全身に瞬間的な筋収縮が起こり、発作持続時間が短く、意識消失の自覚症状が無いことが多いてんかん発作はどれか。
■選択肢
1. 複雑部分発作
2. 欠神発作
3. 強直間代発作
4. ミオクロニー発作
5. 脱力発作
病態|問 106-058
遅発性ジスキネジアの典型的な症状はどれか。
■選択肢
1. 高熱
2. 手指関節のこわばり
3. 無意識に口をもぐもぐさせる
4. 筋肉痛
5. じっと座っていられない
病態|問 107-058
重症筋無力症の初発症状として、最も頻度が高いのはどれか。
■選択肢
1. 手指の振戦
2. 嚥下障害
3. 四肢の麻痺
4. 眼瞼下垂
5. 発熱
病態|問 108-058
重大な副作用として血栓性血小板減少性紫斑病を起こす可能性が最も高いのはどれか。
■選択肢
1. イコサペント酸エチル
2. クロピドグレル硫酸塩
3. サルポグレラート塩酸塩
4. ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
5. ワルファリンカリウム
病態|問 109-058
メチルフェニデート塩酸塩が適用される疾患はどれか。
■選択肢
1. 閉塞隅角緑内障
2. 重症うつ病
3. 糖尿病性腎症
4. くも膜下出血
5. ナルコレプシー
病態|問 106-059
パーキンソン様症状はどれか。
■選択肢
1. 口渇
2. 立ちくらみ
3. 小刻み歩行
4. 体重増加
5. 勃起障害
病態|問 107-059
健常者におけるレム睡眠に関する記述のうち、正しいのはどれか。
■選択肢
1. 急速な眼球運動が特徴である。
2. 筋肉の緊張が亢進する。
3. 入眠直後に多い。
4. 脳波で高振幅徐波を認める。
5. 加齢とともに増加する。
病態|問 108-059
パーキンソン病で認められる特徴的な症状はどれか。
■選択肢
1. 眼瞼下垂
2. 口渇
3. 動作時振戦
4. 高血圧
5. 無動
病態|問 109-059
高ナトリウム血症の患者に禁忌である薬物はどれか。
■選択肢
1. トルバプタン
2. エプレレノン
3. エナラプリルマレイン酸塩
4. カルベジロール
5. フロセミド
病態|問 106-060
続発性副甲状腺機能低下症の治療に用いられるのはどれか。
■選択肢
1. アルファカルシドール
2. エルカトニン
3. チアマゾール
4. ブロモクリプチン塩酸塩
5. プレドニゾロン
病態|問 107-060
自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意する薬剤はどれか。
■選択肢
1. タムスロシン塩酸塩錠
2. クロルマジノン酢酸エステル錠
3. セルニチンポーレンエキス錠
4. フルタミド錠
5. エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル
病態|問 108-060
遺伝子多型により、フェニトインの体内動態に最も影響を及ぼす代謝酵素はどれか。
■選択肢
1. CYP2C9
2. NAT2
3. CYP2D6
4. UGT1A1
5. CYP2C19
病態|問 109-060
臨床所見としてスプーン状爪が認められる疾患はどれか。
■選択肢
1. 鉄欠乏性貧血
2. 巨赤芽球性貧血
3. 自己免疫性溶血性貧血
4. 腎性貧血
5. 骨髄異形成症候群
病態|問 106-061
白血病細胞の分化を誘導し、急性前骨髄球性白血病の寛解導入療法に用いられるのはどれか。
■選択肢
1. イマチニブ
2. シクロスポリン
3. シクロホスファミド
4. トレチノイン
5. メトトレキサート
病態|問 107-061
閃せん輝き暗点を伴うことがある頭痛はどれか。
■選択肢
1. 片頭痛
2. 反復性緊張型頭痛
3. 慢性緊張型頭痛
4. 反復性群発頭痛
5. 慢性群発頭痛
病態|問 108-061
特徴的な症状の1つとして、間欠性跛行がみられる疾患はどれか。
■選択肢
1. 閉塞性動脈硬化症
2. 筋ジストロフィー
3. 変形性膝関節症
4. 痛風
5. 関節リウマチ
病態|問 109-061
心電図上でQT間隔の延長により生じやすくなる不整脈はどれか。
■選択肢
1. 洞停止
2. 洞房ブロック
3. 心房細動
4. 発作性上室頻拍
5. 多形性心室頻拍
病態|問 106-062
前立腺肥大症の治療薬はどれか。
■選択肢
1. アナストロゾール
2. クロニジン塩酸塩
3. クロルフェニラミンマレイン酸塩
4. シルデナフィルクエン酸塩
5. デュタステリド
病態|問 107-062
依存性の最も少ない薬物はどれか。
■選択肢
1. ペンタゾシン
2. メチルフェニデート
3. グアンファシン
4. メタンフェタミン
5. ペモリン
病態|問 108-062
急性膵炎で通常認められる所見はどれか。
■選択肢
1. 血中ヘモグロビン量の減少
2. 血中リパーゼ活性の低下
3. 白血球数の減少
4. 心窩部痛
5. 右腕への放散痛
病態|問 109-062
副腎皮質ステロイド性薬が適用される腎疾患はどれか。
■選択肢
1. 腎硬化症
2. 糖尿病性腎症
3. 痛風腎
4. 多発性嚢胞腎
5. 特発性膜性腎症
病態|問 106-063
急性膵炎の診断に有用な血液検査値はどれか。
■選択肢
1. アルブミン濃度
2. C反応性タンパク(CRP)濃度
3. 乳酸脱水素酵素(LDH)活性
4. 尿素窒素(BUN)濃度
5. リパーゼ活性
病態|問 107-063
子宮内膜症の治療に用いる薬剤はどれか。
■選択肢
1. エチニルエストラジオール錠
2. エンザルタミド錠
3. オキシトシン注
4. リュープロレリン酢酸塩注
5. レトロゾール錠
病態|問 108-063
アジソン病で特徴的に認められる所見はどれか。
■選択肢
1. 高血圧
2. 高血糖
3. 体重増加
4. 色素沈着
5. 活動性亢進
病態|問 109-063
ポリカルボフィルカルシウムが適用される疾患はどれか。
■選択肢
1. 術後イレウス
2. 高カルシウム血症
3. 過敏性腸症候群
4. 腎不全
5. 虫垂炎
病態|問 106-064
動揺病による嘔気の予防に用いられるのはどれか。
■選択肢
1. アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
2. イソソルビド
3. エチゾラム
4. ジフェニドール塩酸塩
5. ジメンヒドリナート
病態|問 107-064
急性胆管炎に関する記述のうち、正しいのはどれか。
■選択肢
1. 左下腹部に痛みを生じる。
2. 発熱を伴うことはまれである。
3. 血中白血球数が減少する。
4. 血清ALP(アルカリフォスファターゼ)活性が上昇する。
5. 血中間接ビリルビン値が上昇する。
病態|問 108-064
慢性副鼻腔炎の治療に用いられるのはどれか。
■選択肢
1. イソプロピルウノプロストン
2. ムピロシンカルシウム水和物
3. メトキサレン
4. ナフトピジル
5. クラリスロマイシン
病態|問 109-064
尿路結石を有する痛風患者に対して、最も適切な尿酸降下薬はどれか。
■選択肢
1. ベンズブロマロン
2. コルヒチン
3. ドチヌラド
4. トピロキソスタット
5. プロベネシド
病態|問 106-065
空気感染する病原体はどれか。
■選択肢
1. インフルエンザウイルス
2. ヒト免疫不全ウイルス(HIV)
3. ポリオウイルス
4. 風しんウイルス
5. 麻しんウイルス
病態|問 107-065
原発性アルドステロン症の臨床所見として、正しいのはどれか。
■選択肢
1. 低血圧症
2. 低ナトリウム血症
3. 低カリウム血症
4. インスリン分泌の増加
5. レニン活性の上昇
病態|問 108-065
テープ剤が光線過敏症の原因となりやすいのはどれか。
■選択肢
1. ビソプロロールフマル酸塩
2. ケトプロフェン
3. オキシブチニン塩酸塩
4. 硝酸イソソルビド
5. ツロブテロール
病態|問 109-065
手術が適応とならないクッシング症候群の治療に用いる薬物はどれか。
■選択肢
1. チアマゾール
2. ミトタン
3. デスモプレシン酢酸塩水和物
4. レボチロキシンナトリウム水和物
5. メチロシン
病態|問 106-066
帯状疱疹の治療薬はどれか。
■選択肢
1. ガンシクロビル
2. ザナミビル水和物
3. バラシクロビル塩酸塩
4. ラルテグラビルカリウム
5. リトナビル
病態|問 107-066
活性型ビタミンD3外用薬が適用される皮膚疾患はどれか。
■選択肢
1. 接触性皮膚炎
2. 爪白癬
3. アトピー性皮膚炎
4. じん麻疹
5. 尋常性乾癬
病態|問 108-066
以下は骨肉腫に対するメトトレキサート・ホリナート救援療法の初日の処方例である。副作用回避の目的で用いる薬剤Aとして最も適切なのはどれか。
■選択肢
1. アセタゾラミドナトリウム注
2. ピペラシリンナトリウム注
3. フィルグラスチム(遺伝子組換え)注
4. フロセミド注
5. メスナ注
・108_166

病態|問 109-066
褥瘡治療に用いる外用薬のうち、壊死組織除去効果を有するのはどれか。
■選択肢
1. アルプロスタジルアルファデクス
2. ブロメライン
3. ポビドンヨード
4. ジメチルイソプロピルアズレン
5. トレチノイントコフェリル
病態|問 106-067
乳がん発症の危険因子はどれか。
■選択肢
1. 初経年齢が早い
2. 初産年齢が早い
3. 出産歴がある
4. 授乳歴がある
5. 閉経年齢が早い
病態|問 107-067
がん終末期における呼吸困難に対する治療薬はどれか。
■選択肢
1. アセトアミノフェン
2. アドレナリン
3. スキサメトニウム
4. デキストロメトルファン
5. モルヒネ
病態|問 108-067
マイコプラズマ肺炎の治療に用いられるのはどれか。
■選択肢
1. アシクロビル錠
2. イベルメクチン錠
3. テビペネムピボキシル細粒
4. アジスロマイシン錠
5. リネゾリド錠
病態|問 109-067
我が国において、肝硬変の原因となるウイルス性肝炎として最も頻度が高いのはどれか。
■選択肢
1. A型肝炎
2. B型肝炎
3. C型肝炎
4. D型肝炎
5. E型肝炎
病態|問 106-068
甘草の副作用として注意すべき電解質異常はどれか。
■選択肢
1. 低カルシウム血症
2. 低カリウム血症
3. 低ナトリウム血症
4. 低マグネシウム血症
5. 低リン血症
病態|問 107-068
組換え体医薬品でないのはどれか。
■選択肢
1. アルテプラーゼ
2. カルペリチド
3. ソラフェニブ
4. ニボルマブ
5. レノグラスチム
病態|問 108-068
脳梗塞後遺症で、興奮症状を伴う場合に用いられる漢方薬はどれか。
■選択肢
1. 葛根湯
2. 大建中湯
3. 抑肝散
4. 五苓散
5. 猪苓湯
病態|問 109-068
組換え体医薬品の生産プロセスに関する記述について、[ ]に入る適切な語句はどれか。「目的遺伝子を挿入した発現ベクターを細胞に導入し、産生された[ ]を精製して、組換え体医薬品とする。」
■選択肢
1. DNA
2. RNA
3. ゲノム
4. タンパク質
5. 脂質
病態|問 106-069
図中のアに入る語句はどれか。
■選択肢
1. COCHRANE LIBRARY
2. DRUG SAFETY UPDATE
3. INTERVIEW FORM
4. PHYSICIANSʼ DESK REFERENCE
5. RISK MANAGEMENT PLAN
・106_169

病態|問 107-069
厚生労働省が発行する資料はどれか。
■選択肢
1. 医療用医薬品添付文書
2. 医薬品インタビューフォーム
3. 医薬品リスク管理計画
4. 医薬品・医療機器等安全性情報
5. くすりのしおり
病態|問 108-069
医療用医薬品の「使用上の注意」改訂を取りまとめた医薬品情報源はどれか。
■選択肢
1. 医薬品リスク管理計画(RMP)
2. 重篤副作用疾患別対応マニュアル
3. 緊急安全性情報
4. 医薬品安全対策情報(DSU)
5. 医療用医薬品製品情報概要
病態|問 109-069
下図の1~5は、既存薬Xを対照とした新薬Yの非劣性を検討した5つの臨床試験の結果について、両群の差の95%信頼区間を示したものである。あらかじめ設定された非劣性マージンが-Δのとき、両側5%水準で非劣性が結論づけられるのはどれか。
■選択肢
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
・109_169

病態|問 106-070
パラメトリック法に分類される仮説検定法はどれか。
■選択肢
1. Mann-Whitney のU検定
2. t検定
3. カイ二乗検定
4. フィッシャーの直接確率検定
5. ログランク検定
病態|問 107-070
被験者100人について、ある臨床検査値Xを調べた時のヒストグラムが以下のようになった。同じデータに基づいて作成した箱ひげ図として、妥当なのはどれか。
■選択肢
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
・107_170

病態|問 108-070
全身状態の指標であるパフォーマンスステータス(PS)の値を統計処理する際の、データ尺度はどれか。
■選択肢
1. 分類尺度
2. 間隔尺度
3. 名義尺度
4. 順序尺度
5. 比例尺度
病態|問 109-070
コンパニオン診断(医薬品の適応判定を目的とした体外診断)のうち、生殖細胞系列遺伝子に対する検査項目はどれか。
■選択肢
1. ALK融合遺伝子
2. BRAF遺伝子変異
3. BRCA1/2遺伝子変異
4. EGFR遺伝子変異
5. KRAS遺伝子変異
3. 論点解説 全60問 必須問題【病態】
薬剤師国家試験問題 必須問題【病態】第106回 - 第109回
Creator: Yukiho Takizawa, PhD
Tool: Copilot powered by GPT4 & Google AI Studio by Gemini 1.5 Pro
Date: 2024/ 05/11

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n92a81f3546a9
Matsunoya|薬剤師国家試験対策ノート
■科目|病態|問 106-056 ■正答| 3
血中間接ビリルビン値が血中直接ビリルビン値に比べて優位に上昇する疾患はどれか。1つ選べ。
■選択肢
肝硬変
アルコール性肝障害
溶血性貧血
胆石症
膵頭部がん
■■Copilot
病態|問 106-056 ■正答| 3
■論点 |血中間接ビリルビン値が血中直接ビリルビン値に比べて優位に上昇する疾患
この問題の論点は、血中間接ビリルビン値が血中直接ビリルビン値に比べて優位に上昇する疾患を特定することです。
■解説1|
溶血性貧血では、赤血球が過剰に破壊されるため、血中の間接ビリルビン(未処理のビリルビン)が増加します。これは、肝臓がビリルビンを処理する能力を超えているためです。
■解説2|
他の選択肢(肝硬変、アルコール性肝障害、胆石症、膵頭部がん)は、肝臓の機能障害や胆道の閉塞に関連しており、これらの状況では直接ビリルビン(処理済みのビリルビン)が主に増加します。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-056
■論点 |ビリルビン代謝と疾患の関係
この問題の主な論点は、血中ビリルビンの種類と疾患の関係を理解し、どの疾患で間接ビリルビンが優位に上昇するかを特定することです。以下に解説をまとめます。
■解説1|
ビリルビンは赤血球のヘムが分解されて生じる黄色い色素で、肝臓で代謝されます。未処理の間接ビリルビンと処理済みの直接ビリルビンが存在し、それぞれ上昇する疾患が異なります。
• 間接ビリルビン優位の上昇: 赤血球の破壊が亢進し、間接ビリルビンの産生が増加する疾患、例えば溶血性貧血が該当します。
• 直接ビリルビン優位の上昇: 肝臓でのビリルビン処理に障害が生じる疾患、例えば肝硬変や胆石症、膵頭部がんなどが該当します。アルコール性肝障害は、間接ビリルビンと直接ビリルビンの両方が上昇する可能性があります。
よって、選択肢の中で間接ビリルビンが優位に上昇する疾患は3. 溶血性貧血となります。
■解説2|
• 溶血性貧血: 赤血球が何らかの原因で破壊され、寿命が短くなることで起こる貧血です。破壊された赤血球からヘムが放出され、間接ビリルビンが過剰に産生されます。
• 肝硬変: 肝臓の線維化が進行し、肝機能が低下する疾患です。肝臓でのビリルビン処理能力が低下するため、直接ビリルビンが上昇します。
• アルコール性肝障害: 過剰なアルコール摂取により肝臓が障害を受ける疾患です。肝細胞が損傷を受けると、間接ビリルビンと直接ビリルビンの両方が上昇する可能性があります。
• 胆石症: 胆汁の流れが胆石によって妨げられる疾患です。胆汁の流れが悪くなると、直接ビリルビンが上昇します。
• 膵頭部がん: 膵臓の頭部にがんが発生し、胆管を圧迫することで胆汁の流れが悪くなる疾患です。胆汁の流れが悪くなると、直接ビリルビンが上昇します。
■科目|病態|問 107-056 ■正答| 2
全身性エリテマトーデス(SLE)に特異性の高い抗体はどれか。1つ選べ。
■選択肢
抗チログロブリン抗体(抗サイログロブリン抗体)
抗二本鎖DNA抗体
抗CCP抗体(抗環状シトルリン化ペプチド抗体)
抗Jo-1抗体
抗GAD抗体(抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体)
■■Copilot
病態|問 107-056 ■正答| 2
■論点 |全身性エリテマトーデス(SLE)に特異性の高い抗体
この問題の論点は、全身性エリテマトーデス(SLE)に特異性の高い抗体を特定することです。
■解説1|
全身性エリテマトーデス(SLE)は、抗二本鎖DNA抗体の存在が特徴的な自己免疫疾患です。これらの抗体は、患者の約70%に見られ、SLEの診断に有用です。
■解説2|
他の選択肢(抗チログロブリン抗体、抗CCP抗体、抗Jo-1抗体、抗GAD抗体)は、それぞれ他の自己免疫疾患(甲状腺疾患、関節リウマチ、筋炎、1型糖尿病など)と関連しています。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-056
■論点 |自己免疫疾患と特異的抗体
この問題の主な論点は、全身性エリテマトーデス(SLE)に特異性の高い抗体を特定することです。SLEは様々な自己抗体が産生される自己免疫疾患ですが、その中でも特異性の高い抗体が存在します。
■解説1|
SLEに特異性の高い抗体は2. 抗二本鎖DNA抗体です。
• 抗二本鎖DNA抗体は、SLE患者の約70%に認められ、SLEの診断や病勢の評価に有用な指標となります。
• その他の選択肢の抗体は、他の自己免疫疾患や臓器特異的自己免疫疾患に関連する抗体であり、SLEに特異的ではありません。
■解説2|
• 抗チログロブリン抗体(抗サイログロブリン抗体): 橋本病などの自己免疫性甲状腺疾患に関連する抗体です。
• 抗CCP抗体(抗環状シトルリン化ペプチド抗体): 関節リウマチに特異性の高い抗体です。
• 抗Jo-1抗体: 多発性筋炎/皮膚筋炎に関連する抗体です。
抗GAD抗体(抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体): 1型糖尿病やStiff-person症候群などの神経疾患に関連する抗体です。
■科目|病態|問 108-056 ■正答| 3
眼窩部の激痛を特徴とする頭痛はどれか。1つ選べ。
■選択肢
筋緊張性頭痛
片頭痛
群発頭痛
くも膜下出血による頭痛
脳腫瘍による頭痛
■■Copilot
病態|問 108-056 ■正答| 3
■論点 |眼窩部の激痛を特徴とする頭痛
この問題の論点は、眼窩部の激痛を特徴とする頭痛を特定することです。
■解説1|
群発頭痛は、眼窩部の激痛を特徴とする頭痛です。これは、一方の眼窩部に限局した激痛で、しばしば数時間ごとに「群発」します。
■解説2|
他の選択肢(筋緊張性頭痛、片頭痛、くも膜下出血による頭痛、脳腫瘍による頭痛)は、それぞれ異なる特徴を持つ頭痛で、眼窩部の激痛は主な特徴ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-056
■論点 |頭痛の種類と特徴
この問題の主な論点は、眼窩部の激痛を特徴とする頭痛の種類を特定することです。頭痛には様々な種類があり、それぞれ特徴的な症状があります。
■解説1|
眼窩部の激痛を特徴とする頭痛は3. 群発頭痛です。
• 群発頭痛は、片側の目の奥に激痛が走るのが特徴で、目の充血や涙、鼻水などの自律神経症状を伴うこともあります。
• 群発期には、1日に数回、数週間から数ヶ月にわたって頭痛が続きます。
■解説2|
• 筋緊張性頭痛: 頭全体が締め付けられるような痛みが特徴で、最も一般的な頭痛です。
• 片頭痛: 頭の片側に脈打つような痛みが特徴で、吐き気や嘔吐、光や音に敏感になるなどの症状を伴うこともあります。
• くも膜下出血による頭痛: 突然の激しい頭痛が特徴で、意識障害や嘔吐、項部硬直などの症状を伴うこともあります。
• 脳腫瘍による頭痛: 頭痛の程度や特徴は様々ですが、吐き気や嘔吐、視力障害、運動障害などの症状を伴うこともあります。
■科目|病態|問 109-056 ■正答| 2
神経筋接合部のアセチルコリン受容体に対する自己抗体が産生されることにより、筋力低下をきたす自己免疫疾患はどれか。1つ選べ。
■選択肢
イートン・ランバート症候群
重症筋無力症
ギラン・バレー症候群
進行性筋ジストロフィー
筋萎縮性側索硬化症
■■Copilot
病態|問 109-056 ■正答| 2
■論点 |神経筋接合部のアセチルコリン受容体に対する自己抗体が産生されることにより、筋力低下をきたす自己免疫疾患
この問題の論点は、神経筋接合部のアセチルコリン受容体に対する自己抗体が産生されることにより、筋力低下をきたす自己免疫疾患を特定することです。
■解説1|
重症筋無力症は、神経筋接合部のアセチルコリン受容体に対する自己抗体が産生され、筋力低下を引き起こす自己免疫疾患です。
■解説2|
他の選択肢(イートン・ランバート症候群、ギラン・バレー症候群、進行性筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症)は、それぞれ異なるメカニズムで筋力低下を引き起こします。これらの疾患では、神経筋接合部のアセチルコリン受容体に対する自己抗体は主な原因ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-056
■論点 |自己免疫性神経筋疾患と症状
この問題の主な論点は、神経筋接合部のアセチルコリン受容体に対する自己抗体が産生されることにより、筋力低下をきたす自己免疫疾患を特定することです。
■解説1|
神経筋接合部のアセチルコリン受容体に対する自己抗体が産生され、筋力低下をきたす自己免疫疾患は
2. 重症筋無力症 です。
• 重症筋無力症は、神経から筋肉への情報伝達が障害されることで、筋力低下や易疲労性を引き起こします。
• 眼瞼下垂や複視などの眼の症状、嚥下障害、四肢の筋力低下などが特徴的な症状です。
■解説2|
• イートン・ランバート症候群: 神経筋接合部のカルシウムチャネルに対する自己抗体が産生され、筋力低下をきたす自己免疫疾患です。
• ギラン・バレー症候群: 末梢神経の髄鞘に対する自己抗体が産生され、筋力低下や感覚障害をきたす自己免疫疾患です。
• 進行性筋ジストロフィー: 遺伝子の異常により筋肉が変性し、筋力低下をきたす疾患です。
• 筋萎縮性側索硬化症: 運動神経が変性し、筋力低下や筋萎縮をきたす神経変性疾患です。
■科目|病態|問 106-057 ■正答| 2
肝臓のタンパク質合成能の指標となるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
アルカリホスファターゼ(ALP)
コリンエステラーゼ(ChE)
クレアチンキナーゼ(CK)
γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)
乳酸脱水素酵素(LDH)
■■Copilot
病態|問 106-057 ■正答| 2
■論点 |肝臓のタンパク質合成能の指標
この問題の論点は、肝臓のタンパク質合成能の指標を特定することです。
■解説1|
コリンエステラーゼ(ChE)は、肝臓で合成される酵素であり、肝臓のタンパク質合成能の良い指標となります。
■解説2|
他の選択肢(ALP、CK、γ-GTP、LDH)は、それぞれ異なる生体反応を反映していますが、肝臓のタンパク質合成能の直接的な指標ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-057
■論点 |肝機能検査とタンパク質合成能
この問題の主な論点は、肝臓のタンパク質合成能を反映する検査値を特定することです。肝臓は様々なタンパク質を合成するため、その機能低下は血液検査で評価できます。
■解説1|
肝臓のタンパク質合成能の指標となるのは
2. コリンエステラーゼ(ChE) です。
• コリンエステラーゼは、肝臓で合成される酵素であり、その血中濃度は肝臓のタンパク質合成能を反映します。
• 肝機能障害が起こると、コリンエステラーゼの合成が低下し、血中濃度が低下します。
■解説2|
• アルカリホスファターゼ(ALP): 肝臓や骨、胆道などに存在する酵素で、胆道系疾患や骨疾患などで上昇します。
• クレアチンキナーゼ(CK): 筋肉に多く存在する酵素で、筋肉の損傷などで上昇します。
• γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP): 肝臓や胆道に存在する酵素で、アルコール性肝障害や胆道系疾患などで上昇します。
• 乳酸脱水素酵素(LDH): 多くの臓器に存在する酵素で、肝疾患や心疾患、筋肉疾患などで上昇します。
■科目|病態|問 107-057 ■正答| 5
間質性肺炎の指標として、特異度が高いのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
アミラーゼ(AMY)
脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)
クレアチンキナーゼ(CK)
グリコヘモグロビン(HbA1c)
シアル化糖鎖抗原(KL-6)
■■Copilot
病態|問 107-057 ■正答| 5
■論点 |間質性肺炎の指標として、特異度が高いもの
この問題の論点は、間質性肺炎の指標として、特異度が高いものを特定することです。
■解説1|
シアル化糖鎖抗原(KL-6)は、間質性肺炎の指標として特異度が高いです。これは、肺胞上皮細胞から分泌され、肺胞上皮細胞の障害や再生を反映します。
■解説2|
他の選択肢(AMY、BNP、CK、HbA1c)は、それぞれ異なる生体反応を反映していますが、間質性肺炎の特異的な指標ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-057
■論点 |間質性肺炎の指標と特異度
この問題の主な論点は、間質性肺炎の指標として特異度が高い検査値を特定することです。間質性肺炎は肺の間質に炎症が起こる疾患群であり、診断には様々な検査が行われます。
■解説1|
間質性肺炎の指標として、特異度が高いのは
5. シアル化糖鎖抗原(KL-6) です。
• KL-6は、肺胞上皮細胞から産生される糖タンパク質であり、間質性肺炎では血中濃度が上昇します。
• KL-6は間質性肺炎に比較的特異的な指標であり、診断や病勢の評価に有用です。
■解説2|
• アミラーゼ(AMY): 膵臓から分泌される消化酵素で、急性膵炎などで上昇します。
• 脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP): 心臓から分泌されるホルモンで、心不全などで上昇します。
• クレアチンキナーゼ(CK): 筋肉に多く存在する酵素で、筋肉の損傷などで上昇します。
• グリコヘモグロビン(HbA1c): 過去1〜2ヶ月の平均血糖値を反映する指標で、糖尿病の診断や管理に用いられます。
■科目|病態|問 108-057 ■正答| 3
プロトロンビン時間が延長する疾患はどれか。1つ選べ。
■選択肢
鉄欠乏性貧血
抗リン脂質抗体症候群
播種性血管内凝固症候群(DIC)
血友病A
腎性貧血
■■Copilot
病態|問 108-057 ■正答| 3
■論点 |プロトロンビン時間が延長する疾患
この問題の論点は、プロトロンビン時間が延長する疾患を特定することです。
■解説1|
播種性血管内凝固症候群(DIC)は、全身の血管内で血液が凝固し、同時に出血も起こる状態で、プロトロンビン時間が延長します。
■解説2|
他の選択肢(鉄欠乏性貧血、抗リン脂質抗体症候群、血友病A、腎性貧血)では、プロトロンビン時間が延長することは一般的にはありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-057
■論点 |血液凝固異常と疾患
この問題の主な論点は、プロトロンビン時間が延長する疾患を特定することです。プロトロンビン時間は血液凝固の指標であり、延長は凝固因子の異常を示唆します。
■解説1|
プロトロンビン時間が延長する疾患は
3. 播種性血管内凝固症候群(DIC) です。
• DICは、様々な原因で血液凝固が亢進し、全身の血管内で血栓が形成される疾患です。
• 凝固因子や血小板が消費されるため、出血傾向も伴います。
• プロトロンビン時間の延長は、凝固因子消費による血液凝固能の低下を示唆します。
■解説2|
• 鉄欠乏性貧血: 鉄の不足によりヘモグロビンの合成が低下し、貧血が起こる疾患です。
• 抗リン脂質抗体症候群: リン脂質に対する自己抗体が産生され、血栓症を引き起こす疾患です。
• 血友病A: 遺伝性凝固因子異常症であり、第VIII因子の欠乏により出血傾向をきたします。
• 腎性貧血: 腎機能障害によりエリスロポエチンの産生が低下し、貧血が起こる疾患です。
■科目|病態|問 109-057 ■正答| 4
身体の一部又は全身に瞬間的な筋収縮が起こり、発作持続時間が短く、意識消失の自覚症状が無いことが多いてんかん発作はどれか。1つ選べ。
■選択肢
複雑部分発作
欠神発作
強直間代発作
ミオクロニー発作
脱力発作
■■Copilot
病態|問 109-057 ■正答| 4
■論点 |身体の一部又は全身に瞬間的な筋収縮が起こり、発作持続時間が短く、意識消失の自覚症状が無いことが多いてんかん発作
この問題の論点は、身体の一部又は全身に瞬間的な筋収縮が起こり、発作持続時間が短く、意識消失の自覚症状が無いことが多いてんかん発作を特定することです。
■解説1|
ミオクロニー発作は、身体の一部又は全身に瞬間的な筋収縮が起こるてんかん発作で、発作持続時間が短く、意識消失の自覚症状が無いことが多いです。
■解説2|
他の選択肢(複雑部分発作、欠神発作、強直間代発作、脱力発作)は、それぞれ異なる特徴を持つてんかん発作で、ミオクロニー発作の特徴とは異なります。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-057
■論点 |てんかん発作の種類と特徴
この問題の主な論点は、瞬間的な筋収縮が起こり、発作持続時間が短く、意識消失のないてんかん発作を特定することです。てんかん発作には様々な種類があり、症状や持続時間などが異なります。
■解説1|
身体の一部又は全身に瞬間的な筋収縮が起こり、発作持続時間が短く、意識消失の自覚症状が無いことが多いてんかん発作は
4. ミオクロニー発作 です。
• ミオクロニー発作は、筋肉の不随意な短時間の収縮を特徴とするてんかん発作です。
• 単独で起こることもあれば、他のてんかん発作の一部として起こることもあります。
■解説2|
• 複雑部分発作: 意識障害を伴う部分発作であり、自動症(無意識の動作)や精神症状などが見られます。
• 欠神発作: 小児に多いてんかん発作で、短時間の意識消失を特徴とします。
• 強直間代発作: 全身性のてんかん発作であり、筋肉の強直と間代的な痙攣を繰り返します。
• 脱力発作: 筋肉の緊張が突然低下し、転倒することがあります。
■科目|病態|問 106-058 ■正答| 3
遅発性ジスキネジアの典型的な症状はどれか。1つ選べ。
■選択肢
高熱
手指関節のこわばり
無意識に口をもぐもぐさせる
筋肉痛
じっと座っていられない
■■Copilot
病態|問 106-058 ■正答| 3
■論点 |遅発性ジスキネジアの典型的な症状
この問題の論点は、遅発性ジスキネジアの典型的な症状を特定することです。
■解説1|
遅発性ジスキネジアは、神経系の疾患で、特に抗精神病薬の長期使用に関連しています。典型的な症状は、無意識に口をもぐもぐさせる動き(舌や顔の筋肉の不随意運動)です。
■解説2|
他の選択肢(高熱、手指関節のこわばり、筋肉痛、じっと座っていられない)は、遅発性ジスキネジアの典型的な症状ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-058
■論点 |遅発性ジスキネジアの症状
この問題の主な論点は、遅発性ジスキネジアの典型的な症状を特定することです。遅発性ジスキネジアは、抗精神病薬の長期投与による副作用として知られています。
■解説1|
遅発性ジスキネジアの典型的な症状は
3. 無意識に口をもぐもぐさせる です。
• 遅発性ジスキネジアは、顔面や口、舌、四肢などの不随意運動を特徴とします。
• 口をもぐもぐさせる、舌を突き出す、顔をしかめるなどの症状が典型的です。
■解説2|
• 高熱: 感染症や炎症などで体温が上昇した状態です。
• 手指関節のこわばり: 関節リウマチなどの関節疾患でみられる症状です。
• 筋肉痛: 筋肉の損傷や炎症などで起こる痛みです。
• じっと座っていられない: アカシジアと呼ばれる症状で、抗精神病薬の副作用として知られています。
■科目|病態|問 107-058 ■正答| 4
重症筋無力症の初発症状として、最も頻度が高いのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
手指の振戦
嚥下障害
四肢の麻痺
眼瞼下垂
発熱
■■Copilot
病態|問 107-058 ■正答| 4
■論点 |重症筋無力症の初発症状として、最も頻度が高いもの
この問題の論点は、重症筋無力症の初発症状として、最も頻度が高いものを特定することです。
■解説1|
重症筋無力症は、神経筋接合部の障害により筋力低下を引き起こす自己免疫疾患です。最も頻度が高い初発症状は眼瞼下垂(まぶたの垂れ下がり)です。
■解説2|
他の選択肢(手指の振戦、嚥下障害、四肢の麻痺、発熱)は、重症筋無力症の初発症状としては一般的ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-058
■論点 |重症筋無力症の初発症状
この問題の主な論点は、重症筋無力症の初発症状として最も頻度の高いものを特定することです。重症筋無力症は、神経筋接合部の伝達障害により筋力低下をきたす自己免疫疾患です。
■解説1|
重症筋無力症の初発症状として、最も頻度が高いのは
4. 眼瞼下垂 です。
• 重症筋無力症では、眼の症状が最初に現れることが多く、眼瞼下垂や複視などがみられます。
• 眼瞼下垂は、まぶたが下がる症状であり、片側または両側に起こります。
■解説2|
• 手指の振戦: 手が震える症状で、パーキンソン病や本態性振戦などでみられます。
• 嚥下障害: 食べ物が飲み込みにくい症状で、神経筋疾患や食道疾患などでみられます。
• 四肢の麻痺: 手足が動かしにくい症状で、脳卒中や脊髄損傷などでみられます。
• 発熱: 感染症や炎症などで体温が上昇した状態です。
■科目|病態|問 108-058 ■正答| 2
重大な副作用として血栓性血小板減少性紫斑病を起こす可能性が最も高いのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
イコサペント酸エチル
クロピドグレル硫酸塩
サルポグレラート塩酸塩
ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
ワルファリンカリウム
■■Copilot
病態|問 108-058 ■正答| 2
■論点 |重大な副作用として血栓性血小板減少性紫斑病を起こす可能性が最も高い薬物
この問題の論点は、重大な副作用として血栓性血小板減少性紫斑病を起こす可能性が最も高い薬物を特定することです。
■解説1|
クロピドグレル硫酸塩は、抗血小板薬であり、稀に血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)という重大な副作用を引き起こす可能性があります。
■解説2|
他の選択肢(イコサペント酸エチル、サルポグレラート塩酸塩、ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩、ワルファリンカリウム)は、一般的にTTPのリスクは低いとされています。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-058
■論点 |血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)と薬剤
この問題の主な論点は、血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)を起こす可能性が最も高い薬剤を特定することです。TTPは、血小板減少と微小血管内の血栓形成を特徴とする疾患です。
■解説1|
重大な副作用としてTTPを起こす可能性が最も高いのは
2. クロピドグレル硫酸塩 です。
• クロピドグレルは、抗血小板薬であり、血栓症の予防に用いられます。
• まれにTTPを引き起こすことが報告されており、注意が必要です。
■解説2|
• イコサペント酸エチル: 高脂血症治療薬であり、中性脂肪を低下させる作用があります。
• サルポグレラート塩酸塩: 胃粘膜保護薬であり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の治療に用いられます。
• ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩: 抗凝固薬であり、血栓症の予防や治療に用いられます。
• ワルファリンカリウム: 抗凝固薬であり、血栓症の予防や治療に用いられます。
■科目|病態|問 109-058 ■正答| 5
メチルフェニデート塩酸塩が適用される疾患はどれか。1つ選べ。
■選択肢
閉塞隅角緑内障
重症うつ病
糖尿病性腎症
くも膜下出血
ナルコレプシー
■■Copilot
病態|問 109-058 ■正答| 5
■論点 |メチルフェニデート塩酸塩が適用される疾患
この問題の論点は、メチルフェニデート塩酸塩が適用される疾患を特定することです。
■解説1|
メチルフェニデート塩酸塩は、中枢神経系刺激薬であり、主に注意欠陥・多動性障害(ADHD)の治療に用いられますが、ナルコレプシーの治療にも適用されます。
■解説2|
他の選択肢(閉塞隅角緑内障、重症うつ病、糖尿病性腎症、くも膜下出血)は、メチルフェニデート塩酸塩の主な適応症ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-058
■論点 |メチルフェニデート塩酸塩の適応疾患
この問題の主な論点は、メチルフェニデート塩酸塩が適用される疾患を特定することです。メチルフェニデート塩酸塩は、中枢神経刺激薬に分類される薬剤です。
■解説1|
メチルフェニデート塩酸塩が適用される疾患は
5. ナルコレプシー です。
• ナルコレプシーは、日中の過度の眠気や情動脱力発作などを特徴とする睡眠障害です。
• メチルフェニデート塩酸塩は、中枢神経を刺激することで覚醒を維持し、ナルコレプシーの症状を改善します。
■解説2|
• 閉塞隅角緑内障: 眼圧が上昇し、視神経が障害される疾患です。
• 重症うつ病: 気分の落ち込みや意欲の低下などを特徴とする精神疾患です。
• 糖尿病性腎症: 糖尿病の合併症であり、腎機能が低下する疾患です。
• くも膜下出血: 脳の表面を覆うくも膜の下に出血が起こる疾患です。
■科目|病態|問 106-059 ■正答| 3
パーキンソン様症状はどれか。1つ選べ。
■選択肢
口渇
立ちくらみ
小刻み歩行
体重増加
勃起障害
■■Copilot
病態|問 106-059 ■正答| 3
■論点 |パーキンソン様症状
この問題の論点は、パーキンソン様症状を特定することです。
■解説1|
パーキンソン様症状は、パーキンソン病やその他の神経変性疾患に見られる一連の症状を指します。その中でも、小刻み歩行は典型的な症状の一つで、歩幅が狭く、足を引きずるように歩く様子を指します。
■解説2|
他の選択肢(口渇、立ちくらみ、体重増加、勃起障害)は、パーキンソン様症状の典型的な症状ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-059
■論点 |パーキンソン様症状の識別
この問題の主な論点は、パーキンソン様症状を他の症状から区別することです。パーキンソン様症状は、パーキンソン病に特徴的な運動症状と類似した症状を指します。
■解説1|
パーキンソン様症状は
3. 小刻み歩行 です。
• パーキンソン病では、動作が緩慢になる、筋肉が硬くなる、振戦が起こる、姿勢が不安定になるなどの症状がみられます。
• 小刻み歩行は、歩幅が狭く、すり足のような歩き方になる症状であり、パーキンソン病に特徴的な運動症状の一つです。
■解説2|
• 口渇: 口の中が渇く症状で、脱水や薬の副作用などでみられます。
• 立ちくらみ: 起立時にめまいがしたり、意識が遠のいたりする症状で、低血圧や貧血などでみられます。
• 体重増加: エネルギー摂取量が多かったり、代謝が低下したりすることで体重が増える状態です。
• 勃起障害: 勃起が維持できない、または勃起が起こらない症状で、血管障害や神経障害などでみられます。
■科目|病態|問 107-059 ■正答| 1
健常者におけるレム睡眠に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
急速な眼球運動が特徴である。
筋肉の緊張が亢進する。
入眠直後に多い。
脳波で高振幅徐波を認める。
加齢とともに増加する。
■■Copilot
病態|問 107-059 ■正答| 1
■論点 |健常者におけるレム睡眠に関する記述
この問題の論点は、健常者におけるレム睡眠に関する正しい記述を特定することです。
■解説1|
レム睡眠は、急速な眼球運動(Rapid Eye Movement)が特徴であることからその名が付けられました。この眼球運動は、睡眠中の夢を見ている時に特に活発になります。
■解説2|
他の選択肢(筋肉の緊張が亢進する、入眠直後に多い、脳波で高振幅徐波を認める、加齢とともに増加する)は、レム睡眠に関する一般的な記述ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-059
■論点 |レム睡眠の特徴
この問題の主な論点は、レム睡眠の特徴を正しく理解することです。睡眠はレム睡眠とノンレム睡眠に分けられ、それぞれ異なる特徴があります。
■解説1|
健常者におけるレム睡眠に関する記述のうち、正しいのは 1. 急速な眼球運動が特徴である です。
• レム睡眠は、Rapid Eye Movement sleep の略であり、眼球が急速に動くのが特徴です。
• 脳波は覚醒時と似ており、夢を見ていることが多いとされています。
■解説2|
• 筋肉の緊張が亢進する: ノンレム睡眠の特徴です。
• 入眠直後に多い: ノンレム睡眠の特徴です。
• 脳波で高振幅徐波を認める: ノンレム睡眠の特徴です。
• 加齢とともに増加する: ノンレム睡眠の特徴です。
■科目|病態|問 108-059 ■正答| 5
パーキンソン病で認められる特徴的な症状はどれか。1つ選べ。
■選択肢
眼瞼下垂
口渇
動作時振戦
高血圧
無動
■■Copilot
病態|問 108-059 ■正答| 5
■論点 |パーキンソン病で認められる特徴的な症状
この問題の論点は、パーキンソン病で認められる特徴的な症状を特定することです。
■解説1|
パーキンソン病は、ドーパミン産生細胞の喪失により引き起こされる神経変性疾患で、無動(運動の開始や続行の困難)はその典型的な症状の一つです。
■解説2|
他の選択肢(眼瞼下垂、口渇、動作時振戦、高血圧)は、パーキンソン病の典型的な症状ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-059
■論点 |パーキンソン病の症状
この問題の主な論点は、パーキンソン病に認められる特徴的な症状を特定することです。パーキンソン病は、神経変性疾患の一つであり、運動症状を主徴とします。
■解説1|
パーキンソン病で認められる特徴的な症状は
5. 無動 です。
• 無動は、動作が開始しにくくなったり、動作が緩慢になったりする症状です。
• パーキンソン病の主要症状の一つであり、日常生活に大きな支障をきたします。
■解説2|
• 眼瞼下垂: 重症筋無力症などでみられる症状です。
• 口渇: 脱水や薬の副作用などでみられる症状です。
• 動作時振戦: 動作時に手が震える症状で、本態性振戦などでみられます。
• 高血圧: 血圧が正常値よりも高い状態です。
■科目|病態|問 109-059 ■正答| 1
高ナトリウム血症の患者に禁忌である薬物はどれか。1つ選べ。
■選択肢
トルバプタン
エプレレノン
エナラプリルマレイン酸塩
カルベジロール
フロセミド
■■Copilot
病態|問 109-059 ■正答| 1
■論点 |高ナトリウム血症の患者に禁忌である薬物
この問題の論点は、高ナトリウム血症の患者に禁忌である薬物を特定することです。
■解説1|
トルバプタンは、尿中に排泄されるナトリウム量を増加させることで、血中のナトリウム濃度を上昇させる作用があります。そのため、既に高ナトリウム血症の患者には禁忌となります。
■解説2|
他の選択肢(エプレレノン、エナラプリルマレイン酸塩、カルベジロール、フロセミド)は、一般的に高ナトリウム血症の患者に対して禁忌とはされていません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-059
■論点 |高ナトリウム血症の治療薬
この問題の主な論点は、高ナトリウム血症の患者に禁忌となる薬物を特定することです。高ナトリウム血症は、体内の水分が不足し、ナトリウム濃度が上昇した状態です。
■解説1|
高ナトリウム血症の患者に禁忌である薬物は 1. トルバプタン です。
• トルバプタンは、バソプレシンV2受容体拮抗薬であり、尿を濃縮するバソプレシンの作用を抑えることで利尿作用を示します。
• 高ナトリウム血症の患者に投与すると、脱水がさらに悪化するため禁忌です。
■解説2|
• エプレレノン: アルドステロン受容体拮抗薬であり、高血圧や心不全の治療に用いられます。
• エナラプリルマレイン酸塩: アンジオテンシン変換酵素阻害薬であり、高血圧や心不全の治療に用いられます。
• カルベジロール: β遮断薬であり、高血圧や狭心症の治療に用いられます。
• フロセミド: ループ利尿薬であり、浮腫や高血圧の治療に用いられます。
■科目|病態|問 106-060 ■正答| 1
続発性副甲状腺機能低下症の治療に用いられるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
アルファカルシドール
エルカトニン
チアマゾール
ブロモクリプチン塩酸塩
プレドニゾロン
■■Copilot
病態|問 106-060 ■正答| 1
■論点 |続発性副甲状腺機能低下症の治療
この問題の論点は、続発性副甲状腺機能低下症の治療を特定することです。
■解説1|
続発性副甲状腺機能低下症の治療には、アルファカルシドールが用いられます。これはビタミンD3のアナログで、カルシウムの吸収を促進し、副甲状腺ホルモンの分泌を抑制します。
■解説2|
他の選択肢(エルカトニン、チアマゾール、ブロモクリプチン塩酸塩、プレドニゾロン)は、一般的に続発性副甲状腺機能低下症の治療には用いられません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-060
■論点 |続発性副甲状腺機能低下症の治療薬
この問題の主な論点は、続発性副甲状腺機能低下症の治療に用いられる薬物を特定することです。続発性副甲状腺機能低下症は、副甲状腺ホルモンの分泌が低下した状態です。
■解説1|
続発性副甲状腺機能低下症の治療に用いられるのは 1. アルファカルシドール です。
• アルファカルシドールは、活性型ビタミンD3製剤であり、腸管からのカルシウム吸収を促進し、血清カルシウム濃度を上昇させます。
• 続発性副甲状腺機能低下症では、血清カルシウム濃度が低下するため、アルファカルシドールを投与することで治療します。
■解説2|
• エルカトニン: 甲状腺C細胞から分泌されるホルモンであり、骨吸収を抑制することで血清カルシウム濃度を低下させます。
• チアマゾール: 抗甲状腺薬であり、甲状腺ホルモンの合成を抑制することで甲状腺機能亢進症の治療に用いられます。
• ブロモクリプチン塩酸塩: ドーパミン受容体作動薬であり、高プロラクチン血症やパーキンソン病の治療に用いられます。
• プレドニゾロン: 副腎皮質ステロイド薬であり、抗炎症作用や免疫抑制作用があります。
■科目|病態|問 107-060 ■正答| 1
自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意する薬剤はどれか。1つ選べ。
■選択肢
タムスロシン塩酸塩錠
クロルマジノン酢酸エステル錠
セルニチンポーレンエキス錠
フルタミド錠
エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル
■■Copilot
病態|問 107-060 ■正答| 1
■論点 |自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意する薬剤
この問題の論点は、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意する薬剤を特定することです。
■解説1|
タムスロシン塩酸塩錠は、前立腺肥大症の治療に用いられる薬剤で、副作用としてめまいや低血圧を引き起こす可能性があります。これらの症状は、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
■解説2|
他の選択肢(クロルマジノン酢酸エステル錠、セルニチンポーレンエキス錠、フルタミド錠、エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル)は、一般的に自動車の運転等危険を伴う機械の操作に影響を及ぼす副作用は報告されていません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-060
■論点 |機械操作に注意が必要な薬剤
この問題の主な論点は、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意する薬剤を特定することです。
■解説1|
自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意する薬剤は 1. タムスロシン塩酸塩錠 です。
• タムスロシンは、α1遮断薬であり、前立腺肥大症に伴う排尿障害の治療に用いられます。
• 起立性低血圧や眠気などの副作用を引き起こすことがあり、運転等に支障をきたす可能性があります。
■解説2|
• クロルマジノン酢酸エステル錠: 抗精神病薬であり、統合失調症や躁病の治療に用いられます。
• セルニチンポーレンエキス錠: 前立腺肥大症に伴う排尿障害の治療に用いられる漢方薬です。
• フルタミド錠: 抗アンドロゲン薬であり、前立腺癌の治療に用いられます。
• エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル: 抗悪性腫瘍薬であり、前立腺癌や乳癌の治療に用いられます。
■科目|病態|問 108-060 ■正答| 1
遺伝子多型により、フェニトインの体内動態に最も影響を及ぼす代謝酵素はどれか。1つ選べ。
■選択肢
CYP2C9
NAT2
CYP2D6
UGT1A1
CYP2C19
■■Copilot
病態|問 108-060 ■正答| 1
■論点 |遺伝子多型により、フェニトインの体内動態に最も影響を及ぼす代謝酵素
この問題の論点は、遺伝子多型により、フェニトインの体内動態に最も影響を及ぼす代謝酵素を特定することです。
■解説1|
フェニトインは、主に肝臓のCYP2C9によって代謝されます。したがって、CYP2C9の遺伝子多型は、フェニトインの体内動態に大きな影響を及ぼします。
■解説2|
他の選択肢(NAT2、CYP2D6、UGT1A1、CYP2C19)も薬物代謝に関与する酵素ですが、フェニトインの代謝には主に関与していません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-060
■論点 |フェニトインの代謝と遺伝子多型
この問題の主な論点は、フェニトインの体内動態に最も影響を及ぼす代謝酵素の遺伝子多型を特定することです。フェニトインは、てんかん発作の治療に用いられる抗てんかん薬です。
■解説1|
遺伝子多型により、フェニトインの体内動態に最も影響を及ぼす代謝酵素は 1. CYP2C9 です。
• CYP2C9は、フェニトインの主要代謝酵素であり、その遺伝子多型はフェニトインの代謝速度に影響を与えます。
• CYP2C9の活性低下型遺伝子を持つ患者では、フェニトインの血中濃度が上昇しやすく、副作用のリスクが高まります。
■解説2|
• NAT2: イソニアジドやスルファメトキサゾールなどの薬物の代謝に関与する酵素です。
• CYP2D6: デブリソキンやノルチプチリンなどの薬物の代謝に関与する酵素です。
• UGT1A1: ビリルビンやイリノテカンなどの薬物の代謝に関与する酵素です。
• CYP2C19: オメプラゾールやクロピドグレルなどの薬物の代謝に関与する酵素です。
■科目|病態|問 109-060 ■正答| 1
臨床所見としてスプーン状爪が認められる疾患はどれか。1つ選べ。
■選択肢
鉄欠乏性貧血
巨赤芽球性貧血
自己免疫性溶血性貧血
腎性貧血
骨髄異形成症候群
■■Copilot
病態|問 109-060 ■正答| 1
■論点 |臨床所見としてスプーン状爪が認められる疾患
この問題の論点は、臨床所見としてスプーン状爪が認められる疾患を特定することです。
■解説1|
スプーン状爪(爪がくぼんでスプーンのようになる症状)は、鉄欠乏性貧血の典型的な臨床所見の一つです。
■解説2|
他の選択肢(巨赤芽球性貧血、自己免疫性溶血性貧血、腎性貧血、骨髄異形成症候群)では、一般的にスプーン状爪は認められません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-060
■論点 |スプーン状爪と関連疾患
この問題の主な論点は、スプーン状爪が認められる疾患を特定することです。スプーン状爪は、爪がスプーンのように反り返った状態を指します。
■解説1|
臨床所見としてスプーン状爪が認められる疾患は 1. 鉄欠乏性貧血 です。
• 鉄欠乏性貧血では、鉄の不足によりヘモグロビンの合成が低下し、貧血が起こります。
• スプーン状爪は、鉄欠乏性貧血の典型的な症状の一つであり、爪が薄く、脆くなり、反り返った状態になります。
■解説2|
• 巨赤芽球性貧血: ビタミンB12や葉酸の不足により赤血球の成熟が障害され、貧血が起こる疾患です。
• 自己免疫性溶血性貧血: 自己抗体が赤血球を攻撃し、貧血が起こる疾患です。
• 腎性貧血: 腎機能障害によりエリスロポエチンの産生が低下し、貧血が起こる疾患です。
• 骨髄異形成症候群: 造血幹細胞に異常が生じ、血液細胞の産生が低下する疾患です。
■科目|病態|問 106-061 ■正答| 4
白血病細胞の分化を誘導し、急性前骨髄球性白血病の寛解導入療法に用いられるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
イマチニブ
シクロスポリン
シクロホスファミド
トレチノイン
メトトレキサート
■■Copilot
病態|問 106-061 ■正答| 4
■論点 |白血病細胞の分化を誘導し、急性前骨髄球性白血病の寛解導入療法に用いられる薬物
この問題の論点は、白血病細胞の分化を誘導し、急性前骨髄球性白血病の寛解導入療法に用いられる薬物を特定することです。
■解説1|
トレチノインは、ビタミンAの誘導体であり、白血病細胞の分化を誘導します。これにより、急性前骨髄球性白血病(APL)の寛解導入療法に用いられます。
■解説2|
他の選択肢(イマチニブ、シクロスポリン、シクロホスファミド、メトトレキサート)は、一般的に急性前骨髄球性白血病の寛解導入療法には用いられません。
■解説2|
他の選択肢(反復性緊張型頭痛、慢性緊張型頭痛、反復性群発頭痛、慢性群発頭痛)は、一般的に閃せん輝き暗点を伴うことはありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-061
■論点 |急性前骨髄球性白血病の治療薬
この問題の主な論点は、白血病細胞の分化を誘導し、急性前骨髄球性白血病(APL)の寛解導入療法に用いられる薬物を特定することです。 APLは急性骨髄性白血病(AML)の一種です。
■解説1|
白血病細胞の分化を誘導し、APLの寛解導入療法に用いられるのは
4. トレチノイン です。
• トレチノインは、ビタミンAの誘導体であり、APL細胞の分化を促進することで寛解導入に用いられます。
• APLの治療成績はトレチノインの導入により劇的に改善されました。
■解説2|
• イマチニブ: チロシンキナーゼ阻害薬であり、慢性骨髄性白血病(CML)の治療に用いられます。
• シクロスポリン: 免疫抑制薬であり、臓器移植後の拒絶反応の抑制や自己免疫疾患の治療に用いられます。
• シクロホスファミド: 抗悪性腫瘍薬であり、様々な悪性腫瘍の治療に用いられます。
• メトトレキサート: 抗悪性腫瘍薬や免疫抑制薬であり、様々な悪性腫瘍や自己免疫疾患の治療に用いられます。
■科目|病態|問 107-061 ■正答| 1
閃せん輝き暗点を伴うことがある頭痛はどれか。1つ選べ。
■選択肢
片頭痛
反復性緊張型頭痛
慢性緊張型頭痛
反復性群発頭痛
慢性群発頭痛
■■Copilot
病態|問 107-061 ■正答| 1
■論点 |閃せん輝き暗点を伴うことがある頭痛
この問題の論点は、閃せん輝き暗点を伴うことがある頭痛を特定することです。
■解説1|
片頭痛は、閃せん輝き暗点(視覚異常)を伴うことがある頭痛です。これは、片頭痛の前兆症状として知られています。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-061
■論点 |閃輝暗点を伴う頭痛
この問題の主な論点は、閃輝暗点を伴う頭痛の種類を特定することです。閃輝暗点は、視覚障害の一種であり、視野の一部がキラキラと光って見えたり、暗点が出現したりする症状です。
■解説1|
閃輝暗点を伴うことがある頭痛は 1. 片頭痛 です。
• 片頭痛では、頭痛発作の前に閃輝暗点が出現することがあります。
• 閃輝暗点は、数分から30分ほど続き、その後頭痛が始まります。
■解説2|
• 反復性緊張型頭痛: 頭全体が締め付けられるような痛みが特徴の頭痛です。
• 慢性緊張型頭痛: 緊張型頭痛が慢性化した状態です。
• 反復性群発頭痛: 片側の目の奥に激痛が走る頭痛です。
• 慢性群発頭痛: 群発頭痛が慢性化した状態です。
■科目|病態|問 108-061 ■正答| 1
特徴的な症状の1つとして、間欠性跛行がみられる疾患はどれか。1つ選べ。
■選択肢
閉塞性動脈硬化症
筋ジストロフィー
変形性膝関節症
痛風
関節リウマチ
■■Copilot
病態|問 108-061 ■正答| 1
■論点 |特徴的な症状の1つとして、間欠性跛行がみられる疾患
この問題の論点は、特徴的な症状の1つとして、間欠性跛行がみられる疾患を特定することです。
■解説1|
閉塞性動脈硬化症は、血管の硬化により血流が妨げられ、特に運動時に筋肉への血流が不足することで、間欠性跛行(歩行時の足の痛み)を引き起こす疾患です。
■解説2|
他の選択肢(筋ジストロフィー、変形性膝関節症、痛風、関節リウマチ)では、一般的に間欠性跛行は主な症状ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-061
■論点 |間欠性跛行を特徴とする疾患
この問題の主な論点は、間欠性跛行を特徴的な症状の一つとする疾患を特定することです。間欠性跛行は、歩行時に下肢の痛みや痺れが出現し、休息により症状が軽減する状態を指します。
■解説1|
特徴的な症状の一つとして、間欠性跛行がみられる疾患は 1. 閉塞性動脈硬化症 です。
• 閉塞性動脈硬化症は、下肢の動脈が動脈硬化により狭窄・閉塞することで血流が悪くなり、間欠性跛行や冷感、皮膚潰瘍などを引き起こす疾患です。
• 歩行時に筋肉への血流が不足することで症状が出現し、休息により血流が回復すると症状が軽減します。
■解説2|
• 筋ジストロフィー: 遺伝子の異常により筋肉が変性し、筋力低下をきたす疾患です。
• 変形性膝関節症: 膝関節の軟骨がすり減ることで痛みや変形をきたす疾患です。
• 痛風: 尿酸が関節に沈着することで激しい痛みをきたす疾患です。
• 関節リウマチ: 自己免疫疾患の一つであり、関節の炎症や破壊をきたす疾患です。
■科目|病態|問 109-061 ■正答| 5
心電図上でQT間隔の延長により生じやすくなる不整脈はどれか。1つ選べ。
■選択肢
洞停止
洞房ブロック
心房細動
発作性上室頻拍
多形性心室頻拍
■■Copilot
病態|問 109-061 ■正答| 5
■論点 |心電図上でQT間隔の延長により生じやすくなる不整脈
この問題の論点は、心電図上でQT間隔の延長により生じやすくなる不整脈を特定することです。
■解説1|
QT間隔の延長は、心室再分極の異常を反映し、これにより多形性心室頻拍が生じやすくなります。これは、心電図上でT波の形状が変動する不整脈で、重篤な場合には心停止を引き起こす可能性があります。
■解説2|
他の選択肢(洞停止、洞房ブロック、心房細動、発作性上室頻拍)は、一般的にQT間隔の延長により生じる不整脈ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-061
■論点 |QT延長と不整脈
この問題の主な論点は、心電図上でQT間隔の延長により生じやすくなる不整脈を特定することです。QT間隔は、心室の興奮と回復にかかる時間を表しており、延長は不整脈のリスクを高めます。
■解説1|
心電図上でQT間隔の延長により生じやすくなる不整脈は
5. 多形性心室頻拍 です。
• 多形性心室頻拍は、心室から発生する頻脈性不整脈であり、心電図上のQRS波形が変化するのが特徴です。
• QT延長は、心室の再分極過程が遅延することを示唆しており、多形性心室頻拍の発生リスクを高めます。
■解説2|
• 洞停止: 洞結節からの電気刺激が停止し、心拍が停止する不整脈です。
• 洞房ブロック: 洞結節からの電気刺激が心房に伝わらない不整脈です。
• 心房細動: 心房が無秩序に興奮し、心房が細かく震える不整脈です。
• 発作性上室頻拍: 心房や房室結節から発生する頻脈性不整脈です。
■科目|病態|問 106-062 ■正答| 5
前立腺肥大症の治療薬はどれか。1つ選べ。
■選択肢
アナストロゾール
クロニジン塩酸塩
クロルフェニラミンマレイン酸塩
シルデナフィルクエン酸塩
デュタステリド
■■Copilot
病態|問 106-062 ■正答| 5
■論点 |前立腺肥大症の治療薬
この問題の論点は、前立腺肥大症の治療薬を特定することです。
■解説1|
デュタステリドは、前立腺肥大症の治療に用いられます。これは、5α-還元酵素阻害薬であり、前立腺の肥大を引き起こす男性ホルモン(ジヒドロテストステロン)の生成を抑制します。
■解説2|
他の選択肢(アナストロゾール、クロニジン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、シルデナフィルクエン酸塩)は、一般的に前立腺肥大症の治療には用いられません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-062
■論点 |前立腺肥大症の治療薬
この問題の主な論点は、前立腺肥大症の治療に用いられる薬物を特定することです。前立腺肥大症は、加齢に伴い前立腺が肥大し、排尿障害を引き起こす疾患です。
■解説1|
前立腺肥大症の治療薬は
5. デュタステリド です。
• デュタステリドは、5α還元酵素阻害薬であり、テストステロンからジヒドロテストステロンへの変換を阻害することで前立腺の肥大を抑えます。
• 前立腺肥大症に伴う排尿障害の改善に効果があります。
■解説2|
• アナストロゾール: アロマターゼ阻害薬であり、乳癌の治療に用いられます。
• クロニジン塩酸塩: α2アドレナリン受容体作動薬であり、高血圧の治療に用いられます。
• クロルフェニラミンマレイン酸塩: 抗ヒスタミン薬であり、アレルギー症状の緩和に用いられます。
• シルデナフィルクエン酸塩: ホスホジエステラーゼ5阻害薬であり、勃起障害の治療に用いられます。
■科目|病態|問 107-062 ■正答| 3
依存性の最も少ない薬物はどれか。1つ選べ。
■選択肢
ペンタゾシン
メチルフェニデート
グアンファシン
メタンフェタミン
ペモリン
■■Copilot
病態|問 107-062 ■正答| 3
■論点 |依存性の最も少ない薬物
この問題の論点は、依存性の最も少ない薬物を特定することです。
■解説1|
グアンファシンは、中枢神経系に作用する薬物で、高血圧の治療や注意欠陥・多動性障害(ADHD)の治療に用いられます。依存性は非常に低いとされています。
■解説2|
他の選択肢(ペンタゾシン、メチルフェニデート、メタンフェタミン、ペモリン)は、それぞれ異なる程度の依存性を持つ薬物で、一般的にはグアンファシンよりも依存性が高いとされています。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-062
■論点 |依存性の低い薬剤の特定
この問題の主な論点は、提供された選択肢の中から依存性の最も低い薬剤を特定することです。様々な薬剤は異なる作用機序やリスクプロファイルを持つため、依存性の度合いも異なります。
■解説1|
依存性の最も少ない薬物は
3. グアンファシン です。
• グアンファシンは、α2アドレナリン受容体作動薬であり、主にADHDの治療や高血圧の治療に用いられます。
• 中枢神経系への作用は比較的穏やかであり、乱用や依存のリスクは低いとされています。
■解説2|
• ペンタゾシン: 麻薬性鎮痛薬であり、中等度から重度の疼痛緩和に用いられます。 依存性や乱用のリスクがあります。
• メチルフェニデート: 中枢神経刺激薬であり、主にADHDの治療に用いられます。 乱用や依存のリスクがあります。
• メタンフェタミン: 中枢神経刺激薬であり、覚醒剤として乱用されることがあります。 依存性や乱用のリスクが非常に高いです。
• ペモリン: 中枢神経刺激薬であり、主にADHDの治療に用いられていましたが、重篤な肝障害を引き起こす可能性があるため、現在は使用されていません。 依存性や乱用のリスクがありました。
■科目|病態|問 108-062 ■正答| 4
急性膵炎で通常認められる所見はどれか。1つ選べ。
■選択肢
血中ヘモグロビン量の減少
血中リパーゼ活性の低下
白血球数の減少
心窩部痛
右腕への放散痛
■■Copilot
病態|問 108-062 ■正答| 4
■論点 |急性膵炎で通常認められる所見
この問題の論点は、急性膵炎で通常認められる所見を特定することです。
■解説1|
急性膵炎は、膵臓の炎症により引き起こされる疾患で、心窩部痛(上腹部の痛み)が典型的な所見です。この痛みは、しばしば背部に放散します。
■解説2|
他の選択肢(血中ヘモグロビン量の減少、血中リパーゼ活性の低下、白血球数の減少、右腕への放散痛)は、一般的に急性膵炎の典型的な所見ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-062
■論点 |急性膵炎の典型的な所見
この問題の主な論点は、急性膵炎で一般的に見られる所見を特定することです。急性膵炎は、膵臓の炎症を特徴とする疾患で、様々な症状を引き起こします。
■解説1|
急性膵炎で通常認められる所見は
4. 心窩部痛 です。
• 急性膵炎の最も特徴的な症状は、みぞおちの激しい痛みです。
• 背部痛や吐き気、嘔吐を伴うこともあります。
■解説2|
• 血中ヘモグロビン量の減少: 貧血を示唆しており、急性膵炎の典型的な所見ではありません。
• 血中リパーゼ活性の低下: 膵臓の機能低下を示唆しており、急性膵炎ではむしろリパーゼ活性の上昇がみられます。
• 白血球数の減少: 免疫機能の低下を示唆しており、急性膵炎ではむしろ白血球数の増加がみられます。
• 右腕への放散痛: 胆石症や胆嚢炎などでみられる症状です。
■科目|病態|問 109-062 ■正答| 5
副腎皮質ステロイド性薬が適用される腎疾患はどれか。1つ選べ。
■選択肢
腎硬化症
糖尿病性腎症
痛風腎
多発性嚢胞腎
特発性膜性腎症
■■Copilot
病態|問 109-062 ■正答| 5
■論点 |副腎皮質ステロイド性薬が適用される腎疾患
この問題の論点は、副腎皮質ステロイド性薬が適用される腎疾患を特定することです。
■解説1|
特発性膜性腎症は、腎臓の病変によりタンパク尿を引き起こす疾患で、副腎皮質ステロイド性薬が適用されます。これは、免疫抑制作用により腎病変を改善するためです。
■解説2|
他の選択肢(腎硬化症、糖尿病性腎症、痛風腎、多発性嚢胞腎)では、一般的に副腎皮質ステロイド性薬の主な適応症ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-062
■論点 |副腎皮質ステロイド薬の適応となる腎疾患
この問題の主な論点は、副腎皮質ステロイド薬が適用される腎疾患を特定することです。副腎皮質ステロイド薬は、抗炎症作用や免疫抑制作用があり、様々な疾患の治療に用いられます。
■解説1|
副腎皮質ステロイド薬が適用される腎疾患は
5. 特発性膜性腎症 です。
• 特発性膜性腎症は、糸球体の基底膜に免疫複合体が沈着することでタンパク尿やネフローゼ症候群を引き起こす疾患です。
• 副腎皮質ステロイド薬は、免疫反応を抑えることでタンパク尿を軽減させる効果があります。
■解説2|
• 腎硬化症: 腎臓の血管が硬くなり、腎機能が低下する疾患です。
• 糖尿病性腎症: 糖尿病の合併症であり、腎機能が低下する疾患です。
• 痛風腎: 尿酸が腎臓に沈着することで腎機能が低下する疾患です。
• 多発性嚢胞腎: 腎臓に多数の嚢胞が形成される遺伝性疾患です。
■科目|病態|問 106-063 ■正答| 5
急性膵炎の診断に有用な血液検査値はどれか。1つ選べ。
■選択肢
アルブミン濃度
C反応性タンパク(CRP)濃度
乳酸脱水素酵素(LDH)活性
尿素窒素(BUN)濃度
リパーゼ活性
■■Copilot
病態|問 106-063 ■正答| 5
■論点 |急性膵炎の診断に有用な血液検査値
この問題の論点は、急性膵炎の診断に有用な血液検査値を特定することです。
■解説1|
急性膵炎の診断には、血中リパーゼ活性の測定が有用です。リパーゼは膵臓で産生される酵素で、急性膵炎では膵臓細胞の破壊により血中に放出され、その活性が上昇します。
■解説2|
他の選択肢(アルブミン濃度、C反応性タンパク(CRP)濃度、乳酸脱水素酵素(LDH)活性、尿素窒素(BUN)濃度)は、一般的に急性膵炎の診断には直接用いられません。
■科目|病態|問 107-063 ■正答| 4
子宮内膜症の治療に用いる薬剤はどれか。1つ選べ。
■選択肢
エチニルエストラジオール錠
エンザルタミド錠
オキシトシン注
リュープロレリン酢酸塩注
レトロゾール錠
■■Copilot
病態|問 107-063 ■正答| 4
■論点 |子宮内膜症の治療に用いる薬剤
この問題の論点は、子宮内膜症の治療に用いる薬剤を特定することです。
■解説1|
子宮内膜症の治療には、リュープロレリン酢酸塩注が用いられます。これはゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)アゴニストで、卵巣からのエストロゲンの分泌を抑制し、子宮内膜症の症状を改善します。
■解説2|
他の選択肢(エチニルエストラジオール錠、エンザルタミド錠、オキシトシン注、レトロゾール錠)は、一般的に子宮内膜症の治療には用いられません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-063
■論点 |子宮内膜症の治療薬の特定
この問題の主な論点は、子宮内膜症の治療に用いられる薬剤を特定することです。子宮内膜症は、子宮内膜様の組織が子宮腔以外に発生し、増殖することで痛みや不妊などの症状を引き起こす疾患です。
■解説1|
子宮内膜症の治療に用いる薬剤は
4. リュープロレリン酢酸塩注 です。
• リュープロレリンは、性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)アナログであり、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌を抑制することで、エストロゲンの産生を低下させます。
• エストロゲンの低下は、子宮内膜症の増殖を抑える効果があり、症状の改善や不妊治療に用いられます。
■解説2|
• エチニルエストラジオール錠: エストロゲン製剤であり、ホルモン補充療法などに用いられますが、子宮内膜症を悪化させる可能性があります。
• エンザルタミド錠: 抗アンドロゲン薬であり、前立腺癌の治療に用いられます。
• オキシトシン注: 子宮収縮薬であり、分娩誘発や産後出血の治療に用いられます。
• レトロゾール錠: アロマターゼ阻害薬であり、乳癌の治療に用いられます。
■科目|病態|問 108-063 ■正答| 4
アジソン病で特徴的に認められる所見はどれか。1つ選べ。
■選択肢
高血圧
高血糖
体重増加
色素沈着
活動性亢進
■■Copilot
病態|問 108-063 ■正答| 4
■論点 |アジソン病で特徴的に認められる所見
この問題の論点は、アジソン病で特徴的に認められる所見を特定することです。
■解説1|
アジソン病は、副腎皮質機能の低下により引き起こされる疾患で、色素沈着が特徴的な所見として認められます。これは、副腎皮質ホルモンの減少によりメラノサイト刺激ホルモン(MSH)の分泌が亢進し、皮膚や粘膜にメラニン色素が沈着するためです。
■解説2|
他の選択肢(高血圧、高血糖、体重増加、活動性亢進)は、一般的にアジソン病の典型的な所見ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-063
■論点 |アジソン病の特徴的な所見
この問題の主な論点は、アジソン病で特徴的に認められる所見を特定することです。アジソン病は、副腎皮質ホルモンの分泌が低下した状態です。
■解説1|
アジソン病で特徴的に認められる所見は
4. 色素沈着 です。
• アジソン病では、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌が亢進し、メラニン細胞刺激ホルモン(MSH)の産生も増加します。
• MSHの増加により、皮膚や粘膜に色素沈着がみられます。
■解説2|
• 高血圧: アルドステロンの分泌低下により、むしろ低血圧になりやすいです。
• 高血糖: コルチゾールの分泌低下により、むしろ低血糖になりやすいです。
• 体重増加: コルチゾールの分泌低下により、むしろ体重減少がみられます。
• 活動性亢進: コルチゾールの分泌低下により、むしろ倦怠感や筋力低下がみられます。
■科目|病態|問 109-063 ■正答| 3
ポリカルボフィルカルシウムが適用される疾患はどれか。1つ選べ。
■選択肢
術後イレウス
高カルシウム血症
過敏性腸症候群
腎不全
虫垂炎
■■Copilot
病態|問 109-063 ■正答| 3
■論点 |ポリカルボフィルカルシウムが適用される疾患
この問題の論点は、ポリカルボフィルカルシウムが適用される疾患を特定することです。
■解説1|
ポリカルボフィルカルシウムは、便秘型の過敏性腸症候群(IBS-C)の治療に用いられます。これは、腸内で水分を吸収して便を膨らませ、便通を促進する作用があります。
■解説2|
他の選択肢(術後イレウス、高カルシウム血症、腎不全、虫垂炎)では、一般的にポリカルボフィルカルシウムの主な適応症ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-063
■論点 |急性膵炎の診断に有用な血液検査
この問題の主な論点は、急性膵炎の診断に有用な血液検査値を特定することです。急性膵炎は、膵臓の炎症を特徴とする疾患で、血液検査により診断を支援できます。
■解説1|
急性膵炎の診断に有用な血液検査値は
5. リパーゼ活性 です。
• リパーゼは、膵臓から分泌される消化酵素であり、急性膵炎では血中リパーゼ活性が著しく上昇します。
• リパーゼ活性の上昇は、急性膵炎の診断に非常に有用な指標です。
■解説2|
• アルブミン濃度: 肝臓のタンパク質合成能を反映する指標です。
• C反応性タンパク(CRP)濃度: 炎症反応の指標です。
• 乳酸脱水素酵素(LDH)活性: 多くの臓器に存在する酵素であり、様々な疾患で上昇します。
• 尿素窒素(BUN)濃度: 腎機能の指標です。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-063
■論点 |ポリカルボフィルカルシウムの適応疾患
この問題の主な論点は、ポリカルボフィルカルシウムが適用される疾患を特定することです。ポリカルボフィルカルシウムは、膨潤性下剤に分類される薬剤です。
■解説1|
ポリカルボフィルカルシウムが適用される疾患は
3. 過敏性腸症候群 です。
• ポリカルボフィルカルシウムは、水分を吸収して膨潤し、便の量を増やすことで排便を促進します。
• 過敏性腸症候群の便秘型に効果があります。
■解説2|
• 術後イレウス: 手術後に腸の動きが悪くなる状態です。
• 高カルシウム血症: 血清カルシウム濃度が上昇した状態です。
• 腎不全: 腎機能が低下した状態です。
• 虫垂炎: 虫垂に炎症が起こる疾患です。
■科目|病態|問 106-064 ■正答| 5
動揺病による嘔気の予防に用いられるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
イソソルビド
エチゾラム
ジフェニドール塩酸塩
ジメンヒドリナート
■■Copilot
病態|問 106-064 ■正答| 5
■論点 |動揺病による嘔気の予防に用いられる薬物
この問題の論点は、動揺病による嘔気の予防に用いられる薬物を特定することです。
■解説1|
ジメンヒドリナートは、乗り物酔い(動揺病)による嘔気の予防に用いられます。これは、内耳の前庭系に作用し、乗り物酔いによるめまいや嘔気を抑制する作用があります。
■解説2|
他の選択肢(アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物、イソソルビド、エチゾラム、ジフェニドール塩酸塩)は、一般的に動揺病による嘔気の予防には用いられません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-064
■論点 |動揺病の治療薬
この問題の主な論点は、動揺病による嘔気の予防に用いられる薬物を特定することです。動揺病は、乗り物酔いや船酔いなど、乗り物に乗った時に起こる自律神経系の不調です。
■解説1|
動揺病による嘔気の予防に用いられるのは
5. ジメンヒドリナート です。
• ジメンヒドリナートは、抗ヒスタミン薬であり、嘔吐中枢を抑制することで嘔気を抑えます。
• 動揺病の予防や治療に用いられます。
■解説2|
• アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物: エネルギー代謝に関与する物質であり、疲労回復などに用いられます。
• イソソルビド: 血管拡張薬であり、狭心症や心不全の治療に用いられます。
• エチゾラム: 抗不安薬であり、不安や緊張の緩和に用いられます。
• ジフェニドール塩酸塩: 抗コリン薬であり、パーキンソン病の治療に用いられます。
■科目|病態|問 107-064 ■正答| 4
急性胆管炎に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
左下腹部に痛みを生じる。
発熱を伴うことはまれである。
血中白血球数が減少する。
血清ALP(アルカリフォスファターゼ)活性が上昇する。
血中間接ビリルビン値が上昇する。
■■Copilot
病態|問 107-064 ■正答| 4
■論点 |急性胆管炎に関する正しい記述
この問題の論点は、急性胆管炎に関する正しい記述を特定することです。
■解説1|
急性胆管炎は、胆管の炎症により引き起こされる疾患で、血清ALP(アルカリフォスファターゼ)活性の上昇が特徴的な所見として認められます。これは、胆管の炎症や閉塞により、肝臓や胆管からALPが血液中に放出されるためです。
■解説2|
他の選択肢(左下腹部に痛みを生じる、発熱を伴うことはまれである、血中白血球数が減少する、血中間接ビリルビン値が上昇する)は、一般的に急性胆管炎の典型的な所見ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-064
■論点 |急性胆管炎の特徴
この問題の主な論点は、急性胆管炎に関する正しい記述を特定することです。急性胆管炎は、胆管に炎症が起こる疾患です。
■解説1|
急性胆管炎に関する記述のうち、正しいのは
4. 血清ALP(アルカリフォスファターゼ)活性が上昇する です。
• 急性胆管炎では、胆汁の流れが障害されることで、血清ALP活性やビリルビン値が上昇します。
• ALPは肝臓や胆道に存在する酵素であり、胆汁うっ滞があると血中に漏出してきます。
■解説2|
• 左下腹部に痛みを生じる: 虫垂炎などでみられる症状です。
• 発熱を伴うことはまれである: 急性胆管炎では、発熱は一般的な症状です。
• 血中白血球数が減少する: 感染症や免疫機能の低下でみられる症状です。
• 血中間接ビリルビン値が上昇する: 溶血性貧血などでみられる症状です。
■科目|病態|問 108-064 ■正答| 5
慢性副鼻腔炎の治療に用いられるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
イソプロピルウノプロストン
ムピロシンカルシウム水和物
メトキサレン
ナフトピジル
クラリスロマイシン
■■Copilot
病態|問 108-064 ■正答| 5
■論点 |慢性副鼻腔炎の治療に用いられる薬物
この問題の論点は、慢性副鼻腔炎の治療に用いられる薬物を特定することです。
■解説1|
慢性副鼻腔炎の治療には、クラリスロマイシンが用いられます。これは、抗生物質の一種で、感染により引き起こされる炎症を抑制します。
■解説2|
他の選択肢(イソプロピルウノプロストン、ムピロシンカルシウム水和物、メトキサレン、ナフトピジル)は、一般的に慢性副鼻腔炎の治療には用いられません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-064
■論点 |慢性副鼻腔炎の治療薬
この問題の主な論点は、慢性副鼻腔炎の治療に用いられる薬物を特定することです。慢性副鼻腔炎は、副鼻腔に炎症が慢性的に続く疾患です。
■解説1|
慢性副鼻腔炎の治療に用いられるのは
5. クラリスロマイシン です。
• クラリスロマイシンは、マクロライド系抗生物質であり、副鼻腔炎の原因菌に効果があります。
• 慢性副鼻腔炎の治療では、原因菌に対する抗菌薬の投与が重要です。
■解説2|
• イソプロピルウノプロストン: 緑内障治療薬であり、眼圧を下げる作用があります。
• ムピロシンカルシウム水和物: 抗生物質であり、皮膚感染症の治療に用いられます。
• メトキサレン: 光線増感剤であり、乾癬などの皮膚疾患の治療に用いられます。
• ナフトピジル: α1遮断薬であり、前立腺肥大症に伴う排尿障害の治療に用いられます。
■科目|病態|問 109-064 ■正答| 4
尿路結石を有する痛風患者に対して、最も適切な尿酸降下薬はどれか。1つ選べ。
■選択肢
ベンズブロマロン
コルヒチン
ドチヌラド
トピロキソスタット
プロベネシド
■■Copilot
病態|問 109-064 ■正答| 4
■論点 |尿路結石を有する痛風患者に対して、最も適切な尿酸降下薬
この問題の論点は、尿路結石を有する痛風患者に対して、最も適切な尿酸降下薬を特定することです。
■解説1|
トピロキソスタットは、尿酸生成を抑制する薬剤で、尿路結石を有する痛風患者に対して適切な尿酸降下薬とされています。これは、尿酸排泄を増加させる薬剤(例えば、ベンズブロマロンやプロベネシド)が尿路結石のリスクを増加させる可能性があるためです。
■解説2|
他の選択肢(ベンズブロマロン、コルヒチン、ドチヌラド、プロベネシド)は、一般的に尿路結石を有する痛風患者に対して最も適切な尿酸降下薬ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-064
■論点 |尿路結石を有する痛風患者への尿酸降下薬
この問題の主な論点は、尿路結石を有する痛風患者に最も適切な尿酸降下薬を特定することです。痛風は、尿酸が関節に沈着することで激しい痛みをきたす疾患であり、尿酸降下薬を用いて治療します。
■解説1|
尿路結石を有する痛風患者に対して、最も適切な尿酸降下薬は
4. トピロキソスタット です。
• トピロキソスタットは、キサンチンオキシダーゼ阻害薬であり、尿酸の産生を抑制します。
• 他の尿酸降下薬と異なり、尿路結石のリスクを高めないため、尿路結石を有する痛風患者に適しています。
■解説2|
• ベンズブロマロン: 尿酸排泄促進薬であり、尿酸の排泄を促進しますが、尿路結石のリスクを高めます。
• コルヒチン: 痛風発作の治療に用いられますが、尿酸値を下げる作用はありません。
• ドチヌラド: 尿酸排泄促進薬であり、尿酸の排泄を促進しますが、尿路結石のリスクを高めます。
• プロベネシド: 尿酸排泄促進薬であり、尿酸の排泄を促進しますが、尿路結石のリスクを高めます。
■科目|病態|問 106-065 ■正答| 5
空気感染する病原体はどれか。1つ選べ。
■選択肢
インフルエンザウイルス
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)
ポリオウイルス
風しんウイルス
麻しんウイルス
■■Copilot
病態|問 106-065 ■正答| 5
■論点 |空気感染する病原体
この問題の論点は、空気感染する病原体を特定することです。
■解説1|
麻しんウイルスは、空気感染する病原体の一つです。これは、感染者が咳やくしゃみをすることで、ウイルスが空気中に広がり、他の人がこれを吸い込むことで感染します。
■解説2|
他の選択肢(インフルエンザウイルス、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、ポリオウイルス、風しんウイルス)も空気感染する可能性がありますが、麻しんウイルスは特に感染力が強く、空気感染することで大流行を引き起こすことが知られています。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-065
■論点 |空気感染する病原体の特定
この問題の主な論点は、選択肢の中から空気感染する病原体を特定することです。感染経路には様々な種類がありますが、空気感染は特に感染力が強いとされています。
■解説1|
空気感染する病原体は
5. 麻しんウイルス です。
• 麻しんウイルスは、麻疹を引き起こすウイルスであり、空気感染によって広がります。
• 麻疹は感染力が非常に強く、ワクチン接種が重要です。
■解説2|
• インフルエンザウイルス: 飛沫感染や接触感染によって広がります。
• ヒト免疫不全ウイルス(HIV): 血液や体液を介した感染によって広がります。
• ポリオウイルス: 糞口感染によって広がります。
• 風しんウイルス: 飛沫感染や接触感染によって広がります。
■科目|病態|問 107-065 ■正答| 3
原発性アルドステロン症の臨床所見として、正しいのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
低血圧症
低ナトリウム血症
低カリウム血症
インスリン分泌の増加
レニン活性の上昇
■■Copilot
病態|問 107-065 ■正答| 3
■論点 |原発性アルドステロン症の臨床所見
この問題の論点は、原発性アルドステロン症の臨床所見を特定することです。
■解説1|
原発性アルドステロン症は、アルドステロンの過剰分泌により引き起こされる疾患で、低カリウム血症(血中のカリウム濃度が低下する状態)が特徴的な臨床所見として認められます。これは、アルドステロンが腎臓でのナトリウムの再吸収とカリウムの排泄を促進するためです。
■解説2|
他の選択肢(低血圧症、低ナトリウム血症、インスリン分泌の増加、レニン活性の上昇)は、一般的に原発性アルドステロン症の典型的な所見ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-065
■論点 |原発性アルドステロン症の臨床所見
この問題の主な論点は、原発性アルドステロン症の臨床所見として正しいものを特定することです。原発性アルドステロン症は、副腎からアルドステロンが過剰に分泌される疾患です。
■解説1|
原発性アルドステロン症の臨床所見として、正しいのは
3. 低カリウム血症 です。
• アルドステロンは、腎臓でのナトリウムの再吸収とカリウムの排泄を促進する作用があります。
• 原発性アルドステロン症では、アルドステロンの過剰分泌により、低カリウム血症や高血圧がみられます。
■解説2|
• 低血圧症: アルドステロンの作用により、むしろ高血圧になりやすいです。
• 低ナトリウム血症: アルドステロンの作用により、ナトリウムが再吸収されるため、低ナトリウム血症は起こりにくいです。
• インスリン分泌の増加: アルドステロンの作用とは直接関係ありません。
• レニン活性の上昇: 原発性アルドステロン症では、アルドステロンの過剰分泌により、レニン-アンジオテンシン系が抑制されるため、レニン活性は低下します。
■科目|病態|問 108-065 ■正答| 2
テープ剤が光線過敏症の原因となりやすいのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
ビソプロロールフマル酸塩
ケトプロフェン
オキシブチニン塩酸塩
硝酸イソソルビド
ツロブテロール
■■Copilot
病態|問 108-065 ■正答| 2
■論点 |テープ剤が光線過敏症の原因となりやすい薬物
この問題の論点は、テープ剤が光線過敏症の原因となりやすい薬物を特定することです。
■解説1|
ケトプロフェンは、非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)の一つで、テープ剤として皮膚に貼付する形で用いられます。しかし、ケトプロフェンが日光に曝露されると光化学反応を起こし、これが皮膚の光線過敏症を引き起こすことが知られています。
■解説2|
他の選択肢(ビソプロロールフマル酸塩、オキシブチニン塩酸塩、硝酸イソソルビド、ツロブテロール)は、一般的に光線過敏症の原因となりやすい薬物ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-065
■論点 |光線過敏症の原因となりやすいテープ剤
この問題の主な論点は、テープ剤の中で光線過敏症の原因となりやすいものを特定することです。光線過敏症は、日光に当たると皮膚に炎症が起こる症状です。
■解説1|
テープ剤が光線過敏症の原因となりやすいのは
2. ケトプロフェン です。
• ケトプロフェンは、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)であり、消炎鎮痛作用があります。
• ケトプロフェンを含むテープ剤は、光線過敏症を引き起こすことが知られており、貼付部位が日光に当たると皮膚に炎症を起こすことがあります。
■解説2|
• ビソプロロールフマル酸塩: β遮断薬であり、高血圧や狭心症の治療に用いられます。
• オキシブチニン塩酸塩: 抗コリン薬であり、過活動膀胱の治療に用いられます。
• 硝酸イソソルビド: 血管拡張薬であり、狭心症の治療に用いられます。
• ツロブテロール: β2刺激薬であり、気管支喘息やCOPDの治療に用いられます。
■科目|病態|問 109-065 ■正答| 2
手術が適応とならないクッシング症候群の治療に用いる薬物はどれか。1つ選べ。
■選択肢
チアマゾール
ミトタン
デスモプレシン酢酸塩水和物
レボチロキシンナトリウム水和物
メチロシン
■■Copilot
病態|問 109-065 ■正答| 2
■論点 |手術が適応とならないクッシング症候群の治療に用いる薬物
この問題の論点は、手術が適応とならないクッシング症候群の治療に用いる薬物を特定することです。
■解説1|
ミトタンは、クッシング症候群の治療に用いられる薬物で、特に手術が適応とならない場合に用いられます。これは、副腎皮質の機能を抑制し、クッシング症候群の症状を改善する作用があります。
■解説2|
他の選択肢(チアマゾール、デスモプレシン酢酸塩水和物、レボチロキシンナトリウム水和物、メチロシン)は、一般的に手術が適応とならないクッシング症候群の治療には用いられません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-065
■論点 |手術非適応のクッシング症候群の治療薬
この問題の主な論点は、手術が適応とならないクッシング症候群の治療に用いる薬物を特定することです。クッシング症候群は、副腎皮質ホルモンが過剰に分泌される疾患です。
■解説1|
手術が適応とならないクッシング症候群の治療に用いる薬物は
2. ミトタン です。
• ミトタンは、副腎皮質の細胞を破壊する作用があり、コルチゾールの産生を抑制します。
• 手術が適応とならないクッシング症候群の治療に用いられます。
■解説2|
• チアマゾール: 抗甲状腺薬であり、甲状腺機能亢進症の治療に用いられます。
• デスモプレシン酢酸塩水和物: バソプレシンアナログであり、尿崩症の治療に用いられます。
• レボチロキシンナトリウム水和物: 甲状腺ホルモン製剤であり、甲状腺機能低下症の治療に用いられます。
• メチロシン: チロシン水酸化酵素阻害薬であり、褐色細胞腫の治療に用いられます。
■科目|病態|問 106-066 ■正答| 3
帯状疱疹の治療薬はどれか。1つ選べ。
■選択肢
ガンシクロビル
ザナミビル水和物
バラシクロビル塩酸塩
ラルテグラビルカリウム
リトナビル
■■Copilot
病態|問 106-066 ■正答| 3
■論点 |帯状疱疹の治療薬
この問題の論点は、帯状疱疹の治療薬を特定することです。
■解説1|
バラシクロビル塩酸塩は、帯状疱疹の治療に用いられます。これは、ウイルスDNAの合成を阻害する抗ウイルス薬で、帯状疱疹を引き起こす水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)に対して効果があります。
■解説2|
他の選択肢(ガンシクロビル、ザナミビル水和物、ラルテグラビルカリウム、リトナビル)は、一般的に帯状疱疹の治療には用いられません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-066
■論点 |帯状疱疹の治療薬
この問題の主な論点は、帯状疱疹の治療に用いられる薬物を特定することです。帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルスが再活性化することで皮膚に水疱や痛みを引き起こす疾患です。
■解説1|
帯状疱疹の治療薬は
3. バラシクロビル塩酸塩 です。
• バラシクロビルは、抗ウイルス薬であり、水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖を抑えます。
• 帯状疱疹の治療には、抗ウイルス薬の早期投与が重要です。
■解説2|
• ガンシクロビル: 抗ウイルス薬であり、サイトメガロウイルス感染症の治療に用いられます。
• ザナミビル水和物: 抗ウイルス薬であり、インフルエンザの治療に用いられます。
• ラルテグラビルカリウム: 抗HIV薬であり、HIV感染症の治療に用いられます。
• リトナビル: 抗HIV薬であり、HIV感染症の治療に用いられます。
■科目|病態|問 107-066 ■正答| 5
活性型ビタミンD3外用薬が適用される皮膚疾患はどれか。1つ選べ。
■選択肢
接触性皮膚炎
爪白癬
アトピー性皮膚炎
じん麻疹
尋常性乾癬
■■Copilot
病態|問 107-066 ■正答| 5
■論点 |活性型ビタミンD3外用薬が適用される皮膚疾患
この問題の論点は、活性型ビタミンD3外用薬が適用される皮膚疾患を特定することです。
■解説1|
活性型ビタミンD3外用薬は、尋常性乾癬の治療に用いられます。これは、皮膚の細胞増殖を抑制し、炎症反応を抑える作用があります。
■解説2|
他の選択肢(接触性皮膚炎、爪白癬、アトピー性皮膚炎、じん麻疹)では、一般的に活性型ビタミンD3外用薬の主な適応症ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-066
■論点 |活性型ビタミンD3外用薬の適応疾患
この問題の主な論点は、活性型ビタミンD3外用薬が適用される皮膚疾患を特定することです。活性型ビタミンD3は、皮膚細胞の増殖や分化を調節する作用があります。
■解説1|
活性型ビタミンD3外用薬が適用される皮膚疾患は
5. 尋常性乾癬 です。
• 尋常性乾癬は、皮膚細胞の増殖が亢進することで皮膚が厚くなり、紅斑や鱗屑が生じる疾患です。
• 活性型ビタミンD3外用薬は、皮膚細胞の増殖を抑えることで乾癬の症状を改善します。
■解説2|
• 接触性皮膚炎: 外部からの刺激物質に接触することで起こる皮膚炎です。
• 爪白癬: 白癬菌が爪に感染することで起こる疾患です。
• アトピー性皮膚炎: アレルギー反応が関与する慢性的な皮膚炎です。
• じん麻疹: アレルギー反応などにより皮膚に膨疹や痒みが生じる疾患です。
■科目|病態|問 108-066 ■正答| 1
以下は骨肉腫に対するメトトレキサート・ホリナート救援療法の初日の処方例である。副作用回避の目的で用いる薬剤Aとして最も適切なのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
アセタゾラミドナトリウム注
ピペラシリンナトリウム注
フィルグラスチム(遺伝子組換え)注
フロセミド注
メスナ注
・108_166

■■Copilot
病態|問 108-066 ■正答| 1
■論点 |骨肉腫に対するメトトレキサート・ホリナート救援療法の副作用回避
この問題の論点は、骨肉腫に対するメトトレキサート・ホリナート救援療法の初日の処方例で副作用回避の目的で用いる薬剤Aを特定することです。
■解説1|
メトトレキサートの副作用: メトトレキサートは化学療法薬であり、高濃度で使用されると重篤な副作用が発生する可能性があります。
アセタゾラミドの作用: アセタゾラミドナトリウム注は尿をアルカリ化する作用があり、メトトレキサートの排泄を促進し、副作用を軽減します。
■解説2|他の選択肢の排除: ピペラシリンナトリウム注は抗生物質であり、フィルグラスチムは白血球増加作用があります。フロセミド注は利尿剤であり、メスナ注はシクロフォスファミドの副作用を軽減するために使用されます。これらはメトトレキサートの副作用回避には直接関係ありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-066
■論点 |メトトレキサート・ホリナート救援療法の副作用回避
この問題の主な論点は、骨肉腫に対するメトトレキサート・ホリナート救援療法の副作用回避のために用いられる薬剤を特定することです。メトトレキサートは抗悪性腫瘍薬ですが、腎障害などの副作用を引き起こすことがあります。
■解説1|
副作用回避の目的で用いる薬剤Aとして最も適切なのは 1. アセタゾラミドナトリウム注 です。
• メトトレキサートは腎臓から排泄される際に、腎臓に沈着して腎障害を引き起こすことがあります。
• アセタゾラミドは利尿薬であり、尿をアルカリ化することでメトトレキサートの溶解度を高め、腎臓からの排泄を促進します。
• これにより、メトトレキサートによる腎障害のリスクを軽減することができます。
■解説2|
• ピペラシリンナトリウム注: 抗生物質であり、細菌感染症の治療に用いられます。
• フィルグラスチム(遺伝子組換え)注: 白血球を増やす作用があり、抗がん剤による骨髄抑制の改善に用いられます。
• フロセミド注: 利尿薬であり、浮腫や高血圧の治療に用いられます。
• メスナ注: 抗がん剤の副作用である出血性膀胱炎の予防に用いられます。
■科目|病態|問 109-066 ■正答| 2
褥瘡治療に用いる外用薬のうち、壊死組織除去効果を有するのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
アルプロスタジルアルファデクス
ブロメライン
ポビドンヨード
ジメチルイソプロピルアズレン
トレチノイントコフェリル
■■Copilot
病態|問 109-066 ■正答| 2
■論点 |褥瘡治療に用いる外用薬のうち、壊死組織除去効果を有する薬物
この問題の論点は、褥瘡治療に用いる外用薬のうち、壊死組織除去効果を有する薬物を特定することです。
■解説1|
ブロメラインは、パイナップルの茎から抽出される酵素で、タンパク質を分解する働きがあります。このため、壊死組織の除去に効果があり、褥瘡の治療に用いられます。
■解説2|
他の選択肢(アルプロスタジルアルファデクス、ポビドンヨード、ジメチルイソプロピルアズレン、トレチノイントコフェリル)は、一般的に壊死組織除去効果を有するとは言えません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-066
■論点 |褥瘡治療薬と壊死組織除去
この問題の主な論点は、褥瘡治療に用いる外用薬のうち、壊死組織除去効果を有するものを特定することです。褥瘡は、長時間の圧迫により皮膚や皮下組織が壊死した状態です。
■解説1|
褥瘡治療に用いる外用薬のうち、壊死組織除去効果を有するのは
2. ブロメライン です。
• ブロメラインは、パイナップルから抽出されるタンパク質分解酵素であり、壊死組織を分解する作用があります。
• 褥瘡の治療では、壊死組織を除去することが重要であり、ブロメラインはその目的に用いられます。
■解説2|
• アルプロスタジルアルファデクス: 血管拡張薬であり、血行を改善する作用があります。
• ポビドンヨード: 消毒薬であり、殺菌作用があります。
• ジメチルイソプロピルアズレン: 抗炎症薬であり、炎症を抑える作用があります。
• トレチノイントコフェリル: ビタミンA誘導体とビタミンEの配合剤であり、皮膚の再生を促進する作用があります。
■科目|病態|問 106-067 ■正答| 1
乳がん発症の危険因子はどれか。1つ選べ。
■選択肢
初経年齢が早い
初産年齢が早い
出産歴がある
授乳歴がある
閉経年齢が早い
■■Copilot
病態|問 106-067 ■正答| 1
■論点 |乳がん発症の危険因子
この問題の論点は、乳がん発症の危険因子を特定することです。
■解説1|
初経年齢が早いことは、乳がんの危険因子の一つです。これは、エストロゲンとプロゲステロンの曝露期間が長くなることで、乳腺組織のがん化が進行しやすくなるためです。
■解説2|
他の選択肢(初産年齢が早い、出産歴がある、授乳歴がある、閉経年齢が早い)は、一般的に乳がんの危険因子とは考えられていません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-067
■論点 |乳がん発症の危険因子
この問題の主な論点は、乳がん発症の危険因子を特定することです。乳がんは、女性に最も多い悪性腫瘍の一つです。
■解説1|
乳がん発症の危険因子は 1. 初経年齢が早い です。
• 初経年齢が早いほど、エストロゲンにさらされる期間が長くなり、乳がんのリスクが高まるとされています。
■解説2|
• 初産年齢が早い、出産歴がある、授乳歴がある、閉経年齢が早い: これらは、乳がん発症のリスクを低下させる因子とされています。
■科目|病態|問 107-067 ■正答| 5
がん終末期における呼吸困難に対する治療薬はどれか。1つ選べ。
■選択肢
アセトアミノフェン
アドレナリン
スキサメトニウム
デキストロメトルファン
モルヒネ
■■Copilot
病態|問 107-067 ■正答| 5
■論点 |がん終末期における呼吸困難に対する治療薬
この問題の論点は、がん終末期における呼吸困難に対する治療薬を特定することです。
■解説1|
モルヒネは、がん終末期における呼吸困難の治療に用いられます。これは、強力な鎮痛作用と鎮静作用を持ち、呼吸中枢を抑制することで呼吸困難を緩和します。
■解説2|
他の選択肢(アセトアミノフェン、アドレナリン、スキサメトニウム、デキストロメトルファン)は、一般的にがん終末期における呼吸困難の治療には用いられません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-067
■論点 |がん終末期の呼吸困難の治療薬
この問題の主な論点は、がん終末期における呼吸困難に対する治療薬を特定することです。呼吸困難は、がん患者にしばしば見られる苦痛症状の一つです。
■解説1|
がん終末期における呼吸困難に対する治療薬は
5. モルヒネ です。
• モルヒネは、麻薬性鎮痛薬であり、呼吸中枢を抑制することで呼吸困難を軽減します。
• がん終末期の呼吸困難の治療では、モルヒネが第一選択薬となります。
■解説2|
• アセトアミノフェン: 解熱鎮痛薬であり、発熱や疼痛の緩和に用いられます。
• アドレナリン: 強心薬や気管支拡張薬として用いられます。
• スキサメトニウム: 筋弛緩薬として用いられます。
• デキストロメトルファン: 鎮咳薬として用いられます。
■科目|病態|問 108-067 ■正答| 4
マイコプラズマ肺炎の治療に用いられるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
アシクロビル錠
イベルメクチン錠
テビペネムピボキシル細粒
アジスロマイシン錠
リネゾリド錠
■■Copilot
病態|問 108-067 ■正答| 4
■論点 |マイコプラズマ肺炎の治療に用いられる薬物
この問題の論点は、マイコプラズマ肺炎の治療に用いられる薬物を特定することです。
■解説1|
アジスロマイシン錠は、マイコプラズマ肺炎の治療に用いられます。これは、マクロライド系の抗生物質で、マイコプラズマ属の細菌に対して効果があります。
■解説2|
他の選択肢(アシクロビル錠、イベルメクチン錠、テビペネムピボキシル細粒、リネゾリド錠)は、一般的にマイコプラズマ肺炎の治療には用いられません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-067
■論点 |マイコプラズマ肺炎の治療薬
この問題の主な論点は、マイコプラズマ肺炎の治療に用いられる薬物を特定することです。マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマという細菌によって引き起こされる肺炎です。
■解説1|
マイコプラズマ肺炎の治療に用いられるのは
4. アジスロマイシン錠 です。
• アジスロマイシンは、マクロライド系抗生物質であり、マイコプラズマに効果があります。
• マイコプラズマ肺炎の治療では、マクロライド系抗生物質が第一選択薬となります。
■解説2|
• アシクロビル錠: 抗ウイルス薬であり、ヘルペスウイルス感染症の治療に用いられます。
• イベルメクチン錠: 抗寄生虫薬であり、疥癬や糞線虫症の治療に用いられます。
• テビペネムピボキシル細粒: カルバペネム系抗生物質であり、グラム陽性菌やグラム陰性菌に幅広い抗菌スペクトルを有します。
• リネゾリド錠: オキサゾリジノン系抗生物質であり、MRSAなどの薬剤耐性菌に効果があります。
■科目|病態|問 109-067 ■正答| 3
我が国において、肝硬変の原因となるウイルス性肝炎として最も頻度が高いのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
A型肝炎
B型肝炎
C型肝炎
D型肝炎
E型肝炎
■■Copilot
病態|問 109-067 ■正答| 3
■論点 |我が国において、肝硬変の原因となるウイルス性肝炎として最も頻度が高いウイルス
この問題の論点は、我が国において、肝硬変の原因となるウイルス性肝炎として最も頻度が高いウイルスを特定することです。
■解説1| 我が国において、肝硬変の原因となるウイルス性肝炎として最も頻度が高いのはC型肝炎です。これは、C型肝炎ウイルス(HCV)に感染することで引き起こされ、慢性化すると肝炎、肝硬変、肝細胞がんを引き起こす可能性があります。
■解説2| 他の選択肢(A型肝炎、B型肝炎、D型肝炎、E型肝炎)も肝炎を引き起こすウイルスですが、我が国においてはC型肝炎が最も頻度が高いとされています。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-067
■論点 |日本における肝硬変の原因となるウイルス性肝炎
この問題の主な論点は、日本で肝硬変の原因となるウイルス性肝炎の中で最も頻度が高いものを特定することです。肝硬変は、肝臓の線維化が進行し、肝機能が低下する疾患であり、ウイルス性肝炎が主な原因の一つです。
■解説1|
我が国において、肝硬変の原因となるウイルス性肝炎として最も頻度が高いのは
3. C型肝炎 です。
• C型肝炎ウイルスは、血液を介して感染し、慢性肝炎を経て肝硬変や肝細胞癌を引き起こすことがあります。
• 日本では、C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎や肝硬変の患者が多く、対策が重要です。
■解説2|
• A型肝炎: 糞口感染によって広がり、急性肝炎を引き起こしますが、慢性化することはありません。
• B型肝炎: 血液や体液を介して感染し、慢性肝炎を経て肝硬変や肝細胞癌を引き起こすことがあります。
• D型肝炎: B型肝炎ウイルスに重複感染することで発症します。
• E型肝炎: 糞口感染によって広がり、急性肝炎を引き起こしますが、慢性化することはありません。
■科目|病態|問 106-068 ■正答| 2
甘草の副作用として注意すべき電解質異常はどれか。1つ選べ。
■選択肢
低カルシウム血症
低カリウム血症
低ナトリウム血症
低マグネシウム血症
低リン血症
■■Copilot
■科目|病態|問 106-068 ■正答| 2
■論点 |甘草の副作用として注意すべき電解質異常 この問題の論点は、甘草の副作用として注意すべき電解質異常を特定することです。
■解説1| 甘草にはグリチルリチンという成分が含まれており、これが体内で代謝されると鉱質コルチコイド様の作用を示し、尿中からカリウムが排泄されることが増えます。その結果、血中のカリウム濃度が低下し、低カリウム血症を引き起こす可能性があります。
■解説2|他の選択肢(低カルシウム血症、低ナトリウム血症、低マグネシウム血症、低リン血症)は、一般的に甘草の副作用としては報告されていません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-068
■論点 |甘草の副作用と電解質異常
この問題の主な論点は、甘草の副作用として注意すべき電解質異常を特定することです。甘草は、漢方薬や食品添加物などとして広く用いられていますが、副作用にも注意が必要です。
■解説1|
甘草の副作用として注意すべき電解質異常は
2. 低カリウム血症 です。
• 甘草に含まれるグリチルリチン酸は、アルドステロンと似た作用を持ち、腎臓でのナトリウムの再吸収とカリウムの排泄を促進します。
• そのため、甘草の過剰摂取により、低カリウム血症や高血圧、浮腫などが起こることがあります。
■解説2|
• 低カルシウム血症: カルシウムの不足により起こる電解質異常です。
• 低ナトリウム血症: ナトリウムの不足により起こる電解質異常です。
• 低マグネシウム血症: マグネシウムの不足により起こる電解質異常です。
• 低リン血症: リンの不足により起こる電解質異常です。
■科目|病態|問 107-068 ■正答| 3
組換え体医薬品でないのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
アルテプラーゼ
カルペリチド
ソラフェニブ
ニボルマブ
レノグラスチム
■■Copilot
■科目|病態|問 107-068 ■正答| 3
■論点 |組換え体医薬品でない薬物 この問題の論点は、組換え体医薬品でない薬物を特定することです。
■解説1| ソラフェニブは、組換え体医薬品ではなく、小分子の抗がん剤です。これは、複数のチロシンキナーゼを阻害することで、がん細胞の増殖を抑制し、血管新生を阻害します。
■解説2|他の選択肢(アルテプラーゼ、カルペリチド、ニボルマブ、レノグラスチム)は、組換え体医薬品で、遺伝子組換え技術を用いて生産されます。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-068
■論点 |組換え体医薬品の識別
この問題の主な論点は、選択肢の中から組換え体医薬品でないものを特定することです。組換え体医薬品は、遺伝子組換え技術を用いて製造される医薬品であり、近年開発が進んでいます。
■解説1|
組換え体医薬品でないのは
3. ソラフェニブ です。
• ソラフェニブは、低分子化合物であり、チロシンキナーゼ阻害薬として、腎細胞癌や肝細胞癌の治療に用いられます。
• 他の選択肢は、すべて遺伝子組換え技術を用いて製造されるタンパク質製剤です。
■解説2|
• アルテプラーゼ: 組換え体組織プラスミノーゲンアクチベーター(t-PA)であり、血栓溶解薬として用いられます。
• カルペリチド: 組換え体ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(hANP)であり、急性心不全の治療に用いられます。
• ニボルマブ: 抗PD-1抗体であり、免疫チェックポイント阻害薬として、様々な悪性腫瘍の治療に用いられます。
• レノグラスチム: 組換え体ヒト顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)であり、抗がん剤による骨髄抑制の改善に用いられます。
■科目|病態|問 108-068 ■正答| 3
脳梗塞後遺症で、興奮症状を伴う場合に用いられる漢方薬はどれか。1つ選べ。
■選択肢
葛根湯
大建中湯
抑肝散
五苓散
猪苓湯
■■Copilot
■科目|病態|問 108-068 ■正答| 3
■論点 |脳梗塞後遺症で、興奮症状を伴う場合に用いられる漢方薬 この問題の論点は、脳梗塞後遺症で、興奮症状を伴う場合に用いられる漢方薬を特定することです。
■解説1| 抑肝散は、肝気鬱滞型の症状(例えば、イライラや怒りっぽさなどの興奮症状)を改善するために用いられる漢方薬です。したがって、脳梗塞後遺症で興奮症状を伴う場合には、抑肝散が適応となります。
■解説2|他の選択肢(葛根湯、大建中湯、五苓散、猪苓湯)は、一般的に脳梗塞後遺症で興奮症状を伴う場合の主な治療薬ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-068
■論点 |脳梗塞後遺症の興奮症状に用いる漢方薬
この問題の主な論点は、脳梗塞後遺症で興奮症状を伴う場合に用いられる漢方薬を特定することです。漢方薬は、複数の生薬を組み合わせたものであり、様々な症状の治療に用いられます。
■解説1|
脳梗塞後遺症で、興奮症状を伴う場合に用いられる漢方薬は
3. 抑肝散 です。
• 抑肝散は、イライラや興奮、不眠などの症状を改善する作用があります。
• 脳梗塞後遺症で、興奮症状や情緒不安定がみられる場合に用いられます。
■解説2|
• 葛根湯: 風邪の初期症状や肩こり、頭痛などに用いられます。
• 大建中湯: 胃腸の働きを改善する作用があり、腹痛や下痢、食欲不振などに用いられます。
• 五苓散: 利尿作用があり、浮腫や頭痛、めまいなどに用いられます。
• 猪苓湯: 利尿作用があり、頻尿や排尿困難、残尿感などに用いられます。
■科目|病態|問 109-068 ■正答| 4
組換え体医薬品の生産プロセスに関する記述について、[ ]に入る適切な語句はどれか。1つ選べ。「目的遺伝子を挿入した発現ベクターを細胞に導入し、産生された[ ]を精製して、組換え体医薬品とする。」
■選択肢
DNA
RNA
ゲノム
タンパク質
脂質
■■Copilot
■科目|病態|問 109-068 ■正答| 4
■論点 |組換え体医薬品の生産プロセスに関する記述について、[ ]に入る適切な語句 この問題の論点は、組換え体医薬品の生産プロセスに関する記述について、[ ]に入る適切な語句を特定することです。
■解説1| 組換え体医薬品の生産プロセスでは、目的遺伝子を挿入した発現ベクターを細胞に導入し、その細胞が産生するタンパク質を精製して、組換え体医薬品とします。
■解説2|他の選択肢(DNA、RNA、ゲノム、脂質)は、一般的に組換え体医薬品の生産プロセスにおいて、細胞が産生する主要な成分ではありません。 user ゴール 各問題について、以下の出力形式で解説を生成してください。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-068
■論点 |組換え体医薬品の生産プロセス
この問題の主な論点は、組換え体医薬品の生産プロセスにおける適切な語句を特定することです。組換え体医薬品は、遺伝子組換え技術を用いて製造される医薬品であり、特定のタンパク質を生産するプロセスが必要です。
■解説1|
組換え体医薬品の生産プロセスに関する記述について、[ ]に入る適切な語句は
4. タンパク質 です。
• 組換え体医薬品の生産プロセスでは、目的のタンパク質をコードする遺伝子をベクターに組み込み、細胞に導入します。
• 細胞内で目的のタンパク質が産生され、それを精製することで組換え体医薬品となります。
■解説2|
• DNA: 遺伝情報を担う物質であり、タンパク質の設計図となります。
• RNA: DNAから転写された遺伝情報であり、タンパク質合成の鋳型となります。
• ゲノム: 生物のもつすべての遺伝情報の総体です。
• 脂質: 細胞膜の構成成分やエネルギー源となる物質です。
■科目|病態|問 106-069 ■正答| 2
図中のアに入る語句はどれか。1つ選べ。
■選択肢
COCHRANE LIBRARY
DRUG SAFETY UPDATE
INTERVIEW FORM
PHYSICIANSʼ DESK REFERENCE
RISK MANAGEMENT PLAN
・106_169

■■Copilot
病態|問 106-069 ■正答| 2
■論点 |図中のアに入る語句
この問題の論点は、図中のアに入る適切な語句を特定することです。
■解説1|
図中のアに最も適切な語句は「DRUG SAFETY UPDATE」です。これは医薬品の安全性に関する最新情報を提供する文書であり、医療専門家が治療において安全な判断を下すために重要な情報源となります。
■解説2|
他の選択肢である「COCHRANE LIBRARY」は医学的な系統的レビューを提供するデータベース、「INTERVIEW FORM」は患者のインタビューに使用されるフォーム、「PHYSICIANSʼ DESK REFERENCE」は医薬品の情報を提供する参考書、「RISK MANAGEMENT PLAN」は医薬品のリスク管理計画を指します。これらは図中のコンテキストには合致しないため、選択肢2が最も適切です。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-069
■論点 |医薬品安全性情報の入手方法
この問題の主な論点は、図中の安全性情報に関する情報源を特定することです。医薬品の安全性情報は、様々な情報源から入手できます。
■解説1|
図中のアに入る語句は
2. DRUG SAFETY UPDATE です。
• DRUG SAFETY UPDATE(医薬品安全対策情報)は、厚生労働省が発行する医薬品安全性情報誌であり、医薬品の副作用情報や安全対策に関する情報が掲載されています。
• 医療関係者や一般向けに情報提供を行っています。
■解説2|
• COCHRANE LIBRARY: 系統的レビューやメタアナリシスなどのエビデンスを収集したデータベースです。
• INTERVIEW FORM: 医薬品インタビューフォームは、医薬品の安全性や有効性に関する情報を収集するために、製薬企業が医療関係者に対して行うインタビューの記録です。
• PHYSICIANSʼ DESK REFERENCE: 米国で発行されている医薬品情報源であり、医薬品の添付文書などが掲載されています。
• RISK MANAGEMENT PLAN: 医薬品リスク管理計画は、医薬品の副作用を最小限に抑えるために、製薬企業が作成する計画です。
■科目|病態|問 107-069 ■正答| 4
厚生労働省が発行する資料はどれか。1つ選べ。
■選択肢
医療用医薬品添付文書
医薬品インタビューフォーム
医薬品リスク管理計画
医薬品・医療機器等安全性情報
くすりのしおり
■■Copilot
■科目|病態|問 107-069 ■正答| 4
■論点 |厚生労働省が発行する資料 この問題の論点は、厚生労働省が発行する資料を特定することです。
■解説1| 「医薬品・医療機器等安全性情報」は、厚生労働省が発行する資料です。これは、医薬品や医療機器の安全性に関する最新情報を提供するためのもので、医療関係者や一般の人々に向けて発行されます。
■解説2|他の選択肢(医療用医薬品添付文書、医薬品インタビューフォーム、医薬品リスク管理計画、くすりのしおり)も医薬品に関する情報を提供する資料ですが、これらは一般的に製薬会社や他の組織によって作成・発行されます。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-069
■論点 |厚生労働省発行の医薬品情報資料
この問題の主な論点は、選択肢の中から厚生労働省が発行する資料を特定することです。厚生労働省は、医薬品の安全性や有効性に関する情報を提供しています。
■解説1|
厚生労働省が発行する資料は
4. 医薬品・医療機器等安全性情報 です。
• 医薬品・医療機器等安全性情報は、厚生労働省が発行する安全性情報誌であり、医薬品の副作用情報や安全対策に関する情報が掲載されています。
• 医療関係者や一般向けに情報提供を行っています。
■解説2|
• 医療用医薬品添付文書: 製薬企業が作成する医薬品情報資料であり、医薬品の用法・用量、効能・効果、副作用などに関する情報が記載されています。
• 医薬品インタビューフォーム: 製薬企業が医療関係者に対して行うインタビューの記録です。
• 医薬品リスク管理計画: 製薬企業が作成する医薬品の副作用を最小限に抑えるための計画です。
• くすりのしおり: 一般向けの医薬品情報誌であり、医薬品の用法・用量、効能・効果、副作用などに関する情報がわかりやすく解説されています。
■科目|病態|問 108-069 ■正答| 4
医療用医薬品の「使用上の注意」改訂を取りまとめた医薬品情報源はどれか。1つ選べ。
■選択肢
医薬品リスク管理計画(RMP)
重篤副作用疾患別対応マニュアル
緊急安全性情報
医薬品安全対策情報(DSU)
医療用医薬品製品情報概要
■■Copilot
■科目|病態|問 108-069 ■正答| 4
■論点 |医療用医薬品の「使用上の注意」改訂を取りまとめた医薬品情報源 この問題の論点は、医療用医薬品の「使用上の注意」改訂を取りまとめた医薬品情報源を特定することです。 ■解説1| 「医薬品安全対策情報(DSU)」は、医療用医薬品の「使用上の注意」改訂を取りまとめた医薬品情報源です。これは、医薬品の安全性に関する最新情報を提供し、医療関係者が適切な治療判断を下すための重要な情報源となります。
■解説2|他の選択肢(医薬品リスク管理計画(RMP)、重篤副作用疾患別対応マニュアル、緊急安全性情報、医療用医薬品製品情報概要)も医薬品に関する情報を提供する資料ですが、これらは「使用上の注意」改訂を取りまとめる主な情報源ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-069
■論点 |「使用上の注意」改訂の情報源
この問題の主な論点は、医療用医薬品の「使用上の注意」の改訂を取りまとめた医薬品情報源を特定することです。「使用上の注意」は、医薬品の適正使用のために重要な情報源です。
■解説1|
医療用医薬品の「使用上の注意」改訂を取りまとめた医薬品情報源は
4. 医薬品安全対策情報(DSU) です。
• DSUは、厚生労働省が発行する安全性情報誌であり、医薬品の副作用情報や安全対策に関する情報が掲載されています。
• 「使用上の注意」の改訂情報もDSUに掲載され、医療関係者への情報提供が行われます。
■解説2|
• 医薬品リスク管理計画(RMP): 製薬企業が作成する医薬品の副作用を最小限に抑えるための計画です。
• 重篤副作用疾患別対応マニュアル: 厚生労働省が作成するマニュアルであり、重篤な副作用が発生した場合の対応方法が記載されています。
• 緊急安全性情報: 製薬企業が緊急に情報提供を行う必要がある場合に発行される安全性情報です。
• 医療用医薬品製品情報概要: 製薬企業が作成する医薬品情報資料であり、医療関係者向けに医薬品の概要を説明しています。
■科目|病態|問 109-069 ■正答| 4
下図の1~5は、既存薬Xを対照とした新薬Yの非劣性を検討した5つの臨床試験の結果について、両群の差の95%信頼区間を示したものである。あらかじめ設定された非劣性マージンが-Δのとき、両側5%水準で非劣性が結論づけられるのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
1
2
3
4
5
・109_169

■■Copilot
病態|問 109-069 ■正答| 4
■論点 |新薬Yの非劣性評価
この問題の論点は、新薬Yが既存薬Xに対して非劣性であるかを評価することです。
■解説1|
非劣性試験では、新薬Yの効果が既存薬Xよりも劣っていないことを示す必要があります。非劣性マージン-Δより右側に95%信頼区間がある場合、新薬Yは非劣性であると結論づけられます。選択肢4の臨床試験結果は、この条件を満たしています。
■解説2|
他の選択肢(1, 2, 3, 5)の臨床試験結果は、95%信頼区間が非劣性マージン-Δを含んでいるか、または左側にあるため、非劣性が結論づけられません。したがって、正答は選択肢4です。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-069
■論点 |非劣性試験の結果の解釈
この問題の主な論点は、非劣性試験の結果を解釈し、非劣性が結論づけられる試験を特定することです。非劣性試験は、新薬が既存薬に劣っていないことを示すことを目的とした臨床試験です。
■解説1|
あらかじめ設定された非劣性マージンが-Δのとき、両側5%水準で非劣性が結論づけられるのは
4. 4 です。
• 非劣性試験では、新薬と既存薬の治療効果の差が、あらかじめ設定された非劣性マージン以内であれば、新薬は既存薬に劣っていないと判断されます。
• 図4では、95%信頼区間の上限が-Δよりも小さいことから、新薬Yは既存薬Xに対して非劣性であると結論づけられます。
■解説2|
• 図1、2、3、5では、95%信頼区間が-Δを超えているため、非劣性を示すことができません。
• これは、新薬Yが既存薬Xよりも劣っている可能性があることを示唆しています。
■科目|病態|問 106-070 ■正答| 2
パラメトリック法に分類される仮説検定法はどれか。1つ選べ。
■選択肢
Mann-Whitney のU検定
t検定
カイ二乗検定
フィッシャーの直接確率検定
ログランク検定
■■Copilot
■科目|病態|問 106-070 ■正答| 2
■論点 |パラメトリック法に分類される仮説検定法 この問題の論点は、パラメトリック法に分類される仮説検定法を特定することです。
■解説1| パラメトリック法は、データが特定の確率分布(例えば正規分布)に従うという仮定のもとで行われる統計的手法です。t検定は、このパラメトリック法に分類されます。t検定は、2つの群の平均値が統計的に異なるかどうかを判断するために使用されます。
■解説2|他の選択肢(Mann-Whitney のU検定、カイ二乗検定、フィッシャーの直接確率検定、ログランク検定)は、非パラメトリック法に分類されます。これらの手法は、データが特定の確率分布に従うという仮定を必要とせず、順位や頻度などの情報に基づいて統計的な判断を行います。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 106-070
■論点 |パラメトリック法とノンパラメトリック法
この問題の主な論点は、仮説検定法をパラメトリック法とノンパラメトリック法に分類し、パラメトリック法に属するものを特定することです。
■解説1|
パラメトリック法に分類される仮説検定法は
2. t検定 です。
• パラメトリック法は、データが正規分布に従うことを前提とした仮説検定法であり、t検定はその代表的なものです。
• t検定は、2群の平均値を比較する際に用いられます。
■解説2|
• Mann-Whitney のU検定: ノンパラメトリック法であり、2群の中央値を比較する際に用いられます。
• カイ二乗検定: ノンパラメトリック法であり、2つのカテゴリカル変数の関連を調べる際に用いられます。
• フィッシャーの直接確率検定: ノンパラメトリック法であり、2×2分割表のデータに対して用いられます。
• ログランク検定: ノンパラメトリック法であり、2群の生存期間を比較する際に用いられます。
■科目|病態|問 107-070 ■正答| 3
被験者100人について、ある臨床検査値Xを調べた時のヒストグラムが以下のようになった。同じデータに基づいて作成した箱ひげ図として、妥当なのはどれか。1つ選べ。
■選択肢
1
2
3
4
5
・107_170

■■Copilot
■科目|病態|問 107-070 ■正答| 3
■論点 |臨床検査値Xのヒストグラムに対応する箱ひげ図 この問題の論点は、臨床検査値Xのヒストグラムから、それに対応する妥当な箱ひげ図を特定することです。
■解説1|
データの分布: ヒストグラムはデータがどのように分布しているかを示します。この場合、データは中央付近に集中しており、両端に向かって減少しています。
箱ひげ図の特徴: 箱ひげ図は中央値、四分位数、外れ値を視覚的に表現します。選択肢3の箱ひげ図は、中央値がデータの中心に位置し、四分位範囲がデータの集中度を示しています。
■解説2|
選択肢3の妥当性: 選択肢3の箱ひげ図は、中央値がヒストグラムの最も高いバーに対応し、四分位範囲がデータの主要な集中範囲をカバーしています。また、外れ値の表示もヒストグラムのデータ分布と一致しています。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 107-070
■論点 |ヒストグラムと箱ひげ図の関係
この問題の主な論点は、ヒストグラムから箱ひげ図を作成する方法を理解し、妥当な箱ひげ図を特定することです。
■解説1|
同じデータに基づいて作成した箱ひげ図として、妥当なのは
3. 3 です。
• 箱ひげ図は、データの分布を視覚的に表現するものであり、最大値、最小値、四分位数などを示します。
• ヒストグラムから箱ひげ図を作成する際には、データの分布や外れ値などを考慮する必要があります。
• 選択肢3の箱ひげ図は、ヒストグラムの分布と一致しており、外れ値も適切に表現されています。
■解説2|
• 選択肢1、2、4、5の箱ひげ図は、ヒストグラムの分布と一致していなかったり、外れ値の表現が不適切であったりします。
■科目|病態|問 108-070 ■正答| 4
全身状態の指標であるパフォーマンスステータス(PS)の値を統計処理する際の、データ尺度はどれか。1つ選べ。
■選択肢
分類尺度
間隔尺度
名義尺度
順序尺度
比例尺度
■■Copilot
病態|問 108-070 ■正答| 4
■論点 |パフォーマンスステータス(PS)の値のデータ尺度
この問題の論点は、パフォーマンスステータス(PS)の値を統計処理する際のデータ尺度を特定することです。
■解説1|
パフォーマンスステータス(PS)は、患者の全身状態を評価するための指標で、活動能力や自立性を数値化したものです。PSの値は順序を持つカテゴリーであり、その間には等間隔が存在しないため、これらの値は順序尺度に分類されます。
■解説2|
他の選択肢(分類尺度、間隔尺度、名義尺度、比例尺度)は、PSの値の特性とは一致しません。例えば、分類尺度や名義尺度は順序関係を持たず、間隔尺度や比例尺度は等間隔の数値を持つ特性を示します。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 108-070
■論点 |パフォーマンスステータスのデータ尺度
この問題の主な論点は、パフォーマンスステータス(PS)の値を統計処理する際のデータ尺度を特定することです。PSは、患者の全身状態を評価する指標です。
■解説1|
全身状態の指標であるパフォーマンスステータス(PS)の値を統計処理する際の、データ尺度は
4. 順序尺度 です。
• 順序尺度は、データの大小関係はわかるが、その差の大きさはわからない尺度です。
• PSは、0から5までの段階で評価され、数字が大きいほど全身状態が悪いことを示しますが、それぞれの段階の差は等間隔ではありません。
■解説2|
• 分類尺度: データをいくつかのカテゴリーに分類する尺度です。
• 間隔尺度: データの大小関係や差の大きさはわかるが、絶対零点がない尺度です。
• 名義尺度: データを名前で区別する尺度です。
• 比例尺度: データの大小関係、差の大きさ、絶対零点がわかる尺度です。
■科目|病態|問 109-070 ■正答| 3
コンパニオン診断(医薬品の適応判定を目的とした体外診断)のうち、生殖細胞系列遺伝子に対する検査項目はどれか。1つ選べ。
■選択肢
ALK融合遺伝子
BRAF遺伝子変異
BRCA1/2遺伝子変異
EGFR遺伝子変異
KRAS遺伝子変異
■■Copilot
病態|問 109-070 ■正答| 3
■論点 |生殖細胞系列遺伝子に対するコンパニオン診断の検査項目
この問題の論点は、生殖細胞系列遺伝子に対するコンパニオン診断の検査項目を特定することです。
■解説1|
コンパニオン診断は、特定の医薬品の適応判定を目的とした体外診断で、患者が特定の治療に反応する可能性を予測します。BRCA1/2遺伝子変異は、生殖細胞系列遺伝子の一つで、特定のがん(例えば乳がんや卵巣がん)のリスクを高めることが知られています。
■解説2|
他の選択肢(ALK融合遺伝子、BRAF遺伝子変異、EGFR遺伝子変異、KRAS遺伝子変異)も重要な遺伝子変異であり、特定のがんの発症や治療反応性と関連していますが、これらは一般的に体細胞の変異であり、生殖細胞系列遺伝子ではありません。
■■Gemini 1.5 Pro
病態|問 109-070
■論点 |生殖細胞系列遺伝子に対するコンパニオン診断
この問題の主な論点は、コンパニオン診断(医薬品の適応判定を目的とした体外診断)のうち、生殖細胞系列遺伝子に対する検査項目を特定することです。
■解説1|
コンパニオン診断のうち、生殖細胞系列遺伝子に対する検査項目は
3. BRCA1/2遺伝子変異 です。
• BRCA1/2遺伝子は、DNA修復に関与する遺伝子であり、その変異は乳癌や卵巣癌のリスクを高めます。
• BRCA1/2遺伝子変異の検査は、PARP阻害薬などの抗がん剤の適応判定に用いられます。
■解説2|
• ALK融合遺伝子、BRAF遺伝子変異、EGFR遺伝子変異、KRAS遺伝子変異: これらは、体細胞遺伝子変異であり、がん細胞で獲得された遺伝子変異です。
• これらの遺伝子変異の検査は、分子標的薬の適応判定に用いられます。
これらの解説は、病態学の基本的な概念に基づいており、特定の薬剤の作用機序や臨床応用に関する一般的な情報を提供するものです。もし更に詳細な情報が必要な場合は、専門の文献や資料を参照してください。
病態の場合、オリジナルの公的な科学的根拠は添付文書です。
下記から検索できます。PDFよりはHTMLで見るほうが軽いです。
時間があれば、読み込んでおくと応用力がつきます。(滝沢)
PMDA|医療用医薬品 情報検索
このコンテンツの制作者|
滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD
■Facebook プロフィール
https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa
■X (Former Twitter) プロフィール
https://twitter.com/YukihoTakizawa
CONTACT|
mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)
tel: 029-872-9676
参考資料|
厚生労働省ホームページ / 薬剤師国家試験のページ
薬剤師国家試験のページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
過去の試験問題及び解答|
第109回(令和6年2月17日、2月18日実施)
第108回(令和5年2月18日、2月19日実施)
第107回(令和4年2月19日、2月20日実施)
第106回(令和3年2月20日、2月21日実施)
第105回(令和2年2月22日、23日実施)
第104回(平成31年2月23、2月24日実施)
第103回(平成30年2月24、2月25日実施)
第102回(平成29年2月25、2月26日実施)
第101回(平成28年2月27、2月28日実施)
第100回(平成27年2月28、3月1日実施)
第99回(平成26年3月1、2日実施)
第98回(平成25年3月2、3日実施)
第97回(平成24年3月3、4日実施)
過去の薬剤師国家試験の結果|
第109回(令和6年2月17日、18日実施)[PDF形式:2,589KB][2.6MB]
第108回(令和5年2月18日、19日実施)[PDF形式:471KB][471KB]
第107回(令和4年2月19日、20日実施)[PDF形式:803KB][803KB]
第106回(令和3年2月20日、21日実施)[PDF形式:871KB][871KB]
第105回(令和2年2月22日、23日実施)[PDF形式:371KB][371KB]
第104回(平成31年2月23、2月24日実施)[PDF形式:620KB][620KB]
第103回(平成30年2月24、2月25日実施)[PDF形式:457KB]
第102回(平成29年2月25、2月26日実施)[PDF形式:564KB]
第101回(平成28年2月27、2月28日実施)[PDF形式:796KB]
第100回(平成27年2月28、3月1日実施)[PDF形式:2,005KB]
第99回(平成26年3月1、2日実施)[PDF形式:1,116KB]
第98回(平成25年3月2、3日実施)[PDF形式:634KB]
第97回(平成24年3月3、4日実施)[PDF形式:285KB]
いかがでしたか?前回の4年前の集計と比較して、文章での解説を省略して、グラフだけで見せるアプローチにしてみました。
薬学生の皆さんは、ぜひ、グラフから分析と考察に挑戦してみてください。
今日はこの辺で、
それではまた
お会いしましょう。
Your best friend
Mats & BLNt
よろしければ、こちらもどうぞ
matsunoya|note
マガジンをお気に入りに登録してください!
薬剤師国家試験対策ノートはここでしか手に入らないe-ラーニング教材と学習空間。ワンストップでお届けいたします。
薬剤師国家試験対策ノート on note|matsunoya|note
お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!
|
This magazine "PROMPTS! PROMPTS!" features Matsunoya's unique perspective on prompt input to generation AI and content of output results.
PROMPS! PROMPTS!|matsunoya|note
Here;
ここから先は
¥ 700
医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya
