
音楽家の腕の痺れ〜胸郭出口症候群〜
今回は音楽家においてしばしば症状訴えが聞かれる腕の痺れについて書いていきたいと思います。
腕の痺れで病院に行くと「首から来てますね」と言われ「頸椎症性神経根症」のような難しい診断名がつくことがよくあります。医師が診断するのは画像所見であり、神経の通り道が画像上狭くなっていればそれは確定事実となり診断名がつきます。
それに対して今回お話しする「胸郭出口症候群」というのはあくまで“症候群”であり画像に写ることはないため確定診断することが難しく、所見から診断するしかありません。
なので今回の記事は医師の診断を否定するものではなく、あくまでたくさんある症状の1つと思って読み進めていただければと思います。
また、この疾患は原因に対してしっかり対応しなければなかなか治らない厄介な疾患です。腕の痺れがある方で病院で治療を受けたのになかなか治らないという方がいれば、この記事を読んで「もしかしたら」と疑うきっかけになればと思います。
胸郭出口症候群とは
簡単に言うと胸郭(肋骨などで構成される部分)の(神経の)出口に症状が出現する病気です。
腕の神経は頸椎という背骨の首の部分から腕に伸びていき指先まで支配します。この神経が腕の方に向かう過程のどこかで圧迫されたり牽引(引っ張られたり)されたりすることでストレスがかかり痺れや痛みなどの症状が出現します。
症状
主に腕から指先にかけての痺れが主症状となります。痺れの他にも痛みや血が止まる感じといった症状を訴える方もいます。
症状の多くは、朝は比較的楽ですが、音楽家で言えば練習中や練習後に強くなるということが多いようです。これは胸郭出口症候群の原因が影響します。
原因は?
神経や動脈の圧迫
首から腕にかけて神経や血管が走っていますが、その通り道を「胸郭出口」と呼びます。
この胸郭出口にはいくつか狭窄部位(狭くなっている場所)があり神経や動脈などが圧迫されやすい構造になっています。
斜角筋と呼ばれる首の筋肉の間
鎖骨と肋骨の間
小胸筋と呼ばれる胸の深いとことにある筋肉と肩甲骨で構成される部分
狭窄部位は主にこの3つとされ、それぞれ「斜角筋症候群」「肋鎖症候群」「小胸筋症候群」と呼ばれこれらを総称して「胸郭出口症候群」と呼びます。

頚肋
頚肋とは肋骨の名残のようなもので、先天的に存在する人がいます。この頚肋が存在すると上記にあげた狭窄部位での圧迫がより生じやすくなるとされています。
肩甲骨周りの機能低下(筋力低下)
厳密に言えば胸郭出口ではありませんが、同様の症状としてはこれが一番多いと言っても良いでしょう。
首には重要な神経や血管が通っており、胸郭出口から腕にかけてその神経や血管が走っています。
この神経は時に牽引(引っ張られる)ストレスにより痺れを誘発します。その牽引ストレスの原因となるのが肩甲骨が下がってしまうことです。特に元々「なで肩」という方は注意が必要です。
この症状は10代や20代の頃と比べて30代を過ぎた人に多く発症すると言われています。
学生を卒業した社会人の多くは運動不足を自覚しています。それが知らず知らずのうちに肩甲骨周りの筋力低下を引き起こし、徐々に肩が下がって来ていることに気づかないのです。そしてその状態で重たい楽器等を持ち続けることなどで肩が下がり徐々に神経に牽引ストレスが生じさせた結果、痺れとして症状が出て来てしまいます。
もちろん10代や20代でも筋力が不十分な方は発症するリスクはありますのでご注意ください。
なで肩や猫背(姿勢不良)
姿勢が悪いと良くない、というのは誰もが知ってると思いますが、この胸郭出口症候群においてはそれが顕著に現れます。
いわゆる猫背と呼ばれる姿勢は胸椎という肩甲骨の間に位置する背骨(脊柱)が曲がっている姿勢です。そのような姿勢になることで肩甲骨は外に広がりいわゆる「巻き肩」になります。

特に音楽家の演奏姿勢は管楽器などでは顕著にその姿勢不良が生じます。

肩甲骨が巻くことで肩は前に突出し、姿勢のバランスをとるために頭も前に突出します。そうして斜角筋症候群や小胸筋症候群の原因となる斜角筋や小胸筋が短縮し縮こまり硬くなることでより神経や動脈を圧迫しやすくなるのです。
治療方法
保存療法
まずは保存療法で対応する場合がほとんどでしょう。
基本的に姿勢不良や、肩甲骨周りの機能低下が原因で生じる場合が多いため、リハビリテーションによって肩甲骨周囲の筋力強化や姿勢指導などが有効となります。
具体的には前鋸筋と言った肩甲骨を安定させる作用を持つ筋力を鍛えることに重点を置き、合わせて体幹機能にもアプローチします。

音楽家はその特異性から姿勢をいきなり変えることは難しいかもしれません。そういう場合は練習の合間でストレッチなど縮こまりやすい筋を伸ばすといったセルフケアを行うことも多いに効果を発揮します。
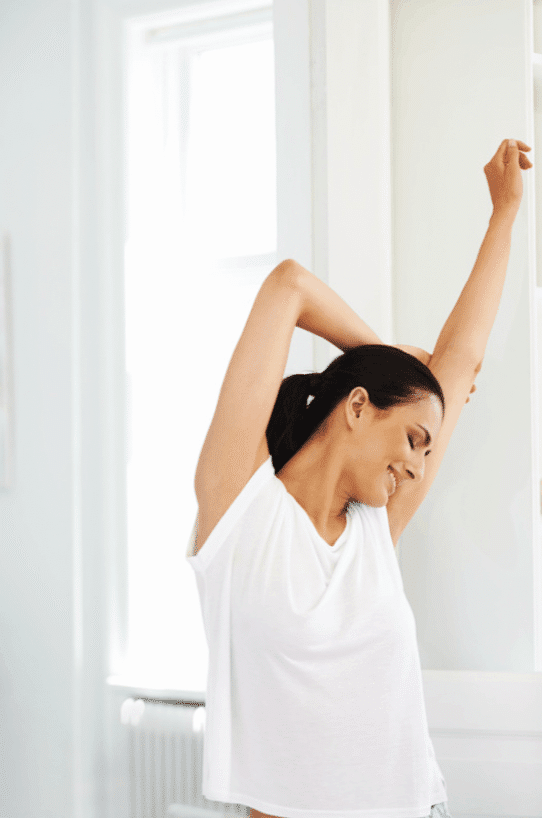
音楽活動以外でもデスクワークなど仕事柄姿勢が崩れやすい人などは、仕事中の環境を整える(ディスプレイや椅子の高さを調整する)ことも有効となります。
まずは自分で姿勢がいかに崩れているかを認識し、それを治そうという意識が必要となります。
手術療法
上記の原因であげた頚肋などがある場合、姿勢や機能改善だけでは症状が警戒しあい場合があります。まずは保存療法で対応し改善が見られなければ頚肋を除去す手術療法を検討します。
まとめ
手に痺れが出たらやっぱり不安になると思います。
特に音楽家は練習を休むわけにもいかず痺れや痛みに格闘しながら日々の練習を行っている方も少なくありません。
この胸郭出口症候群は炎症による痛みとは違います。そのため安静をとる必要は全くありません。むしろ必要のない安静により更なる機能低下を生み、症状の悪化に繋がることもあります。
原因をしっかり把握して適切な治療をすればほとんどの方が症状改善しますので心配せずにまずは専門家に相談してみてください。
本日は「音楽家の腕の痺れ〜胸郭出口症候〜」についての記事でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
