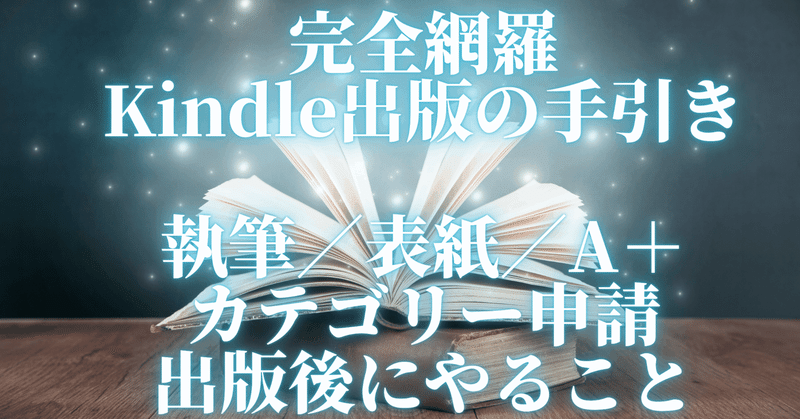
【完全網羅】20冊以上リリースした作家が実際にやっているKindle出版の手引き
みなさんこんにちは。
Kindle作家のミツです。
去年1月からコミットし始めたKindle出版も
20冊を超えました。
うまくいった本もあれば失敗した本もあり
いろいろな経験をしてきました。
出版するまでにやることもかなり増えました。
増える?
いやいや本なんて原稿書いて出版すればいいんでしょ?
そう思う方もいらっしゃいますよね。
その通りです。
確かに1年前はそんな感じでした。
ぼくも表紙は外注していましたけど、
基本的な作業は『原稿を書いて出版する 以上!』でした。
でもこの1年でKindle出版の世界は大きく変わりました。
原稿を書いて終わり
・・・というフェーズは終わったのです。
ならばどんなことをどんな手順でやればいいのか?
これまで21冊書いてきたぼくが
実際にやっている手順を全てお教えします。
原稿を書く
当たり前ですが
これをやらないと本になりません。
Kindle本に適した文章量は、1万5000字〜2万字ぐらい。
これがデビュー作という方は
このぐらいの範囲に収めた方が良いです。
なぜなら長いと最後まで読んでもらえる確率が下がり
レビューがつくスピードが落ちるからです。
Kindle界隈で無名作家さんの1冊目が
いきなり5万字とか10万字とかあってもキビシイ・・・
悲しいかな、これが現実です。
ただでさえ、いまは『文字離れ』が進んでいます。
くれぐれも1冊目は、
30分ぐらいで読者がスカッと読める文章量に抑えてくださいね。
かといって1万字未満だと短すぎて
読者が物足りなく感じてしまいます。
最低でも1万字は超えたいところです。
モニターをお願いする
コストゼロでめちゃくちゃオススメなのがこれです。
ぼくも、最近はずっと実践してます。
ようは第一稿を、
他の作家さんに試し読みしていただき、
感想や意見をもらうんです。
この方法は、19冊目のKindle本に書いたところ
ぼくの周りでも取り入れる作家さんが増えました。
そんなことして意味あるの?
なんて思うかもしれませんが、
はっきり言って、いいことしかありません。
▽自分の原稿を客観的にみてもらえる。
強すぎる表現、わかりづらい箇所、独りよがりな文章
すべて指摘してもらえます。
▽誤字も見つけてくれます。
人によってはわざわざスクショを撮って誤字を
指摘してくれます。校正も大助かり!
▽出版後は応援してくれます。
Kindle作家は基本、ギブ精神にあふれた方が多いです。
出版後は、拡散を手伝ってくれます。
▽レビューを書いてもらえるかも!?
100%とは限りませんが、レビューを書いてもらえる可能性はあります。
自分が関わった本にレビューを書くと、
内輪感が出ることを懸念して、敢えて書かない作家さんもいますが、
それでも、星はつけてくれます。
モニター依頼するときの注意点
全力で書いた原稿をモニターしてもらいましょう。
いまいち自信がないから
モニターしてもらうことで、
本の箔付け(はくづけ)や拡散を狙うのはやめましょう。
それはあなたの信頼も失うし、
モニターを引き受けてくれた相手にも迷惑をかけます。
「自分の全力は尽くした!」
その上で、アドバイスが欲しい、客観的な意見が欲しい、
・・・という感覚でモニターはお願いするようにしてくださいね。
だから未完成の原稿は
送らない方がいいでしょう。
モニターする方も困ってしまいます。
それと、モニターは、出版サポートとは違います。
KDPについての基礎知識、
原稿をアップロードする方法などは自分で調べましょう。
この辺りの情報は、ネットやKindle本を読めば分かりますから。
※KDP・・・Kindle Direct Publishing
(キンドル・ダイレクト・パブリッシング)は
AmazonのKindleストアで本を出版し、販売するためのサービス。
Kindle作家の間では『KDP』と略されることが多い。
表紙を作る
原稿と並行してやるのが『表紙作り』です。
作り方は2つ。
▽自分で作る
▽外注する
ぼくは、これまで3冊ほど表紙を自作しました。
メリットは『コスト』と『時間』です。
自作するのでお金はかかりません。
締切りだって自分が頑張るだけなので
作ろうと思えば、1日で作ることもできます。
さらに自由に要素をプラスできます。
例えば、
出版後、ベストセラーやカテゴリー10冠を達成したら
それを本の帯に加えることができるんです。
これは書店で並んでいる商業本でもやりますよね。
「直木賞候補作!」とか
「芥川賞 受賞作!」とか。
あれと同じことが自分の本でサクッとできます。
あとから実績を表紙にも反映できるってことです。
外注だと別料金がかかります。
ぼくはまだ依頼したことがないのですが、
おそらく1000〜2000円ぐらいはかかるかと。
デメリットは『クオリティ』ですね。
今は、表紙作りに特化したBrain教材があったりして
以前と比べると、
かなりクオリティの高い表紙が作れるようになりました。
それでもプロの仕事にはかなわないなと思うことが多いです。
だからぼくは21冊をリリースした今でも
表紙は外注でお願いしています。
(今後は自作にも挑戦しようとは思ってますけどね)
・・・ということで
ここからは『表紙の外注』について書きます。
外注のメリットは
繰り返しますが『プロのクオリティ』です。
自分では絶対に作れないような表紙を作ってくれます。
デメリットは『コスト』と『時間』ですね。
自作でのメリットがキレイに180度ひっくり返ります。
まずコスト。
プロにお願いするので当然お金がかかります。
大体、3000〜5000円ぐらいが多いですね。
中には1万円以上かかるデザイナーさんもいます。
続いて時間。
人にお願いするわけですから
自分の都合だけで締め切りは決められません。
人気のデザイナーさんは同時に複数の案件を抱えています。
だから最初に、あなたが希望する締切日を伝えましょう。
(常識の範囲内で伝えましょうね。
今日頼んで明日あげて!とか絶対に無理ですからね!)
6月上旬ぐらいに出版したいので、
そこに間に合うようにお願いしたいです。
・・・という感じですね。
最低でも1週間、
できたら2週間ぐらい余裕があると良いです。
タイトルを早めに決めて
原稿が書き上がる頃に表紙が完成するように
逆算して作業を進めてください。
ぼくがすすめる表紙デザイナー
Kindle界隈で
お世話になっている作家も多いデザイナーさん。
それが、みっつさんです!
こちらはみっつさんのTwitterです。
気になる方は、コンタクトを取ってみて下さい!
ぼくの代表作となった
『今さら病を治すウサギ』の表紙はみっつさん作です。

表紙と合わせてA+を作る
表紙と合わせて作りたいのがA+(エープラス)です。
この部分のことですね。



※このA+も、先ほど紹介したみっつさん作です。
ちょっと前だとみんな過去のKindle本を
並べておくぐらいしか活用していませんでした。
ですが、今では多くの作家さんが、
その本のPRポイントをまとめた画像を1〜3枚置いています。
確実にランキングが上がるとは言い切れませんが
ぱっと見で本の魅力が分かるので効果は大きいと
実感しています。
こちらも自作するか外注になります。
内容的には
①『その本を読むとどうなるのか?』
②『どんな人に読んで欲しいのか?』
③『○○なレビューが続々!』
(リリースしてレビューが集まったら)
①と②を最初に自作or外注して作っておき、
③はレビューが集まった時点で良いものを選んで
A+に反映させます。
モニター戦略をやっておくと
リリースして数日で、
3〜5個ぐらいはレビューが頂けると思います。
A+についてはこちらのKindle本で
めっちゃわかりやすく解説されているのでオススメです。
なお、作者のあゆさんは
Kindle本の表紙クリエーターとしても実績がある方です。
気になる方は、
Twitterからコンタクトを取ってみてください。
ぼくはまだ依頼したことがないのですが、
今後はお願いしようとひそかに思ってます。
デザイナーさんに丸投げはNGです
これは表紙でもA+でも言えることです。
「プロなんだから、タイトルだけ伝えれば
あとはいい感じに仕上げてくれるっしょ!」
・・・という考えはやめた方がイイです。
どんなにつたなくても
あなたのイメージはしっかり伝えましょう。
好きな表紙やA+があったら、
スクショで撮ってデザイナーさんに送るのも良いです。
丸投げではなく
一緒に良いモノを作っていく気持ちが大事です。
互いにイメージをすり合わせて
良い表紙、良いA+を作ってくださいませ!
表紙が仕上がったらプロダクトローンチ
プロダクトローンチとは
発売に合わせて情報を小出しで発信していくことで、
少しずつお客さんの期待を高めていくマーケティング手法です。
Twitterで『次回作の表紙が上がってきました!』と言って
途中経過を報告して、フォロワーさんの期待を高めましょう。
デザイナーさんの了解を取った上で
『A案とB案で迷っています。
どっちがいいですか?』
・・・という風に、アンケートを取るのも手です。
一人でも多くの人に、
あなたのKindle本に興味を持ってもらい
まわりをうまく巻き込んでいってください。
早めのプロダクトローンチ
このプロダクトローンチを
本の執筆前から展開する作家さんもいて、賢いやり方です。
次回作が『積み立てNISA』だとしたら
普段のツイートの中に、
ちょっと多めに積み立てNISAの情報を入れていきます。
まわりの人に
「積み立てNISAって大事なんだ」とすりこんだ所で
「実はいまKindle本を書き始めました。
来月リリースする予定なのでお楽しみに~」と発信。
こんなやり方も効果的です。
すでに書くテーマが決まっている人はぜひやってみて下さい。
超大事!カテゴリー申請
原稿を上がって表紙も上がって
さあ出版!・・・といきたくなりますが、ちょっと待ってください。
カテゴリー申請の準備をしましょう。
カテゴリーとはこの部分のことです。

ようは本のジャンル。
あなたの本を置く売り場ですね。
リリース直後はAmazonサイドから
割り振られた3つが、手持ちカテゴリーになります。
この3つは必ずしも本と合っているわけではないので
リリース後、なるべく早く申請して
『追加』『削除』をする必要があります。
カテゴリーは最大10個まで登録することができます。
この『追加カテゴリー』をあらかじめ調べておくのです。
そしてこんな文章を作っておいてください。
⇩
お世話になっております。
カテゴリーの追加手続きの件でメッセージいたしました。
タイトル:副業初心者のぼくがはまった10の落とし穴
ASIN : B09YTHF3QX
追加希望のカテゴリー
Kindle本>ビジネス・経済>タイムマネジメント
Kindle本 > ビジネス・経済 > スキル>コミュニケーション
Kindle本>ビジネス・経済>意思決定・問題解決
Kindle本>ビジネス・経済>ビジネスマナー
Kindle本>ビジネス・経済>ビジネス教育
Kindle本>ノンフィクション
Kindle本>社会・政治>マスメディア
Kindle本>社会・政治>コミュニティ
以上です。
GW前でお忙しい中、スミマセン。
よろしくお願いいたします。
※ちょうどGW前だったので
先方を気づかう一文も入れています。
カテゴリー申請の場所はこちらです

『Amazonカテゴリーの更新』という部分を
クリックするとこんな画面になりますので

このウインドウの中を消して
さっき作った文章を入れて
(本のタイトルとASINは変えて下さいね)
右下にある『メッセージを送信』を押して下さい。
1回でうまくいかないこともありますが
画面を更新して再度行えば、たいてい送れます。
カテゴリー申請を通すコツ
これはぼくもさんざん苦労してきました。
今でも試行錯誤の連続です。
そんな中で見つけた方法をいくつかご紹介しますが・・・
その前にカテゴリー申請の
厳しい現状について少しだけ書かせてください。
これは新人作家さんも知っておいた方が良いことです。
厳しくなったカテゴリー申請
2022年のはじめぐらいから
強引なカテゴリー申請が通りにくくなりました。
要するに
本とマッチしないカテゴリー申請が通りにくくなったんです。
極端な例だと、
トレーニング本なのに『音楽』で申請する、みたいなことです。
Kindle作家は
割り当てられたカテゴリーでランキング上位を目指します。
そのために、
なるべくニッチでライバルが少ないカテゴリーを狙います。
だから強引な申請を試す人がいるんです。
ぼくもやったことがあります。
これまでは運が良ければ通っていました。
でも、Kindle作家が増えたことで
Amazon側で
「少し規制をかけよう」という動きが出たのでしょう。
加えて読者からクレームが入ったと思われます。
「なんで音楽カテゴリーに、
トレーニング本が入ってるんだ?」
・・・という感じです。
結果、前と比べてカテゴリー申請が通りにくくなりました。
これは他のKindle作家さんも感じていていて
Twitterでつぶやいているので確実と見られます。
ならばどうすればいいのか?
3つのコツをご紹介します。
コツ① 強引な申請はしない
あまりに
自分の本と関係がない強引なカテゴリー申請はしない。
どのみち断られるなら、
やり取りをする時間がお互いムダです。
Amazon側に良い印象も持たれないでしょう。
担当者の方だって人間です。
「この作家、また強引な申請してきたな・・・」
というイメージがつくと、今後の申請にも悪影響です。
前とは状況が変わったことを理解して
あまりに強引な申請はしない方がいいでしょう。
その上で、通りやすくする2つ目のコツを一つご紹介します。
それが・・・
コツ② 内容紹介を詳しく書く
例えばこんな感じです。

この内容紹介は
『Kindle出版戦国時代 初心者が有利に戦うには?』で書いたものです。

ちなみにこの本の目次はこちら

目次だけだと分からない内容を
あえて箇条書きにして加えました。
「こんな内容も入ってますよ~」というアピールですね。

なぜこんなことを書き加えたのか?
それは、カテゴリー申請を却下された際、
Amazon担当者からのメールにこんな文言があったからです。

タイトル、表紙、内容紹介、キーワードを見ると
希望カテゴリーとは合わない本に見受けられます。
・・・ということですね。
あくまで想像ですが、
担当の方は本の内容までは読んでいません。
(出版される本が多すぎてムリでしょう)
チェックしているのは、メールにも書いてある通り、
▽本のタイトル(サブタイトル含む)
▽本の表紙
▽内容紹介(目次も含む)
ということは、
この3つの中に希望カテゴリーの要素を入れれば
申請は通りやすくなる、ということです。
※キーワードはまだ分析しきれていないので
ここでは割愛します。
だからぼくは内容紹介に詳しく書いちゃいました。
これだと仮に一度は断られたとしても
「内容紹介にも書いたのですが・・・」と交渉することができます。
再交渉することも知らない方が多いですよね。
却下メールに対して返信すれば担当者とやり取りすることができます。
クレームばかりつけるのはダメですが、
「さすがにこれは変かな?」と思ったらメッセージを送ってみて下さい。
そして最後、3つ目のコツ。
それが・・・
コツ③ 厳しい担当者に当たったら1回寝る
Kindle作家としてカテゴリー申請をやっていると
イヤでも気づくのですが、
Amazon担当者の中に、めちゃくちゃ厳しい方がいます。
この方に当たると
かなりの確率でカテゴリー申請が却下されます。
さすがに具体名はあげませんが、・・・いらっしゃるんです。
この例えが伝わるかわかりませんが、
バレーボールアニメ『ハイキュー!!』に登場する
鉄壁ブロックを誇る強豪校・伊達工(だてこう)並です。
どれだけ申請(スパイク)しようと
ことごとく却下(ブロック)されます。

別にその方を責める意図はありません。
ご自分の信念をもって仕事を全うしているだけなのですから。
考えてもみて下さい。
こういう方ってどの職場にもいるじゃないですか。
Aさんだとサクッと決済が通るのに
Bさんだと全く決済が通らない
職場だと逃げるわけにもいきませんが、
Amazonの中には、他の担当者もいらっしゃいます。
だからその日はカテゴリー申請するのを諦めて
翌日とか翌々日にするのです。
・・・すると、意外とあっさり通ることがあります。
押してダメなら引く・・・ってヤツです。
まとめると・・・
カテゴリー申請する際は
『強引な申請はなるべくやめる』
『内容紹介に書いたことをしっかり書く』
『厳しい担当者に当たったらいったん引く』
この3つのやり方を駆使してみてください。
ぼくはこのやり方をはじめてから
カテゴリー申請がスムーズに進むようになりました。
A+(エープラス)の補足
これは過去作品がある作家さんに限った話です。
A+で自分の過去作品をPRしている方も多いですよね。
その際の注意点を一つ書いておきます。
それが・・・
PR作品はリリース作品と相性がいいモノにしましょう。
これをとてもうまくやっている
作家さんが まいごさんです。
「仮想通貨」「NFT」「メタバース」についての
Kindle本を3冊書かれた作家さんです。
この方のA+の設計がお見事という他ありません。
こちらです。

4枚目のA+の下に、
明らかに同じシリーズの本が3冊、並んでいます。
仮想通貨、NFT、メタバース
この3つのネタは親和性が高いので
気になる読者は続けて読んでいくことが予想できます。
見事な導線です。
まいごさんはたった3冊のKindle本で
1カ月10万近い収益を上げています。
すさまじいの一言ですね。
だからもしあなたが新刊をリリースしたら
過去作品をやみくもに並べるのではなく
新刊と関連する作品、続けて手に取りたくなる作品を
選んで配置すると良いです。
まいごさんはA+クリエーターとしても優秀
Kindle作家以外に
まいごさんはA+クリエーターとしても優秀です。
ぼくも3冊ほど作って頂きました!
気になる方はぜひコンタクトを取ってみて下さい!
https://twitter.com/maigo123456
Kindle本は初速が命
個人出版のKindle本は初速が命です。
リリース直後に
どれだけたくさんの読者に認知してもらうかが勝負!
なのでリリースした時点で(遅くとも1週間以内)
▽A+の設置
▽過去作品の配置
▽カテゴリーの申請
この3つを終わらせた状態で無料キャンペーンを行なって下さい。
おまけ:ティザーを作る
ティザーとは要するに
30秒〜1分ぐらいの紹介動画です。
こちらですね。
どうかお願いです。ぼくの失敗を笑ってください。
— ミツ│固ツイでおバカ企画やってます (@mitsu_kindle) May 8, 2022
笑ったあとで自分にあてはまるものがあったら、
笑いを引っ込めて真剣に考えてみてください。
あなたのお金と時間を救いたい。そう思って書いた本です。
一部の方には不都合なことも書いてます。これはそういう本です。https://t.co/cQgkUkWoiv pic.twitter.com/lX0HkKh1EH
今は少数派、でも今後は・・・
この動画、今はまだ作れる人が少なくて
Kindle本のPRに使っている人も少ないです。
しかし今後は、A+と並んで重要な役割を担いそうです。
やっぱり映像の力って大きいですから。
ぼくがやり取りしているデザイナーさんは
とても優秀な方で、
いつも素晴らしい動画を作ってくれます。
ちなみにデザイナーさんはこちら。
自身もKindle作家として活躍している
TACKさんです。
こちらも表紙やA+同様、
丸投げしない方が良いでしょう。
TACKさん自身は
「丸投げでOKですよ」というスタンス。(本人確認済み)
ホントに心優しいデザイナーさんです。
でもより良いものを作るためには
どんな些細な言葉やイメージでも、伝えた方が良いです。
参考までに
『副業初心者のぼくがハマった10の落とし穴』で
ぼくが提案したシナリオを以下に書いておきます。
⇩
どうか笑ってください
副業ビギナーのぼくがハマった 10の落とし穴
たくさんのお金と 時間をムダにしました
でも 失敗したからこそ見えた光があった
著名人の名言と共に綴る
(アインシュタイン、エジソン、本田宗一郎 ビル・ゲイツ、
本田圭佑、羽生善治、 モハメド・アリ、
夏目漱石、アンミカ、さくらももこ)
10の失敗と大事な教訓
伝えたいことはただ一つ
あなたのお金と時間を救いたい
ミツ著 「副業初心者のぼくがハマった 10の落とし穴」
何回だって転べばいい
立ち上がって歩き出そう
未来を見据えて
今後いろんな作家さんがティザーを作っていくと思います。
「ほ〜、すごいなあ」と他人事にせず
繰り返し見て、シナリオの作り方を研究しておくと
きっと今後、役に立ちます。ぜひトライして下さい。
最後にお伝えしたいこと
Kindle作家は一人で何役もこなさねばならない
ということです。
作家・宣伝・営業、
表紙やA+を自作する場合はデザイナーの資質も問われます。
大変だと思いますが
それぞれのスキルを磨いておけば
Kindle以外のプラットフォームに流用することができます。
例 ココナラでスキルを販売したり
Brain教材を作ったり
Kindle出版を入り口にして
コンテンツクリエーターの可能性を広げていって下さい。
公式LINEへのお誘い
Kindle出版、ビジネスマインドを中心に
時々、おすすめBrain情報なども発信しています。
よろしくお願いいたします<(_ _)>
プレゼントを一つご用意しました。
こちらです。

これはKindle本の最初のページに
ぼくが使っている『連続スクロール設定』です。
これは横書きの原稿を読んでもらう時に
とても有効な設定なんです。
設定をすると、ブログのように下へ下へと
本を読むことができるようになります。
この赤線で囲った画像をプレゼントいたします。

ぼくの公式LINEに登録して頂いた上で
『スクロール画面ください』とメッセージ下されば
TwitterのDMから、データ便にてお送りします。
その際、LINEとTwitterで名前の表記が異なる場合は
あわせてお教えくださいませ。
コンテンツ紹介
最後に・・・
2冊のKindle本と2つのBrain教材のリンクを置かせて下さい。
『Kindle出版』『コンテンツビジネス』『ライティング』
これらについて、役立つ情報を書いたものです。
どうかよろしくお願いいたします。
Kindle本
Brain教材
これでまた、栄養(本やマンガ)摂れます!
