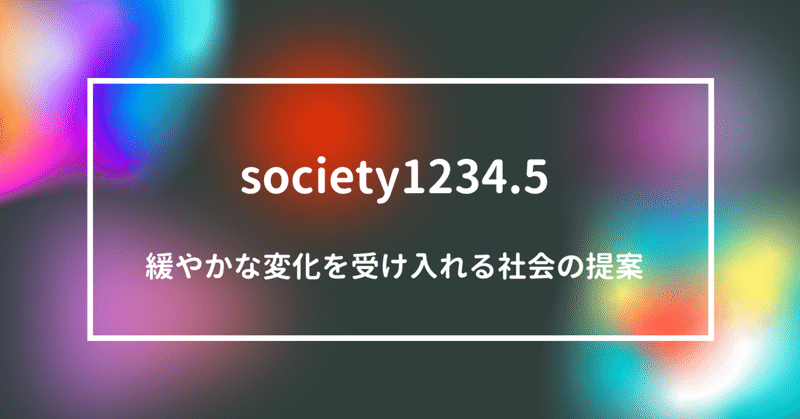
society1234.5 ~緩やかな変化を受け入れる社会の提案~
未来の暮らしを考える
最近未来の暮らしはどうなっているのだろうかと未来予想をする事が多いのですが、このテーマであれこれ最近のトレンドを追いかけていくとぶち当たるのは「society5.0」というテーマ。
そもそもどこでどう暮らすかという事を考えた時、自分の身を置くところがどう変化していくのかという事もとても重要で実は思います。以前"暮らし"についての記事を書いて欲しいという依頼をいただいたこともあり、未来予想について一部書いた事もあるのですが、そんな内容も交えて公開していこうと思います。
society5.0について改めて考える
Society 5.0とは
サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)。狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会を指すもので、第5期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。 ※内閣府HPより
どんな社会が実現されるか
Society 5.0で実現する社会は、IoT(Internet of Things)で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服します。また、人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されます。社会の変革(イノベーション)を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍できる社会となります。※内閣府HPより
さて素晴らしい理想論なので本当にそれが実現できるのであれば、それを目指していくべきだと思いますが、改めて考えてみても前提となるテクノロジーだけではこれを実現できるようには思えません。そこでこの違和感を解きほぐしながら、どこを目指すべきなのか改めて考えていきたいと思います。
包括的に進む社会を捉える際のミスリード
少し先の未来はsociety5.0という理想の社会を創ってそこで生きようといわれても、実際の所現代社会においてはsociety1.0~4.0まで混在しています。本来的な狩猟社会というのは中々ないけれど、港町で漁をする町なんかはどちらかといえば狩猟社会(society1.0)に近いだろうし、農業に従事した暮らしは農耕社会(society2.0)に生きているともいえます。工場に勤めて暮らせば工業社会(society3.0)に身を置けるし、IT企業なんて今は当たり前になりましたが現在は情報社会(society4.0)という事になっています。
society1.0~4.0まで進んできたという話ではありますが、実際はどこかのタイミングで新しい社会に切り替わって刷新されているわけではなく、すべての要素を包括しながら現代の社会に続いています。そしてどの時間軸の文化が色濃いかは土地ごとに異なり、その土地がどの時代に大きく発展したかという事がその配分を決めているように思います。
また、私たちはそのギャップを利用する事で現代に同じく生きながら、自分が住みたい時代の文化に近い社会で住むことができます。個々の理想の暮らしを考えた時、この多様な時間軸や文化を抱擁する現代でこの複雑さを感じ取りながら、自分にとって心地よい文化圏で自身の能力を活かすのが良いように思います。ここでは日本での話を書きましたが、全世界で見ればもっと広い時間軸の文化を内包しているとも言えるでしょう。
そんな背景を元に改めて考えるとsociety5.0で掲げられる理想社会はこれから新しく生まれてくるテクノロジーだけでは実現は困難だろうと、田舎に暮らしていて改めてそんな風に感じるのです。これはある意味テクノロジーへの信奉が深い大企業群が自身の存在意義を懸けて産みだした大きなミスリードという捉え方もできます。
society5.0の異質な点
society1.0~4.0までの変革を牽引してきたのは、人間の暮らしを大きく変える程に便利なテクノロジーなのは確かだと思います。狩猟社会から農耕社会には稲作をはじめとした農業技術、農耕社会から工業社会に向かったのは蒸気機関をはじめとしたエネルギー関連技術、情報社会に変わったのはインターネット通信をはじめとした通信技術とされています。
ただしいずれの地点でも、新しい技術革新があってそれをみんなが好き好んで使ったというのが一番のポイントではないでしょうか。稲作はなぜ広まっていったか、ある人は新石器で木を切り倒せる事に気づき土地を開拓できるようになったからと解くし、ある人はそもそも住処を守ってきた女性が種を育てて収穫できるという事に気づいたからとも解きます。おそらくどれも正解なのでしょうが、それは長いスパンで色んなひらめきが積み重なって出来ているはずです。
しかしsociety5.0の異質な点は理想の社会像を先に提示して、そのために新しいテクノロジーを生み出し配置しようとしている所かもしれません。なぜそんなことを提示しているのかというとやはり現代社会の行き詰まりや窮屈感に対して何かしら回答を見つけないといけないというような焦燥感があり、そこに対して戦後日本と同様の論理を過去の栄光的な発想にすがりながらまたやり直そうとしているからのように感じます。
そもそもあまりにも短いsociety3.0と4.0
実際の所、狩猟社会というのはホモサピエンスが生まれたとされる10万年以上前から続いてきたことで、農耕社会は1万年前くらいから、工業社会はここ300年くらいの話で、情報社会に至っては長く見積もっても40年くらいのものでしょうか。その期間が示すように狩猟社会や農耕社会というのはそれだけ私たちの暮らしの中に深く根付いています。そして狩猟社会や農耕社会においてもテクノロジー(特に道具と暮らし)のアップデートはゆっくりと長い時間をかけて行われ、社会に根付いて今に至るはずです。誰かの根気強い取り組みと閃きで社会が大きく変わる事は度々ありながらも、社会に根付いて今に残ってくるには数多くの失敗や淘汰があった結果ではないでしょうか。どこかのタイミングで突然切り替わったわけでは決してないでしょう。
私が仮に分類するとしたら「society1.0狩猟社会」、「society2.0農耕社会」、「society3.0工業社会」、「society3.1情報社会」のように考えます。確かに近現代は多くの閃きが生まれ加速度的に変化しているかもしれませんが、soceity1.0やsoceity2.0といった長いスケールで人類の営んできた社会を捉えるのであればそれくらいのちょっとしたアップデートと捉えておいた方がミスリードしないのではないでしょうか。近代史に'もくじ'をつけて何となくまとめる事は出来るかもしれませんが、総括するにはあまりにも期間が短すぎるのではないだろうかと感じる所です。
"新しい"が"理想"であるはずがない
新しいテクノロジーでよりよい社会を作ろうとする「society5.0」。次なる社会が人類にとってぴったりの理想となればいいねと望む事は良いと思いますが、実際の所は新しい変化には未知の要素が含まれます。その際問題も一緒に生じます。素晴らしい点も問題もひっくるめて少しずつあり方が変わっていくのが新しさを受け入れた自然な変化の形のはずです。一方で具体的に提示される理想の社会のイメージには未知の要素や不確定要素がほとんど排除されています。理想は具体的になればなるほど完璧さを求めてきます。そして「新しさと完璧さ」はそもそも相いれない物ではないでしょうか。
もし本当に具体的な理想像というものがあってそこを目指すならば、現時点ですべての進歩や変革を止めて今あるものを再配置する事で実現すべきなのでしょう。しかし新しい物事を生み出そうという流れは止まるはずもありません。そう考えた時「新しさと完璧さ」どちらに理があるかは言うまでもないでしょう、新しい変化を取り込んでいきながら完璧にはならない不完全さを残しながらこれまでもこれからも続いていくでしょう。新しい技術を導入して次世代は素晴らしくなればいいと望むのは良いですが、思い通りに行くはずはないという前提の下で進めるべきです。
現状私たちが持ち得ている身体的能力の限界
やはり現時点に存在する森羅万象を支配したつもりになっている事、そして未来についても支配できるつもりでいる事へ奢りや浅はかさを感じる所であります。人類全体の知識や理解はテクノロジーの進歩によって積み重なったかもしれませんが、一方で僕ら一人一人の身体性はそこまで変化してはいません。全てを持ち得たようでいて一人一人が発揮できる能力も行動原理にある欲求だって相変わらずで大した事はありません。道具を用いて身体や能力の拡張というのはこれまで普遍的に行われてきましたが、身体自体に作用する拡張についてはまだまだ駆け出しであり未知の事が多いように思います。倫理的な問題や本能的な忌避もある部分ですが、きっと今後はそれらも超えていくのでしょう。
いつかは身体的限界を何らかの形で超えていくのかもしれませんが、今後の技術革新によって示される可能性と現状我々が持ち得ている能力については切り分けて考えた方がよいように思います。ただし今の時代が人類にとっての大きな変革を伴う時代である事は確かだし、道具によって拡張された能力との向き合い方や一人一人の生存のための戦略というのも多様化して、ある意味選択をするのが難しくなっているというのは間違いないでしょう。
「society5.0」に対しての「society1234.5」
という事でsociety5.0というワードには大きなミスリードがあるという事が何となく見えてきましたが、ではどうすればいいだろうかという話を考えていきます。「society5.0」の文脈で考えるのであれば、「society1234.5」を目指そうという事だと私は考えています。既存の社会の整理をしつつ、未来に向けて0.5のアップデートを少しずつ進めていこうという事です。つまり現代に至るまでの私たちの祖先が培ってきた暮らしや生きる知恵というと生まれたばかりの技術を改めて並べなおして、良い配置を考えてはどうだろうという提案です。
例えば、デジタルデバイスによる情報共有ができれば、便利に素早く情報を共有できるというのは事実ですが、回覧板と世間話による地域に住む人間によって最適化された情報ネットワークの力も中々便利で素早い事もあるよというのも事実としてあります。デジタルデバイスへ過度に依存する事が社会的なリスクとなり得ることも考えるべきです。
ただし、どちらかに傾倒しようという事では無くて「デジタルデバイス」と「回覧板と世間話」についてどちらがカタログスペック的に優れているかという事だけでなく、現状からの導入コスト(どれぐらい文化として普及しているか)、今後の継続コスト(みんながそれを無理なく維持できるか)、等もフェアに考えるべきという事で、これまで我々が培ってきたテクノロジーをベースに根付いた「暮らしの知恵」と新しく生まれてくるテクノロジーによる変革「イノベーション」へのリソース配分をよりフラットに比較すべきという事です。
緩やかな変化をお互いが受け入れる事
革新派、つまりイノベーションのおかげで豊かな暮らしを創り出し、自分達も最大限にその恩恵にあやかり続けている側の人は、これまでのように過激な変化ばかりが続けらない事を感じて、テクノロジーが社会に実装されていく際の"緩やかさ"を受け入れる事。
保守派、つまり昔ながらの暮らしを続けていて、これまで通りにそれが続いていく事を望む側の人は、新しいテクノロジーが日々生み出され少しずつ自分たちの暮らしに根付いている事を感じて、"変化"を受け入れていく事。
共通して言える事は”緩やかな変化”を受け入れる事ではないかとそんな風に考えます。こういった部分への相互理解の無いままに進んでいけば今後もっと格差は広がり欺瞞ばかりの社会になり、より希望が見いだせないままになっていく様に感じられます。そんな分断の果てに行きつく先は、きっと大きな争いや悲劇的事件を引き起こす事、もしくは全体としての緩やかな虐待や衰退の上の一部虚栄的な繁栄や支配的構図の堅牢化であり、私たち自身もしくはほんの少し先の世代が当事者となるのではないでしょうか。
理想社会の実現のためのリソース配分の歪み
society5.0で掲げるような理想社会の実現を目指すのは良い事だと私も思います。ただし未来に対して行う取り組みのリソース配分が既存の資本や既得権益、イノベーション志向の思想それに準ずる権力に大きく依存したものであり物凄くアンフェアな物になっているというのをやはり感じます。というかそもそも未来のテクノロジーを創造し実装するような場所に関われるのはほんの一握りの人なので、society5.0目指しているのは”革新社会”というイメージを持っています。そういった発想は戦後日本を大きく発展させ、今豊かに暮らせている背景にある考え方というのは間違いないでしょう。ただ今は平均年齢47歳の高齢社会であり、それがより進んでいきます。年を重ねるほどに人間色んな価値観を持ち、急激な変化がしにくくなります。そんな現状で今後”革新社会”を好んで受け入れていく様にはあまり思えません。
でもどんなに頭のいい人でも結局は人間で、神様のように私たちの身近な困った事まで理解することは出来ないし、ダイナミックな仕掛けだけでは取りこぼされる人達がいるという事が、飽き飽きするほど前に進まない政治の風景を見ていても、もういい加減はっきりと分かると思います。日本社会全体を通じて頭のいい人の選別と配置、そしてトップダウンな施策づくりという人材育成の発想を改める必要があるように感じる所です。
小さな社会づくりから根本的な発想を改める
小さな社会を地域と捉えて考えた時に、各地域がなぜどのようにして発展したか、今現在にどういった歴史や暮らし、文化が残っているか、そこに住む人は実の所はどんな未来を創造するかという事の対話や再考のないまま、そして近代において結ばれた都市と地域の関係性と今に至る歪みを捉えなおさないまま、漠然とした理想論へのリソース配分が進んでいきます。これは今なお至る所で惰性で続いている事が多く、特に最近であればスーパーシティ構想などもいい例だと思います。根本的な所への理解や変化がないまま偏った資金の投下が続いていると感じる所です。個人的にはsociety5.0的でスーパーな都市は日本の中で1つや2つ作る事を目指し、それを作るためにリソースを配分し、そのデータは普遍的な地域づくりのため活用するというのがフェアだろうと思います。こういったなんだか頭でっかちに感じる取り組みばかりを見ていると、これまでの事を全部一旦ご破算にして考え直そうとそういう発想からやり直さなければこれからを生きる人たちは希望を見出せないのではないだろうかというのがやはり正直に思う所です。
これから向かうべき先の展望について
現状の流れへの批判的な内容が多くなったので、ではどういう方向性が良いだろうか改めて考えてみます。リソース配分を変えると言っても、①無駄な事を止める、②お金や権限を持つ人を変える。大きくこの2つかと思います。イノベーションに頼りすぎるのはある意味”いちかばちか”という事で、社会全体のリスクが大きく、リターンは一部の人にしか回らないかもしれません。そこで前述の例示に沿って言うとスーパーシティへの予算取りをするならば、地域の普通で普遍的に暮らしている人達の知恵の体系化と再配置、そしてアップデートにリソースを割き続けるべきではないだろうかという提案です。もし最近のトレンドに乗って言葉を作るとすれば、ゼロカーボンを超えてマイナスカーボンビレッジとか、サステイナブルでかつ外からの人を受け入れる余白を残したレジリエンスローカルコミュニティなど、そんなテーマを代案としてはどうだろうかという事です。そしてそこで得られた知見を各地に生かして小さな社会をアップデートしていくのが理想ではないでしょうか。
いずれにせよそれは教育的な事が中心であり試行錯誤し続ける事は必須だろうし、社会包括的なアプローチが必要になると考えています。教育や文化のような所へのリソース投下は特定の目的を目指すのと違って、インプットとアウトプットの関係性が難しい複雑系へのリソース配分となるので、その理解はとても難しく多くの人が共有できる論理や価値観まで落とし込むのはまだまだ私自身探究が必要に感じています。
なにはともあれ自分の事は自分で考えて決めるという機能を個人個人が取り戻し、社会として考え抜かれた事柄が実装されていく、そんな社会を目指すのが良いのではとそんな風に思います。そう考える一方で自分の考えなど持たず従順な方が個人としての自己実現のための無駄を省けて、さらに上に立つ人から素直でいい奴(御し易い)のような評価される事が多いという風土は、実は凄く身近で普遍的な価値観として共有されています。そんな価値観の中、囚人のジレンマ的な重力と向き合っていく新しいゲームメイクはとても難儀しそうとも感じています。
最後に、私自身の追い求めるところ
society5.0で語られるようなSFチックな未来を夢と理想に溢れながら日々しのぎを削りながら、本気で追い求め続けている人は敬意を持って応援させてもらいつつ、私自身は「society1234.5」というようなテーマ設定をして、「society1.0~4.0」と語られている部分についての整理し0.5のアップデートを取り入れ続けるような、より普遍的に"緩やかな変化"を包括した社会とは何かと考えていきたいなと思っています。それはきっとイノベーションやチャレンジし続けた人にとっても、その後夢や理想から一線退いた時にそこに戻ってこれる社会という事でもあると考えています。
という事で「society5.0」から未来の社会を考えるそんな考察でした。最後まで読んでいただきありがとうございました。よければハート押してってもらえると励みになります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
