コロナウイルスに学ぶ生物③~ウイルス感染のメカニズム~
皆さんこんにちは、大友雅斗です。
前回のnoteを御覧になって頂いた皆様、ありがとうございます。
フィードバックもどしどしお待ちしています。
前回、ウイルスとはそもそもどういうものか、を説明しましたが、今回の第三回目の記事では、どのような仕組みでウイルス感染症が起こるのか、について説明していきます。
体内への侵入
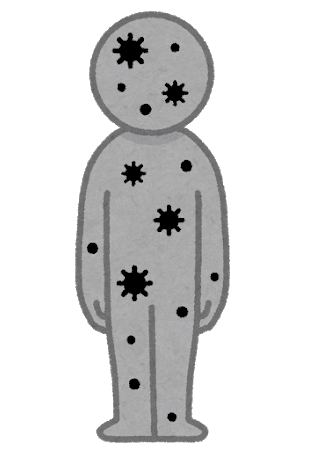
ウイルスを、人体が取り込んでしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。
まず前回の記事の、ウイルスは、DNAまたはRNAという遺伝情報と、数種類のたんぱく質だけで構成されている、という話を思い出して頂きたいと思います。
体内に侵入したウイルスは、体内の細胞の膜表面に存在するタンパク質(受容体)と、ウイルス表面のタンパク質が結合し、細胞の中に取り込まれます。(これを宿主細胞への感染といいます)
取り込まれたウイルスは、DNAやRNAなどの遺伝情報を細胞内に放出、その遺伝情報をもとに、ウイルスの持つタンパク質と、遺伝情報が細胞内の小器官や分子の働きにより複製されます。
それらを材料に新しいウイルスが合成され、細胞外に排出されると、他の細胞に感染が拡大してゆきます。
イラストで簡単に説明すると以下の流れになります。(画伯なのでクオリティーはご承知おきを…)

以上のようなプロセスを繰り返して感染を拡大していくわけですね。
なぜ新型コロナウイルスが肺炎を起こすか
特に今回のコロナウイルス感染症では、肺炎の症状や、味覚嗅覚障害、下痢など消化器系の症状が知られていますが、これも先ほど説明したメカニズムで説明がつきます。
コロナウイルスの表面に存在するタンパク質(スパイクという突起状のもの。写真などでよく見るかと思います)が、細胞表面のコロナウイルスの受容体と結合することをきっかけに細胞内に入り込み、感染が起こります。
コロナウイルスの受容体(とウイルスと細胞の融合を助けるタンパク質)は、主に肺、小腸、嗅覚上皮などに多く存在しているため、これらの器官における感染、炎症などの症状が起き、以上のような症状が起こる、と説明がつきますね。
また、この受容体の量が、年齢を重ねるごとに増加、女性よりも男性に多い、という傾向があることが言われています。
また、基礎疾患や喫煙習慣がある人も、この受容体が肺において多くなっていることが指摘されています。
以上の理由から、高齢の方や、喫煙習慣のある方、基礎疾患がある方は、感染のリスクが高く、重症化に注意する必要がある、と説明ができますね。
参考としてこんな感じの論文が出ています、というリンクを貼っておきますので、もし興味があれば、、、
今回はウイルスが人体に侵入すると、どのようなメカニズムで感染が起こるのか、コロナウイルスを例にとり説明しました。
前回治療についても説明予定、と書いていましたが、免疫の話題と関連させた方がよいと思い、1つの記事にすると長くなってしまうので、また改めて書きたいと思います。
次回は、よく聞くワードである、PCR検査とは何か?などを説明する予定です。
また、他に扱ってほしいテーマや、質問事項がございましたらできる範囲でお答えいたしますので、こちらのコメントか、Twitterのリプライなどで頂ければ嬉しいです。
また第四回もよろしくお願い致します。最後まで読んでいただきありがとうございました!
