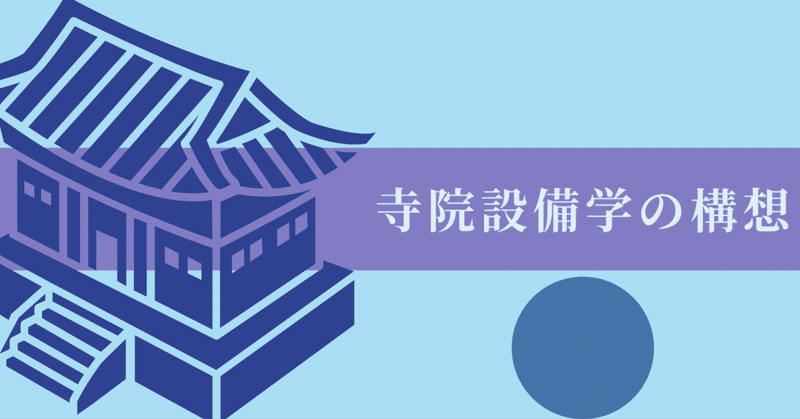
構想の主旨
この構想を描くきっかけになったのはブッダガヤでのある経験がもとになっています。
自己紹介にも少し書きましたが僕は元・法衣店の営業マンでした。
また僕が勤めていた法衣店は曹洞宗専従の会社でした。
ご寺院様ならこの専従性のことを知っておられる方がほとんどかと思いますが補足させていただきます。
日本には簡単に整理すると13の宗派があるとされています。曹洞宗はその中の一つで最も全国の寺院数の多い宗派になります。
専従性というのは曹洞宗以外の仕事は行わないということです。
一体なぜそうなるのかというと、法衣が縫えないからです。
13種の分類の中にもいくつかのグループがあります。例えば曹洞宗は臨済宗と同じ禅宗系のグループです。また四国遍路の元になる真言宗は天台宗とセットで密教系のグループになります。
同じグループの曹洞宗と臨済宗でもお坊さんの法衣は袈裟ひとつとっても全く違う形状をしています。

そのために縫製を行う仕立て師さん(縫子:ぬいことも言います)は宗派をまたぐとそれだけ違う仕立て方を覚え、通常より長い修行期間が必要になり、会社側もより多くの仕立て師さんを抱える必要があります。
これがひとつの理由になります。
また法衣組合で発行した法衣史の資料を紐解くと最初の法衣仕立てを始めた会社は現在も京都に拠点を置くある呉服店さんで(この呉服店さんは現在は法衣は扱っていません)その分家や暖簾分けで分かれていった集団が顧客の取り合いを避けるために住み分けをしていったということがもう一つの要因の可能性があります。
ですので僕は曹洞宗の寺院さんのもとで修行をした法衣屋さんになります。
(*ちなみに業界全体で数社だけ宗派を横断出来る法衣店さんもあります)
少しブッダガヤの出来事を引き出しますが、僕は曹洞宗のお坊さんばかりにあっていたのでこの時はじめて浄土宗や臨済宗のお坊さんと仏具や法衣の話をしました。旅行記に登場いただいた日本寺で出会ったお坊さんたちは他宗派の方達でした。
曹洞宗のお坊さんたちのいうところよると仏教学部のある大学や各地の修行道場において仏具や法衣のケヤや保管、製造法や修理法についての座学はなく実際に壇務(お寺では職務と言わず壇務といいます)についてから先輩僧侶や自分で経験を重ねて学んでいく状態だそうです。
そしてそれが他宗派でも似たような状態ということを知りました。
このことが今回の寺院設備学の構想への発想の芽生えであったと思います。
また元々勤めていた時から何らなの方法で法衣・仏具の取り扱いや保管、作り方や直すときの注意点を整理したアーカイブのようなものがあれば良いなぁと考えいました。
それは勤めていた時のある出来事に一因があります。

この写真は「ワンタッチ香合」と言われる商品です。
茶道をされる方であればお寺さんと同じようにお使いになるのでご存知の方もいるかもしれませんが、沈香や白檀などの香木(燃やすと香りのする木)を保管する木箱のようなものです。
主に造りは2種類あります。
○フタを重ねてかぶせて置くだけの香合
○この写真のように溝や爪をつけたフタを本体と噛み合うようにした香合
この噛み合わすものの中に「ねじ切り」というものがあります。
水筒の蓋のように蓋と本体にオス・メスの溝を掘って噛みわせて閉めるタイプのものです。
勤めていた頃にこれを作れる職人さんがもう日本に居なくなったという情報が流れました。
ワンタッチは意外と簡単にできるそうなのですが、ぴったりと合う溝を掘る技術は高度なもので熟練の木地師でも掘るのが難しいそうです。
理由は簡単で木製品なので、気候条件や素材の個性により作った溝が過乾燥で割れたり、湿度で変形するのです。木は伐採し乾燥させても生き物です。この木それぞれの個性を読み、未来を予想して加工することが非常に高度な技術なのです。
実は僕が勤めていた当時からいつか職人がいなくなり無くなってしまう仏具が他にもいくつかあると言われています。
また原料調達が困難なものやコストの問題で消えてしまう可能性のあるものあります。
僕はこの職人さんたちが居たという記録や今使っているものがいつかは手に入らなくなることは共有されるべきではないか。
そして現状使われているものをケアし修理しながら使っていく知識を整理されても良いのではないかという考えに至っていました。
そうしなければこんなに凄い人たちがいたことも作ったものも価値が理解されず忘れられていくのではないかと感じたからです。また将来、日本の寺院を支える人たちのためにもバトンそのものを用意するべきと考えます。
仏教の浄土系のグループ、浄土宗や浄土真宗・時宗・融通念仏宗の中に末法思想という考え方があります。
【末法思想】
釈迦の入滅後、1000年や500年という期間で切り分けた仏教の深度を三つの時代に分けて捉える考え方
○正法
釈迦が亡くなって最初の500年は正しく釈迦の教えが伝わる時代
○像法
次の1000年期は正法の時代の教えが正確な形を失い始め正法に似た理論体系の中で行われる時代
○末法
仏教が衰退し、釈迦の残した正しい教えは終わりを迎えられるとされる時代
この「末法」の時代がはじまったのが日本の仏教では平安時代末期の1052年とされています。ちなみに中国での末法思想はもう少し早い時代にはじまるので必ずしもこのタイムスケジュールというわけではないようです。
この思想の通り、現代の仏教には様々な困難と向かい合い、その教えの形は本当の意味において原型を留めているのかは正直、誰にも分からないのではないかというものが僕の正直な意見です。

そして来る2052年に1000年目を迎える時がきます。末法思想では1052年以降は2000年とか10000年とか数億年先まで永遠に末法の時代であるとされています。
現在、仏教界と法衣・仏具の業界は信仰離れの中で様々な問題を抱え、時代の要請が変わる中でこれまでの宗教の立場や役割も変わっていき、末法思想にあるように教えは閉じて行くのかも知れません。これは誰にもわからないと思います。
約30年後に初めて1000年期が明けるときにこの国の法衣・仏具が護られるためにも今何ができるのかという事を問いながら日々の法衣・仏具のケアやその仏具の背景や使用の目的を記した情報源を構築したいと考えます。
少しでも次の世代の人たちのために今ある法衣や仏具の知識や製作者の意志が残され、日々僧侶の皆さんや檀信徒の皆さんの手で繋いでいく一助になるものを目指してみたいです。
ただ自分一人でこの発想が完成にいたるという自信や確信は持てずにいるというのが今の正直な気持ちです。
それでもいつかもう一度宗教というものが必要な世が来た時のため礎となるように自分の中に留めず持てるものと手の届く範囲の情報を形にするべきと考えこれを「寺院設備学の構想」とします。
それでは次回、「天蓋」から進めていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
