
バリアフリーは踊る─「ファイティング黒田のラーメン劇場」
こちらで上演台本を公開している「ファイティング黒田のラーメン劇場」が2024年5月18日、「こうばこの会」第59回公演にて上演されました。100名を超えるお客さんを前に、当事者役を当事者に演じていただいての初演。「あるある」が身につまされる作品に仕上げていただきました。
「脚本家は現場では弱者です」
自分で書いたセリフに泣き笑い。
出演のお一人、脚本家・黒田を演じたかわいいねこさんが稽古から本番までのことをnoteに綴ってくださっています。
「束の間の一花」に音声ガイドがついた
6月21日、「束の間の一花」のBlu-rayとDVDが発売され、ゆるゆる(萬木)と一花がわが家にやって来た。
庭で採れたミニトマト(去年は間に合わず、今年こそはと八百屋さんで苗を購入)をふたつ並べて歓迎したが、もったいなくてまだ開封できていない。

同じく6月21日、「束の間の一花」のHulu配信に「音声ガイド」版が加わった。「音声ガイド」を選ぶと、全10話が並んでいる。

音声ガイド版が誕生したきっかけは、バリアフリー演劇結社「ばっかりばっかり」で活動され、音声ガイド制作の現場経験も豊かな全盲の美月めぐみ(めーたん)さんと夫の鈴木橙輔さんからの働きかけ。「一花に音声ガイドを!」の気持ちとご縁がつながり、美月さんと橙輔さんのお二人が指導されている音声ガイドサークル「ブルーベリーボイス」による原稿制作と、美月さんによるナレーションで実現した。
放送時は橙輔さんの「生音声ガイド」つきで観ていたという美月さん。想像で膨らませる余地を残し、語りすぎず、でも的確な情報を届けられるガイド原稿を一緒に探った。
美月さんと橙輔さんとわたしの出会いはclubhouseで、その後、バリアフリー演劇企画でご一緒した。オムニバスのオリジナル脚本を手がける4人の作家の中にわたしと橙輔さんがいた。
「バリアフリーを題材にしたコメディ」というお題に応え、音声ガイドのモニター会を舞台にした上演時間30分ほどの脚本を書いた。
音声ガイドのモニター会とは、映像作品に仮ナレーションを組み込んだものを当事者に確認してもらい、「このガイドで情景が思い浮かぶか?」「描写は適切か?」などを検討するもの。より良い表現や言葉がないか、その場で代案を出したり、持ち帰ったりして、収録用の音声ガイドに反映させる。
わたしは『嘘八百 京町ロワイヤル』『嘘八百 なにわ夢の陣』の音声ガイド制作に監修として関わり、モニター会にも立ち会った。そこで感じたのは、「答えは一つではない」ということだった。
同じ音声ガイドでも、人によって必要か不必要かの判断は変わるし、障害の程度や、いつから視覚が不自由になったかによっても、知りたい情報は変わる。十人に聞けば、十通りの「マイベスト・音声ガイド」があり、落としどころを探ることになる。しかも、限られた秒数の中で。
音声ガイド原稿を執筆する「ディスクライバー」さんももちろんいるが、脚本家が居合わせると、一緒に言葉を探したり選んだりできる。『嘘八百』シリーズの場合は、配給会社のGAGAの担当者も数名同席し、アイデアを出し合えた。
音声ガイドのモニター会は、瞬発力を求められるブレストを繰り返しながら進む。とてもクリエイティブな作業だ。各場面で映っているものの優先順位をつけ、大事なことを立たせ、言葉に凝縮する。取捨選択のセンスと今流行りの「解像度」の高い描写力が求められる。脚本や演出を勉強中の人が立ち合ったら、吸収できることがたくさんあると思う。
ということで、登場人物はかなりクセを強くしているが、刺激的なモニター会でのやりとりを煮込んだ「ファイティング黒田のラーメン劇場」が誕生した。
バリアフリー演劇企画は仕切り直しとなり、脚本はお蔵入りとなったが、蔵から取り出して広げられる良い時代。noteに公開したら、上演したい人につながるかもしれない。
提出時から加筆したものをclubhouseで読み上げて校正し、公開。素読みで約30分だった。
2024年2月9日追記)「音声ガイドがどういうものであるか、わからない方には理解しづらいのでは」というご指摘をいただき、その部分を中心に加筆しました。細かく気づいたところも加筆しています。また、あらすじをつけました。変更箇所確認用にオリジナル版を改訂版の後に残しています。
今井雅子作「ファイティング黒田のラーメン劇場」
あらすじ
劇場公開を控える映画『夜明けの二人』の音声ガイドのモニター会。音声ガイドの原稿を書いたディスクライバーの白田が進行役を務め、仮ナレーションの入った本編を視覚障害者である当事者モニターの青井と赤井に観てもらう。
作品の関係者を代表して、脚本を書いた黒田が立ち会っている。ヒット作は特になく、次の仕事も入っていないため、時間を作れるのが黒田だけだったのだ。モニター会がどんなものなのかもわからず参加したが、何かのネタになるかもしれないという下心はあった。
映像の状況が音声描写で伝わるかを当事者に確認してもらうのがモニター会の目的なのだが、音声ガイドの内容ではなく映画本編への疑問やツッコミが入り、代案のアイデア出しが白熱し、なかなか前に進まない。
ムキになって反論する黒田のキャラをモニター二人が面白がり、黒田のような視覚障害者を主役にしたコメディを作ってはという妄想で盛り上がる。時間通りに終わらせようと焦っていた白田も加わり、ラーメン屋で胡椒と爪楊枝を間違えても負けを認めない「ファイティング黒田」というキャラクターが生まれる。
後日、青井がコンクールに応募した脚本が受賞したという知らせを受ける黒田。あの日のモニター会がきっかけで生まれた作品だという。そのコンクールに黒田も出していた。
上演脚本
登場人物
黒田 脚本家
白田 ディスクライバー
赤井 視覚障害者モニター
青井 視覚障害者モニター
舞台下手、画面に見立てた横長の黒い板。
その前に長机が一つと椅子が二つ。
画面脇に立つ、ディスクライバーの白田。
白田「ディスクライバーの白田です。ディスクライバーという職業をご存知ない方も多いかもしれません。映画やドラマの音声ガイドの原稿を書いています。音声ガイドというのは、視覚が不自由な人のために、画面に映っている場所や人物、場面転換などを音声で解説するものです。できるだけ作品の邪魔にならないよう、それでいて、できるだけ作品を楽しんでもらえるよう、毎日が勉強です。音声ガイドの完成前に、当事者に伝わる内容になっているかどうか意見を聞くモニター検討会が開かれることが多いです。映像作品に仮ナレーションを組み込んだものを当事者に確認してもらい、このガイドで情景が思い浮かぶか、描写は適切か、などを検討します」
白杖をついて、モニターの青井が上手から来る。立ち止まって客席に向き直り、
青井「モニターの青井です。全盲で生まれました。目で見るというのがどんな感じなのか、よくわかりません。仕事は、視覚障害のある方にパソコンの操作を教えています。モニター会に参加するのは、今年で3回目、ですかね。よく呼んでいただいているほうだと思います」
青井、手で椅子を探し当て、腰を下ろす。
白杖をついて、モニターの赤井が上手から来る。
青井に比べて、白杖のつき方が危なっかしい。
立ち止まり、本人は客席に向き直っているつもりだが、少しずれた方向を向いて、
赤井「モニターの赤井です。二十代の終わりから、見えるところが少しずつ塗りつぶされていきました。今は自分の手を目の前にかざしても、ぼんやりとしか見えません。仕事は、ずっと休んでいます。モニター会に参加するのは初めてです」
椅子を探す赤井。見つけられず、手がさまよう。
青井「こちらです」
青井、机を叩き、音を立てて教える。
赤井「どうも」
赤井、着席する。
黒田「遅くなりました!」
黒田、下手から小走りに来る。立ち止まり、客席に向き直り、
黒田「脚本家の黒田です。映画やドラマの脚本を書いています。デビューして二十年。ヒット作は特にありません。図太そうに見られますが、小心者です。作品を否定されると、自分が否定された気持ちになります。モニター会がどういうものなのか、よくわかっていませんが、誰か立ち会ったほうがいいってことで。まぁ、これも何かのネタになるかもしれません」
黒田、青井と赤井の後ろ、上手側に立つ。
白田「これから観ていただくのは、三月公開予定の劇場映画『夜明けの二人』です。仮ナレーションの音声ガイドをつけた本編を少しずつ区切って流します」
白田がリモコンを操作すると、仮ナレーションの音声ガイドをつけた本編映像が流れる。
音声ガイド「停電し、真っ暗な夜道。まわりが見えず、立ち往生する歩行者たちの間を縫って、大学教授の手を引いて歩く学生。迷いのない足取りでホールの入り口に着く」
学生(劇中音声)「こちらです教授」
教授(劇中音声)「おお、ここか。ありがとう。君のおかげで講演会に間に合ったよ」
学生(劇中音声)「お役に立てて良かったです」
教授(劇中音声)「それにしても、どうして明かりがないのにこんなにスタスタ歩けたんだい?」
学生(劇中音声)「私、目が見えないんです」
音声ガイド「学生、一礼し、去っていく。教授、学生が去った方向に深く頭を下げる」
赤井、途中から退屈している。
青井、最後まで集中している。
二人の反応を気にして落ち着かない黒田。
白田、画面にリモコンを向けて一時停止し、
白田「ここまで、いかがですか?」
どちらが先に言うか様子見の間があって、
赤井「じゃあ私から、いいですか?」
白田「赤井さん、どうぞ」
赤井「ちょっとお聞きしたいんですけど、教授を誘導した学生って、全盲の設定なんですか?」
白田「黒田さん、いかがでしょう?」
黒田「全盲とは、とくに言っていないんですが……」
赤井「セリフで言ってますよね? 『私、目が見えないんです』って」
黒田「ああ。限りなく見えていない、ですね」
赤井「こんなにスタスタ歩けます?」
黒田「この学生にとっては、灯りがついてるかどうかは関係ないので、普段と同じようにスタスタと……」
赤井「そこなんですけど、普段からスタスタじゃないと思うんですよ。白杖もついてないんですよね?」
黒田「ハクジョウ?」
白田「杖です。白い杖と書いて、ハクジョウと読みます」
黒田「ああ」
赤井「白杖はついてるけど、そのことについての音声ガイドはついてないってことですか?」
白田「はい。ついていません」
赤井「どっちが?」
白田「どっちと言いますと?」
赤井「白杖? 音声ガイド?」
白田「劇中で白杖をついていませんので、その描写の音声ガイドもついていません」
赤井「杖なしでスタスタ歩けるかなー」
青井「盲導犬を連れているんじゃないですか?」
赤井「それだと『明らかに見えない人』になって、驚きがなくなっちゃいますよね」
青井「あ、そうですね。(考えて)わかりました! この学生さん、停電になると特殊能力が発揮されて、見えるようになるって設定じゃないですか?」
赤井「それなら成立するか」
青井「しますよね!」
黒田「いえ、特殊能力という設定では……」
赤井「違うんだ?」
白田「赤井さん、モニター会初めてでしたよね? 映画の内容ではなく、音声ガイドについてご意見いただきたいんですが」
青井「思ったんですけど、立場の逆転を描きたい、ということではないでしょうか」
赤井「逆転?」
青井「真っ暗な世界では、普段、視覚に頼っている人が障害者になる。そういうことなのかなって」
黒田「そうです! このシーンは、まさにそれを描きたいんです! わかっていただけて、うれしいです」
青井「合ってましたか。良かった」
白田「青井さん、今の場面、音声ガイドについては、いかがでしょう」
青井「そうですね。学生と教授がどんな服を着て、どんな顔立ちなのかは、詳しく知りたいです」
白田「そこは秒数の関係で」
青井「でも、この後、二人の恋が始まるんですよね」
黒田「残念ながら、そういう展開には……」
青井「ならないんですか。結構重要な人物なのかなって思ったんですけど」
赤井「今のシーン、もう一度流してもらえます?」
白田「これで最後ですよ」
白田がリモコンを操作すると、音声ガイドをつけた本編映像が流れる。
音声ガイド「停電し、真っ暗な夜道。まわりが見えず、立ち往生する歩行者たちの間を縫って、大学教授の手を引いて歩く学生。迷いのない足取りでホールの入り口に着く」
学生(劇中音声)「こちらです教授」
教授(劇中音声)「おお、ここか。ありがとう。君のおかげで講演会に間に合ったよ」
学生(劇中音声)「お役に立てて良かったです」
教授(劇中音声)「それにしても、どうして明かりがないのにこんなにスタスタ歩けたんだい?」
学生(劇中音声)「私、目が見えないんです」
音声ガイド「学生、一礼し、去っていく。教授、学生が去った方向に深く頭を下げる」
赤井「やっぱりスタスタをやりたいだけのシーンに見えるんですよ」
白田「また話が戻っちゃいました」
赤井「でも、この役者さんはスタスタ歩けたわけですよね」
黒田「学生役の方は見えている方なので」
赤井「見える人が見えない人の役をやっているんですか?」
黒田「宇宙人の役を宇宙人がやりますか?」
赤井「そりゃあ宇宙人はそうだけど、イギリス人の役はイギリス人がやるでしょう」
黒田「そうとは限りません。イギリス人に見えれば、なに人の役者が演じたっていいんです。ハリウッドでも、日本人の役を中国人がやったりしてますよね? それと同じく視覚障害のある人に見えれば……」
赤井「見えなかったです」
黒田「あれ? 赤井さんって、見えてらっしゃるんですか」
赤井「いえ、ほぼ見えてませんよ。映像では見えてないですけど、音で見てます」
黒田「なるほど」
赤井「視覚障害があるようには見えなかったなー」
黒田「それは……学生役の役者の演技力の限界です」
赤井「役者のせいにしちゃうんですか?」
黒田「そういうわけでは……」
白田「あのー、皆さん、くどいようですけど、映画の内容ではなく、音声ガイドについての意見をお願いします。次のシーンに行きますね」
白田、リモコンを向ける。
青井「当事者が演じるっていう話は、なかったんですか?」
黒田「当事者?」
青井「実は私、お芝居やってるんです。この役のオーディションがあったら、受けたかったなあって」
赤井「青井さんがやってたら、リアリティーが全然違いますよ」
青井「はい。私、ガチ盲人ですから」
黒田「でも、教授と別れ際に、実は目が見えないってわかるのがミソなので」
青井「私みたいなガチモーだとダメですか?」
黒田「ダメといいますか……」
白田「みなさん、そろそろいいですか。昼食までに前半を見終えてしまいたいです」
赤井「脚本を書くとき、視覚障害のある人に取材はされたんですか?」
黒田「いえ」
赤井「じゃあ、どっから湧いてきたんですか、スタスタ?」
青井「今思い出したんですけど、英語の教科書に、これと似た話が出てました」
赤井「教科書?」
青井「ロンドンで霧の深い日に教授が道に迷っていたら親切な人が現れて大学まで誘導してくれて、最後に、目が見えないんですって言うんです」
赤井「まんま、おんなじじゃないですか」
白田「次のシーン、行ってよろしいですか?」
赤井「ていうか、スマホの懐中電灯で照らせば良かったんじゃないですか」
白田「(ため息)」
赤井「停電して完全に真っ暗ってのが、嘘臭いんだよなあ」
黒田「教授はスマホに懐中電灯機能がついていることを知らなかった。これでどうでしょう?」
白田「それで行きましょう。では、続きを」
青井「目は見えていなくても実はすごいって描き方じゃなくて、もっと普通でいいと思うんです」
白田「(たしなめ)青井さん……」
黒田「普通、ですか」
青井「私がこの学生の役をやるとしたら、教授につかまらせてもらって、においや音を目印にして、視覚以外の感覚を使って教授を誘導します」
赤井「二人で支え合って進む。いいシーンじゃないですか」
青井「ありがとうございます。普通のことを、視覚に頼らずに、どうやって普通にやるか。そこにドラマがあると思うんです。たとえば私、ラーメン屋に一人で食べに行くんですけど、結構驚かれるんです。普通にラーメン屋行けるんだって」
黒田「注文、どうやってるんですか?」
青井「あらかじめネットでメニュー調べたり、文字認識アプリにメニューを読み上げさせたりしてます」
黒田「文字認識アプリ?」
青井「こうして文字を写真に撮ると」
青井、スマホを壁に向け、写真を撮る。
読み上げ音声「うがい・手洗い・思いやり」
黒田「すごい」
青井「今、壁の貼り紙を読み上げました。文字だけじゃなくて」
青井、スマホを壁に向け、さっきより引いた写真
を撮る。
読み上げ音声「大きなテレビモニターに映像のようなものが映っています」
黒田・赤井「おおっ」
赤井「これがあれば、音声ガイド、いらなくないですか?」
白田「え?」
赤井「今画面に何が映っているか、教えてもらえるんでしょ? 同時通訳みたいに」
黒田「そんなこともできるんですか?」
青井「そこまで性能は良くないです。動画の読み上げには対応できてないですし、静止画の説明もまだまだ不安定で。たとえば、この机の上をスキャンすると」
青井、スマホを向け、机の上をスキャンする。
読み上げ音声「床に物が置かれています」
黒田「机と床の区別がつかないんだ?」
赤井「惜しい」
青井「でも、技術が追いつくのは時間の問題だと思います」
赤井「スマホが同時通訳みたいに音声ガイドしてくれるようになったら、白田さん、仕事なくなっちゃいますね?」
白田「ご心配ありがとうございます。五年後十年後の音声ガイドがどうなってるかはわかりませんが、今日のところは、この作品の音声ガイドを最後まで見ていただきたいです」
青井「そうですね。もしかしたら、この先、面白くなるかもしれませんし」
黒田「今は面白くないってことですね」
白田「こんなの誰が見るんだって作品でも、誰かが見るかもしれない。その誰かのために、音声ガイドは、つける意味があるんです」
黒田「作品が気に入らなくても音声ガイドは嫌いにならないでください、みたいな言い方、やめてください」
白田「音声ガイドで視覚情報のバリアは超えられても、面白さのバリアは超えられないんです!」
青井「うまい! (と思わず拍手して)すみません」
黒田「……私だって作品の出来に百パーセント満足しているわけじゃないんです。だけど、できてしまったものは仕方ないじゃありませんか」
白田「そんな言い方、ないんじゃないですか」
黒田「え?」
白田「黒田さん、脚本家は作品の生みの親なんですよ? 人が何と言おうと、わが子を愛してください。生まれて来たのが間違いだった、みたいに言わないでください。そうじゃないと、このハテナだらけの作品を音声ガイドでなんとかしようとした私の努力が報われません」
黒田「じゃあどうしたらいいんですか? スタスタにリアリティーがあるのか、私も疑問でしたけど、監督がずっとあれやりたかったらしいんです。視覚障害のある学生役を当事者の役者にやってもらうのはどうかって言いましたよ。でも、演技したことないアイドルに決まりました。映画は商品だから、お客さんを呼べる人をキャスティングしたい。そういう事情があるんです。なのに監督とプロデューサーは次の作品が入っていて、脚本家だけがモニター会に駆り出されて、一人でサンドバッグにされてるんです。この会の趣旨は、音声ガイドの検討ですよね? 脚本家へのダメ出し会じゃないですよね?」
白田「ごめんなさい。黒田さんを責めるつもりは、ないんです。モニター会に一人も立ち会われない作品だって、あります。黒田さんの誠意、ありがたいです」
黒田「ヒマなだけですけど」
青井「こういう主人公、いいんじゃないでしょうか?」
黒田「こういう?」
青井「プライドが高くて、傷つきやすくて、負けを認められなくて……」
赤井「否定されると逆切れする残念な人」
黒田「全部悪口じゃないですか」
青井「でも一生懸命で憎めない」
白田「たしかに、キャラは立ってます」
青井「こういうの、どうですか。目の不自由な黒田が一人でラーメン食べに行って、胡椒と爪楊枝を間違えて、丼に爪楊枝をバサって入れてしまうんです。でも、頑固な黒田は、胡椒と爪楊枝を間違えて、ガリっと噛んでしまっても、なかなか負けを認めません」
赤井「(芝居がかって)俺は爪楊枝入りのラーメンが好きなんだ」
青井「頬に爪楊枝が刺さって、血がドクドク流れても、黒田は、やはり負けを認めません」
赤井「(芝居がかって)俺は血の味のするラーメンが好きなんだ」
黒田「それじゃB級ホラーじゃないですか!」
白田「これくらいぶっ飛んでいたら、遠慮なく笑えます!」
青井「そうなんです。中途半端な障害者あるあるネタって、笑っていいのかどうか、お客さんも困っちゃうんですよね」
黒田「白田さん、いいんですか? 音声ガイドの検討会から脱線してますよ」
白田「こっちのほうが面白いですから」
赤井「負けを認めないファイティング黒田」
白田「リングネームみたいでいいですね!」
青井「ファイティング黒田のラーメン劇場」
黒田「勝手に人を主人公にして、タイトルつけないでください!」
四人、順番に客席に向き直り、
青井「モニターの青井です。モニター会に出ると、元気が出ます。自分の言ったことをちゃんと聞いてもらえて、透明人間になってないなって。お芝居してみたい気持ちもウズウズします。いつか、障害の当事者じゃなくて、作品の関係者としてモニター会に出てみたいです」
赤井「モニターの赤井です。久しぶりに電車に乗って、出かけました。人としゃべって、好き勝手言って、お弁当と謝礼をもらいました。映画観たの、いつぶりかな。ちゃんと見えてた頃は、よく行ってました。今日の作品が公開されたら、映画館に行ってみようかな。俺、ちょっと関わってるんだぞって」
黒田「脚本家の黒田です。人の意見を取り込むのだけはどんどん上手くなって、使い勝手のいい脚本家になっている、そんな自分の底の浅さを見透かされた気がします。予算もスケジュールもプロデューサーに握られ、脚本家は現場では弱者です。仕方ない、そういうもんだと諦めて戦って来なかった……その結果がこの作品であり、今の私です」
白田「ディスクライバーの白田です。映画を作る人たちが音声ガイドを必要とする人たちの顔を思い浮かべられるようになったら、作品も、世の中も、変わっていく気がします。黒田さんには色々と失礼なことを言いましたが、次の作品もバリアフリー対応にしたいと思ってくれたらいいな。これからも黒田さんに仕事があれば、の話ですが」
黒田を上手に残し、白田と青井を下手に残し、上手にはける赤井。
スマホの呼び出し音が鳴る。
黒田「(出て)もしもし」
下手で電話している白田。隣に青井。
白田「黒田さん? ディスクライバーの白田です。モニター会ぶりですね」
黒田「ああ。その節はどうも」
白田「黒田さんの映画『夜明けの二人』、劇場で観たかったんですけど、あっという間に終わっちゃいましたね」
黒田「もう少しやるはずだったんですけど、打ち切られてしまって」
白田「そうでしたか。ほんとあっという間で」
黒田「何度も言わないでください」
白田「モニター会に来ていた青井さん、覚えてます?」
黒田「ああ。お芝居をやっている方?」
白田「そうです。今、隣にいるので代わりますね」
青井「(電話代わり)黒田さん、ご無沙汰しています。黒田さんの映画『夜明けの二人』、せっかく音声ガイドがついたので、劇場で観たかったんですけど、あっという間に終わってしまって」
黒田「その話はもういいです。あの、私に何か?」
青井「お礼を伝えたくて」
黒田「お礼、ですか?」
青井「テレビ局の脚本コンクールに初めて応募したんです。そしたら大賞をいただいて、ドラマ化して放送されることになったんです」
黒田「すごいじゃないですか青井さん。で、なんで私にお礼を?」
青井「受賞作のタイトル、『ファイティング黒田のラーメン劇場』です」
黒田「ファイティング黒田?」
白田「(横から)青井さん、あの日のモニター会の体験を脚本にされたそうです」
青井「実は、よく似た応募作品があって、盗作じゃないかって疑われたんですけど、私のオリジナルだってわかってもらえて、無事、受賞が決まりました」
黒田「よく似た作品?」
白田「(横から)多分、もう一人のモニターの赤井さんが応募されたんだと思います」
黒田「ファイティング黒田って、私がモデルですか? 胡椒と爪楊枝を間違えて、口から血を流しても間違えを認めない意地っ張り」
青井「いえ、タイトルのインパクトだけ、いただきました」
黒田「インパクト?」
青井「主人公の視覚障害者は私がモデルです。モニター会がきっかけで、全盲の自分が主人公を演じられる作品がないのなら自分で書いちゃえって脚本を書き始めるっていう、ほぼ実話です」
黒田「……なるほど」
青井「視覚障害者の役を当事者が演じたほうがいいっていう時代の空気にも後押しされて、ヒロインのオーディションにも呼んでもらえることになりました。選ばれるかどうかはわかりませんが、これまで当事者俳優は透明人間にされていたので、大きな進歩です。ほんとありがとうございます。あの日のモニター会がなかったら『ファイティング黒田』は生まれなかったので。それだけ伝えたくて」
黒田「そうでしたか。受賞作が形になって音声ガイドのモニター会をやることになりましたら、立ち会わせてください。一応、タイトルのファイティング黒田の生みの親の一人ですから」
電話を切った黒田、客席に向き直る。
黒田「黒田です。青井さんが受賞された脚本コンクール、私も出していました。コメディです。紛糾したモニター会を面白おかしく描き、これをネタに書いてやろうと脚本家が思いつくところでエンドマークを打ちました。あのモニター会から大賞作品が生まれたら面白いと思いました。実際、その通りになりました。青井さん、おめでとうございます。このラストは思いつきませんでした」
(終)
下記、初稿は現在初稿で稽古されている方の改訂箇所を確認用に残しています。確認が済みましたら表示を終える予定です。
初稿)今井雅子作「ファイティング黒田のラーメン劇場」
登場人物
黒田 脚本家
白田 ディスクライバー
赤井 視覚障害者モニター
青井 視覚障害者モニター
舞台中央、画面に見立てた横長の黒い板。
椅子に腰かけ、画面を向いているモニターの赤井と青井。
二人の後ろに立つ脚本家の黒田。
画面の隣に立つディスクライバーの白田(しろた)。
順番に観客に向き直り、自己紹介する四人。
黒田「脚本家の黒田です。映画やドラマの脚本を書いています。デビューして二十年。ヒット作はありません。図太そうに見られますが、小心者です。作品を否定されると、自分が否定された気持ちになります」
白田「ディスクライバーの白田です。映画やドラマの視覚情報を補う音声ガイドの原稿を書いています。できるだけ作品の邪魔にならないよう、それでいて、できるだけ作品を楽しんでもらえるよう、毎日が勉強です」
赤井「モニターの赤井です。二十代の終わりから見えるところが少しずつ塗りつぶされていきました。今は自分の手を目の前にかざしても、ぼんやりとしか見えません。仕事は、ずっと休んでいます」
青井「モニターの青井です。全盲で生まれました。目で見るというのがどんな感じなのか、よくわかりません。仕事は、視覚障害のある方に、パソコンの操作を教えています」
白田「では、音声ガイドをつけた本編を流します」
白田がリモコンを操作すると、音声ガイドをつけた本編映像が流れる。
音声ガイド「停電し、真っ暗な夜道。まわりが見えず、立ち往生する歩行者たちの間を縫って、大学教授の手を引いて歩く学生。迷いのない足取りでホールの入り口に着く」
学生(劇中音声)「こちらです教授」
教授(劇中音声)「おお、ここか。ありがとう。君のおかげで講演会に間に合ったよ」
学生(劇中音声)「お役に立てて良かったです」
教授(劇中音声)「それにしても、どうして明かりがないのにこんなにスタスタ歩けたんだい?」
学生(劇中音声)「私、目が見えないんです」
音声ガイド「学生、一礼し、去っていく。教授、学生が去った方向に深く頭を下げる」
赤井、途中から退屈している。
青井、最後まで集中している。
二人の様子を気にしている黒田。
白田、画面にリモコンを向けて一時停止し、
白田「ここまで、いかがですか?」
赤井「じゃあ私から、いいですか?」
白田「赤井さん、どうぞ」
赤井「ちょっとお聞きしたいんですけど、教授を誘導した学生って、全盲の設定なんですか?」
白田「黒田さん、いかがでしょう?」
黒田「全盲とは、とくに言っていないんですが……」
赤井「セリフで言ってますよね? 『私、目が見えないんです』って」
黒田「ああ。限りなく見えていない、ですね」
赤井「こんなにスタスタ歩けます?」
黒田「この学生にとっては、灯りがついてるかどうかは関係ないので、普段と同じようにスタスタと……」
赤井「そこなんですけど、普段からスタスタじゃないと思うんですよ。白杖もついてないんですよね?」
黒田「ハクジョウ?」
白田「杖です。白い杖と書いて、ハクジョウと読みます」
黒田「ああ」
赤井「白杖はついてるけど、そのことについての音声ガイドはついてないってことですか?」
白田「はい。ついていません」
赤井「どっちが?」
白田「どっちと言いますと?」
赤井「白杖? 音声ガイド?」
白田「劇中で白杖をついていませんので、その描写の音声ガイドもついていません」
赤井「杖なしでスタスタ歩けるかなー」
青井「盲導犬を連れているんじゃないですか?」
赤井「それだと『明らかに見えない人』になって、驚きがなくなっちゃいますよね」
青井「あ、そうですね。(考えて)わかりました! この学生さん、停電になると特殊能力が発揮されて、見えるようになるって設定じゃないですか?」
赤井「それなら成立するか」
青井「しますよね!」
黒田「いえ、特殊能力という設定では……」
赤井「違うんだ?」
白田「あのー、映画の内容ではなく、音声ガイドについてご意見いただきたいんですが」
青井「思ったんですけど、立場の逆転を描きたい、ということではないでしょうか」
赤井「逆転?」
青井「真っ暗な世界では、普段、視覚に頼っている人が障害者になる。そういうことなのかなって」
黒田「そうです! このシーンは、まさにそれを描きたいんです! わかっていただけて、うれしいです」
青井「合ってましたか。良かった」
白田「青井さん、今の場面、音声ガイドについては、いかがでしょう」
青井「そうですね。学生と教授がどんな服を着て、どんな顔立ちなのかは、詳しく知りたいです」
白田「そこは秒数の関係で」
青井「でも、この後、二人の恋が始まるんですよね」
黒田「残念ながら、そういう展開には……」
青井「ならないんですか。結構重要な人物なのかなって思ったんですけど」
赤井「今のシーン、もう一度流してもらえます?」
白田「これで最後ですよ」
白田がリモコンを操作すると、音声ガイドをつけた本編映像が流れる。
音声ガイド「停電し、真っ暗な夜道。まわりが見えず、立ち往生する歩行者たちの間を縫って、大学教授の手を引いて歩く学生。迷いのない足取りでホールの入り口に着く」
学生(劇中音声)「こちらです教授」
教授(劇中音声)「おお、ここか。ありがとう。君のおかげで講演会に間に合ったよ」
学生(劇中音声)「お役に立てて良かったです」
教授(劇中音声)「それにしても、どうして明かりがないのにこんなにスタスタ歩けたんだい?」
学生(劇中音声)「私、目が見えないんです」
音声ガイド「学生、一礼し、去っていく。教授、学生が去った方向に深く頭を下げる」
赤井「やっぱりスタスタをやりたいだけのシーンに見えるんですよ」
白田「また話が戻っちゃいました」
赤井「でも、この役者さんはスタスタ歩けたわけですよね」
黒田「学生役の方は見えている方なので」
赤井「見える人が見えない人の役をやっているんですか?」
黒田「宇宙人の役を宇宙人がやりますか?」
赤井「そりゃあ宇宙人はそうだけど、イギリス人の役はイギリス人がやるでしょう」
黒田「そうとは限りません。イギリス人に見えれば、なに人の役者が演じたっていいんです。ハリウッドでも、日本人の役を中国人がやったりしてますよね? それと同じく視覚障害のある人に見えれば……」
赤井「見えなかったです」
黒田「あれ? 赤井さんて、見えてらっしゃるんですか」
赤井「映像は見えてないですけど、音で見てます」
黒田「なるほど」
赤井「視覚障害があるようには見えなかったなー」
黒田「それは……学生役の役者の演技力の限界です」
赤井「役者のせいにしちゃうんですか?」
白田「お話は尽きませんが、次のシーンに行きましょうか」
青井「あのー、当事者が演じるっていう話はなかったんですか?」
黒田「当事者?」
青井「実は私、お芝居やってるんです。この役のオーディションがあったら、受けたかったなあって」
赤井「青井さんがやってたらリアリティーが全然違いますよ」
青井「はい。私、ガチ盲人ですから」
黒田「でも、教授と別れ際に、実は目が見えないってわかるのがミソなので」
青井「私みたいなガチモーだとダメですか?」
黒田「ダメといいますか……」
白田「みなさん、そろそろいいですか。昼食までに前半を見終えてしまいたいです」
赤井「脚本を書くとき、視覚障害のある人に取材はされたんですか?」
黒田「いえ」
赤井「じゃあ、どっから湧いてきたんですか、スタスタ?」
青井「今思い出したんですけど、英語の教科書に、これと似た話が出てました」
赤井「教科書?」
青井「ロンドンで霧の深い日に教授が道に迷っていたら親切な人が現れて大学まで誘導してくれて、最後に、目が見えないんですって言うんです」
赤井「まんま、おんなじじゃないですか」
白田「次のシーン、行ってよろしいですか?」
赤井「ていうか、スマホの懐中電灯で照らせば良かったんじゃないですか」
白田「(ため息)」
赤井「停電して完全に真っ暗ってのが嘘臭いんだよなあ」
黒田「教授はスマホに懐中電灯機能がついていることを知らなかった。これでどうでしょう?」
白田「それで行きましょう。では、続きを」
青井「実はすごいって描き方じゃなくて、もっと普通でいいと思うんです」
白田「(たしなめ)青井さん……」
黒田「普通、ですか」
青井「私がこの学生の役をやるとしたら、教授につかまらせてもらって、においや音を目印にして、視覚以外の感覚を使って教授を誘導します」
赤井「二人で支え合って進む。いいシーンじゃないですか」
青井「ありがとうございます。普通のことを、視覚に頼らずに、どうやって普通にやるか。そこにドラマがあると思うんです。たとえば私、ラーメン屋に一人で食べに行くんですけど、結構驚かれるんです。普通にラーメン屋行けるんだって」
黒田「注文、どうやってるんですか?」
青井「あらかじめネットでメニュー調べたり、文字認識アプリにメニューを読み上げさせたりしてます」
黒田「文字認識アプリ?」
青井「こうして文字を写真に撮ると」
青井、スマホを壁に向け、写真を撮る。
読み上げ音声「うがい・手洗い・思いやり」
黒田「すごい」
青井「今、壁の貼り紙を読み上げました。文字だけじゃなくて」
読み上げ音声「大きなテレビモニターに映像が映っています」
赤井「これがあれば、音声ガイド、いらなくないですか?」
白田「え?」
赤井「今画面に何が映っているか、教えてもらえるんでしょ? 同時通訳みたいに」
黒田「そんなことができるんですか?」
青井「そこまで性能は良くないです。動画の読み上げには対応できてないですし、静止画の説明もまだまだ不安定で。たとえば、この机の上をスキャンすると」
青井、机の上をスキャンする。
読み上げ音声「床に物が置かれています」
黒田「なるほど」
青井「でも、行く行くは技術が追いつくかもしれません」
赤井「スマホが同時通訳みたいに音声ガイドしてくれるようになったら、白田さん、仕事なくなっちゃいますね?」
白田「ご心配ありがとうございます。五年後十年後どうなってるかはわかりませんが、今日のところは、この作品を最後まで見ていただきたいです!」
青井「そうですね。もしかしたら、この先、面白くなるかもしれませんし」
黒田「今は面白くないってことですね」
白田「こんなの誰が見るんだって作品でも、誰かが見るかもしれない。その誰かのために、音声ガイドは、つける意味があるんです」
黒田「作品が気に入らなくても音声ガイドは嫌いにならないでください、みたいな言い方、やめてください」
白田「音声ガイドで視覚情報のバリアは超えられても、面白さのバリアは超えられないんです!」
青井「うまい! (と思わず拍手して)すみません」
黒田「私だって作品の出来に百パーセント満足しているわけじゃないんです。だけど、できてしまったものは仕方ないじゃありませんか」
白田「そんな言い方、ないんじゃないですか」
黒田「え?」
白田「黒田さん、脚本家は作品の生みの親なんですよ? 人が何と言おうと、わが子を愛してください。生まれて来たのが間違いだった、みたいに言わないでください。そうじゃないと、このハテナだらけの作品を音声ガイドでなんとかしようとした私の努力が報われません」
黒田「じゃあどうしたらいいんですか? スタスタにリアリティーがあるのか、私も疑問でしたけど、監督がずっとあれやりたかったらしいんです。学生役を視覚障害のある役者にやってもらうのはどうかって言いましたよ。でも、演技したことないアイドルに決まりました。映画は商品だから、お客さんを呼べる人をキャスティングしたい。そういう事情があるんです。なのに監督とプロデューサーは次の作品が入っていて、脚本家だけがモニター会に駆り出されて、一人でサンドバッグにされてるんです。この会の趣旨は、音声ガイドの検討ですよね? 脚本家へのダメ出し会じゃないですよね?」
白田「ごめんなさい。黒田さんを責めるつもりはないんです。モニター会に一人も立ち会われない作品だってあります。黒田さんの誠意、ありがたいです」
青井「こういう主人公、いいんじゃないでしょうか?」
黒田「こういう?」
青井「プライドが高くて、傷つきやすくて、負けを認められなくて……」
赤井「否定されると逆切れする残念な人」
黒田「全部悪口じゃないですか」
青井「でも一生懸命で憎めない」
白田「キャラは立ってます」
青井「こういうの、どうですか。視覚障害者の黒田が一人でラーメン食べに行って、胡椒と爪楊枝を間違えて、丼に爪楊枝をバサって入れてしまうんです。でも、頑固な黒田は、胡椒と爪楊枝を間違えて、ガリっと噛んでしまっても、なかなか負けを認めません」
赤井「(芝居がかって)俺は爪楊枝入りのラーメンが好きなんだ」
青井「頬に爪楊枝が刺さって、血がドクドク流れても、黒田は、やはり負けを認めません」
赤井「(芝居がかって)俺は血の味のするラーメンが好きなんだ」
黒田「それじゃB級ホラーじゃないですか!」
白田「これくらいぶっ飛んでいたら、遠慮なく笑えます」
青井「そうなんです。中途半端な障害者あるあるネタって、笑っていいのかどうか、お客さんも困っちゃうんですよね」
黒田「白田さん、いいんですか? 音声ガイドの検討会から脱線してますよ」
白田「こっちのほうが面白いですから」
赤井「負けを認めないファイティング黒田」
白田「リングネームみたいでいいですね!」
青井「ファイティング黒田のラーメン劇場」
黒田「勝手に人を主人公にして、タイトルつけないでください!」
四人、順番に客席に向き直り、
青井「青井です。モニター会に出ると、元気が出ます。自分の言ったことをちゃんと聞いてもらえて、透明人間になってないなって。お芝居してみたい気持ちもウズウズします。いつか、障害の当事者じゃなくて、作品の関係者としてモニター会に出てみたいです」
赤井「赤井です。久しぶりに電車に乗って、人としゃべって、好き勝手言って、お弁当と謝礼をもらいました。ちゃんと見えてた頃は、よく映画行ってました。今日の作品が公開されたら、映画館に行ってみようかな。俺、ちょっと関わってるんだぞって」
白田「白田です。映画を作る人たちが音声ガイドを必要とする人たちの顔を思い浮かべられるようになったら、作品も、世の中も、変わっていく気がします。黒田さんには色々失礼なことを言いましたが、次の作品もバリアフリー対応にしたいと思ってくれたらいいな。これからも黒田さんに仕事があれば、の話ですが」
黒田「黒田です。人の意見を取り込むのだけはどんどん上手くなって、使い勝手のいい脚本家になっている、そんな自分の底の浅さを見透かされた気がします。予算もスケジュールもプロデューサーに握られ、脚本家は現場では弱者です。仕方ない、そういうもんだと諦めて戦って来なかった。その結果がこの作品であり、今の私です」
黒田を上手に残し、白田と青井を下手に残し、上手にはける赤井。
スマホの呼び出し音が鳴る。
黒田「(出て)もしもし」
下手で電話している白田。隣に青井。
白田「黒田さん? ディスクライバーの白田です。モニター会ぶりですね」
黒田「ああ。その節はどうも」
白田「黒田さんの映画、劇場で観たかったんですけど、あっという間に終わっちゃいましたね」
黒田「もう少しやるはずだったんですけど、打ち切られてしまって」
白田「そうでしたか。ほんとあっという間で」
黒田「何度も言わないでください」
白田「モニター会に来ていた青井さん、覚えてます?」
黒田「ああ。お芝居をやっている方?」
白田「そうです。今、隣にいるので代わりますね」
青井「(電話代わり)黒田さん、ご無沙汰しています。映画、せっかく音声ガイドがついたので、劇場で観たかったんですけど、あっという間に終わってしまって」
黒田「その話はもういいです。あの、私に何か?」
青井「お礼を伝えたくて」
黒田「お礼、ですか?」
青井「テレビ局の脚本コンクールに初めて応募したんです。そしたら大賞をいただいて、ドラマ化して放送されることになったんです」
黒田「すごいじゃないですか青井さん。で、なんで私にお礼を?」
青井「受賞作のタイトル、『ファイティング黒田のラーメン劇場』です」
黒田「ファイティング黒田?」
白田「(横から)青井さん、あの日のモニター会の体験を脚本にされたそうです」
青井「実は、よく似た応募作品があって、盗作じゃないかって疑われたんですけど、私のオリジナルだってわかってもらえて、無事、受賞が決まりました」
黒田「よく似た作品?」
白田「(横から)多分、もう一人のモニターの赤井さんが応募されたんだと思います」
黒田「ファイティング黒田って、私がモデルですか? 胡椒と爪楊枝を間違えて、口から血を流しても間違えを認めない意地っ張り」
青井「いえ、タイトルのインパクトだけいただきました」
黒田「インパクト?」
青井「主人公の視覚障害者は私がモデルです。モニター会がきっかけで、全盲の自分が主人公を演じられる作品がないのなら自分で書いちゃえって脚本を書き始めるっていう、ほぼ実話です」
黒田「……なるほど」
青井「視覚障害者の役を当事者が演じたほうがいいっていう時代の空気にも後押しされて、ヒロインのオーディションにも呼んでもらえることになりました。選ばれるかどうかはわかりませんが、これまで当事者俳優は透明人間にされていたので、大きな進歩です。ほんとありがとうございます。あの日のモニター会がなかったら『ファイティング黒田』は生まれなかったので。それだけ伝えたくて」
黒田「そうでしたか。受賞作が形になって音声ガイドのモニター会をやることになりましたら、立ち合わせてください。一応、タイトルのファイティング黒田の生みの親の一人ですから(と電話を切る)」
黒田「黒田です。その脚本コンクール、私も出していました。紛糾したモニター会を面白おかしく描き、これをネタに書いてやろうと脚本家が思いつくところでエンドマークを打ちました。あのモニター会から大賞作品が生まれたら面白いと思いました。実際、その通りになりました。私は一次選考で落とされましたが。青井さん、おめでとうございます。このラストは思いつきませんでした」
(終わり)
「必要とする人」が思い浮かぶこと
「ファイティング黒田のラーメン劇場」。この話で書きたかったのは、「バリアフリーのニーズは一人一人違う」ということ。
なぜわざわざ言いたいのかというと、「手話通訳がつくから字幕はいりませんよね?」「点字があるから音声読み上げはいりませんよね?」のような話がよくあるからだ。
視覚に障害があっても点字を読めない人はいる。
点字を読めても、音声読み上げにアクセスできない人がいる。
聴覚に障害があっても手話ができない人はいる。
手話ができても、日本語を読むのは苦手な人はいる。
「エレベーターつけたから、階段いりませんよね?」とはならないように、それぞれに必要とする人がいる。
バリアを乗り越える手立てはひとつではなく、選べたほうがいい。けれど、身近に当事者がいないと、なかなか想像が及びづらい。
「てにをは」も含めて単語を手話に置き換える「日本語対応手話」はあるが、「日本手話」は日本語とは文法が違うということを、わたしは手話講習会に通うまでは知らなかった。
手話講習会は通訳養成講座への昇級試験に合格できず脱落したが、聴覚障害者の友人知人ができた。そんなわたしでも、『嘘八百』第一弾が完成したとき、日本語字幕のことをすっかり忘れていた。「字幕つきますよね?」と思い出させてくれたのが、TA-net(シアター・アクセシビリティ・ネットワーク)代表の廣川麻子さんだった。
助成金の申請が間に合わないタイミングだったが、「こんな方法があります!」と実現に向けて今からできることをきめ細かくアドバイスしてくれ、ユニバーサルデザインコンサルタントの松森果林さん(ブログ「松森果林UD劇場〜聴こえない世界に移住して」のファン)とともに日本語字幕監修にも関わってくださった。
松森さんは手話講習会で講演を聞いたことが縁でつながっていたのだが、松森さんがお子さんと初めて見た日本映画が『子ぎつねヘレン』で、その理由は「日本語字幕がついていたから」。
バリアフリー版、やっぱり大事!
『子ぎつねヘレン』には日本語字幕と音声ガイドがついているが、つけることは公開初日に決定した。初日打ち上げの乾杯の席で発表されたので覚えている。2006年公開。今から17年前。当時バリアフリー版を作っていた映画は今の何十分の一という希少さだったかもしれない。
その音声ガイド原稿を書き、ナレーションも担当したのが『嘘八百 京町ロワイヤル』と『嘘八百 なにわ夢の陣』のディスクライバーの堀内里美さんというご縁だった。松田高加子さんとお二人で、信じられないようなスピードで仕上げてくれたらしい。
「松竹の石塚さんに『なるはやで』と言われて」とのことだったが、先日、「大名倒産」応援ルームでプロデューサーの石塚慶生さんにその話をしたら、当時の記憶が抜け落ちていた。それくらいあっという間だったのか、寝てないほど忙しかったのかもしれない。
「バリアフリー版を必要とする人」に話を戻すと、わたしは夫に視覚障害があり、そのつながりでの友人もできた。『嘘八百 京町ロワイヤル』のバリアフリー版試写を一緒に観た全盲の西田梓さんも、その一人。
「視覚を使わないプロ」を自称する梓さんは、緑内障による中途視覚障害者の夫にとっては大先輩で、視覚以外を駆使する方法と心構えを夫婦で学ばせてもらっている。
あと、わたしがnoteを始めたのも梓さんがきっかけだ。
「障害は個性ではない。それをどう乗り越えるかが個性」だという梓さんの主張には、うなずく首が一つじゃ足りない。障害によってできないことのバリエーションは個性ではなく、個人差だと思う。バリアはひとくくりにできないし、障害のある人もひとくくりにはできない。
saitaにて連載中の「漂うわたし」には梓さんがモデルのカズサさんが登場。梓さんからの気づきの数々を物語の中で描いている。
『嘘八百 なにわ夢の陣』バリアフリー版を制作した「Palabra(パラブラ)」代表の山上庄子さんとの対談もあわせてどうぞ。
「共生社会の実現を目指す障害者の芸術文化振興議員連盟」総会に行ってきた
5月19日、Palabra(パラブラ)さんからのお誘いで、「共生社会の実現を目指す障害者の芸術文化振興議員連盟」総会という会合にオブザーバーとして参加した。
会場は参議院議員会館。普段足を踏み入れることのない場所だ。天井が無茶苦茶高く、バスケットボールのコートが何面も取れそうな廊下を進み、会議室に入ると、直線と曲線を組み合わせた競馬のコースのような形の大会議テーブルを議員のセンセイと思しき方々がぐるりと囲み、その外側に椅子がずらりと二重に並べられていた。その一角に、声をかけてくれた「バリフリー映画研究会」に割り当てられた席があり、そのひとつから会議を見守った。
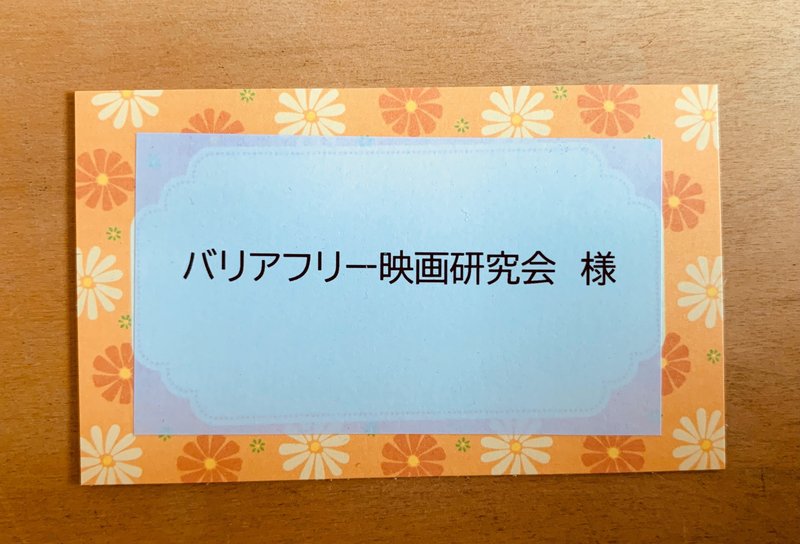
議題は
① 「障害者の芸術文化振興」に関連する令和 5 年度予算について関係省庁よりヒアリング
② 「障がい者の芸術文化活動推進知事連盟」より取り組み状況についてヒアリング
③ 2025 大阪・関西万博に向けた障害者の文化芸術に関する取組について、
「障害者の文化芸術活動を推進する全国ネットワーク」の皆さまとの意見交換
④ その他
手話講習会に通っていた頃、「手話言語条例」とセットで名前を覚えた鳥取県の平井伸治知事が出席されていて、「あの平井知事!」となった。障害者の芸術文化振興についても、全国の知事たちの旗振り役となっている様子。
会議は1時間の予定と告知されていたが、到底1時間ではおさまらないから延長するだろうと思っていたら、きっかり1時間で終わったことに驚いた。分刻みで会議が入っている人たちが集まっているから時間厳守なのだろう。
それを知らなかったわたしは、全国から集まった団体の代表の方々が挙手で意見を言う機会を得たときの発言のまとまりの良さに感心していた。どの人もわずか数分の短い時間に、訴えたいことと熱意を凝縮していた。
とくに引き込まれたのは、記憶の蓄積ができず、一日前のことを覚えていない人が、舞台を見た翌日に「あの続きはどうなった?」と聞いたというエピソードだった。「昨日がなかった人に、昨日ができた」。芸術の力と可能性を強く感じられた。バリアフリーで作品を届けられる機会がふえたら、もっとたくさんの変化が起こせるのではないかと。
他には、なかなか絵を描こうとしない子どもがいて、その理由が「真っ白な紙だと紙の色の刺激が強すぎる」からだとわかり、白くしていない紙を渡したところ絵を描き始めたという話も印象に残った。万博で障害のある人の手がけた作品を展示する場合に、結果物である作品だけではなく、それが生まれる過程も見てもらえるようにできないかという提言で、これにも大きくうなずいた。
ひと月余り経っても、どのエピソードも、会場の空気とともに思い起こせる。出席された議員の方々にも印象を残せていることと思う。
バリアフリー版を作るバリア
バリアフリー映画研究会からは、《年間に邦画洋画あわせて1200本ほど公開されるうちバリアフリー版が作られるのは、わずか100本ほど。テレビや演劇でもまだまだ行き渡っておらず、もっと広まるために予算をつけて欲しい》と訴えた。
だいぶ普及が進んだ印象があったが、思った以上にまだまだだった。公開規模は決して大きくない『嘘八百 京町ロワイヤル』と『嘘八百 なにわ夢の陣』のバリアフリー版を作れたのは配給のGAGAをはじめ製作委員会の理解があったから。さらに公開規模が小さい足立紳さん監督の『雑魚どもよ、大志を抱け!』もバリアフリー版が作られたが、これはプロデューサーとして参加している足立晃子さんの熱意と行動力が大きいと思う。
バリアフリーを進めるにもバリアがある。
予算(と費用対効果)のバリア。
納期のバリア。
人員不足(余計な仕事が増える)のバリア。
それらを「できない言い訳」にする人たちのバリア。
最後のバリアが一番厄介だったりする。
「必要!」という強い思いはバリアフリーを進めるエンジンになるが、個人の頑張りには限界があるから、「予算がつく」のは大きな後押しになる。実績をひとつひとつ積み上げて、「障害のある人も一緒に楽しめるようにすることが当たり前」という地盤ができていくのではないかと思う。
clubhouse朗読をreplayで
2023.7.21 こたろんさん&中原敦子さん
目に留めていただき、ありがとうございます。わたしが物書きでいられるのは、面白がってくださる方々のおかげです。
