
建築の変出
「建築を解体する」「建築家を解体する」のではなく、「建築を変出」させることに挑戦できないか?
よく建築の革新的な文脈で使われる「解体」は再構築を求めた言葉であり、なんとなくであるが無条件に、既存の否定や思考停止を生み出してしまう。どこか暴力的で、投げやりな意味が生まれてしまう。建築の解体に始まるような建築への批評は理解できるものの、個人的にはどこか頂けなかった。
ある時、建築に批評を与えて、社会とともに進化を志すとき、解体ではなく建築の変出と言い換えれないかと考えた。変出は、建築の次の姿をゆっくりとみんなで考え、世代を超えて育て、時には待機し、他業界を巻き込んで溶かすように進化させていく様な空気がある。なんだかうねうねしながら変化していきそうな楽しさすらある。
黒川紀章は25歳でメタボリズムを始めた。現在23歳の自分は25歳までの2年間で「建築の変出を建築する」ことを考え、その発想から建築や建築家の次の姿を希求していきたいと考えてる。
建築を変出させる背景とその方法論曖昧な断片をまず記載し、ここに提示しようと思う。そして、これから実践ともに育んでいく。
時代のトランジションと近代建築の限界性
昨年、ITA設計事務所でプランニングから関わらせてもらった。
重症障害児福祉施設の設計で最も感じたことは、現在の建築や空間は豊かさに対して鋭すぎる局地的な定義と一般解を押し付けていることだった。
色々と試行錯誤をしたが、重症障害児の子供達の全く異なる身体性、知的なレベルや感覚の違い、命の時間軸のズレ…そのような違いを包括できる空間を、近代建築の技術では完全に生み出すことが十分にできなかった。
これは個人的にはとても恥ずかしく、建築技術の敗北だとも強く感じてしまった。
「一つの住宅の設計が生活者や地域を変える」という文言は良く建築設計の際に使われる。その理念のもとに、生活者への想像力を巡らして線を引き、空間を構築していく。しかし、一度人間の対象を変えた途端、生命への認識を変えた途端それが通じなかったのだ。
これをどう捉えたらいいのかを考えてみる。
少しスケールを飛ばして、社会や経済のことを考えると、今社会はトランジションを前提に強引にも駆動しようとしてる。(と自分は認識している)
それに対して、現代の生活空間自体がトランジションするムードが薄いこと、それをリードする建築家の絶対数が少ないことなのかもしれない。
ブルネレスキがルネッサンスを始め、るネッサンスをミケランジェロが終わらせたように、コルビジェがパンデミック以降に人間の空間解釈を変えようと戦略的に動いたように、社会デザインを変えることを空間をトランジションすることを現在から試みる必要があるのではないだろうか。
そろそろ、近代建築の方程式を改め、建築が変わらなければならないのかもしれない。衣食住が発生した原点に立ち返り、建築の長く重い伝統に立ち返った上で革新に変えていく必要がある。
特に若い世代であるGenZ(これも単なるラベリングに過ぎないけれど)がこの課題をどのように解釈し、検討していくのかに挑戦せねばならないのは自明なのではないだろうか?
社会を作る建築家に進化できるか?
「社会が建築を作る。」
それが、社会に最も利する建築や空間のあり方である。
という考えが今日の今日まであらゆる空間のあり方、人々の豊かさをドライブしていることは間違いがない。今の都市空間に一度足を踏み入れればそれは自分達の意志が介在して構築されているわけではないことは一目瞭然だ。つまりは、前項でも書いたように、その豊かさは鋭すぎる局地的な定義と一般解を押し付けている。
そこに現在の都市の苦しさの理由があり、その豊かさはいつまでも続かない。また、デベロッパー達が建ててしまった、おそらく数十年後は使えない構造物を回収するのは確実に私たちの世代なのである。
社会が建築を作る。という思想で駆動した空間の結末を現在の我々は目撃した上で、尻拭いを始めねばならないのだろう。
公共であれ,超高層であれ,資本主義の隷になり下がってしまった今生み出されている多くの建物は,瞬く間に忘れ去られていくだろう.クライアントとの閉じられた共感,マネーゲームに勤しむ人たちとの共感,なんの責任も取ろうとはしない人たちとの共感,そんな虚しいものにばかり血道を上げているのだから仕方がない.何かが欠けている.
建築は真の意味でピアソラのように大衆に開かれていない.
今の建築は,勇気をもってそこに橋を架け渡す意志に欠けている。もちろん私自身もだ.他者を断罪するつもりはない.このことについて,みんなで考えてほしいのだ.
現代美術集団であれば、Chin↑Pomが主張するように、都市的な公共性は実のところ完全に失われているのは自明でありながらも、その違和感は潜在的に人々に作用している様に思う。
だからこそ、人々がメタバースやWeb3のような物理的な経済圏の外に、自律した新たな秩序の中に可能性を見出すのは、マネー的な意味以上に理解できるし、自分自身も可能性を感じている。
問題意識はそこにあるとして、では建築家をどう進化させていくのか?が個人的には大きなトピックである。
自分はもう一度、戦後国家をデザインする建築家であった丹下健三の世代のような建築家像を捉え直す必要を感じている.
しかし、それは役割としての捉え直しである。
丹下健三の世代のような建築家像をもう一度トレースするわけではない。これからの建築家とはフィジカル空間の世界線に閉じた存在ではないし,未来的な社会デザインすらも再検討し,テク、ロジーと人間のバランスをも設計するような建築家である。
そして、その未来的な姿を実現するためにある意味ではアクティビズム的に振る舞う存在としての建築家である。
立ち戻ると、建築家にとって建築空間を作ることは、自身がイメージした未来の社会の姿を表現する手段であった。施主の要望に応え、商業的に売れる空間を作ることではなかったはずで、未来を具体的に妄想し、イメージを作る技術であり、よりよい社会を作ろうとする姿勢であった。
その具体性を極端に昇華すると、それは未来を示唆する芸術となった。
ゆえに、建築家には未来を具体的に想像し、社会に伝えていく力があるはずであり、その様な新しい建築家像を諸先輩方、そしてあらゆる世代とみんなでこれからの社会という建築と作り上げていきたいと思うのが個人的な願いだ。
(このような唱え方をすると、ときたま教授陣の方々には疑問符をつけられることも多々あるが、バックミンスター・フラーが建築家であると、なかなか認められなかったのと同様なのかもしれないとも解釈できそうである。)
A designer is an emerging synthesis of artist, inventor, mechanic, objective economist and evolutionary strategist.
デザイナーとは芸術家,発明家,機械工,客観的経済学者,そして進化論的戦略家の突如現れる合成者である.
乗り込み、溶かし、そして変出させる
とは言いつつも,今の建築家に社会が求めているのは、個別具体な建築空間を設計することと商業建築を作ること、そして少しばかりの公共建築のみだ。
残念ながら、その様な仕事はギリギリ40代前後の建築家が受けることができるが、20代の我々には下働き以外にできることがない。(残念ながら)
しかし社会は仕切りにトランジションをしようと胎動している。トランジションの先ではおそらく、建築家が建築するものの姿すらも異なっている。
そのようなタイミングにおいて、権威的な建築学は緩やかに変化して金ばんらない。建築は社会に対して強い力を持っているという建築学問範疇の論理は崩れ去ろうとしてる。その枠組みから死に物狂いで脱しないといけない。
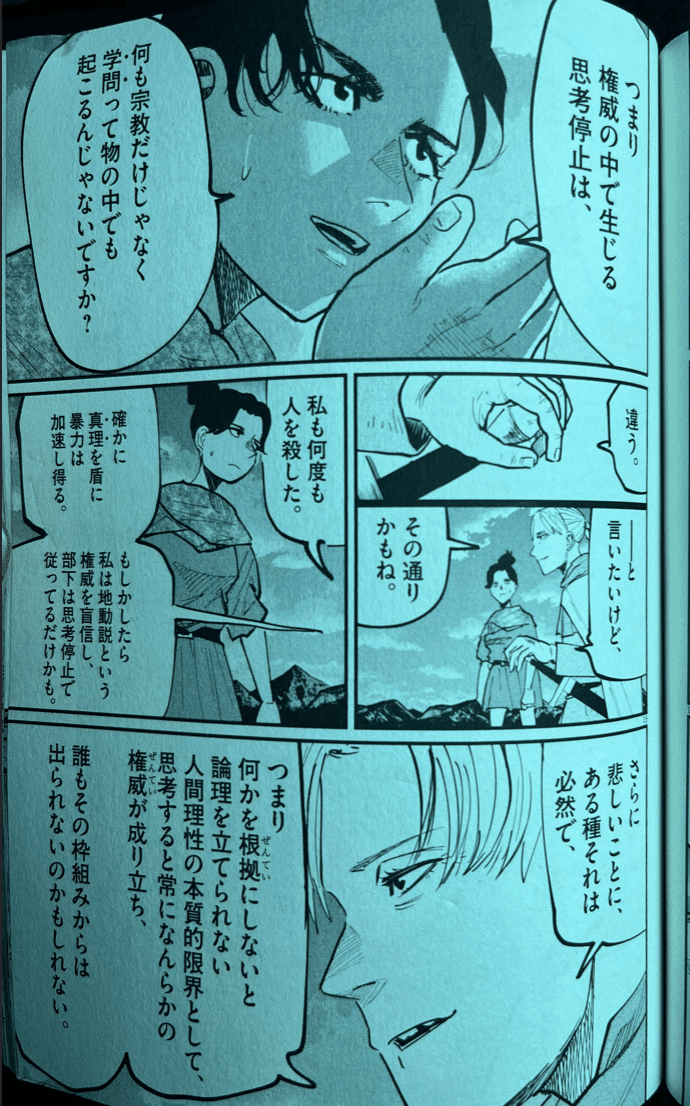
そこへの一手として、我々は業界に閉じ困らずに業界の外に出て、然るべき時までその境界を溶かし続け、建築学を実践の中で変出させることなのではないか?と考えている。
そしてその解き方は、重松象平が言うように、テックスタートアップに答えがあるような気がしているのだ。
そういう時代だからこそ、建築家は社会的な価値を生み出す存在として発言していかなければならないと思うのですが、いま実際に社会のムーヴメントをリードしているのは、テクノロジ―系のスタートアップですよね。思想とビジネスが連動しているからだと思いますし、あそこまで非物理化しないと、社会的な価値につなげていきづらい時代なのだとは思います。
そんなシリコンヴァレー系の人たちが、ようやく肥大化した都市の課題について関心をもちはじめています。これまで都市というのは、人間性の対極にあったと思うのですが、テクノロジーを活用することで、人間の生理的なものにこまやかに対応できる都市ができそうな気がします。しかしそれを実現するためには、建築だけではなく、バイオロジーやナノテクノロジーをはじめ、さまざまな分野が集まって取り組んでいかなければなりません
自分がテックスタートアップで働き、XRに若い建築的視点を介入させた時に何が起こるのかを自己実験しようとしているのもその一環であり、建築という社会や世界への姿勢、そして感性のあり方を、技術革新を考え多額の資金が集まるテックスタートアップに溶かしていけないかと考える。
そして溶かした先で固め直し、新たに建築家像を導き出せないかという気持ちがある。
そこにこの2年充分な挑戦していきたい。
最後に、中谷礼仁が寄稿されていた一文を残しておく。
世界平和を望み建築を作り続けた吉阪隆正のように、その弟子の内藤廣のように、先端を盲信的に作るのではなく、底なしの社会に底を作ること、つまり広い意味での公共を意識して建築の変出に挑めないだろうか?
心では彼らの系譜の延長に自分をおき、建築を模索して行こうと思う。
条件の矛盾を統合的に解決することから、新しい建築の姿、そして社会を信じて、あらゆる技術性を保持しつつ待機することだったのではないだろうか。立場はそれぞれ違うけれども根っこではそれが共有されて、建築がかたちづくる社会の素地が徐々にでも社会に回復していくこと。そうして底なしの世界に建築という底を作ることが託されていたはずではないか。そう考えると、建築界に身を置く一人として身の引き締まる思いがする。
終わり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
