
【脳機能から解説】やる気を引き出し行動を変えるための動機付けの科学
こんにちは!
イクサポです!!
今回は、『動機付け』について見ていこうと思います!!
現場で指導していると、こちらが提示したプログラムをやる気なさそうにやっている選手に遭遇します。
また臨床においても患者さんがリハビリテーションに意欲的でないことは多々あるでしょう。
こういう選手に対しては頭ごなしに怒っても良くなることはありませんし、患者さんにいくら『頑張りましょう!!』と言っても頑張ってはくれません。
それを改善するには、動機付けが重要になります!!
この動機付けには、脳の報酬系という部分が非常に大きく関わっています。
今回は、脳の報酬系について神経生理学的に見ていきながら、動機付けの仕方について解説していきます!!
それではいきましょう^^
脳報酬系に関わる脳領域
脳報酬系は、中脳の腹側被蓋野(VTA)に存在するドパミン細胞から、線条体の側坐核(NAc)や前頭葉へ投射する経路です。
VTAのドパミン細胞から放出されるドパミン(DA)がNAcに作用することで、快情動や意欲、学習の強化に影響を与え、自主的な行動選択や意思決定といった、リハビリテーションを行う上で重要な要素に影響を与えます。
このように、脳報酬系はドパミン細胞から放出されるドパミンが重要なファクターとなっているため、ドパミンシステムとも呼ばれます。
まずは、脳報酬系に関わる脳領域とその機能を見ていきましょう!
(1)前頭葉
前頭葉は主に、1次運動野、補足運動野、運動前野といった運動の表出に関わる部位と、認知・情動のコントロールを行う前頭前野(PFC)に分けられます。主に、運動や行動に関連した情報を表現し、行動の制御に関わることが知られています。
補足運動野と運動前野は、合わせて運動連合野と呼ばれ、運動のプログラム形成を行っています。そして1次運動野は、運動の出力を行う部位です。
PFCはさらに、
・背外側部
・腹内側部
・眼窩部
の3領域に分けられます。
背外側部は注意機能やワーキングメモリといった認知面の機能を有しています。一方、腹内側部と眼窩部は情動のコントロールを担っています。
背外側部と腹内側部・眼窩部の活動は互いに拮抗しており、どちらか一方が活動すると、もう一方の活動が抑制されることが分かっています。
例えば、「痛み」に注意が向くほど(背外側部の活性化)、情動のコントロールが難しくなる(腹内側部・眼窩部の抑制)といった具合です。
(2)側坐核
NAcは、大脳基底核の1つである線条体の前方部分に存在しています。
NAcは主観的な価値(与えられる報酬の価値など)を表現する部位で、脳報酬系において中心的な役割を果たします。
(3)中脳腹側被蓋野
VTAは、欲求を満たすための行動の動機づけに関しており、脳報酬系を形成するドパミン細胞が多く存在しています。このドパミン細胞は、期待していた結果と実際の結果の誤差に合わせて活動量が変化するとされています。
この期待していた結果(報酬)と、実際に得られた結果の誤差は、
予測誤差と呼ばれます。
期待以上の結果が得られれば、つまり、予測誤差が正の方向に大きい場合、ドパミン細胞は活性化し、その軸索終末から多くのドパミンが放出されます。
一方、期待よりも報酬が少なければ、つまり、予測誤差が負の方向に大きい場合、ドパミン細胞の興奮は抑制され、軸索終末からシナプスへのドパミンの放出量も少なくなります。
脳報酬系の仕組み
それでは、上述してきた脳領域がそれぞれどのような繋がりを持ち、脳報酬系を形成しているのか見ていきたいと思います。
ここから先は

Physio365〜365日理学療法学べるマガジン〜
365毎日お届けするマガジン!現在1000コンテンツ読み放題、毎日日替わりの現役理学療法士による最新情報をお届け!コラム・動画・ライブ配信…
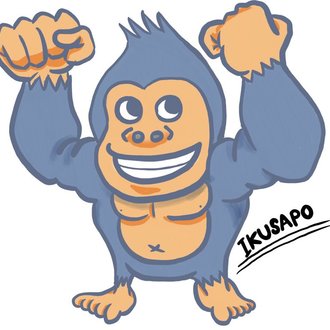
PITTOCK ROOM
サッカーコーチ・指導者のために作ったフィジカル特化型マガジン!! 育成・大学・プロの場で活躍する現役フィジカルコーチの3人が毎週更新して…
育成年代のフィジカルサポートの環境改善に使わせて頂きます!🙇 皆さんの力で日本サッカーを発展させて行きましょう🔥
