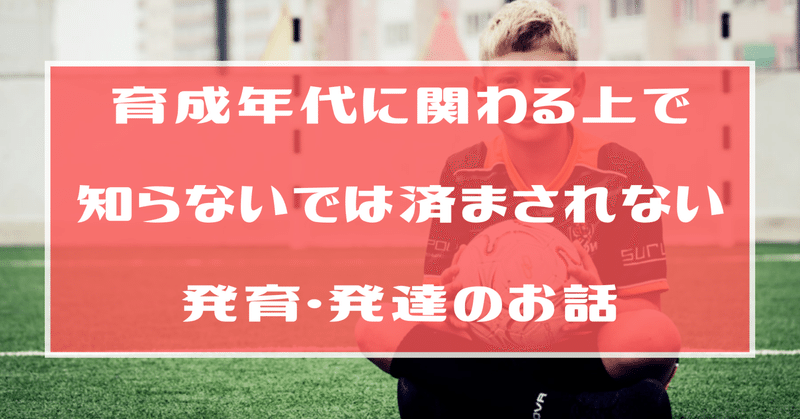
育成年代に関わる上で知らないでは済まされない発育・発達のお話
こんにちは!
イクサポです!
今回は、僕が関わっている育成年代において特に重要な
発育・発達
について書いていこうと思います!
長くなるので、いくつかにわけて書いていきます!
育成年代に関わるトレーナーや指導者は絶対に知っておいてほしい内容ですので、読んでみてください!!
それではいきましょう^^
発育と発達とは?
一般的には「体の成長」と簡単にまとめてますが、成長は二つに分けられます。「発育」と「発達」です。
シンプルに言うと、
発育=体が大きくなる(量)
発達=体の機能が高くなる(質)
つまり、体が大きい(ガタイのある)ジュニアは「発育がいい」となります。
一方で、体の大きさは並ですが、すごく洗礼された動きやいい体力を持つジュニアは「発達がいい」となります。
この二つはイコールではありません。
それをこれから説明していきます!
ゴールデンエイジ理論の誤り
いきなりですが、スキャモンの発育曲線というものがあります。日本では有名なので、知ってる方も多いのではないでしょうか。

横軸は年齢、縦軸は発育の割合を示しています。
よく言われる「ゴールデンエイジ理論」はこの曲線が根拠の一つになっています。
ゴールデンエイジ理論は有名ですがかいつまんで言うと、9~12歳前後は神経系が発達しやすいので、この時期にスポーツすれば上手くなる!!
みたいなやつです。
上の曲線を見ると、確かに神経系は12歳くらいで100%に近くなります。
なので、一見スキャモンの曲線や、それが元になったゴールデンエイジ理論は素晴らしく思えるかもしれません。
しかし、ここでさっきの「発育」と「発達」の話が出てきます。
スキャモンの曲線というのは、正しくは
【スキャモンの「発育」曲線】
と言います。
これは発育です。体の大きさです。
この曲線はもともと、スキャモンっていう方がいろんな年齢の人を解剖して、それぞれの臓器の重さを図りで測るという方法で調べました。
つまり、上の図のグラフは「量」であってそれを上手く使えるか(=質的な発達)とは別の話です。
これが、近年のゴールデンエイジ理論が否定的に見られている理由の一つです。
じゃあ、ゴールデンエイジ理論は間違ってるのか?
幼少期に練習しても上手くならない?って思うかもしれませんが、そうでもありません。
実際に神経系は量も質も13歳ぐらいまでに80%は出来上がると言われますし、現場で見ててもこの時期が一番上手くなると実感しています。
もう一度、スキャモンの表を見てみましょう。

黒点線の6~12歳の成長期までは、神経系がもっとも発育する時期(黒○)
赤の点線は一般型(筋骨格や心臓、呼吸器系)が発育する時期(赤○)で、これは成長期の時期に相当する、という感じです。
以下は、上記を踏まえて考えるそれぞれの時期に行うべきトレーニングについてまとめると、
ここから先は

Physio365〜365日理学療法学べるマガジン〜
365毎日お届けするマガジン!現在1000コンテンツ読み放題、毎日日替わりの現役理学療法士による最新情報をお届け!コラム・動画・ライブ配信…
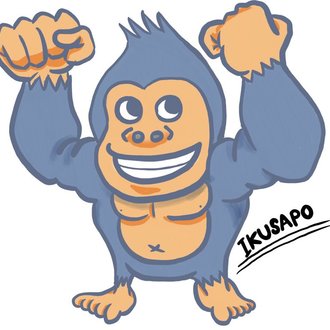
PITTOCK ROOM
サッカーコーチ・指導者のために作ったフィジカル特化型マガジン!! 育成・大学・プロの場で活躍する現役フィジカルコーチの3人が毎週更新して…
育成年代のフィジカルサポートの環境改善に使わせて頂きます!🙇 皆さんの力で日本サッカーを発展させて行きましょう🔥
