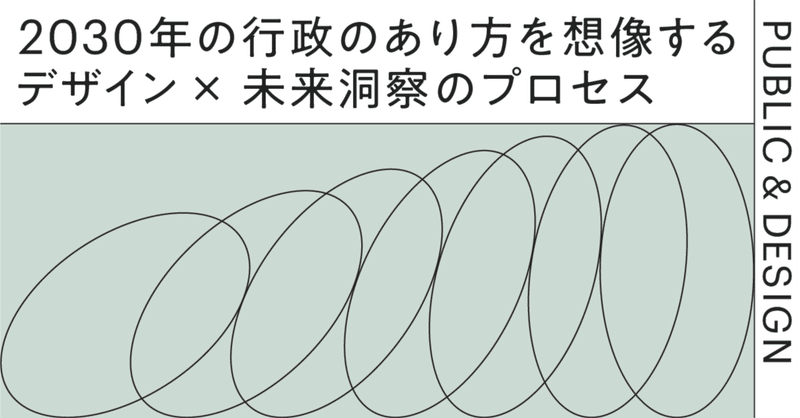
2030年の行政のあり方を想像する、デザイン×未来洞察のプロセス
行政のあり方は、未来においてどう変わりうるのか?
ー10年後の行政は、いったいどうなっているのでしょう。
フェイクニュース、政府の信頼度の低下、データプライバシーと監視など、いろいろな問題が議論される現代。一方では、AIの発展やソーシャルメディアによるコミュニケーションの変化、デジタルプラットフォームを通した市民の参画など新しいテクノロジーが統治のあり方に影響をあたえていたり、市民の私的な関心と行動からクリエイティブなプロジェクトが生まれたり。
はたして、これら多様な変数はいったいどんな行政や民主主義の未来の可能性につながるのでしょうか。その未来では、政府や市民の役割はどのようなもので、互いの関係性はどうなっているのでしょう。
こうした問いを探索するために、EUではThe future of government 2030+と称して、市民・民間企業・政府間の関係の変化とガバナンスの新しいモデルを描き、対話を行い、今後の行政運営へつなげるためのリサーチプロジェクトを立ち上げました。プロジェクトは、デザインと未来洞察(Foresight)のアプローチおよび参参画の手法(ワークショップ、フォーカスグループ、オンライン討論会など)を組み合わせながら進めました。今回は、このリサーチの進め方および最終的にどういった未来の行政モデルが描かれたのかを詳しく取り上げます。
なぜ未来の可能性を描く必要があるのか?
まず未来を描くことの意義とはなんでしょうか?未来学(Futures Studies/futurology)という学問の重要性はとても高まっています。未来学者のMilojeveicによれば「未来」はまだ決定されていないが、部分的には人々の現在の選択や歴史、社会構造、現実に起きていること、などなどにより影響を受けます。とはいえ、ひとつの未来の外側には、幅広い未来の可能性が横たわっています。
そして「想像上の未来」は現在のぼくたちの精神状態や行動、感情へと影響をあたえます。例えば「AIが仕事を奪う」という言説は、ひとつの未来のイメージですが、これにより不安を煽られ、
「AIに代替されないような仕事に変えよう」
と考えるかもしれません。もっと身近にかんがえると、
「5年後には和菓子屋をやりたいからまずは弟子入りするんだ!」
「今日の夜には焼肉を食べるから、お昼はすこしあっさりしたものにしよう、蕎麦の機運が高まってきた」
というのも未来に影響された考えです。
ぼくたち一人ひとりが前提として描いている未来は、いまの行動をかたちづくるのですが、問題は気づかないうちに"未来はこうなる"とひとつのイメージに縛られてしまうことです。それはイメージの外側にある多様な可能性を捨ててしまうことになり、もっと望ましい状態があるかもしれないのに諦めて現実を受け止めしまうから。
なので、いかにあらゆる可能性に想いを巡らせるかが重要です。近年の未来学では、可能な未来というのは往々にして実現可能であったり既存の想定・前提に囚われるものになるため、「あり得ない未来」を描くくらいに外側へ飛び出てから戻ることが唱えられています。

参照: Voro(2003)のFuture Cones: On examining Preposterous! futures
その可能性・不可能性を描いた上で何が望ましい未来なのかを考え、現在の行動や感情にポジティブな影響と希望を生み出す。これが未来を描く意義となります。
実際に、多くの政府では未来を描くちからを政策や公共サービスに活用するための機関を設置しています。シンガポールでは、首相直下に政府全体の未来シナリオに基づいたプランニングや調整をおこなうCenter for Strategic Futuresを置いていたり、エストニアの議会では長い時間軸で未来を捉え、機会やリスクを洞察するためのForesight Centerが存在します。
このロジックに則り、行政のもつ影響力の大きさを考えれば、現実に直面する民主主義・ガバナンスの崩壊を乗り越える希望を生み出すことは、誰しもの生活に関わることです。The future of government 2030+で描かれる未来は、そうした希望と変革のドライバーとしての役割を果たすかもしれません。
2030年・未来の行政プロジェクト
The future of government 2030+のプロジェクトの概要は以下のようにまとめられます。
何をやる?:未来の行政府を思索する
なぜやる?:急速な変化や行政/民主主義の直面する問題に対し、必要な政府の要件を特定して、民主主義やガバナンスを再考する
どうやる?:デザイン・未来洞察のアプローチを用いて、生活者を含めた多様な人々と協働する
この骨格の下、6つの異なる国(オーストリア・アイルランド・マルタ・ポーランド・スペイン・スウェーデン)の政策研究室やデザインスクールの支援を通じて、市民、企業、市民社会組織、政策立案者、公務員などと、未来の政府の可能性についての議論を誘発して最終的には学びと行動の指針へとつなげました。これらの国は、異なる政治的な伝統やガバナンスの文化、人口や地理的サイズ、政府への信頼度、市民参加の度合いといった視点から、多様性を鑑みて選ばれたそうです。
全体プロセスとして、5つの段階に沿って進めていきます。

ここから、プロセスの流れのままに、描かれた未来の行政シナリオとともに、詳しく見ていきましょう。
Step0|トレンドの把握
「未来洞察(Foresight)」というアプローチでは、今現時点で起きているトレンドや、兆し(まだ一般的ではないが、これからの未来に対して主要なトレンドになりうる可能性を示唆するイベントや出来事)、主要な議論をリサーチします。これらの情報が、未来の行政システムの進化や、市民と政府の関係の変化の理解に役立ち、この次のステップである市民とのワークショップ設計や、未来シナリオの素材にもなります。
主要なトピックとしては、一例としてこんなものが取り上げられています。
・オープンガバメントの実態
・市民参加の尖った事例(ex アイスランドで1000人近くのランダムに選ばれた市民が憲法の草稿づくりに関わる)
・民主主義におけるポピュリズム
・リキッドデモクラシーなど新しい形式
・市民のアクティヴィズム
・テクノロジーによるリスクや新しい機会(ex: データプライバシー・フェイクニュース・アルゴリズムの政治性...)
Step1|市民との対話
リサーチを終えたあとは、市民を中心とした半日のワークショップを1年にかけて行いました。1回の参加者は15-40人ほどで、計150人以上の市民が参加したそう。すべてのワークに最低一人ずつ、行政と民間企業からも参加者をおくことで、意見の交換を促しています。
ワークショップの目的は、政策決定や公共サービス提供の分野における、市民、政府、その他のステークホルダーとの今日的な関係を理解・マップ化し、将来起こりうる関係性や相互作用に対する市民のイメージ、期待、恐怖、理想などを探ることでした。
ワークショップは、参加者にとって重要な現在の課題を特定することから始まりました。例えば、フェイクニュース、移民問題、若者の失業、データ管理、公共交通機関、若者の参加、生活の質、サービスの提供などなど。この特定のテーマが足掛かりとなって具体的な話ができるようになります。いきなり未来の行政のかたちを描いてね、では「いや、わからんし..」となるのがオチです。
次に、特定された関心事に基づいて、異なるアクター間の力関係についての洞察や理解を生むために、ステークホルダー・マップを作成しました。

The Future of Government 2030+ レポート
次に、15年前の主要な出来事を探ったり、様々な未来の映像を見せたりして、15年後に何が起きているのかを想像しやすくすることで、参加者に未来への没入感を与え、未来ペルソナとユーザージャーニー(起こりうる未来の物語)を描きました。

The Future of Government 2030+ レポート
これを元に、最終的には未来のアクターの関係性の変化をを描いて、そのための変化のキードライバーを特定し、政府への重要思考の提言をつくるところまでを行ったそう。
ワークショップのアウトプットや出てきた議論自体が未来シナリオを描くための材料になります。というのも、希望・欲望・恐怖から生み出された物語は、参加者の過去の理解、現在の認識、未来の想像力を反映しているので、分析にかけることで、望ましさなどを炙り出していけるのです。出てきた物語は、たとえば政府の役割・市民と行政の関係性・テクノロジー・経済・政策規制..などを切り口にグループ化および再構築されました。
Step2|シナリオの構築
ワークショップで得られた豊富な定性データは、2030年以後の行政の4つの未来シナリオへつながりました。このシナリオは、未来予測ではなく、あくまで可能性を提示することで新しい政府の役割やありかたに対して議論を生み出すための触媒です。重要なことは議論を経て、「望まない未来を避け、ほしい未来を引き寄せるために、今日のより良い意思決定がどのように可能か?」を問うことであり、シナリオをつくりっぱなしでは意味がありません。では、どんな未来の可能性が提示されているのかを、簡潔に見ていきましょう。

The Future of Government 2030+ レポート
Step3|未来の行政府のコンセプト設計
上記のシナリオを出発点として、個人と政府との未来の関係性についての具体的アイデアを展開していくために、6ヵ国のデザインスクールから100名以上の学生とリサーチャーが参加しました。特に学生ら若い世代は未来の政府を考える上で重要な主役であり、彼らを中心に40ものコンセプトが生み出されたとのことです。
例えば、Rebirthは、民間企業が運営する「グローバルな移動を可能にする」データ駆動型のシステムです。公式の書類を持っていない違法難民・移民が法的に入国できる手段を提供し、運命を変える力を与えてくれます。政府はこのシステムを管理するために民間企業と提携しており、運営企業は、移民を雇用する需要に合わせて移民を移転させます。また、新しい国での基本的な生活必需品への支援や提供を行い、社会インフラとの統合を管理する。政府は、移民の流れを監視するためのデータトラッキングと引き換えに、プログラムに登録された人に合法的な市民権を保証する、というものです。


Rebirthのストーリーボード
または、もしAIのサポートのもとで、市民が未来の意思決定に完全にアクセスおよびコントロール権をもっていたら?という問いのもとで、最終的にはSherlockという、市民の投票やそれぞれの意思決定によるリスク・影響・利益を予測するシステムのプロトタイプを構築・提案も見受けられます。

レゴでユーザージャーニーをプロトタイピング
様々なデザイン学生の提案の結果、多くのコンセプトは、今日の課題を解決するものであると同時に、まだ見ぬ社会問題を想定したものでした。既存の価値観・あり方に提起を行い、物語や道具に落とし込むことで議論を誘発したり、未来の課題に対する視点を多様化する手段としてデザインを活用することがデザインアプローチを用いた有効な点であったとまとめられています。
Step4|対話のためのツール制作
重要なのは、一度未来の物語をつくり、議論し、終わる。ではなくて、継続的な議論と洞察を海続けることです。そのために、プロジェクト終了以降も、多くの人が活用できるような、対話とリフレクションのためのツールを開発することが重要でした。そのため、立場の異なる人々が協働と"未来に没入"することで議論が誘発されるボードゲームを作成。ゲームにはルールがあるので、そのルールをうまく設定すれば、プレイヤー間のやりとりも活性化できるかつ、成果報告のレポートは読む人は限られるため、よりカジュアルに能動的な参加を生み出す方法として適しています。

ゲームのプレイイメージ
上述の4つの未来シナリオにもとづいて、プレイヤーはアクションカードと役割カード(政府・インフルエンサー・市民・民間企業)を配られます。役割カードをもとに、国籍や年齢、価値観などのプロフィールを想像して記述していったうえで、未来シナリオに抱くそれぞれの信念や期待を共有します。架空の人物や自分と異なる立場の人間の視点からロールプレイ(演じる)を交えて、未来の対話を行うというのが主旨です。
このFuture Goveゲームについては、遊びと民主主義の記事にも紹介しているので、そちらも合わせてご覧ください。
Step5|未来の行政府についての対話
欧州委員会で開催される公的なイベントで各国の政治家、NGO、シンクタンク、学識経験者、関心のある一般市民を集め、プロジェクトの成果発表とその意味についての対話を行い、プロジェクトは終了となりました。
最後にいくつかの洞察や政策への提言やもいくつか述べられています。
例えば、伝統的な形式を超えた市民の関与が重要であり、これを念頭に置いた行政のリデザインをすること、その際にEnabling Environment=参加・協働・創造を促すルールやサポート、透明性あるプロセスや環境を整備することが必要だと述べられます。
また、政策提言のひとつとして、未来に向けた新しいリテラシーを育むことが重要だと述べられています。例えば、"未来のリテラシー"は市民が先の見えない中で意思決定を行い、不確実で複雑な文脈を認識し、この状況下で社会のレジリエンスを構築に向けた協働に必要です(参考: フューチャーズ・リテラシーとは)。デジタル化する世界で、社会として個人としてデータに操作されたり、自律を取り戻すために日常で利用するデジタルサービスの可能性および危険性をよりよく理解するデータリテラシーも必須。また多様な情報が溢れメディアの信頼性も低下するなかで、批評的な思考も育まれるべきです。こうした観点と共に、新しい市民のあり方を耕していくことも求められます。
おわりに
EUとしてのリサーチプロジェクトとして、デザインや未来洞察、市民関与のアプローチを交えるプロセス自体が非常に実験的であったと思われます。従来の専門家・シンクタンクに閉じて作成される、トレンドから"予測"した現実の延長上の未来シナリオとは異なり、実際の生活者の期待や欲望、不安といった側面から可能性として物語を描き出すこと、それを提案と具現化をして対話に結びつけることが肝でした。ゲームを作成した部分からわかるように、敷居をさげる&遊びをもたせることで、多くの人の参加を促すことも、学ぶべきポイントでしょう。
ただ私見としては少し抽象度が高く、行動に結びつくレベルでまとめられたのではないかと感じ、少々残念にも思いました。未来を描き、対話から協働で学びを生み出し、最終的には望ましい未来に向かって「何を変えるのか、そのためにどんな一歩を踏み出すか」に繋ぎ込まなければ、どんな未来も絵に描いた餅になってしまいます。
本マガジンでは公共×デザインの記事を定期的に更新しているので、よろしければマガジンのフォローをお願いします。また、遊びやゲームの活用に関して・またはその他なにかご一緒に模索していきたい行政・自治体関係者の方がいらっしゃいましたら、お気軽にTwitterのDMまたは📩アドレスpublicanddesign.pad@gmail.com宛にご連絡ください。
追記
政策の提言および実施については別途レポートが出ていましたので、こちらも参照ください。
Reference
European Union, 2019. The Future of Government 2030+: A Citizen Centric Perspective on New Government Models.
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115008/futurgov_web_lq_v2.pdf
Rebirth https://www.servicedesignmaster.com/futuregov2030/rebirth.html
Yoo, P. 2018. Open Democracy in Hyper-Egovernment https://www.poorumeyoo.com/future-of-government-2030
Twitter:より断片的に思索をお届けしています。 👉https://twitter.com/Mrt0522 デザイン関連の執筆・仕事依頼があれば上記より承ります。
