
学ぶということについて考える
こんにちは。臨床心理士/公認心理師/精神保健福祉士のまりぃです。
大学院を終了してまだ一桁年の若輩心理職で、臨床心理士試験・公認心理師試験のダブル受験生応援公式LINEやtwitter、Instagram、YouTubeを運営しています。
今までの公式LINEの動画はこちら
大学生だけでなく,公認心理師試験を受けた人にも読んでほしい
先日,某通信制大学の学生さんの勉強会にお呼ばれしましたので,その時話したことをちょっとまとめておこうと思います。というのも,私は,理系の大学を休学,復学,休学からの中退という挫折経験のあと,通信制大学で精神保健福祉士のコースをとって学士を得ました。通信制大学の先輩でもあるわけですね笑
勉強会を主催している方に「通信制大学でどうやって勉強するんですか?」と聞かれて,答えを考え……はて……と考え込みました。

考えすぎるのが私の良いところ!
ねえ,そもそも
「勉強」ってなんですか?
昔の人は,自分の生まれた立場に見合った能力とその立場を運営していくための知識,技能があればそれで良かったわけです。農民は農作業に必要な知識と技術があれば,殿様は領地を運営するための知識と技術があればよかったし,それを身につけることが「勉強」でした。
でも今は,世の中が複雑になって,先人の知識も文明技術もたんまりあるので,「日本では,みんな最低限これくらい知っておこうね」という共有知識,日本に住む者同士が共通の常識をもって会話するための土台として,義務教育があります。加えて,試験で好成績を収めて有能さを示せば,(経済的に)良い条件で働かせてやろう,というシステムもできてきました。
だからでしょうか,みんな「勉強」というと「知識のコレクション」をイメージします。数学であっても「解法の仕方」をたくさん覚えて,その技術をいかに組み合わせて数学を解けるか,の競い合いがおおむねで,イチから自分で解法を考えるなんて入試は,数えるくらいの大学でしか行われていないのではないでしょうか。
しかし……果たしてそれは「勉強」なのでしょうか。
「大学で学ぶのは,知識ではない,視点である」
先日知り合いの大学教授が,高校生向けに作っていたスライドの中に,こんな(感じの)言葉がありました。
なるほどそのとおりだな,と思いましたが,しかしどれだけの大学生がこの言葉を実践しているのかは疑問です。
失礼ながら多くの大学生は,なんとなく大学に行って,課題をこなして,単位のために「知識」をつめこんで(それは高校生までの勉強の仕方と同じ方法なのでしょう),単位をとって,卒業していくのではないでしょうか。
しかし,勉強という言葉には,知識のコレクションの他に,「視点を学ぶ」「考える」という概念も含まれていると思うのです。

つまり,勉強には「卒業・単位・試験のための勉強」の他に,「学問としての勉強」があるはずです。
さてここで,公認心理師試験を受けたあなたに質問です。
試験のために「勉強」したこと,学問として,活かせていますか?
あるいは大学生の皆さん,特に大学院進学を考えている皆さん。
「学問としての勉強」できていますか?
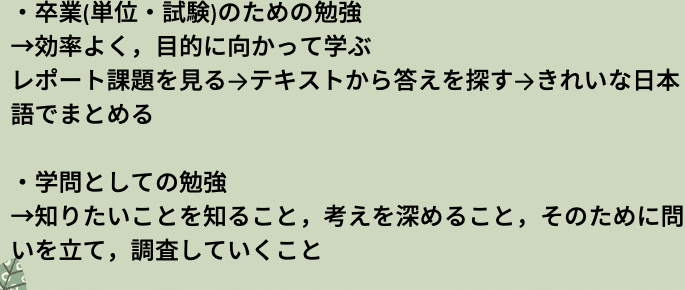
資格試験のためには,効率の良い勉強が必要です。
単位のためにも,効率の良い勉強が必要です。
それらは,大雑把に言えば,国語能力とでもいいましょうか,テキストを読んでどこが重要かを見極め,覚える,理解することができれば良いものです。そしてそれは,悪いことではなく,大切なことでもあります。
でも,せっかくの大学です。せっかくの公認心理師試験勉強です。もう一歩先「学問としての勉強」してみませんか?
学問としての勉強のために
ここで,学問としての勉強のために,私が普段やっていることをご紹介します。
まずは,思考を刺激すること。問いを持つことです。

この「問い」は言語化しておくことをおすすめします。
世の中には,AだからB,とか,A+B=Cというような明確な答えがあるものだけでなくて,「論拠は何?」「それとこれとはどうして矢印でつながるの?」「どうしてそのようにこの人は考えるのだろう?」「どうしてAとBには共通点があるのにAとCには共通点がないのだろう?」などなど,考えなければ分からないこと,時には考えて調べてもはっきりとして答えのでないことがたくさんあります。
だから,公認心理師試験のテキストをもう一度出してきて,あるいは大学生さんなら大学のテキストを,試験に出そうなところだけじゃなくてしっかり読んで,「なせ?」ポイントを探してみてください。
たとえば,ウェクスラー系の検査で○○では視覚からの能力を見られる,と書いてあったらそれを丸暗記するのではなくて,「なんで?」と立ち止まることです。〇〇の検査では聴覚だけでなく注意維持力を見られる,と書いてあったら,やはり丸暗記するのではなくて「なんで?」と考えてみてください。
私の読書方法
ここで,「なぜ?」ポイントを持つために,私が普段読書をするときの方法をお伝えします。
私は,思想系の本であれ,専門書であれ,娯楽書であれ,いつも100均の細ーい付箋をお供にします。そして

こんな感じで,心に引っかかったところ全部に付箋を付けて読んでいきます。
あとで,付箋のついたところを見直し,読書ノートに書き出すと完成。
書き出すとき,本文を要約したりせずにそのまま書くと,自分では作らない文章,作者の考えたままの文章をインストールできるので,写しながら違和感を感じたり,泣きそうなほど共感したり,自分の心がざわめくポイントが明確になります。
そしてそのポイントについて時間をとって考える……時間がなければ夜,ベッドに入ってから寝るまでの間とか,歯磨き中とか,電車の中とか,ちょっとした時間にぼんやり思い返すと,思考が刺激されます。
立体的な思考を持とう
こういった学問としての勉強をすることで,知識が深まり,立体的になり,Aという分野とBという分野がつながって,ああ,こういうことか!が分かってきます。
だから,どうか,公認心理師試験,合格して終わり,にしないでください。各種検査などの勉強会に行って「AだからB」と覚えて帰ってくるのではなくて,あるいは「今すぐ役立つ解決方法」を求めて勉強会に行くのではなくて,「考えること」「視点をもつこと」をしてほしいなと思います。それがきっと,ひいては,あなたの目の前のクライエントのためになるでしょう。
予告
自己研鑽専用 新公式LINE鋭意準備中です。
お知らせは公式LINEよりまもなく!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
