
丸和運輸機関(東証プライム/9090) 株主総会レポート 2022/6/27
東証プライム上場の丸和運輸機関の株主総会に出席しました。株主総会の様子について、当記事にてご紹介したいと思います。なお、当レポートは私の心証に基づき脚色されており、意図せず誤認している可能性もありますのでご容赦頂ければと思います。また、同社の株式売買を推奨するものではございません。ご指摘、コメント等ございましたら、ぜひ私のツイッターアカウントより頂ければ幸いです。

1.参考記事
まず同社の関連記事についてご紹介したいと思います。ここでは昨年の株主総会のレポートと、直近の決算の内容を受けたメモの記事となります。
2.基礎情報
それでは、当日の総会運営の基礎情報からご紹介します。まず全体の流れとしては、今年も株主総会と新中期経営計画の説明という2部構成でした。コロナ禍の下、信託銀行さんの定型的なご指導があってか、来場自粛が呼びかけられていましたが、説明はきちんと尽そうという姿勢が後退していない点はいいなと思います。既にコロナ禍とはいえ、withコロナになりつつある中で、説明会を相変わらず中止にしたり、審議の時間を大幅に削減するという会社さんも未だにありますからね。
当日の大まかなタイムテーブルは以下の通りでした(手元の時計の大まかな測定のため、あくまでイメージとして捉えて頂ければと)。
10:00 開会の前の挨拶 (和佐見社長)
10:03 開会宣言 (和佐見社長)
10:05 議決権行使数の確認(事務局)
10:07 監査報告(田中監査役)
10:09 事業報告・対処すべき課題(ナレーション)
10:16 議案上程(ナレーション)
10:27 質疑応答(1人1回につき1問)
11:13 議案決議
11:16 閉会
~休憩~
11:28 新中期経営計画の説明(和佐見社長)
12:03 終了
2部の新中計説明会後にも質疑応答が予定されていましたが、時間が押してしまい、質疑応答の取り扱いがなく終了となりました、これはとても残念でした。昨年比は12:10~12:18で時間が押している中でも短く質疑応答を取り扱って下さったので今年も1,2問であればいけたと思うのですけどね。まぁこの辺りは様々な事情を勘案した事と思います。来年はもう少し後ろの予定を調整するか、全体の配分を工夫する等でより闊達な対話がなされる事を期待したいと思います。
それから議決権の行使状況についても確認しておきたいと思います。
■一昨年
・1,465人/4,172人(35.1%)
・599,802個/640,011個(93.7%)
■昨年
・2,598人/7,423人(35.0%)
・1,159,616個/1,259,791個(92.0%)
■今年
・2,651人/7,758人(34.2%)
・1,124,078個/1,260,308個(89.2%)
今年は株主数が微増に留まりました。一昨年から昨年に大きく増加しました。コロナ禍真っただ中でも業績、株価形成共に底堅かったですし分割効果もあったのでしょう。一方で、直近1年は株価も軟調に推移している辺りが影響しているのでしょうか。
そしてちょっと気になるのは、議決権の行使率です。元々同社では行使率が90%をずっと超えてきていたわけですが、今年は行使率が90%を割り込みました。当然、これでも高い行使率ですし何の問題もないのですが、株主側の状況にも何らかの変化があるのかなーなんて過りました。まぁ単なる誤差だと思いますが。
出席者の状況ですが、会場は80席程度の席が用意されていましたが、最終的に9割強の席が埋まっておりほぼ満席です(予備で用意されていた第2会場は映像からは使われてなかったようでしたので、ぎりぎりという感じだったかもしれません)。自粛を促されているのに集結してしまっていますね(笑)、まぁ私もその一人ですが…。今年も地元の方が多数でしょうか。時々おられる背広族の方は、取引先や金融機関等の関係者の方かもしれませんね。現役世代の個人株主も散見されますが少数ですね。どうしても平日の昼で、場所も少々不便なところでありますので参加がしにくいという部分もあるかもしれません。しかし、だからといって地元を蔑ろにするという発想はないでしょうから、こういう運営が今後も続くことと思います。それでいいと思います。
3.開会までの過ごし方
株主総会当日について書いていきたいと思いますが、まずは開会までの当日の過ごし方からです。前段が長くていつも申し訳ないのですが、今年はここがメインかもしれないので、少し詳細を書いていきたいと思います。
株主総会の会場は丸和運輸機関の本社です。東京本社は東京駅至近の利便性抜群の所にあるわけですが、創業地である埼玉県吉川市です。周囲は一面の田んぼ。そんな中に突如出現するテクノポリスと呼ばれる一角に、物流やセントラルキッチン等を備えた工場などが集積している場所があり、そこに丸和運輸機関の本社もあります。駅からのアクセスはバスで20分くらいで、株主総会用にシャトルバスが運行されます。このバスはこの地域の路線バスを運行するタローズバスです。もちろん、丸和運輸機関の桃太郎便(たろう)に由来しており、子会社になります。この地域のバス運行も司っているわけですね。

株主総会当日は相当の猛暑が予想されており、コロナ戻りで電車も混雑しており、更に総会後の所用も鑑みて、車で出向くこととしました。私は株主総会出席時は、いつも余裕をみて現地に赴くようにしていることもあり、この日も早朝に自宅を出ました。幸いにして道も空いており、なんと受付開始の9時まで1時間以上前の8時前についてしまいました(笑)。既に本社エントランスには看板が掲示されていて、スタッフの方が慌ただしく準備をされている様子でしたが、一度隣のコンビニに避難します。
この界隈は工業地域のような感じで、その一角にコンビニが唯一待機できる場所です。ここで朝食を買い込み、車の中で食べます。普段はなかなか聴かないFM局から流れてくる朝の爽やかな音楽に癒されながら時間が過ぎるのを待ちます。
質問は前日の夜に一夜漬けで原稿を書き上げていました。まぁ長年株主をやっていると、息を吐くように質問が思い浮かんできますからね(笑)。少しでも会社の励みになるような内容、あるいは建設的な対話の機会になるようなものを出来るだけ選定するようにしています。とはいえ、私の能力にも限度があり、いつも平凡な質問を重ねてしまうわけですけどね。いずれにせよ、そんなわけで、時間をつぶすといっても、音楽に身を委ねて、コンビニの値上がりを実感しながら過ごすだけです。
時間は8:30を過ぎました。受付は9:00ですから、まぁ5分、10分前に到着したとしても、エントランスでうろうろしていればいいだろうと、残りの時間をFM局のラジオで優雅に過ごすことにすればいいな、なんて皮算用をしていると、急な腹痛が襲ってきたのです。トイレに行こうとコンビニの店内にもう一度トイレを借りようと思ったのですが、なんと、トイレは貸出していないとの掲示が~(汗)。緊急時はご相談下さいとも書き添えられていました。今の自分の状況は緊急時なのかどうか思案します。このコンビニの横には丸和運輸機関の本社があります。逆にいればあとは工業地域なので、借りられる可能性のあるトイレなどありません。
コンビニに緊急事態を宣言してトイレを借りるか、本社に赴きトイレを借りられないか申し出るかの二択となります。悶絶の時間の始まりです(笑)。
コンビニの店員さんは、確か比較的若い女性だったな、そこに緊急事態を宣言しに特攻するのがどうしても躊躇われてしまい、ここは澄ました顔をして、本社に赴くことにします。当然、相変わらずの「いらっしゃいませ~!」の大声が至る所から発せられ、こんなに早くに参上してしまって、そして腹痛を抱える私に挨拶をして下さいます。元気のよい体育会系のお出迎えはありがたいのですが、何より私は今トイレを求めているのです。そして、インカムを付けたちょっと偉い人が、私に申し訳なさそうに、まだ受付が出来ないのですが・・・と恐縮しながらお伝え下さいます。はい、もちろん承知しています。そしてこんなに早くに参上してしまい申し訳ない旨と、トイレをお借り出来ないかお願いをしました。
もちろん、快諾してご案内して下さるのですが、準備に忙しなくされている受付スタッフの方々(主に女性の社員の方)全員が気合の入った「いらっしゃいませ~!」の爽やかな声で最大限の歓迎を受けながら、トイレにご案内~です(笑)。結果としてコンビニの女性店員に緊急事態を宣言した方がまだ羞恥は小さくて済んだかもしれません。受付する時も、あ、あのトイレおじさんだ、ってことになるわけですからね。なんなら、インカムで運営スタッフ全員に、受付前に株主様来場しトイレにご案内~なんて流されてしまっているかもしれません。まだ総会の受付すら始まってないのですが、メンタルはもう終了~って感じですね(笑)。しかし背に腹は代えられないわけです。
そんなこんなでようやく落ち着いて、トイレを後にして、まだ受付が出来ない事を承知しているので、一度エントランスから外に出てお待ちしています~とその偉い方に自らお伝えして外に歩みを進めます。その際も皆さんその場を後にする私に「ありがとうございましたっ~!」って挨拶をして下さります。本当によく教育されています。あ、こちらがありがとうございますなんでという体でペコペコしながら一度外に出ます。
※その節は早い時間に参上した私にトイレを貸して下さり感謝しています。
ようやく落ち着いたので、株主総会の看板を写真に撮ったりして、しばらくそこで待機をしていました。

すると、なんと!建物の奥からわざわざ降りてきてくださった和佐見社長がお迎えにきて下さいました。インカムで「トイレにご案内~♪」だけでなく、「まるのんさん(超早くに)ご到着~♪」までをシェアして頂いたのでしょうか(笑)。まぁトイレに辱められた分の代償としては十分過ぎる嬉しいお出迎えでした。
1年ぶりの再会でしたから、握手をして久々の再開をお互いに嬉しくご挨拶を交わす事が出来ました。そして再びエントランスの中へ案内して下さいます。再び「いらっっしゃいませ~」と熱烈歓迎を受けます(笑)。
同社は創業50周年ということで、エントランスの脇に大きな絵が掲げられたようで、その絵を紹介して下さいます。創業から現在に至る50年の会社の軌跡が一枚の大きな絵になっているということでした。創業時にトラックひとつで創業した時のトラックや様々な取引先さんや社員の皆様、そして今ではハイテクのセンターの様子までが並べられており、笑顔になれる写真でした。創業から苦楽を過ごしてきた和佐見さんからしてみれば、より感慨深いものである事も容易に想像できます。そんな和佐見さんからその絵を紹介頂けるなんて光栄過ぎますね。創業時のトラックのハンドルに見立てたオブジェクト等もあり、しばらくお話をしながら見惚れてしまいました。本当は写真にも撮りたかったのですが、何かそれも違う気がして、写真は撮りませんでした。ですが、創業50周年記念サイトみたいなのを簡単でもいいので作られて、第三の創業の基点として、こういう絵なども紹介して、より多くの人が共感をしてもらえるといいのかなと思います。あるいは来年の株主通信などにも紹介があるといいかなと思います。こういう軌跡を従業員の方、取引先の方、株主と多くの方から共感を広げられる事は、第三の創業にあたってもいいことだと思います。
その後、第二会場となる部屋の一席で総会開会前の慌ただしい中でしたが、ひと時、お話をさせてもらいました。ここではその時の話を書く事は控えますが、今後の丸和運輸機関としてより多くの方にエンゲージメントを築いていってもらえるような話題もありました。こういう近い距離でコミュニケーションが取れる事は、当たり前ではないことです。私のような弱小個人投資家へ耳を傾け、時間を割いてくれるのは、和佐見さんの人たらしさぶりあっての事だと思います。
また、今回和佐見さんは書籍を出されました。経営者が自らの歩みを出版する事をネガティブに捉えられる方もおります。上場ゴールならぬ、経営ゴールと捉える向きがあるからですね。ですが、私はこの本は財界の取材を通して経営論を書かれたもので、同社の泥臭さやご縁を大切にされた中で育まれた会社の強みの理解として、その内容を楽しみにしていました。本当は株主総会前に通読してから質問をこしらえればよかったのですが、怠け者のせいで、結局読む事なく株主総会当日になってしまいました。
そして、この本を大変ありがたいことに献本頂きました(※来場株主向けに会場で配布をされていました)。しかも、私の名前を付してサインまで書いてくださいました。感激ですよね。
※あくまで和佐見社長のご厚意に甘えさせていただいたものとなります。
このサインには以下のようなメッセージも頂きました。
同音同響
同じ響きの詩を
声たからかに歌おう。
このメッセージは会社の文化を示す部分にも記載があります。社長室にはこの「同音同響」の文字が掲げられています。和佐見さんが自ら作られた造語ですが、一貫してこの精神を大切にされ、社内にこれを根付かせてきたのでしょうね。「歌」が「詩」になっていたりしますが、基本的な考え方は変わりません。この言葉に込められた想い等もお聞かせ下さいました。
私のような能天気にサラリーマンをやりながらしがない家庭で日々を暮らす者にとって、このメッセージを理解しようと思っても、その一片を窺い知ることしかできません。想像力では乗り越えられないくらい、このメッセージに行きつくまでに様々な壮絶な日々があったものと思いますからね。安易に理解できると私などが思う事は憚られます。

私は経営者ではありませんし、これからも経営者になる器ではありません。しかし、こういう考えに触れる事は自分の価値感を拡げる意味でも大変勉強になります。企業文化に正解があるわけでもありませんし、その深度や在り方も企業によって様々です。
縁あって、株式投資を通して経営者の方ともやり取りをさせてもらう事がある中で、こういう様々な価値観に触れておくことは投資家としてとても大事な事だと私は思っていますし、人とのご縁を拡げ、深めていくためにも少しずつでも身近な経営者から学びを得ることは貴重な機会であると思います。
受付の時間となり、和佐見さん自ら受付へアテンドして下さりました。もうトイレの羞恥の事など、完全に忘れてしまう位に満たされていました。なんならもう今日はこれで帰ってもいいんじゃないか、くらいにお腹いっぱいお話が出来た事が嬉しかったのです。わざわざ私のために時間を作ってくれたり、様々な声に耳を傾けて下さったり、あるいは色々な考えを教えて下さったりと贅沢過ぎますね。本当にありがたいことです。株式市場は資本市場ですからお金がものをいう世界ではありますが、お金では買えない充足感が得られました。
受付で1番の番号を入手します。この受付表は持ち帰りOKとのことでしたので、ありがたく持ち帰ってきました。新ロゴも映えてますね。思い返せば、同社が上場して初の株主総会も一番最初に現地入りしました。だから何だって話ですし、多くの人にとって理解できない感覚だと思いますが、私にとってはとても大切な過去から現在までの流れなのです。

上場後、初めての総会に出席した時もレポートを書いていました。今読み返すと自分の視座も今とは違いますし、でもどこか通ずるものもあるような気がします。今に至るまでの寄り添いの基点になったところかと思うとまた感慨深いなと思います。
受付を終えて今度はトイレではなく、会場である6階へあがるエレベータに案内下さいます。その手前でお土産を頂きます。元々コロナ前までは終了時のお見送り時にお土産を頂いていたのですが、コロナ禍で帰りの蜜を防ぐためお土産も先に頂くことになっています。昨今お土産を廃止する会社さんも多い中、続けられていますね。あまりお土産だけもらって帰るというような方もおられないので、持続性があるのかなとも思います。
なお、お土産はいつも社員の方が真心を込めて詰めて下さっているのかギフト用の袋に入れて下さったもので、だいたいマツキヨさんのPB日用品が入っています。今年はマツキヨさんの製品が2品でしたので、例年より少なかったのは珍しかったですね。

会場は80席程が用意されており、最前列の机が配されています。その最前列の机に着席をします。着席をするなり、お茶の用意がある旨のご案内を頂いていたり、毎年懲りずに参上していることもあり、様々な方が私にお声がけを頂きます。年に1度しかお会いできない社員さんですが、こうやって今年もこの場で他愛もない事だったり、会社の状況を踏まえて対話が出来る事がありがたいな~と思うわけです。何より私の名前を覚えていてくれてお声がけ頂けるので、そのホスピタリティーにも嬉しくなるわけです。リッツカールトンのようなスタイルですね(笑)。
コロナ前は会場の横のロビーで茶受けと共に供される冷たい飲み物をたしなめながら、他の株主の方などと交流を持てるのもよかったのですが、コロナ禍になり残念ながらそういう機会もなくなってしまいました。そんな中、ある馴染みのある社員の方が私を見かけるなり、そういえば名刺をお渡ししていなかったと、お名刺を頂きました。窓際サラリーマンの私は名刺を交換するって事もあまり機会がないわけですが、それでも名刺を交換させて頂き嬉しく思いました。と同時に、もう少し自分の存在を名刺というものに託して自分を営業するという事も大事だなと感じたわけです。
開会まであと少しというタイミングで、今年も「失礼しますっ!」という大きな声で和佐見社長が役員席へと登壇されます。この頃には座席はほぼ全部埋まりました。幸い、第二会場までを使うまではいかず、ぴったりくらいだったようですね。いよいよ総会が始まります。
4.議事進行
さて、ようやく総会が始まりました。もうここまでお読み頂けた方は希少でしょうし、あまりの前段の長さにウンザリしてこの章に飛んできた方も多いかもしれませんね。ですが、既にこの日の総会のハイライトは終わっています(笑)。前章もぜひお読み頂ければ幸いです。
前段の議決権数の確認や監査結果なども短縮せず、通常通りこなしていかれていました。会社さんによってはこの辺りは割愛されるケースもあります。形式を大事にされる会社なので、こういう部分の割愛というのはなかなか解せられないケースもありそうですが、毎年時間がタイトになる中で、対話をより充実させるという意味では形式的な部分を再考するのも検討してもよいのかもしれません。
報告事項から議案の上程まで全て、ナレーションでの説明となります。議案の上程は社長自ら説明されるケースが多いですが、ここもナレーションです。別に実害はないですし、何なら聞きやすいですしわかりやすいですからね。
報告事項はまずわが国経済は・・・の定型文のような説明から入ります。そしてそんな中でも様々な取り組みにより頑張ってきましたというやつですね。
EC、低温、医薬日用品の各物流の仕事に対して、BCPを4つ目の柱として据えていく取り組みを推進したとあります。BCPは社会的要請の高い一方で、収益モデルを考えた時に、他の既存事業と比べて知恵が必要ですから今後の展開の仕方にはより高い工夫が求めらると考えています。
この他、報告事項としては財務諸表の数値面の解説が多く、決算を一応は見て参加しているのであまり新しい発見はありません。
議案の上程も基本的に招集通知の朗読です。特にここに新たに書いておくべきことはありません。
5.質疑応答
ここからが質疑の時間となります。1人1回につき1問を目安として頂きたい旨の協力要請がございました。「目安にして」という表現が入ることで優しさがが込められていますね。中には1人1問のみで、という何とも押し付けられた圧を感じる会社さんもありますからね。元々同社の総会は地元の方の空のご発言も多く、様々な方に発言をしてもらいたいという趣旨だと私も理解していますから、これでいいと思います。
また、総会後に新中計の説明があるため、中期計画に係る質問はそちらでお願いしたいということでした。つまり総会の目的に適う質問にして欲しいということですね。当然そのような趣旨に則って、事前の自分の質問シートも前者と後者で分けていました。
それでは、質疑の内容についてメモをしておきます。なお、繰り返しになりますが、あくまで私の主観で脚色しています。実際の質問内容や回答内容が事実と異なる点が多分に含まれる可能性がある点についてご了承願います。また投資判断を行う際は必ずご自身にて確認した上で対応頂くようお願いします。★印は私が投じた質問です。
★Q 丸和グループ化へ参画頂く際のポリシー
2号議案でホールディングス化を進めていくということであるが、足元でも日本物流開発やファイズの子会社化等、丸和グループの構築に向けて着々と取り組みを進めてらっしゃる。今後ホールディングス会社を作り、グループの拡大を企図される中で、どういうポリシーでグループを増やしていくのか。和佐見さんの私財で大株主になっている会社さんもあられるが、それ以外の会社さんも含めて多くの企業がある中で、物流会社に捉われることなく、グループ化を図られていく中で、どういう部分を大切にされて選定を行っていくのか。事業シナジー、人財手当、あるいは丸和に今ない機能の補完等様々な観点があろうかと思う。ホールディングス化で拡大していく中でワクワクできるような方針お示し頂きたい。
A
今後の中期計画において、ホールディングス化による拡大は当然考慮において策定をしているが、なによりまずは事業のシナジーが発揮される事が大事。日本物流開発さんやファイズさんを仲間に加えさせていただいたのも我々が示す4つの事業の中のEC事業においてシナジーとなるものを感じられたからである。今後の方針としてもこの4つの事業領域において、シナジーが発揮できるようなグループと手を組んでいきたい。
その上で、大切にしたいと思っていることは企業文化。やはりこの部分の方向性が共有できないとすると、一体感が醸成されず、組織力が十分に発揮できない事になるため、企業文化の相性といったものも大事にしていかねばならないと考えている。(山本取締役)
やはり株主さんの懸念としては、ただグループが大きくなるだけでは不安だという単純な肥大化への危機感だろうと受け止めている。日本物流開発さんにしてもファイズさんにしても各エリアでEC事業に強みを持つ会社であり、当社としてもここに勝機を拡げていく算段を抱く中で、それぞれの強みを正しく理解し、シナジーを発揮していくという事がとても大切だと考えている。我々はEC以外にもそれぞれの注力領域の事業エリアがあるが、ここに深化できるような会社さんと計画的、戦略的に手を取りあってMAをしていく事になる。ただやみくもに規模を追うことではなく、そういうシナジーをきちんと発揮できるような歩みを進めていく事で、株主さんが安心して見守って頂けるよう、進めて参る所存。(和佐見社長)
■考察
今回ホールディングス化を進めてグループとしての成長を目指すということで、やはりMAの方針についてはわかりきっていることではありますが、改めてそういう目線で気をかけているということを示しておきたいと思い、この質問をまず冒頭しました。後に中計の説明の中でも質疑があるということでしたので、2号議案に絡めやすくという事でもあり、この質問を最初に採用しました。
MAの基本として規模の拡大に前のめりになることなく、戦略的に、事業のシナジーを見極めるという所に重きを置いた答弁でした。そして、企業文化の相性といった部分にも言及がありました。丸和運輸機関はこの企業文化はとても強い拘りの下で組成されている組織でもあります。この勢いというか、昭和の根性精神のような一見するとちょっと古臭い、しかし、基本に忠実に人様と向き合っていくという姿勢が共感できないと、結局一緒になってもハレーションを大きくするだけになります。ECを始めとした既存事業の補完的な役割(機能だったりエリアだった)を見出せることと、泥臭いながらもこの企業文化についてこられるような会社さんを見出してグループ化を質的側面を損なわずに進めていくということですね。
そのように考えると、総会の日の引け後に発表のあったM・Kロジ社のMAもまた興味深くみえてきますね。D2C向け事業を支援する3PL事業者であり、ECの強化というカテゴリでナレッジも比較的活用しやすいかなと思います。企業理念や経営方針等も掲げれれていますが、まぁここは総花的になっていますが、まだ若い会社でもあるようなので今後のシナジーに注目をしたいですね。丸和グループとしての経営的にも、事業領域・顧客基盤の拡大による安定を大切にしていく方針でもありますから、今後もこのようなMAが続いていくものと思います。その時に事業シナジーや文化といった点にきちんと配慮をして進めるというご答弁は良いと思いますし、単に規模を追うことへの懸念という部分も伝わっており良かったなと思います。
余談になりますが、この買収はPER20倍程度での買収ですから、相応にプレミアを乗せた感じがします。数値面だけでみると大丈夫か?という懸念が翌日の株価の売りになったのかはわかりませんが、何かしらの非財務面の強さなりがあったものと思います。アドバイザリー費用もそれなりに高い中で、昨今MA仲介会社も近視眼的な対応になりがちとも言われていますので、このMAがうまくいくといいなと願っています。

Q 女性登用について
幹部社員や役員などを見渡してみても女性の登用がみられない。昨今は女性活躍という風潮がある中で、この業界ではなかなか難しい面は理解するものの、女性目線という点も配慮が必要かと思うが、どのように認識されているか。
A
ご指摘の通り、この業界は業務特性からしても男性社会になりがちである事は事実。しかしながら女性も一緒に活躍できる職場作りが大変重要だと考えており、ロボティックス化の推進などを通して環境作りを進めてきているところ。女性社員も徐々に増えてきており、全社員の1割強まで増えてきてはいる。また管理職登用についても積極的に進めており、まだ僅かではあるものの、今後も推進していきたい。執行役員や取締役等の幹部職についても登用出来るように人財育成に引き続き取り組んでいきたい。(葛野取締役)
入社4-5年の若い女性社員でも現場におけるセンター長等を務められ活躍している。こういう人財がいち早く上位職として活躍できるように取り組んでいきたい。(和佐見社長)
■考察
率直に申し上げるとまだまだ女性が活躍しているとは言い難い体制であり課題はあるものと思います。一方で、採用のページや事業紹介などのコンテンツでは女性社員の活躍の様子も垣間見る事が出来ます。まだまだ比率としては小さいものと思いますが、性別隔てなく活躍される事が、多面的にみた時にいい効果をもたらすと思います。
最近、「女性活躍」という文脈でこういった質問が出ることがありますが、そもそも、性別を分けて議論をする事には様々な意見があります。理想的なのはそういう性別の壁を一切設けず、フェアに扱われる事が良い事なのだと思いますが、一方で、ライフステージ等で置かれる状況が変わってくるということも現実としてあります。ですから、人財をスキル的に育てていくという事に加えて、サステナブルにあれることをサポートする事もまた大切ではないかなとも思います。
例えば採用ページのQA欄には育児休暇に係る件で以下のような記載があります。

これはやはり時代の流れからいうと、2周か3周遅れていると思います。そもそも休暇制度だけの言及に留まっていますからね。育児休暇制度は今となっては当たり前に制度があること、またそれが実際に利用される(できる)環境があることが大前提としてまずあるものです。
その上で、例えば短時間勤務だったり、子供を預けられる制度だったりという制度面に言及がないとならないでしょうし、さらに言えばそれが実際に使われている事を示していく事が必要だと思います。採用ページでそういう雰囲気が感じられないと、注力する女性活躍という答弁もその注力具合に疑念を抱いてしまうわけです。
決して女性を軽視しているとかそういう会社でない事は私は重々承知していますが、今後、性別の隔てなく、またそれぞれの強みを発揮できるような多様性を持ち合わせていく会社に更に成長していくためには、人財としてスキルアップしていく施策に加えて、サステナブルに働き続けられる環境作りとそれを訴求して魅力ある人財を引き寄せることだと考えています。丸和グループは、企業体としても大きくなり、地域貢献などの側面でもより影響力を発揮できるような会社に変貌してきました。そういう意味では地域のバス交通を支える等ももちろんですが、子育て世代に寄り添うような、それが自社社員(同志)が同志としてあり続けられる環境作りをサポートしていくとうこともまた、重要な施策だと考えます。
女性目線という文脈でいえば、例えば今松伏町に超先進的・大型物流センターの構築を進めています。ここには海外からの就労者の寮設備等も備えることになります。当然地域に雇用を生み、そのセンターを運用していくために、時に女性の方が活躍しやすいようなシーンが生まれるかもしれません。寮内の日常のメンテナンスや食堂の運営とか。もしくはその中での託児施設なども必要になってくるかもしれません、ひとつのスモールタウンを創るくらいの気概をもって進めているわけで、そういうものを創っていく時には、むしろ女性目線が入った方が上手くいくわけです。物流施設としての機能だけをみるとそうではないかもしれませんが、より広い視座に立ち、活躍機会を見出していって頂きたいなと思います。
Q プライム市場認定への取り組みと大株主の状況について
当社は株主数も増え、プライム市場にも移行していく予定とのことであるが(実際には既に移行しており浮動株比率が経過措置になっています)、今後の見通しについて教えて欲しい。また大株主にはマツキヨさんなど主要取引先も多く存在しているが、大株主になった経緯などを教えて頂きたい。
A
4/8に東証の再編があり、4つの観点の基準のうち浮動株比率のみが該当しないものの、経過措置における改善計画書を提示することにより、プライム市場に当社は所属することになった。現状、浮動株比率が7-8%足りない問う状況を2026年3月末日までに改善していかねばならない。
また大株主については、設立から今に至るまで取引先や調達先との関係強化の観点で株を保有頂いてきたというもの。しかしながら、浮動株比率の観点での改善を進めていかねばならない中では、様々な対話を行う中で、大株主の方とも相談をしながら対応をとっていきたい。(藤田取締役)
株式市場においてはやはり当社はプライム市場で今後も対応をしていきたいと考えているため、改善に係る件は検討して対応して参りたい。大株主の件は、東証の基準を鑑みて様々な政策保有に係る動きも出てくると思うので対応をしつつ、既存の関係性の構築は従来通り深めていかねばならないと考えている。(和佐見社長)
■考察
どうしても大株主の構成をみると浮動株比率が不足しているというのは否めないですからね。改善計画書の中にも以下のような記載があります。
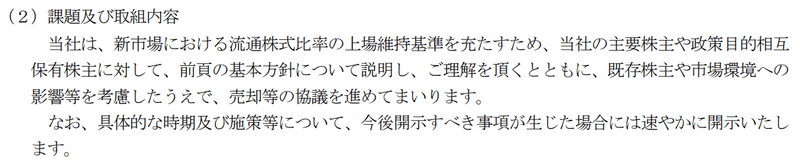
主要株主や政策目的相互保有株主に対して、今後売却等を進めていくことになるのでしょう。そういう意味では短期的には株式の需給面への影響が出てくるでしょうから、株価の下押し要素になってしまうかもしれません。ですから、既存株主等への影響を考慮するとあります。まぁ考慮しても短期目線ではどうしても不可避ですから、この辺りは長期目線である程度覚悟をもっていないとならないのでしょうね。
いずれにせよ、売却を打診していくにしても、今の株価水準ではなかなか進めにくい(納得感という意味で)でしょうから、まずは業績や中計への達成確度のコンセンサスを挙げていくことと、結局この辺りの受け皿になるのは個人株主だとも思いますから、個人投資家へのIR活動がやはり重要になってくると思っています。
会社としての認知を高めていく(副次的に従業員のエンゲージメントにも寄与する)ための広報という側面と、投資家へ向けた投資期待度を実感してもらうというIRという側面の両方で対応が必要だと思っています。
この件でも私は和佐見社長や関係者の方でお話をさせてもらった方には十分メッセージを送ったつもりですので、今後のアクションにぜひ期待したいです。大事なことはかつてのイメージされる株主層(リタイア層)だけではなく、現役世代や若い世代へ向けた活動という事だと思っています。そのためになすことといえば、例えば平日昼に証券会社主催のIRを1時間枠でやるというより、ネットを活用した発信や相互のやり取りを通したエンゲージメント向上といったこれまでと違う趣向を試す、あるいは、メディア戦略を含めた認知向上の対応が求められます。この記事もご覧頂いているかもしれませんので、改めてとなりますが、個人投資家への訴求は一朝一夕にはいきませんので、地味な活動を通して今から更なる魅力を発信され、いざ必要になった時にもそれをむしろ好機と捉えて頂けるような環境醸成に期待したいですね。そしてこれまでは和佐見社長のカリスマに頼った部分が大きかったと思いますが、こういった活動はもちろん和佐見社長が率先して率いて下さることがよいわけですが、藤田さんあるいはIRの実務者の方がもっともっと情報発信していける事もあると思います。
ここで一度質問が枯れました。あれ、いつもは結構手が挙がるんですが…中計の質疑は後でということで、私も本当に聞きたい事は全部温存していたので、そういうことなのかなと思いつつ、特にどなたも手を挙げられなかったので、私が改めて質問をさせて頂くことにしました。昨年の時間からみて、11時前に質疑が打ち切りでは少々寂しいですし、まだ質問を受けて下さると思ったからです。とはいえ、中期見通しの話はここでは遠慮した方が良いかと思い、報告事項に絡む事や足元の状況について伺うよう、咄嗟に優先度の低い質問を先にしました(今思えば先に本当に質問したいことやメッセージをお話すればよかった…)。
★Q 外部環境への対応について
インフレによる購買行動の変化や半導体不足等に起因したサプライチェーンの混乱、各種資材高や物流面の混乱等もあり外部環境はめまぐるしく変化している。このような情勢下では、当社の物流事業における荷量等にも影響があるものと思う。一方で当社には報告事項の中にも言及がある日次決算マネジメントという鉄壁のシステムがあり、業績面でもマネジメントが一定程度効いているものと期待をしている。しかしながら、これだけの外部環境の急激な変化に、従前のシステムでの対応だけでは対応しきれない事もあろうかと思うが、工夫されている点などあれば教えて頂きたい。
A
当社の日次決算マネジメント体制においては3ヶ月先の需給を見越した対応を徹底している。また燃料費の高騰や各種調達時のコスト高への対応としては、AZCOMネットワークの購買力をもって対応をしてきているところ。今後もAZCOM会員の拡大により、当社及び当社の取引先が相対的にリスクヘッジが出来るような体制構築に努めていく。
またお客様にもとりわけ燃料費の高騰などを踏まえてサーチャージを含めた価格転嫁への理解をして頂きながら、当社として業績確保を図っていきたい。(河田取締役)
日次決算マネジメントだけでは厳しいものがあるというのが率直な所。燃料費もここまで高騰するものとは思っていなかった。いくつか対策も打っているが、やはり料金改定は重要なもの。ただし、当社の状況だけで勝手に話を進めるのではなく、お客様にもメリットを感じて頂けるように交渉を進めていく事が大事であると思っている。既存の運用を見直すとか、効率化を図るという事で、お客様の経営目線に立って経営支援を含めた対応していかねばならない。AZCOMネットでもこのような視座に立って、調達力はもちろんのこと、付加価値を高めていくことで結果としてお客様へも高い付加価値が提供できるものと考えている。
加えていえば、お客様から臨機応変の対応が求められる事も増えており、そういうシーンでも配車計画をAIを活用して効率化を進めている中で、AZCOM会員の皆さんの協力を得ながら、またお客様への臨機応変の対応も満たしながら、DXを活かした付加価値を提供して、当社収益を確保していくという努力をして参いりたい。(和佐見社長)
■考察
やはり日次決算マネジメントだけでは厳しいという率直なコメントをも頂いた通り、価格高騰が与える影響には注視が求められる様相です。回答には直接言及はありませんでしたが、サプライチェーンの混乱もありそもそも商品が滞留する(品不足)という状況から荷量の動向においても随所で観測されているだろう中で、影響は多岐に渡るという事だと思います。
そして価格対応はもちろんしていくわけですが、そういう中でも当社都合を押し付けないという従来の発想が堅持されているのはよいですね。そしてそれは自社と顧客だけでなく、AZCOMネットというグループ全体での目線で対応をしていくという点もよいと思います。
燃料費が高騰しているから物流会社はだめなんだ、という事ではないと思うのです。もちろん、Q決算でみたら、粗利率が上がる下がるってことはあると思いますが、もっと俯瞰してみると、こういう環境はどの会社でも同じ条件なわけです。そして、ラストワンマイルというものへの需要はもう不可逆になりつつあるわけです。それは低温物流でも常温医薬でも同じです。どの会社が運んでも燃料費はそこまで変わりません(AZCOMの存在があるが故、丸和グループはむしろ有利なんでしょうけど)。そう見た時に長期的に価値を保ち続けられるという目線で見た時に、相対でみればそういう付加価値を提供しようという視座に立って顧客や会員と共にあろうとしている姿は報われるものと考えています。
株主目線では短期的なコスト高や荷量の変化とかの凹凸により、株価の凹凸も気になる所ですが、そもそも株価は投資家が値付けをするものです。ですから、広く投資家にこういう質問の趣旨の懸念を持たれている部分はあるでしょうから、こういう懸念に対して、決して煽ることなく、丸和グループはこれを乗り越えていくんだというメッセージをIRを通してより発信していく事を期待したいなと思います。総会議題に係る質問ということで、敢えて足元の状況を踏まえた質問をして、近視眼的な質問となりましたが、こういったものの見方をされる投資家さんが相応におられるとも思い質問をしました。こういう懸念に対して、長期目線で答弁にもあったような本質的な価値を顧客や会員と創っていくという姿勢がより広まるといいなと思いました。
Q コロナの影響を総括して欲しい
コロナの影響はどういう実態にあったのかを総括して欲しい。地元吉川市の職員も多くが感染したわけだが、当社においての状況がどうであったか、またそれをどのように工夫してこの業績に繋げられたのか。
A
コロナへの対応としては、本社から全営業所に通達をだし、全事業所で国の基準を超える厳しい管理体制に基づき対応を行ってきた。特に重要視したのは、濃厚接触者を多数出してしまい業務継続性が損なわれないようにすることであった。お陰様で私の所掌するEC事業において日々数千台が稼働する中で稼働を止めるという判断をせなばならないことはなかった。従って業績面でのネガティブな影響はなく、むしろEC化の進展が一気に進んだこともあり、荷量が増えた事で業績寄与をすることが出来たと考えている。また、この段階では従前から取り組んでいる通りパートナー企業にもきちんと報いる事が出来るような価格交渉も重ねて実施してきた。(岩崎取締役)
リモート対策が今までになかった変化であった。最初は手探りであったが、その利便性、とりわけ海外事業でのコミュニケーションには大変活用させる事が出来た。コロナの対策でいえば、業務継続性を重視して、お客様の業務を止めなかった取り組みは社外からもとても評価をして頂けた。(和佐見社長)
■考察
コロナについては、結局のところ影響はなかったということでしょうね。むしろ荷量が増えた、あるいはコミュニケーション手段が進んだこともあり、会社にとっては良い面もあったということですね(相応しい表現ではないかもしれませんが)。このような管理体制において、お客様からも具体的な感謝や信用を高める声を頂けたというのは、株主としても大変嬉しいことですね。
Q 企業のロゴの変更について
これまで数十年愛用してきた企業のロゴを今回変更された。長く使ってきたものを変えられた背景と、新たなロゴに込めた想いがあればお聞かせ願いたい。
A
当社は創立50周年を迎える。そして新たなホールディングス会社として大きくReブランディングをしていくためにコンサルも入れて検討を重ねてきた。新たな意欲的な目標を掲げ、前進していくためにも、ここでNew桃太郎になった方がいいだろうとの想い。株主に対しても、この前進を表す桃太郎のように、会社としてより期待度を高めて頂けるようにして参りたい。(藤田取締役)
新しく何かを変えるというのは勇気が必要。50周年などの区切りは第三の創業という節目でここで変えるんだという勇気が必要だと思った。いざ変えてみると、これがなかなかいいもので、お客様からも若返った、躍動感があるなどポジティブな反応も頂けた。経営には変革が常に求められる中で、こういう部分でも変化を率先していく事が重要であると考えた。(和佐見社長)
■考察
ロゴの変更を取っ掛かりに、今後の姿勢を問ういい質問だなと思いました。コンサルも入っているということで、これは広報だけではなく、事業戦略など全般においてもそうなのかもしれません。中計に出てきている事業戦略から財務戦略に至るまで、昭和の文化が漂う企業とは思えない(失礼)、先駆的な印象があるんですよね。この新旧が織り交ざる融合が、いい意味で過去のよき文化を継承しつつも、変える所はどんどん変わっていくという事を示しているのだとも思います。たかがロゴ、されどロゴというわけですね。
それにしてもこれを変えるとなると、トラックのデザインなども全部変えていくとなると相応のコストが生じそうなんですが、これは大丈夫なんですかね(笑)。まぁ桃太郎も世代交代したとはいえ、新旧織り交ざっているのも悪くない気もしますけどね。。。

Q 株価の状況について
現在の株価水準は昨年の高値から随分下落をしている。業績は順調だがなかなか株価に反映されない会社も多い中で、当社もそのような状況である。既に自己株も多く保有されている中ではあるが、株価の現状認識と対策についてどのように考えられているか。
A
株価は昨年の高値から一時は1000円を割れた中で、今は回復途上にあるという状況。コロナ禍やウクライナ侵攻など世界情勢は大きく変化しており、金利なども含めてボラが大きくなっている。こういう状況下ではグロース系の企業の株価は軟調に推移するわけでGAFAを含めて世界の名だたる成長企業の株価は下落している。当社もそのような影響もあってこのような状況になっているものと考えている。株価対策という面でいえば、我々は株主と共に成長していきたいと考えている会社であるが故、様々な対策を当然考えていくし打っていかねばならないと考えている。また、中計に示す業績をきちんと実績を上げていく事で本質価値と期待度を向上させる活動を進めて参りたい。(藤田取締役)
株価というのは、業績と期待だと思っている。業績は大前提であり、経営者として年々成長させることは使命だと思っている。その上で、期待される会社作りというものが大切になってくる。だからこそ、人財リソースの確保を含めて体制構築を進める事が期待を持ってもらう事が大事だと思っている。但し、株価だけを追うというのも厳しいわけで、様々なステークホルダーがあられる中でそれぞれに配慮しながら、情報を伝えるというIR活動は大事だと思っている。今はコロナでなかなか海外に赴く等出来ない中でも相手に通じる説明を尽していきたい。(和佐見社長)
■考察
私の記憶する限りでは、株価について質問が出たのは初めてではないでしょうか。これまで一貫して株価は堅調に推移しており、一年を通じて軟調だったというのが初めてだったということもあるかもしれません。株価は投資家が値段をつけるものなので、それを経営に問うてもそれは回答に窮することもあるでしょうし、経営が株価に言及するというのもなんとなくタブーのような事も見聞きします。なので、私は結構ドキドキして質問を聞いていました。
グロース系のライナップとしてGAFAと並んでお話されていたのは印象的でした。自分たちがグロース系の会社であると認識しているということですね。物流会社で高いPERがついていますからね。その意味では業績と期待というお答えも、要するにEPS×PERで株価が決まるという事を言っていますね。そして、EPSは堅調に積み上げられている一方でPERが下がっているということです。

これをみると、やはりPERが高過ぎましたね。PERは50倍とかでしたからね。一方で、一時は20倍を割り込んでいましたね。物流会社としては概ねPERは10倍とかですから、現状においても単純に比較するとまだ期待は高いとなります。
一方で同社を単純な物流会社であるとみるかは微妙な所で、BCP事業も含めてサービス業へかなり進化しつつあるとも思っています。またAZCOMネットワークの構築という意味では一種のプラットフォーマー的な立ち回り方も期待される所です。当然現状下での業績としては物流事業がメインになりますし、これは当面変わらないのだと思いますが、運営、サービス、プラットフォームといった基盤が出来てくるとこういう期待度も変わってくるのかなと感じます。
それからIR活動については、コロナ前は特に頑張っていたという話もありつつ、コロナ禍で今は満足いく活動が必ずしも出来ていないという事もお話がありました。これは大きく機関投資家と個人投資家に分けて考えた方が良いと思うのですが、機関投資家向けは一般論としてはリモート活用で接点を増やすという意味ではむしろ現状の方がよりよくなっていると言えると思います。一方で、和佐見社長が語る社の雰囲気だったり魅力は直接交わさないと伝わらない部分も多分にこの会社にはあると思います。またファーストコンタクトはリモートでもより深い理解促進のためにはやはり対面という事になるのだと思います。
一方個人投資家向けについては、再三の通り様々な手段があるものと思います。リモートを活用して、インタラクティブに対話も出来る形式であるとか、土日や夜間等、現役世代等も参加しやすい形での発信ということもあります。また個人投資家界隈では各地で勉強会に企業を招聘してIR時間を設けている機会もあります。こちらは質疑の時間もたっぷりとって、企業にとっても投資家にとってもWin-Winであるとよく聞きます。こういうものへ登壇しより裾野を広げていくという事も重要な事かと思います。
勝手に宣伝してしまいますが、以下のような勉強会では多くの上場会社を招聘し、熱心(かつ大金持ちの方も)参加されてて、企業のIR活動として費用対効果も高いのではないかと思います。
ここで、質疑は終了し、決議を取り株主総会としては閉会となりました。
6.中計説明
総会終了後、10分程度の休憩の後、新中計説明が2部として用意されています。ここで株主も半分くらい退席されたでしょうか。
なお、先に申し上げておくと、この後の質疑の予定は時間の関係で取りやめとなりました。これは大変残念でした。温存していた質疑を沢山用意していたのでそれが叶わなかったこともそうですが、メッセージとして皆さんの前で感謝と激励も申し上げたかったのです。
中計の説明は先に開示のあった資料をベースに和佐見社長がプレゼンにて説明してくださいました。基本的に資料に書かれた内容ですが、主な内容についてメモと記憶の範囲で残しておきたいと思います。
まず前中計の振り返りは割愛され、新中計のコンセプトから解説に入られました。
まずは人財面の話として、大学教育機関も持ち教育には積極的ですよーとか、DX活用の文脈では松伏のセンターに高度化されたものを実装したいということです。成長市場へ経営資源を集中させるという事やESGも頑張るということです。

続いて数値目標です。実際にはこの説明用にこの表をグラフにしたものを用いられていました。経常利益について説明されていました。同社の経営目標は経常利益率8%を目指すということになっていますからね。平均CAGRは売上21.7%、経常利益24.2%ということになり、これは高いものであるから、「創造力」が大事ですねと仰っていましたね。そして利益率は業界平均としても高いという事もアピールされていました。

事業戦略ではEC事業から説明です。アマゾンの仕事としてラストワンマイルから入り込み、幹線輸送、センター運営と幅を広げてきたということです。同社の強みはセンター物流であるので、ようやくこれから本領発揮ということです。ラストワンマイルだけではキャップがでてきてしまうということですね。
そして説明はMAの話となります。ファイズには関西圏の拡大に頑張ってもらいたいということ、日本物流開発さんの開発に必要なリソースを提供していっているということでした。今後も10年スパンで3つくらいのセンターを作っていきたいということです。そして場所柄、費用も安く済むのもよいということですね。


低温物流ですね。長距離ドライバーが減少したことで、かつては太田市場に集まっていたものもなかなか難しくなってきたという背景もあり、産地直送を活性化させる仕組みを構築してきたという話ですね。

低温物流はやはりコロナの反動もあり、やや下押しがあったが、新規センターを開設していくことで、今後も底堅い需要を取り続けていくということですね。

松伏のセンターについても紹介がありました。CG動画を使った完成イメージと共に紹介下さいました。寮設備があったりするわけですね。

医薬医療物流については、マツキヨさんの実績が買われて、ココカラさんも評価して下さり採用になったということで、全体の1.7倍程度の荷量増になるとのことです。

DXの活用については、秩父での活用事例等もお話されながら解説してくださいました。そういえば、あの秩父のPoCはどうなったんでしょうかね。

経営資源の配分に関する説明です。この辺りも新たに出てきた考え方の資料ですね。経営はどんな事業にリソースを向けるかは適材適所で判断していく必要があるねということのようです。人以外でもセンタなどハード面でもどういう位置づけで配置していくかが大事ということです。

この後はESBやBCPの説明が続きますが、時間が迫ってしまい、資料をかいつまんでの説明となりました。ここでは割愛します。
7.さいごに
こんなことを言ってしまってはいけないのかもしれませんが、今回のハイライトは総会開会前の和佐見社長とのひと時だったと思います。ここにその内容を明るみにするのは適切でない(当然のことながら、インサイダーに係るお得情報があったとかそういう話ではありません)と思うので表現出来ない事は残念なのですが、改めて自分は丸和運輸機関という会社が好きなんだなと感じました。他の会社でも投資先企業への愛が深いと、それだけ色々辛辣なこと、耳障りが良くない事も伝えなければいけないとも思っています。今回は直接質問は出来なかったのですが、同社においても様々な課題やネガティブな現象もあったりするわけです。私は同社の熱烈ファンの一人であると自認していますが、だからこそ、こういう点にも言及しないといけないとも思っています。もちろん、その表現の仕方などは配慮が必要なわけですがね。
2部の質疑でこの辺りの考えに基づく対話が消化不良になってしまいました。ですので、帰りのお見送りの際に名刺を差し上げることにしました。総会開会前に名刺を下さった方の行動をヒントにして、私も同じように行動しようと思ったのです。もちろん私の本業の名刺はどうでもよく、裏にプライベートの情報を書いて託したわけです。かなり強引なやり方ですが、それを笑って受け入れてくれる事は大変ありがたいことです。
お見送りの際には他の役員の方からも、この記事もみているよ、などとありがたいお言葉も頂き大変嬉しかったです。冒頭に腹痛の話などでだらだた書いてしまう事が申し訳ないようです(笑)。
投資家観点でいえば、今期待値に迷いがある感じですので、株価形成も短期的には変動が大きくなるような気がします。またコロナ禍での一種需要が一気に伸びた歪みが今後逆の部分が顕在化してくることも考えられます。そういう意味では業績面でもやはりボラティリティが大きくなるのではないかと思います。更に言えば、物流会社としてみれば、明らかにPERは高いわけですから、他社の方がバリューであるということになります。ですが、私の評価軸はそんな指標面だけはないところも大きくて、そういうものをどこまで尊重していいのかってこともあるのですが、しかし自分の投資ポリシーに照らすと、適切な資産分散を図りながら、寄り添っていければいいなと考えています。
書籍に加え、財界の表紙も飾られたようでこちらも頂いたので、拝読しながら考えを深めていこうと思います。
創業50周年、そして第三の創業としてトラック一台から始まった桃太郎のチャレンジは続きますが、今後も期待を寄せていきたいなと思います。
頑張れ、丸和運輸機関!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
