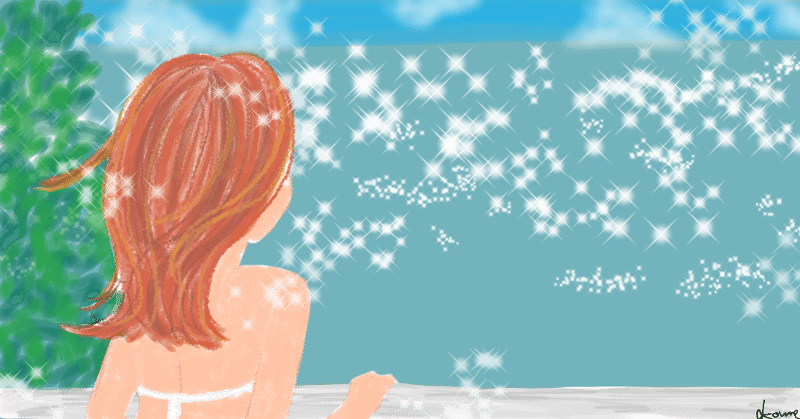
井の中のJK、大海を知る -赤点の数I編-
10月の書くテーマ:2000年代に行ったアメリカ留学での話
脳がバグった。
Algebra(代数学)のクラスで返されたテストは、すべての解答にチェックがついているのに100点だった。
まんまるの目を上から下まで舐めるように動かして、英語と数字だらけの紙面を三往復する。
アメリカの採点では正解を丸ではなくチェックマークでつけるらしい。
このルールを思い出して、ようやく「自分はどうも満点を取ったようだ」と理解できた。
テスト用紙を無言で見つめるわたしに、先生が「素晴らしい点数よ」と褒めてくれる。
いつも、ぱしん! ぱしん! とハサミみたいな切れ味のもの言いをする引っつめ髪の彼女をとっつきづらく思っていた。初めて笑顔で「ありがとう」と返せた。
しかし脳はバグり続けている。
わたしは高校が夏休みに入ってからアメリカへ来た。つまり、終業式で一学期の通信簿を受け取っている。
数Iの成績は5段階の評価で2だった。
しかも3に近い余裕ぶっこいたアヒルではなく、一歩でも間違えれば1に入る、ギリギリ崖っぷちにくちばしが引っかかったアヒルだ。
数Iのサインコサインでつまずいて数学くんに別れを告げた話は、この記事にも書いている。
小テストで赤点を取りまくり、当時の担任にため息をつかれ、定期テストは始まって10分で裏返して寝た。
自分でもどうしたらいいのかわからなくて、数学のある曜日は学校に行きたくなかった。たまにズル休みもした。
Algebraは、数学のなかでも代数学を習うクラスだ。つい最近まで日本の数Iや数Aで学んでいた内容とほぼ同じで、数式も扱うしグラフも描く。
日本では赤点オンリーだったJKが、どうして数週間も経たないうちにアメリカで満点を取れたのか。
その秘密は電卓にある。
実はアメリカの学校では、超性能のいい電卓を使って授業を受けるのがごく当たり前の光景なのだ。
わたしたちが普段の生活で目にするようなタイプではない。
片手には収まらない縦長サイズで、表示される画面も広いし、打つキーも多いタイプの電卓だ。値段もちょっとお高いやつ。
理系や建築系の人なら「関数電卓」で通じると思う。
こういうやつ。
200パーセント文系のわたしは、アメリカのスーパーで初めて出会った。世の中のガジェットが薄さと軽さを競う中で、鈍器みたいな電卓がデデンと棚一面に居座っていてちょっぴり感動した。
わたしの通っていた高校は、マイ電卓を持ち歩く生徒もいたし、持っていない生徒には先生が貸してくれた。クラスでの割合は半々くらいだった。
これを数学の授業でしょっちゅう使う。
足し引き掛け割りの頭でパッとできるような単純な計算でも、ルートやパイなどを用いる特有の計算でも、もちろん三角関数でも問題を見たら秒で電卓を叩く。
グラフはなんとボタンひとつで描いてくれる。
設問に書いてある方程式さえ入力すれば、ブイーンと勝手に画面に作図してくれた。わたしはそれを答案に写すだけだ。
当然ながら、問題文は英語で書いてある。何を問われているのかまったくわからなくても、数式のままに電卓へ入れれば答えが出てきた。
はっきり申し上げてめちゃくちゃ簡単だった。
たぶん、日本で教わる数学に慣れた高校生なら「本当にこれで大丈夫?」と心配になるくらいだと思う。
おかげで小テストで点を取りこぼすこともなく、担当の先生に激しく褒められ、定期テストは10分で終わって裏返してぼーっとしていた。
わたしはまったく勉強をしていない。ただ、場所が変わっただけだ。
脳のバグりが治ったころ、なんとなく「よし。ちょいと数学を勉強するか」という気持ちになった。
そんなこと日本ではカケラも思ったことなかったのに。不思議なものだ。
その日から、図鑑みたいなサイズと重さの教科書をせっせと持ち帰っては、ホームステイ先のテーブルに広げて1ページ目からじっくり読み込んだ。
通っていた高校には、自習のために居残りができる開放日があった。各教科の先生も教室にいるから、自由に訪ねていいことになっている。
わたしはたいてい数学のクラスを選んで、先生に質問したり、予習と復習をする時間に充てたりした。
一年が経つころには、問題文を理解してから解けるまでに英語力がついた。ときどきクラスメイトから教えて欲しいと頼まれることもあった。
誰かに数学を教える日が来るなんて!
ブレザーの制服を着て、バツばかりついた数学の小テストを目の前にしょんぼりしていた頃は微塵も考えていなかったことだ。
アメリカの高校は毎日だいたい同じ時間割で進む。
数学のクラスに行くときは心が弾んでいたし、誰よりも先に教室に入っていちばん前に座る日々を過ごした。
さて。15年以上が過ぎて、さんざん覚えた数式も今はどう英語で読むかすら忘れてしまった。
でも、あのとき脳みそがぐわんと大きく揺れて「井の中の蛙が大海を知った」感覚はずっと頭の引き出しにしまわれている。
その経験のおかげで、勉強に限らず苦手なことをしないとならなくて悩んだり、得意なことを生かせなかったりしたときは「脳がバグれる場所はどこだろう?」と考えるようになった。
自分の苦手なことができない人が多いところや、得意なことをできる人があんまりいないところを探しに行くことを覚えた。
さすがに、コンビニに行く感覚で飛行機に乗ってアメリカに渡るのは難しいかもしれない。
いきなりそんな遠いところでなくてもいい。ちょっとだけ背伸びをして、キョロっとまわりを見渡してみてほしい。
あっちに深さの違う海がないだろうか。
向こうに大きさの違う海はないだろうか。
今いる海がどんな形で色かを、そらで言えるだろうか。
できないと思うことがあっても、たいしてできるわけじゃないと思うことがあっても、それが「できてすごい!」と評価される場所は探せばあったりする。
井の中でうずくまっていた赤点JKは、自分がいる場所のほかに大海がいくつもあることを知った。
ドボンと投げ込まれた場所だったけど、初めての海でしばらく泳いでみたら、うんと息がしやすくなった。
体はスイスイと軽いし、心に好奇心が芽生えて若葉のように色づいていく。
環境を変えて視界がひらけたときの爽快さはそりゃもう格別だ。
もし、できない自分を責めるのに飽きてきているのなら、それは足を動かすタイミングだと思う。
視線を上に向けてみよう。向こうのほうに、見たことのない景色がぼんやり映るかもしれないから。
読んでくださりありがとうございます! いただいたサポートはまるやまの書くエンジンになります☕️
