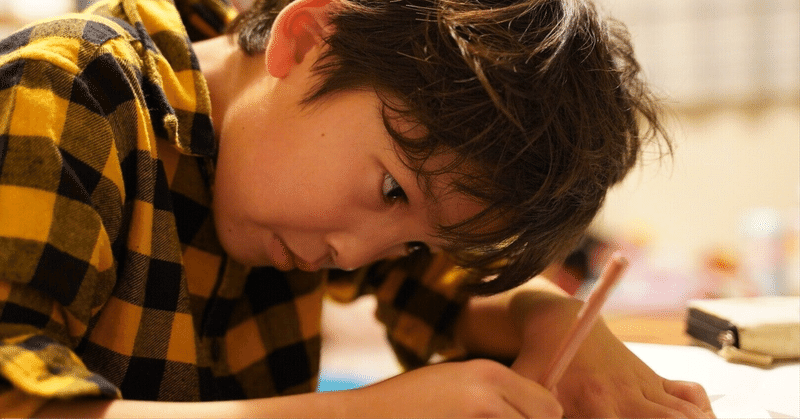
【税理士試験】ポンコツの受験シーズン(あるベテの一例)
全く自慢にならないし、できれば黙っておきたいのだが、僕は税理士試験では完全にベテ受験生だった。
実務でも税理士が何をする人かわからないまま税理士事務所に入り、採用されたもんだから簿記を勉強し始めるという、志が地に這ったスタートだった。
売掛金とか買掛金が何なのかすら知らなかった。
本屋で買ったテキストを適当に読んで簿記3級を合格した後、一応税理士試験を受けることにしたのだが、一番簡単だからと言われた財務諸表論が全然受からない。平成19年に就職して、財務諸表論を取ったのは平成29年だった。簿記2級は未だに持ってない。
恥ずかしいので色々個人的な事情について言い訳をしたいとこではあるが、ここはグッと我慢することにする。
マジメに試験勉強をしている人はポンコツの体験談を聞かされるなんて、この先を読む必要性を感じなくなっただろう。
わかる。僕も書いててそう思う。
そんな僕が正攻法の勉強方法をキリッとした顔でロクロ回しながら語っても仕方ない。
そういうのはTwitterで有名なあの人とか、会計人コースに載ってるあの人とかに任せておけばいい(特定の人が浮かんでるわけではない)。
今回を含めたこのテーマでは、税理士試験に苦労したり、燻ったりしている皆さんに向けて、ポンコツ税理士事務所職員がどのように税理士試験に受かるか、そしてどういう風にウッカリ合格してしまうか、これらを主に具体性のない精神論で書いていこうと思う。先に言っておくが自信はない。
まず、このテーマのnoteが有意義な点を挙げる。
①「自分よりダメな受験生ですら税理士試験に合格しているのを見て安心する」
②「ベテランだからこその経験値を数分で吸収する」
この2点。①は言わずもがなで、どうぞ安心して気持ちよくなっていただきたい。②は少し説明を加える。結果的に僕は10回以上の受験生シーズンを迎えている。
なので「全く歯がたたない年」とか「まあまあうまくいった年」とか「結果的にあっさり受かった年」とか、いろんなパターンを経験している。
だから、これを受験生の方が読んでいてくれてるのならば、なんとなくあなたに当てはまり、僕の経験が役に立つことがあるかもしれないと思うので恥を承知で伝えることにする。
そのうち、今回は1年の過ごし方。
税理士試験を何度も受験すると、自分にとって「やる気の出る時期」と「やる気の出ない時期」をしっかり把握してくる。
このうち、やる気の出る時期から。僕の場合はっきりと8月の試験後と12月の結果発表後だった。
まず8月。本試験がうまくいかなかった年なら本試験で受けた科目と同じ科目を勉強を再開したりする。
一応毎年本試験に向けて勉強をしているので、ワケのわからない難度(当社比)の大原の模試とは違い、優しく易しい個別問題などの基礎的な問題を始めるとすらすら解けて嬉しい。
また、本試験に謎の手応えを感じた年の場合は、次の科目を検討したり、勉強してみたりするのが楽しい。時期的に余裕もあるので危機感もなく、のんびり勉強ができる時期である。こんな感じで余裕もあり、8月後半はやる気がでる時期。
そして最もやる気が出るのが12月で、これは税理士試験の結果が出るタイミング。
落ちた年を前提にするが、ポンコツもやっぱり辛い思いをして受験をしているので、落ちればそれなりに凹む。ただ、凹むのは数日。このあとは「こんだけアドバンテージあるから次は余裕じゃん!!」となる。この後、同じ思いをすることに気づくのは来年なのだが。
それでも、次の試験に向けてリベンジの気持ちが高まり、ロケットスタートを決めようとする。
敢えてもう一つあげると7月。勉強が仕上がってれば万能感を覚えまくる。ただ悲しいかな、受かる年でなく落ちる年もそれなりに感じる。その万能感は大して役割にも指標にもならない。ただやる気はあるので勉強量は増える。
次はやる気の出なくなる時期の話。やる気なんて年間通じてないわけだが、月で言うと11月、2月、3月あたりが特にやる気がなくなる時期である。
11月のやる気ダウンの原因は、ポンコツぶりを露呈して悲しいが「飽きる」からだ。新しい科目のワクワク感とかが薄れる。同じ科目を勉強している場合も、スタートダッシュ感が薄れる。
次に、2、3月のやる気ダウンは会計事務所の繁忙期に起因する。うちの事務所はそう忙しいわけではないが、それでも土曜日出勤したり、残業が始まったりとやる気を削がれる。
毎年、変わらずこんな感じでモチベーションの波がある。
ここまではただの事実。じゃあどのように向き合うことが必要なんだろうか。
結論から言うと、モチベーションのコントロールは難しい。やりたくないもんはやりたくない。
ただ、振り返ってみると、順調だったときは勉強のスケジュール調整に脳みそを使ってなかった気がする。
今日は理論やろうかー、計算やろうかー、個別やろうかー、とかそういうのは大まかには1ヶ月単位くらい決めておく。
強調するが、結構勉強の段取りを組むというのは疲れるものだ。
1ヶ月というのはだいたい税理士試験の定期テストは1ヶ月ごとに決まっているからそうした。
確認テストやら実力判定とか、模試とか、だいたい勉強期間のスパンは1ヶ月で切り替えやすいようにできている。もっと短いときは短く段取りを区切る。
具体例を挙げると、
「朝起きて、早めに職場に行って個別の勉強をする、昼休みは理論。
休みの日は朝マックで11時まで1つ答練をやる。昼飯食ったら歩いたり、電車乗ったりして理論をやる。」
これくらいのスケジュールを「忙しい月」「普通の月」「頑張る月」バージョンそれぞれに大雑把に決めておくとだいぶ楽になる。可能であれば試験までの1年のスケジュールをまず決めておき、必要に応じて軌道修正したり、より具体的にスケジュールを決める。
ただ、スケジュールの決定は最短でも1週間単位にしていた。これ以上短くすると、段取りに気が向き過ぎる。
よく税理士試験を筋トレに例える人がいるが、僕もそう思う。
また、今回の僕の雑記を組み合わせていうと、スポーツ選手のような、1年を通して戦うアスリートの生活に似ている。オリンピックやら世界大会に向けて、本番までに実力を充実させるような人。
結局、本番に力を出せないなら意味がないので、今日やる気があろうとなかろうと、そんなことで本番の出来を邪魔してはいけない。
とにかくなんでもいいから愚直にやるしかない。
忙しいときとかやる気がないときは絶対ある。Twitterのスゴいあの人もやる気がない姿を見たことがある(クドいが、特定の誰かを指してはいない)。
そんなときはもっと緩い、Bプラン、Cプランを予め用意しておいて、もっとも効果的なスケジュールを月単位で作っておくこともポンコツの体験談を踏まえておすすめしたい。
とりとめがなくなったのでまとめる。
・やる気のある時期でない時期はある(優等生にもある)
・やる気の多寡に合わせて勉強量、内容のスケジュールを作る
・スケジュールはひと月単位をベースに、1年単位、1週間単位程度でざっくりと作る。
まとめてみると当たり前のことしか言ってないようだが、試験勉強なんて迷走するものだから、基本に立ち返るのは大切なことだ、開き直りつつ結ぶ。
受験生の皆さん頑張れ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
