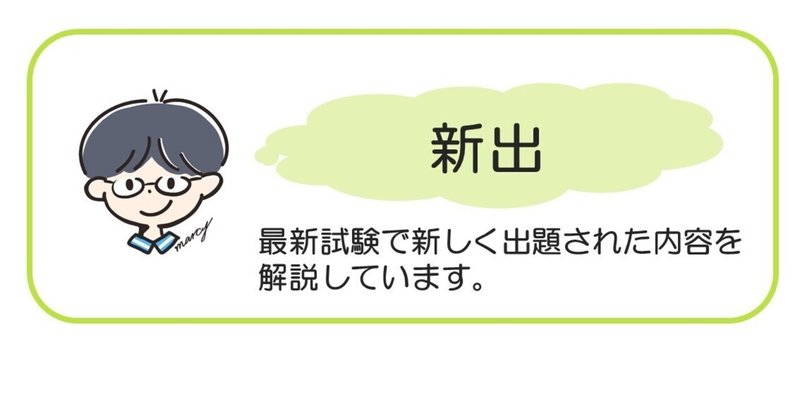
新しく出たとこ。『36回/人体』イヌリン
36回31番(2)
腎・尿路系の構造と機能に関する記述である。
イヌリンは、尿細管で再吸収される。(○or×)
「腎臓とイヌリンの関係」が初登場したので、確認します!
[イヌリンとは]
イヌリンとは、きくいもなどに含まれる多糖類です。これまで、「きくいもの主な炭水化物である」という内容が出題されていました。
[腎臓との関係]
イヌリンは、
生物学的活性がないこと
体内で代謝されないこと
腎臓の糸球体で濾過されること
尿細管で再吸収されないこと
尿細管へ分泌されないこと
などの特徴があります。
これは、体内での変動が少なく、腎臓の初めの段階(糸球体)で濾過された分が、そのまま尿へ出てくることを表します。(途中で増えたり減ったりしない)
そしてこの特徴は、腎臓がどれくらいの機能を維持しているか(GFR/糸球体濾過量)を測定することに役立ちます。
つまりイヌリンは、正確な腎機能の指標(GFR/糸球体濾過量)を測定するのに利用される、という側面をもちます。
[再吸収されない、が大切]
GFR(糸球体で濾過される量)を正確に知るためには、原尿が作られるタイミング(腎臓の糸球体で血液が濾過されるとき)の量と、実際に尿として排泄される量が同じであることが大切です。
(途中で再吸収されたり分泌されたりすると、最終的に尿に含まれている量が変動し、実際はどれくらい濾過されたのかが分からなくなる。)
つまり、「尿細管で再吸収されない」が大切です。イヌリンはこの特徴をもっているため、腎機能の測定に用いられています。
今回は「再吸収されるかどうか」だけの出題でしたが、今後はGFRとの関係性が問われることも予想されます。そう考えると、「尿細管で再吸収されないという特徴の方が、都合がいい」まで理解しておくことが大切といえます(^^
腎・尿路系の構造と機能に関する記述である。
イヌリンは、尿細管で再吸収される。(○or×)
答え × イヌリンは、尿細管で再吸収されない。
今日も勉強おつかれさまです。
marcy
ノートの内容一覧
https://marcyroom.com/notecontentslist/
ここから先は

【marcyノート】(管理栄養士国家試験対策の解説)
marcyノートは、国試対策に特化したマガジン(記事集)です。 自分自身の受験経験・講師としての経験・受験生からいただいた質問を通して、合…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
