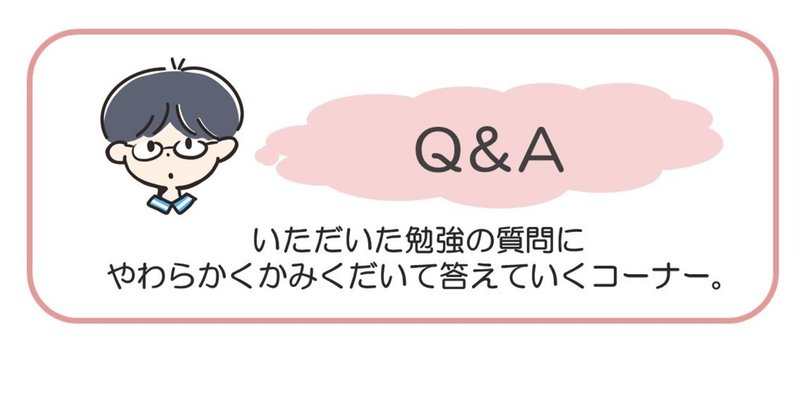
Q&A『勉強の焦りや不安は、ある方がいい。』その2
勉強の焦りや不安があるということは、
その分試験に対して真剣だということ。
だから「焦りがある状態」は、
むしろ自分をほめてあげる要素。
前回はこちらについて
お伝えしました。
今日はこの続きです。
・バランスをとる
適度な焦りや不安はOKですが、
もちろん「焦りすぎの状態」はよくありません。
むりやり頭に詰め込もうとしたり、
手あたり次第、いろいろな勉強方法に飛びついたり。
「焦りすぎの状態」では、
日々の勉強がただの作業になりがちなので、
いったん冷静になるよう意識します。
(ただ問題を解いているだけ、という感覚。
こんな状態のときは要注意。)
・忘れてもいい
試験勉強の本質は、
「自分がわからない部分をわかるようになる」ことです。
また、「わかるようになる」のは、
最終的にわかるようになればOKです。
これを言い換えると、
途中ではなんど忘れても大丈夫ということ。
国試の場合だと、
試験本番の問題を解くときに思い出せる状態がゴール。
それまでの勉強期間は、なんど忘れても大丈夫です。
(だれだって1回じゃ覚えられない。)
むしろ、
忘れる → 思い出す
を繰り返した方が
「覚える」につながります。
ですので、
いちど勉強した部分なのに忘れてしまう...
どうしよう...
と、焦りすぎる必要はありません。
・忘れてしまったときこそチャンス
もちろん、同じように忘れても前には進まないので、
復習するときには前進するための意識が必要です。
その意識こそが、
・なぜ思い出せなかったのだろう?
・どうすれば次は思い出せるだろう?
という視点です。
試験問題のほとんどは、
内容を理解していれば
考えて判断することができます。
(食べ物成分のカタカナなど、
単純な暗記問題もありますが、例外です。)
ですので、
答えを正しく判断できないとき
思い出せないときは、
何かしら自分の中で足りない知識や理解があるはずです。
(これを意識するのが
「なぜ思い出せなかったのだろう?」)
また、足らないもの目星がつけば、
それを覚えたり、理解し直したりすることで、
次につながります。
(これが、
「どうすれば次は思い出せるだろう?」)
これらを意識して
「この知識(理解)がなかったから、
思い出せなかったのか!」
ここまで発見できれば、もう解決したも同然です。
あとは数を重ねれば、覚えられるようになります。
もし、まだ完全に思い出せなかったとしても、
少しずつ理解している範囲は増えているので、
「前進している感」が出ます。
「前進している感」があれば、
「焦りすぎ状態」からは脱出できます。
ちょっと焦りすぎているなぁと感じた時は、
ぜひ、これらを意識してみてください。
昨日より思い出せるようになった、
おしいところまで思い出せた。
この積み重ねの先に合格があります!
・お気軽に質問を。
・なぜ思い出せなかったのだろう?
・どうすれば次は思い出せるだろう?
この2つの意識が大切とお伝えしましたが、
これを自分ですべて解決するのはたいへんです。
調べてもイマイチよくわからない...
調べるのに時間がかかる...
これらはよくあることなので、
そんなときはお気軽にご質問ください。
どんな些細な質問でもお待ちしております!
今日も勉強おつかれさまです。
marcy
ここから先は

【marcyノート】(管理栄養士国家試験対策の解説)
marcyノートは、国試対策に特化したマガジン(記事集)です。 自分自身の受験経験・講師としての経験・受験生からいただいた質問を通して、合…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
