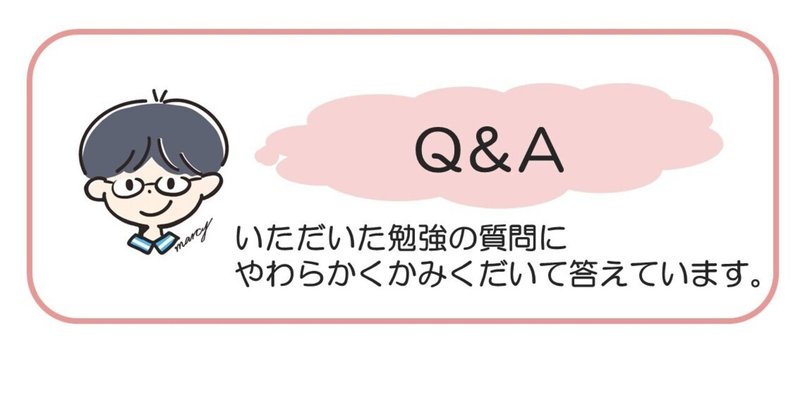
Q&A『疫学研究での、行動変容の準備性とは?』
Q. (30回197番)「結果にバイアスをもたらす事項として強調すべき、研究の限界はどれか?」→「行動変容の準備性が、2群で異なった可能性がある」の意味がよくわかりません。
A. 「研究の限界」とは、その研究方法だとどうしても起こってしまう偏りのことです。そして今回の偏りは、「やる気のある人とそうでない人とで比べてしまっている」という内容になっています(^^♪
次の文を読み「196」、「197」に答えよ。
K病院に勤務する管理栄養士である。糖尿病と初めて診断された患者を対象に希望者を募って、月1回の糖尿病教室を開催している。教室の食事改善効果を学会で発表しようと考えている。なお、研究倫理委員会の承認を得ている。
30-196
同じ月に糖尿病と診断されたが、教室に参加しなかった患者を対照群とすることにした。教室に参加した患者と同じ性・年齢の患者を抽出し、1か月後のHbA1c、BMI、食事内容の変化を比較した。
この研究デザインに該当するものとして、正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)前後比較試験
(2)無作為化比較試験
(3)非無作為化比較試験
(4)症例対照研究
(5)症例研究(ケーススタディ)
解答3
30-197
食事内容の変化から教室の効果を検討し、学会で発表した。結果にバイアスをもたらす事項として強調すべき、研究の限界である。
最も適切なのはどれか。1つ選べ。
(1)教室効果の検討として、1か月間の観察期間は短い。
(2)行動変容の準備性が、2群で異なった可能性がある。
(3)月1回の集団教育では、介入の強度が不十分である。
(4)1つの病院のデータであるため、一般化できない。
解答2
ここから先は
2,081字

読める記事が300以上になりました!
【marcyノート】(管理栄養士国家試験対策の解説)
¥550 / 月
初月無料
marcyノートは、国試対策に特化したマガジン(記事集)です。 自分自身の受験経験・講師としての経験・受験生からいただいた質問を通して、合…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
