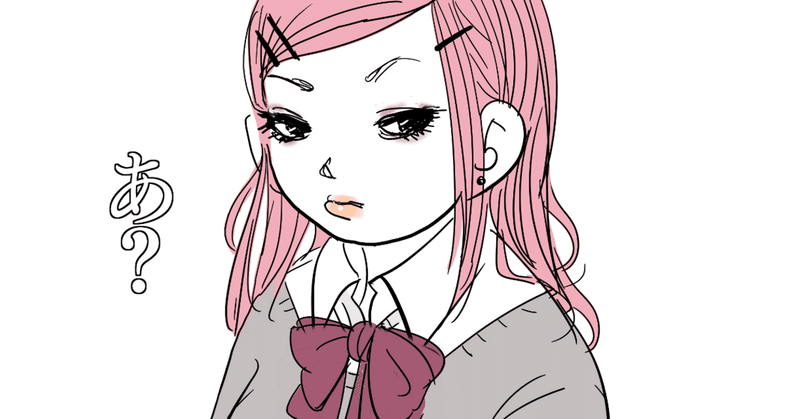
2020/04/23
ウディ・アレン『カフェ・ソサエティ』を観る。なかなか安直に語りづらい映画であり、手強いと感じた。いや、わかりにくい難解な映画というのではない。誰にでもわかるように30年代のハリウッドやニューヨークの雰囲気が料理されていて、ジャズと映画スターのゴシップに満ちた華やかな時代に展開されるラブ・ストーリーを楽しむことができる。この間口の広さは流石はウディ・アレン、と言うべきだろう。展開するラブ・ストーリーも、ありがちと言えばありがちだが嫌いではない。
年の功、という言葉が浮かんだ。ギラギラした野心はスクリーンの中には存在しない。脂ギッシュなくどさでこちらを辟易させるような下品さはない。そこはウディ・アレンの洗練された物腰の強度を感じさせる。だが、枯れているというのでもない。落ち着いたアプローチでこちらをラブ・ストーリーの世界にじわじわと引きずり込むのだ。ではジャズとゴシップに満ちた世界で語られるのはなにか。それは愛であり、その裏返しの要素としての死であるだろう。
騙されてはいけない。この映画では死がかなり呆気なく、それでいて粗暴になり過ぎない程度にマイルドに溶かし込まれている。ギャングたちによって殺される人々のその死に方の呆気なさ。あるいはユダヤ教を信じていた人物が魂の不滅という考え方に惹かれてキリスト教を選ぶところ。このあたりにある「死とはなにか?」という問い、裏返せば「この人生とはなにか?」という問いを読み取らないと、魅力が半減するのではないだろうか。
「この人生とは何か?」という問いはそのまま、主人公もその叔父も、叔父と主人公の間で恋に揺れる女性も一寸先は闇の状態を辛うじて生きている――つまり、「人生は予測不可能」というこの映画のテーゼをそのまま生きている――彼らの生き様にそのまま繋がってくる。人は簡単に変わるし、人だけではなく事物も移ろいゆく。全ては儚い。だからこそ尊い。そんな東洋哲学的な諦観がこの映画からは感じられるのだ。少なくとも私はそうした諦観を感じた。
老獪なウディ・アレンが書いた、これは彼なりの「終活」映画なのではないだろうか……と書くのはもちろん悪ノリが過ぎるというもの。だが、そんな死と生、愛と人生をしかしマニアックに/高踏的になり過ぎずに誰にでもわかるように絵解きするところに私はウディ・アレンの知性と骨太の哲学を観た気がした。脂ギッシュなところがないが故にこの映画は損をしているとも思うのだが(濡れ場ひとつ出て来ない、という。このあたりは私の助平心が満たされていないだけかな)、それでも侮れない映画だと思われた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
