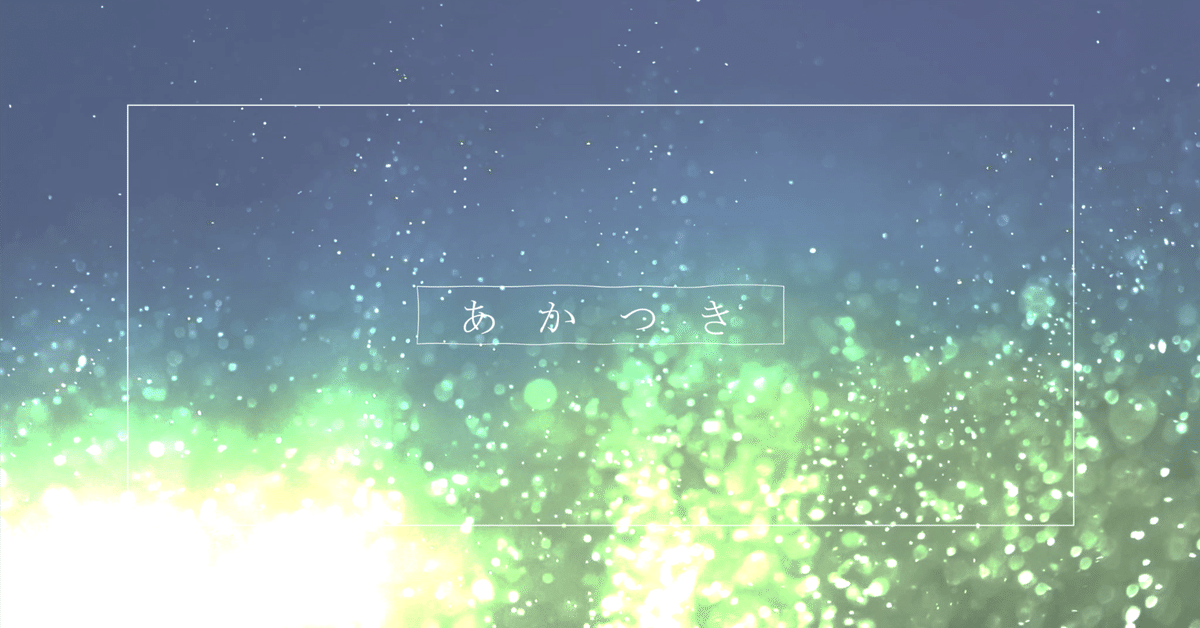
小説「あかつき」4/4
——辞世の句
「笑い話だ。結局その手紙を置いてく勇気も出なかったし、僕はいま生きてるし」
少女Aが読み終わったらしいのを見計って少年Aがそう補足した。すると少女Aは何も言わずに手紙をひるがえして裏側を見る。
「ああ、気づいちゃった?」
こう書いてあった。
——人間の十人十色を示すなら五輪の赤は僕の無チ色——
「辞世の句だよ。あーあー厨二病。バッカみてえ。いや、実際バカなんだな。僕はもう」
すると、「なんだ、君、私なんかより『えらい』じゃん」と少女Aがつぶやいた。
「えらい……?」
「そう。えらい」少女Aがゆっくり少年Aに歩み寄る。
「遅くたって、自分の行いが引き起こすことの、その先の先まで、君はめちゃくちゃ真剣に考えた。その時点で、とてつもなくえらいんだよ。たとえそれで自分が嫌いになったとしても、君はえらいんだ」
少女Aはそっと少年Aの手からカブトをとり、それを王冠のようにして、やさしく少年Aの頭にかぶせにかかる。——おそらく少女Aは知らない。コロナという名称は王冠(corona)に由来する。それを少年Aは知っていた。
――歪んでいる。この王冠を戴いたとき、僕もきっと歪んでしまう。
少年Aはとっさに、王冠をそっと右手で受け止めて、少女Aの動きを止めた。そして、ほんとうにひさしぶりに、冷静になった。
――そうか。僕は、もうすでに、歪んでいたんだよな。
少年Aをすぐさま抱擁してやれたのは、歪んだ世界を見てきた少女Aだったからだ。少女Aが歪んでいるからでは、決してなかった。彼女の困惑した目が、少年Aの眼とカブトとを行き来する。
左手も上にあげ、両手でカブトをしっかり持つと、下を向いて、頭にあてがった。少女Aから彼の表情が見えなくなる。胴着と同じ容量できゅっきゅと紐を結び、くいっと位置を調整して、顔をあげた。
笑顔だった。いままで見てきた彼の表情がぜんぶ作り物で、これが本物の「彼」だ、と悟らずにはいられない、笑顔だった。
――歪んだ世界に救われるのと、僕も歪んでしまうのとは違う。だから僕には、差し出された愛を、受け入れる権利があるんだ。
いっしゅん、ほんとうに見つめあった。ここにあるすべてが、最高だ。
大いにワハハと笑い散らしてしまった。響く声に、つられて少女Aも笑った。ワハハハハハハは壁に跳ね、返ってきて、いつの間にか警告音の消えた静かな空間すべてを埋め尽くした。たぶんこれが、二人の今までの人生の中で、いちばん気持ちのよい笑いだった。ワハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ——
一発。
パァン!——という銃声で、二人の笑いは消えた。シンとした館内に、一人分、コッコッコッと足音が近づいてくる。そして、「それ」は二人の前に現れた。
「お祖父さま……?」
その手には、古いピストル——たぶん展示物——が二丁あり、片方からはたったいま発砲したらしい煙がおそろしくモクモク立ち込めていた。けれどもそんなものより、煙をかぶって窓明かりに照らされる祖父の怒り顔の方が、よほどおそろしかった。凝り固まった、鬼だった。
「な、なんで……」困惑する少年Aに、祖父がもう片方の銃を向ける。するとすかさず、少女Aが間に入って立ちふさがった。
「逃げて。こうなったお祖父さまは何をするかわからない。撃つかもしれない。だから、早く」
そういう彼女に、こんどは少年Aの方から「なんでそこまで」と問うた。
「私はもう、生きるも死ぬも、いっしょだから」との答えだけが返ってきた。
次いで、聞いてもないのに祖父の方も、ここまでやってきた理由を話す。
「お前、俺を殺そうとした。だから、来た」
少女Aはそこに立ったまま、じっと祖父の目を睨み返す。十秒くらい、その場が静まりかえった。
少女Aが、ハァーっと息を吸う。
——ここへ至り まだ知らずなり 家族をも 人の道をも ……汝のことぞ——
彼女に古文を教え込んだ本人である祖父は、その歌の最高の煽りを瞬時に受け取る。即ち、『ここへ来て、まだ知らないらしい。家族のことも、人の道も。——あなたの話だよ?』
「撃ってやる」と唸る鬼に、返す。
「辞世の句だよ、お祖父さま」
——銃声
少女Aは倒れた。——銃によってではなく、少年Aのタックルによって。
少年Aが彼女をかばったのだった。銃弾を頭に受けたようで、ガァンという金属音とともにクイッと頭が上を向き、そのまま力なく膝から崩れ落ちる。少女Aと祖父は、同時に少年Aのところへ駆け寄った。少女Aは、少年Aの安否を知るため。祖父は、少女Aを殴り殺すため。祖父のただならない様子を見た少女Aは、少年Aの刀をうばって祖父の方へ向け構えた。祖父はピタりと止まるしかない。
少しだけ、祖父が冷静になった。
「……けっきょく、間違えたのはお前だ」
少女Aがすかさず応戦する。
「何が? 家出したことが? じゃ、こうする以外で、私に何ができた!? 異常な家庭から抜け出してしまいたくって、それで、どうすればよかった!?」
「異常だと思うんなら、児童相談所なり警察なり、出るところに出りゃよかったんだ。それが正しいことだ」
「そんなことしたって取り合われないのは自明だ!」
「当たり前だ! なぜなら、俺が正しいからな!」
「違う! 何が異常なのか、どうすれば異常と言えるのか、『正しい』人たちじゃあ決断できないから、救えないってだけの話だ! 公権力に取り合われない、だとか、そんなことで、お前の、お前らの、高齢世代の、社会の『まちがい』が否定されてたまるかあ!」
内心の歪みを叫びきり、すっかり空いた脳内に、「そんな……」と、今にも消え入りそうな少年Aの声が耳に入る。
「そんな往時に、捕わるなかれ……!」
両手で頭を押さえ、少年Aが上体を起こした。腕と腕の間から、鋭い眼光が鬼と見つめあった。
「大丈夫!?」と問いかけてから、少女Aは、ここまでの会話が一つの川柳のように、五七五七七のリズムになっていることに気づいた。
——撃ってやる——
——辞世の句だよ、お祖父さま——
——そんな往時に、捕わるなかれ——
少年Aが、しんどいながらな声を出す。
「こんな人が、社会で権力を持ってたのなんて、もう往時……過ぎ去った話なんだよ」
祖父は止めに入りたくても日本刀を突きつけられていて進めない。
「あのクラスメイトと仲良くなって、話してて、それでじっさい僕も思うよ。世の中は不公平で、若者は目の敵にされて、新しい技術は嫌われてる、って。——けれども、実際のところ、社会は変わるんだ。コロナなんかがやってくるよりもっと前から、モゾモゾゴロゴロ世代交代が進んで、少しづつ無理解はなくなり、技術もけっきょく普及していってた。若者やネットを目の敵にする大人なんて、実はもう少数派かもしれない。僕らの培った『上の世代が苦手』って感覚、反骨精神は、それすら時代遅れになりつつある。あんたの家のようなところは、そんな変化に取り残された『特殊な』例なんだ。あんたの自由を否定するようなそんな一個の家の環境を、一般の環境だと思ってしまったなら、それは認知の歪みだ。けれど認知が歪んだのだって、与えられた特殊な環境のせいだよな。だから、世界の方がおかしいのを知って、イヤだ、って思う時、あんたはそれを言い訳に使っても一向に構わないんだよ。——ああ、言いたいことぜんぶ言い切れねえ! 日本語が変になる! つまり、な……」
赤いチが、ツーっと流れる、顔を開き、王冠カブトを、取り払い、表情全てを、見せつける。声の銃口を、鬼に向ける。
「新しくなったこの世界は、きっと、僕らの味方なんだ!」
少年Aの銃声が轟いたその時、物陰からかすかに「確保!」という声が聞こえた。それに気づいた頃には、どこから現れたのか三人ほどの警官が駆け寄っていて、たちまち祖父は取り押さえられてしまった。構えていた日本刀を下ろすと、少女Aの中の王冠もそっと降りた。
「銃刀法違反及び殺人未遂、現行犯!」
カシャン、と、祖父に手枷がかけられた。「生きるも死ぬも変わらない」という心枷から、少女Aは、放たれる。
——家と家
「我々の不注意です。『俺が一人で交渉する』と言って聞かないので先に行かせてしまった」
警察署へ向かうパトカーの中で警官がそう説明してくれた、と、僕の友人は教えてくれた。
そんな騒動を友人が起こしていたあいだ、僕が何をしていたのかといえば、けっきょく、なすすべなくオリンピックを観戦させられてしまった。何も抵抗できなかった。無力だったみたいだ。
けれども、友人を叱りつけようとする先生に意見することができた。友人はそれを聞いて、僕を褒めてくれた。それ以外には何もできなかったと言うと、友人はそれでも、僕を肯定してくれた。
意見で屈しないっていう、とてつもなくえらいことをしているじゃないか。と。
友人は言葉を続ける。
これを君に話したのは、何も、「行動しろ」って言いたいからなんかじゃないし、まして「行動することだけに意味があって、そうでなきゃえらくない」と言いたいからでもない。
家庭かもしれない。国家かもしれない。社会の中で、「家」の中で、生きづらさを感じて、それで、周りが全部敵に見えちゃってる君に、僕らは君の味方で、きっと君の正しさを肯定してあげるって言いたいんだ。
そして暁には、世界は僕らのものだ。
あとがき
コロナはダメです。滅べ。
この小説の由緒について、少し書こうかと思います。
時代が移ろっていく、というのは、基本的にネガティブな文脈で芸術化されます。インテリっぽい人々が「そういう時代」と言ってポジティブな意味なんかほとんどありません。国語の授業で扱うエッセイの中で「インターネットの功罪」があれば、必ず批判の立場です。インターネットバブルが崩壊し、行きすぎた万能論を槍玉に上げたその後遺症とも言える、新技術アレルギー。
この小説は、そういった害的懐古主義に真っ向から対峙し、実態はむしろその対立すら通り越しているという立場で、これを書いた当時の僕の、この議題にかかわるすべてと言っていい手駒をぶち込んだものです。
大人とは、子供とは何か、とか、過去の負の遺産を否定して一向に構わないんだ、とか……17歳の僕であるからこそ、書き、残しておくことに意味がある。そう思って、18歳になるギリギリ前に書き上げて、文芸同好会の会誌に載せました。そして18歳になってから、ところどころ粗雑だった心理描写に肉付けをして、高校生文芸コンテストに応募し、余裕で落選しました。残党。そういう小説です。
……今の僕には、この小説すら過去の遺物です。これで終わりではない。
紀政諮といいます。小説を書きます。今後ともよしなに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
