
『破壊の日』『ディック・ロングはなぜ死んだのか?』『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』『海辺の映画館 キネマの玉手箱』『糸』『僕は猟師になった』『8日で死んだ怪獣の12日の物語』
7月25日

豊田利晃監督『破壊の日』をユーロスペースへ観に家から歩いていく。映像や音はカッコいいし、役者も豊田組な人も多いけど、なんか物足りない。
コロナ禍の時代でやりたいことはわかるんだけど、豊田監督が覚醒剤所持で捕まってから復帰したあとの『蘇りの血』や『モンスターズクラブ』とかの感じ。やりたいことはわかるんだけど、映像もカッコいいのに物語があるようでない。だから、衝撃がない。
8月11日

ヒューマントラスト渋谷でA24制作の『ディック・ロングはなぜ死んだのか?』を鑑賞。最初のうちはうとうとしてしまった。しかし、最終的に死んだ理由それか? それでいいのか。実話を元にしているらしいが「僕はなんて言えばいいんだろう」状態に。A24でも失敗作もあるというのはどこか心強い気すらする。
8月20日
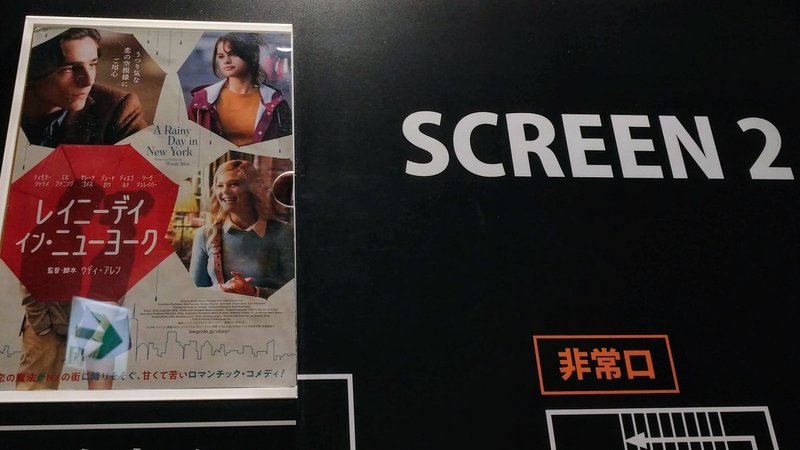
ウディ・アレン監督『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』をシネクイントで鑑賞。「Me too問題」があったりで公開も遅れていた今作だが、やっぱりウディ・アレンというか、きちんとインテリと教養を感じられる内容だった。
主人公のギャッツビー(ティモシー・シャラメ)は裕福な家庭に生まれ育ったNYっ子だが、母とはうまくいっていない。最終的には母と和解というか彼女の秘密を教えられることで関係性はうまく動き出す。
ヒロインであり彼女であるアシュレー(エル・ファニング)はジャーナリズム専攻で有名な映画監督のインタビューのためにギャッツビーと共にNYにやってきたが、監督だけではなく彼と組んでいる脚本家、人気俳優と出会うことで恋人とはNYを楽しむ時間がなくなっていく。
排気ガスまみれなNYが好きだと再確認するギャッツビー、都会っ子でありハイソさの煌びやかさがあるからこそ闇に惹かれていく様はウディ・アレンのような監督が描かないとどこか嘘くさいものになってしまうのかもしれない。
8月22日

大林宣彦監督『海辺の映画館 キネマの玉手箱』をTOHOシネマズ新宿で鑑賞。遺作となった今作は約三時間ある。広島の映画館の話だろうなって思ったら冒頭からぶっ飛んでた。
もちろん、広島の話もあるけど、戊辰戦争の時の福島の会津の白虎隊や女子隊、満洲の話に沖縄での話と戦争についてこれでもかこれでもかとどんどん増し増しにしていく極彩色の大林ワールド。
笑っちゃうし呆れちゃうのになんだか泣けてくる。この異常さ、過剰さ、は大林宣彦という人の映画への熱情と反戦への願いの万華鏡。これはさ、やっぱり映画館で観なきゃいけない作品なんだよね。
8月23日

中島みゆきの『糸』からインスパイアされた瀬々敬久監督『糸』をTOHOシネマズ渋谷で鑑賞。主演は菅田将暉&小松菜奈。
平成元年に生まれた男女の出会いと別れが、「平成」という時間の中で展開していく。最初は二人の地元である北海道から始まり、再開する東京だけではなく、沖縄やシンガポールと舞台は変わっていく。
中学生の時にサッカー少年だった漣(菅田)の将来の夢はサッカー選手になり世界に出ていくことだと思いを寄せる葵(小松)に告げる。しかし、少女は同居する母の恋人から暴力を受けていた。夜逃げ同然でいなくなった彼女の新しい家を訪ねた彼は、駆け落ちのように逃げ出すものに見つかってしまう。そして、月日は経ち友人の結婚式で二人は久しぶりに再会するが、もう二十歳をすぎた二人にはそれぞれ違った人生と恋人がいた。このあと物語は世界に出てきたかった漣はそのまま北海道で生活し、葵はIT企業の社長との交際を得て、シンガポールで派遣ネイルの会社を友人と興す。もう出会うことのないと思っていた運命の糸が交差し、再び彼と彼女は出会う。
「平成」を描いたこの物語は「9.11」やリーマンショック、東日本大地震の影響も物語に入れ込んでいく、そう「平成」という三十年を生きた人ならなにかを自分に投影したり思い出したりすることもあるだろう。
中島みゆき『糸』はそもそも九十年代に野島伸司脚本『聖者の行進』のエンディングテーマだった。ドラマは知的障害者を主人公にした作品であり、多くの批判もあった。この曲だけはそこの問題とは切り離されるように「平成」を代表する名曲のようになっていった気はする。この曲がドラマの展開や気持ちが盛り上がる時や誰かがいてほしい時にかければパブロフの犬のように泣けてきしまう。
あまりにも強い武器だから何度も使えないということもあっただろう、作中で『ファイト!』『時代』も原曲のままではないがアクセントのように使われる。まあ、反射的に曲かかったら泣きますよね、そういう展開にしてるんだから。
葵は家庭内暴力を受けていたし、漣と付き合うことになる香(榮倉奈々)はある病気になってしまう。この辺りは「平成」に何度も見聞きしてきたものだ。そして、その被害者や病気になってしまうのは女性であるということ。確かにこの物語の主の主人公は漣であるから、相手役の女性たちに困難がないとドラマにはしにくい、つまり障害がないといけない。それはよくわかる、わかっているからこそ思うのはあまりにも「昭和」から続いてきた「平成」的な事柄であり、それが「令和」になっても解決はしていないのだということ、東日本大震災やコロナ禍において露わになってしまった格差や断絶、その被害はどうしても女性のほうが多くなっているし、深刻化していると考えてしまう。
ここで描かれた「平成」という時代はたしかに一見平和だったのかもしれない、だけども、経済成長が終わり、世界が新しい段階(ルールやシステム)に入っていく中で、後ろ向きのよかった「昭和」を追い求める人たちによってさらに断絶は増してしまった。
保守系の政治家や自民党が夫婦別姓を認めないことを考えればわかりやすい。家父長制なんてもう古びたOSやシステムに固執する人たちはわかっているのだ、変えられたら自分たちが持っている権力や力が行使できないことを。だから、ずっと女性は奉仕する立場ではないと弱くないと困る。しかし、どうしたって世界は変わっていくし、変わっていることを気づかないまま、ないものにしている人たちはきっと怖いんだろう、そんなことの繰り返ししか歴史にはない。
8月27日

ドキュメンタリー映画『僕は猟師になった』をユーロスペースで鑑賞。もともとNHKで放送したものが好評だったらしく、追加取材したもので再編集して劇場版にしたみたい。罠漁師をしている千松さんの一家の生活と山での猟を追いかける。罠の仕掛け方から捕まえた猪や鹿を仕留めるシーンなどは、生命を食べるということだったり、殺めること、自然と人間との関係性が嫌でも濃厚に漂ってくる。僕の友人も罠猟の資格を取って地元の静岡でやっていたけど、この千松さんの影響だったのかな、ちょっと記憶が曖昧なんだけど、千松さんと同じことを言っていた。それは自分が食べる肉ぐらいは自分で獲って処理して食べたいということだ。千松さんも必要以上には獲らないようにしていた。その距離感と山や動物へのある種の敬意みたいなものがないとやはり難しんだろう。

そのまま渋谷で移動して岩井俊二監督『8日で死んだ怪獣の12日の物語』をアップリンクで鑑賞。リモートによる撮影がメイン。好きな役者が出ているし、岩井さんの作品だから劇場で観ようと思っていた。怪獣の卵を買った斎藤工が主人公で、それはどうやらカプセル怪獣らしく、それが育っていくのだが、という内容。怪獣に詳しい人物として樋口真嗣監督がそのまま出ているのだけど、斎藤工は今度の『シン・ウルトラマン』主役だし、樋口さんはその監督なわけだから、そのスピンオフやちょっと関連している作品と思ってみるのがちょうどいいのかも。コロナ禍における突発的な作品で一気に作れてしまったものでもあるので、そのリアルタイム性はのちに見ると懐かしく思えるのかも。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
